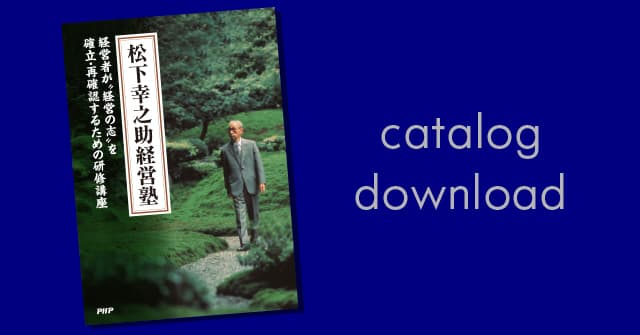御木本幸吉の決断~養殖真珠への挑戦
2014年6月 7日更新

養殖真珠に身を投じて成功を収めた"真珠王" 御木本幸吉。成功を収めた要因は何だったのであろうか。その背景に迫る。
明治末期から大正初期にかけて三度内閣を率いた桂太郎と、蔵相、農水相を務めた曽禰荒助が、御木本幸吉を交えて会食をしたとき、曽禰が御木本をふりかえってこう言った。「この御木本という男も、大風呂敷さえひろげなければ、実にいい男なのだが」
すると、桂が、「しかし、それを取ってしまったら、この男に何が残るのだ」と言って大笑いしたという。
たしかに、"真珠王"と称し、「国定教科書に載るような人物になる」「世界中の女性の首を真珠で締めてご覧に入れる」といったセリフが示すように、大言壮語は御木本の代名詞だった。しかし、口から飛び出た言葉に忠実に、彼はその生涯を真珠に託し精進し続けた。
真珠に対して特別な知識がなかったにもかかわらず、養殖真珠に身を投じて成功を収めた要因は何だったのであろうか。
発明を志すということ
御木本幸吉の人生を眺めると、その輝かしい成功が何がしか最初から仕組まれていた一つのドラマのように感じられる。天職に巡り会えた運命の不可思議なのか。あるいは、「天の時・地の利」といった好条件が、あまりにも見事に融合されていた印象からくるのかもしれない。
御木本が養殖真珠を自分の仕事とするまでの経緯は、彼が置かれた環境と彼の身体に宿っていたDNAが時間とともに作用し合っていった結果といってよいだろう。
御木本が鳥羽に生まれたことは地の利の最たるものである。鳥羽に生まれなくして真珠には出会えない。そして志摩の国鳥羽の歴史と風土も、御木本の人格に大きな影響を与えた。
戦国期、鳥羽を治めていた九鬼嘉隆は、織田信長の配下にあって水軍を率いる勇将であった。志摩の国は平野に乏しく、農業に適するところではない。しかしその一方で、海の幸にはことのほか恵まれていた。そうした地勢的な条件から、嘉隆は海の利を水軍という軍事力で、市井の人びとは海の幸を産業として都市を栄えさせてきた。
こうした志摩の国のことや嘉隆の活躍を、御木本は祖父の吉蔵から幾度となく聞かされていたという。郷土人としてのDNAの刷り込みといってよい。また、まさに血筋として強いDNAを御木本は受け継いでいた。うどん屋「阿波幸」が御木本家の家業であったが、吉蔵はこの家業のほか、伝馬船を数艘持ち、青物や米・薪・炭を扱う名うての商売人だった。吉蔵のやり方は、客の人別帳をつくり、そこに配達記録を記入して、次の注文を受ける前に荷を届けるという抜け目のない商法だったから、"うしろに目があるような男"という異名をとっていた。マーケティングの達人だったのである。
一方、父の音吉は商人としての才はなく家産を減らしたが、一方では、機械器具の改良に関心を持ち、発明家としての資質があった。労力を要するうどんの粉挽き作業を慮って、楽に挽ける粉挽機を発明し、その功績で県の表彰を受けた。つまり、御木本は祖父の商人感覚と父の優れた発明家気質のDNAをともに受け継いでいたのである。
敏感に機運を読む
御木本は、十二歳のときに鳥羽の金満家二人の名を挙げ、「一生涯中には、せめてその次の鳥羽で三番目の金持ちになりたい」と語るほど野心旺盛な少年だった。またそのために積極的に行動することを厭わなかった。
――うどん屋だけではお金持ちにはなれない。
家業を手伝いつつ、そう考えた彼は青物の行商をはじめる。早朝に起きて青物商の仕入れと販売、そして昼からうどんの粉挽き、営業と、連日夜まで働いた。若い身体にもつらい労働だったに違いない。しかし、そうした苦労の甲斐あって、・少年八百屋・として次第に評判になっていった。
十八歳まで青物商を続けたが、利幅の薄い商いで、金満家になるには道はほど遠いと見切りをつけた。
次に手を染めた新しい商売は米穀商である。升で売る零細な小売りからはじめ、努力して俵で売るほどに扱いを大きくしたが、そこでもまた限界を悟った。いくら働いても資本が足らない上、元来志摩地方は米作農村が少なく、扱いをふやすには無理があったのである。
折しも家督を譲られた御木本は一から出直そうと考えた。
そして、天のときといえる機運は唐突にやってきた。明治10(1877)年1月、神武天皇陵親拝および孝明天皇式年祭のため、航路、横浜港から大和をめざして出航した明治天皇の船が、暴風に遭い、にわかに鳥羽に上陸することになったのである。わずか三メートル幅の町内の道を、太政大臣三条実美、参議伊藤博文ら高官を従えていく明治天皇の姿を見て、御木本は大きな衝撃を受けた。きらびやかな行列から新しい日本の空気を感じ、その中心は東京にあることを頭に鉄槌を受けたように感じたのである。
家督を継いだからには鳥羽を捨てることはできない。しかし、今だからこそ、東京の空気を吸い、新たな商売を模索しておく必要がある――そう考えた御木本は、知人が上京することを知り、父の許しを得て同行する。
大きな転機となったのはまさにこのとき、横浜・横須賀を訪れたことにあった。
両都市では多くの外国人が駐留しており、彼ら相手の商売が盛んであった。中国人がイリコやアワビ、寒天を大量に買い付けに来ており、西洋人は真珠を宝石として高額で購入していた。そのさまを目撃して、御木本ははっと思い当たった。
――これらはすべて志摩の国の産物である。海の国に住む者は海の産物を利用すべきだ。
養殖真珠への道
御木本は帰郷するとすぐに海産物を扱う商人になった。ただ、このときはまだ真珠に特化はしていない。むしろこの頃奇妙に見えるのは、政治活動を展開することである。二十二歳で町会議員に、二十六歳で三重県勧業諮問委員、翌年には同商法会議員となる。その真意は商売を捨てるということではなかった。むしろ、商売において自分が不利になる部分、すなわち年齢と実績を肩書きによって補おうというしたたかな意図による行動だった。
結婚もたいへん割り切ったものであった。彼はもっとも信頼する町内の五人の教師に相手の選定を依頼し、彼らが推薦する旧藩士の娘を娶った。通常商家ならば商家から嫁を迎える風習であったが、そんな古式にこだわらず、安心して家宰を任せられる教養ある妻を求めたのである。妻うめは御木本にはまたと得がたい良妻であった。
さて、数ある海産物の中から真珠に情熱を傾斜させていくのは、英虞湾の天然真珠が母貝であるアコヤ貝の乱獲によって、急激に減少していたことが背景にあった。明治21(1888)年、志摩国海産物改良組合の組合長になっていた御木本は、大日本水産会主催の第二回全国水産品品評会が東京で開催されるにあたって、改良イリコとともに真珠を出品し、真珠は大きな注目を浴びた。
その夜、宿から散歩に出て、丸の内を抜けてお堀端に立ったとき、御木本は真珠の産地が長崎の大村湾、能登の七尾湾、そして志摩の英虞湾しかないこと、またアコヤ貝絶滅の危機を思い起こし、「牡蠣が養殖できるのであれば、アコヤ貝も養殖が可能ではないか」という思いがつのった。
主宰者である大日本水産会幹事長の柳楢悦が隣国伊勢出身であることをつてに、御木本は早速柳を訪ね、養殖事業の可能性を熱心に提案する。帰郷すると、連日海に小船を漕ぎ出し、海底に杭を打って回り、しゅろ縄を張り巡らしはじめた。地元の人間は口々に、「阿波幸の御木本は狂ったようじゃ」と思ったという。やがて柳も有力な協力者となって志摩を訪れ、その政治力を生かして御木本を応援する。
そして、アコヤ貝の養殖は可能だという見込みを得た。しかし、本当の悩みはそこからだった。御木本さえ当初は、真珠を産むアコヤ貝の数を養殖してふやせばそれでよいと考えていた。しかし、育成にまず四年かかる。しかも天然真珠が採れる確率は千分の一である。これではとても事業にすることはできない。そんななか、先の柳が水産動物学の権威である東京帝国大学の箕作佳吉を紹介してくれた。そしてその箕作から、養殖母貝から偶然産出する真珠を待つのではなく、科学に基づいて確実に真珠を産ませる方法を考えるべきだと示唆された。真珠を産むアコヤ貝の養殖ではなく、真珠そのものを養殖する、このことはいわば、神の創造物といえる真珠を、人の手に及ぶ生産物にしようという、壮大なテーマである。
ここに至って御木本は養殖真珠挑戦を決断する。
経営力がもたらした発明
「あいつは山師じゃ」
そんな周囲の声に、御木本は、「おれは山師じゃあない。大海師だ。今に見ておれ」とうそぶいた。リスクの中にあっても、御木本はつねにタフであった。
以来、赤潮の報に顔をひきつらせ、死魚の漂う海をかき分けて、アコヤ貝の死骸を引き揚げるのもたびたびであったが、この年明治26(1893)年、千個のアコヤ貝からわずか五個の半円真珠を得たとき、御木本は妻と手を取り合って泣いた。このドラマチックな経過を眺めると、発明というものがいかにたんなる「思いつき」で成るものではないことを考えさせられる。人間の総合力とでも言おうか。
ただ、ともすれば御木本の場合、製造・技術のことだけがクローズアップされがちだが、実像はそうではない。天性の経営感覚と商人魂こそ御木本の本領だと指摘する伝記は多い。
その力量は次の三点に見られる。
(1) 衆知を集めることに秀でていた
結婚でもそうだったが、衆知に頼るのが御木本流であった。それは技術においても、営業においてもいかんなく発揮された。取り立てて学歴のない御木本は養殖について何の知識も持ち合わせていない。しかし、その部分は箕作博士ら水産学の権威に教えを乞い、存分に知識を吸収した。
また実験、研究する協力者も自分のネットワークによって招集した。研究者不足に悩んでいた頃、アコヤ貝に核を入れる作業が職業柄近いからという理由で、知人の歯科医をスカウトしたほどである。こうした衆知を結集する力、人材を調達する力は御木本の大きな長所であった。また先の柳楢悦をはじめ、皇族や政治家といった事業を進める上で有力な人びととの絆を築くことによって信用をいち早く確保した。権威を活用する機微にたいへん通じており、つまり「天の時・地の利」に加えて「人の和」も味方にできたのである。
(2) 宣伝の達人であった
また御木本は商売における演出に抜群のセンスを持っていた。青物商をしていた頃に、こんなエピソードを残している。イギリスの軍艦が鳥羽に入港したというので、小船に乗り込み、艦に近づいて懸命に売り込んだ。しかし、まったく相手にされない。そこで旅の狂言師から習った足芸を兵士に披露する。すると兵士たちは拍手大喝采。その返礼としてすべての青物を買ってもらい、一人艦上に招かれる栄誉も得た。
真骨頂は明治36(1903)年、大阪での第五回内国勧業博覧会において出品した真珠・貴金属製品が、こぞって盗難に遭ったときである。御木本は陳列品の補充を指示する一方、自身は人力車で新聞社に駆けつけ、「盗難品発見の方には、一品につき百円の礼金を呈上する」という広告を頼んだ。これで世間の人はまず驚いた。興味本位に博覧会を訪れると、前にも増して豪華な展示がなされ、訪れた人はまた驚いた。その後、犯人が捕まって盗難品も戻ってきたので、巷間では、御木本は警察に対しても礼金を払うのかと噂し合うなか、御木本は警察関係の公益事業に懸賞金を全額寄付したので、世間は三度驚いたという。
また七十代の御木本を有名にした「真珠の火葬」事件も彼らしい。わざわざ外国人の多い神戸に出向き、御木本はその目の前で、大きな箱に入れてきた真珠をスコップですくって炎に投じ、見ていた外国人をアッと驚かせた。粗悪な真珠を輸出する追随業者がふえて、日本の信用が揺らぎかねないところを、御木本は自分のブランドを守るために演出したのである。
(3) バランス感覚が優れていた
そして、もう一つ忘れてはならないのは、バランス感覚である。養殖には大きな投資が必要である。また失敗も予想できる。そうした状況下、すべてをつぎ込んで運悪く破産してしまっては元も子もない。このリスクに対して御木本は、明治二十九(一八九六)年に半円真珠の特許を得るまでは、家業のうどん屋も海産物・天然真珠の仲買も継続させていた上、四日市では鉄道事業にまで携わって家計のやりくりをしていた。また市場展開や真珠と貴金属の加工製品への対応も敏であった。乾坤一擲を賭けたイメージがあるが、御木本は時代を先取りしつつ、優れたバランス感覚によって、・発明・という事業を、人生を含めて「経営」によって成り立たしめたのである。
一体化できる何かを見つける
今、経営者としての御木本に学ぶことは何だろう。
経営者のタイプとして御木本は天性の「発明家」のように語られ、また自らそれを任じてふるまったが、どちらかといえばマーケティング・センスあふれる「商人」型経営者の色彩が強い。しかし、御木本の場合、そうした経営者タイプの鋳型にはめ込んで長短を論じるだけでは何か物足りない。それは御木本の、日本では他に例を見ない「王」と呼ばれる、どことなく前近代的で、いかにもそれらしかった人格による。
晩年の御木本と面談した作家の吉川英治は、大見得を切り、けれん味たっぷりな御木本の言動をこう評している。
「翁(御木本のこと)の人生は翁自身の語るものを、すべて素直に伺っても、まこと他愛がないものだ。真珠はあんなに産みもし磨かせもしているのに、翁自身の人間は、いまだに帆立貝のままである。この親帆立貝は、割らない方がいいやうに思はれた。教養的な真珠層は巻いて居さうもない」(「新平家今昔紀行」)
やや辛口だが、吉川は御木本を非難しているのではない。御木本の本領を、近代経営の知性などではなく、極論すればその野性的な勘とパワーだと喝破しているのである。またそうであったからこそ、「真珠王」になれたのであろう。御木本の気質は志摩の風土が産んだものであり、真珠もまた然りで、その見事な一致がよい仕事となったわけである。
そう考えると、現代の経営者が御木本に学べることは何であろうか。彼の養殖真珠に匹敵するような、自分のすべての情熱を託せる事業に出会えるかどうかは、変転の激しい今日では運命に頼るしかない気がする。
しかし、少しでも心がけることがあるとすれば、自分のパーソナリティをよく見つめること、たとえば好きなことは何か、強みは何か、適性は何なのかをよく考えることであろう。そして自分を生かせそうな仕事を選ぶこと、その貝あわせを模索し続けることに尽きるのではないだろうか。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。





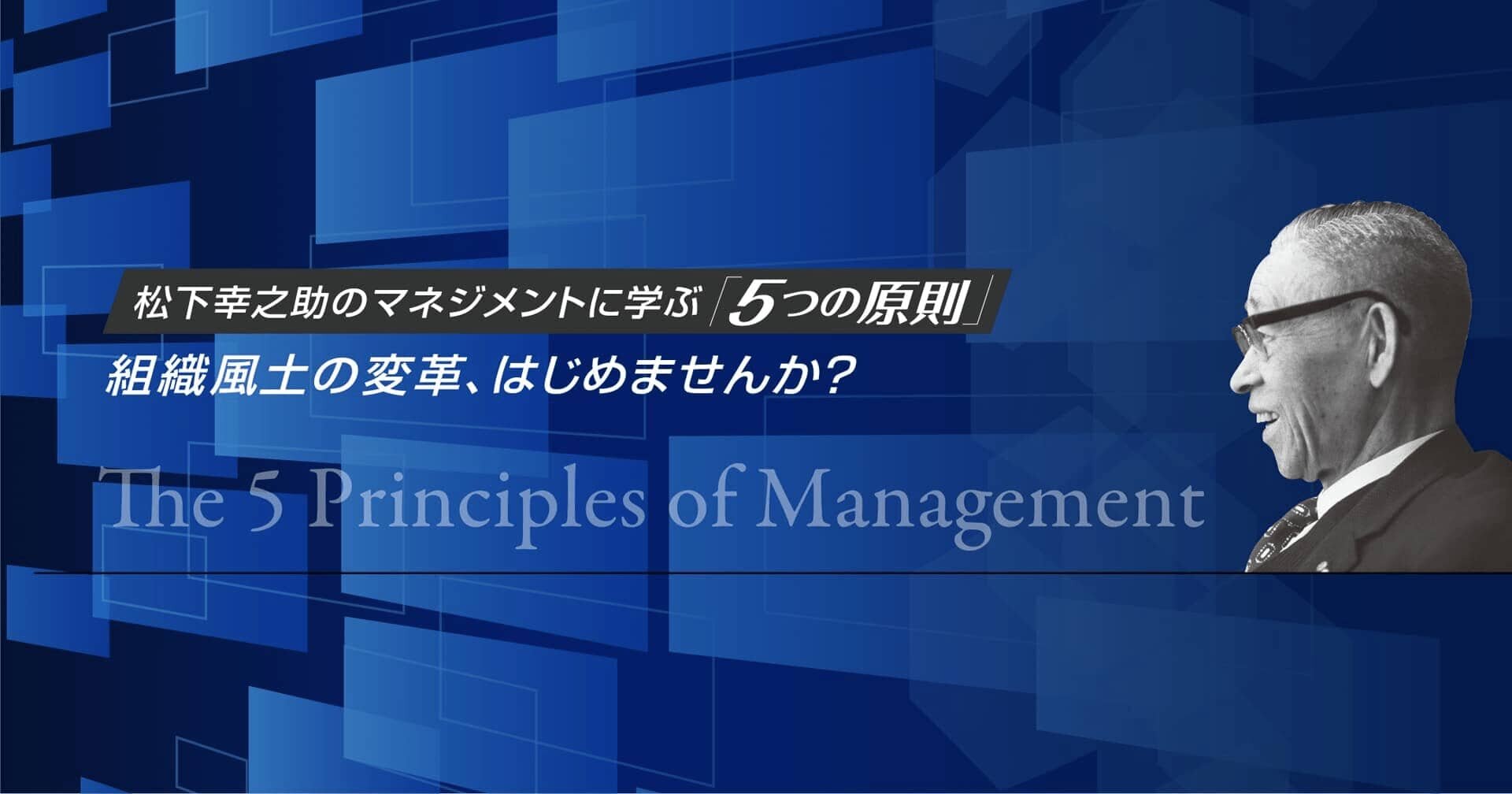



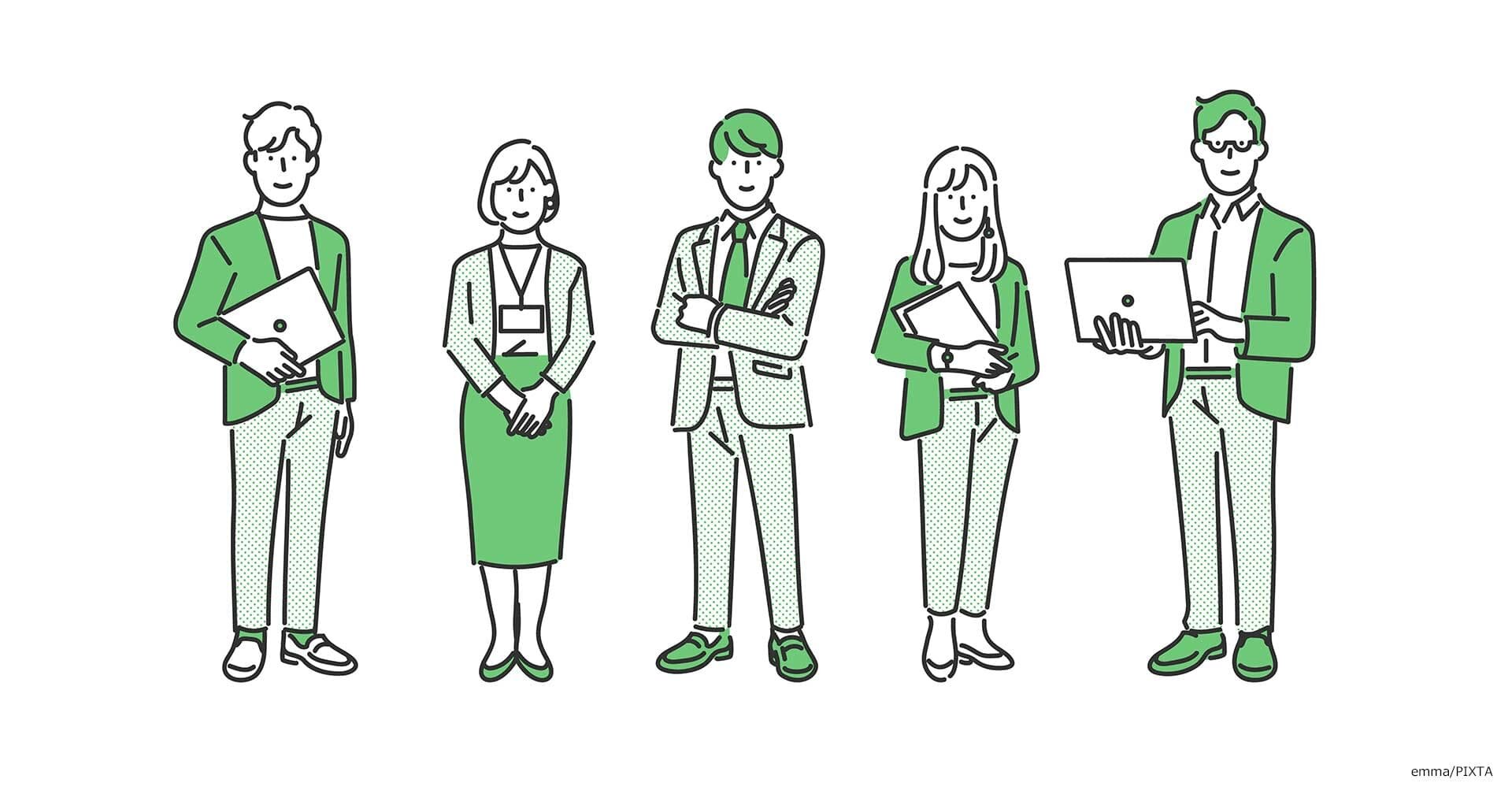





























































![【インターネット添削版】[新版]仕事の基本とビジネスマナー](/atch/tra/AAH.jpg)
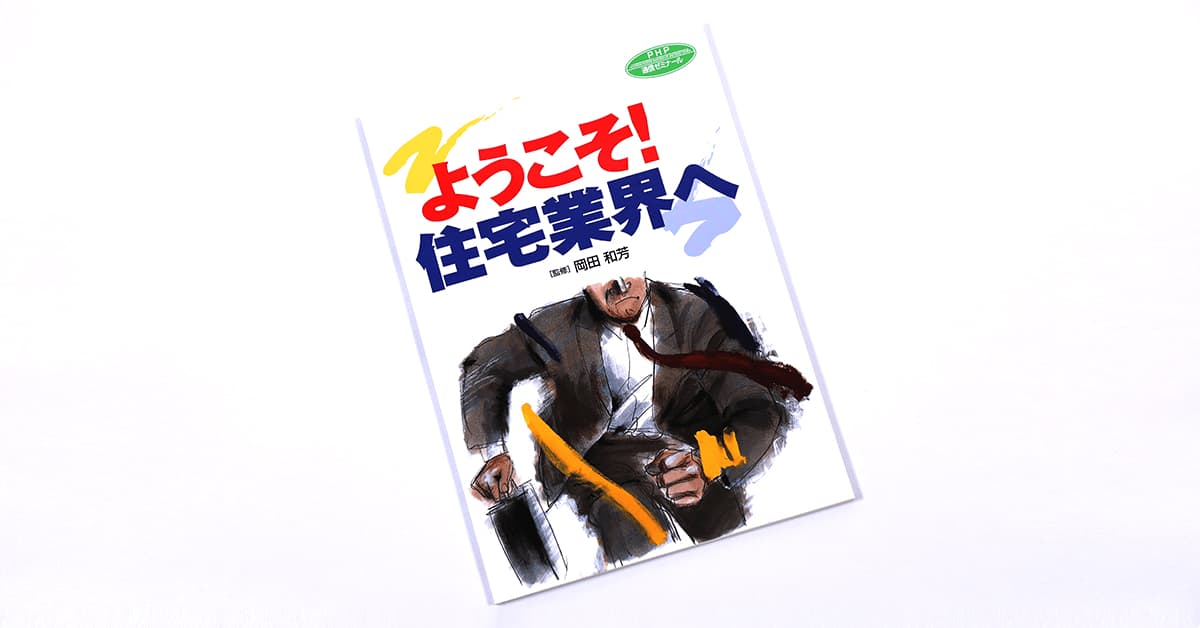




![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)














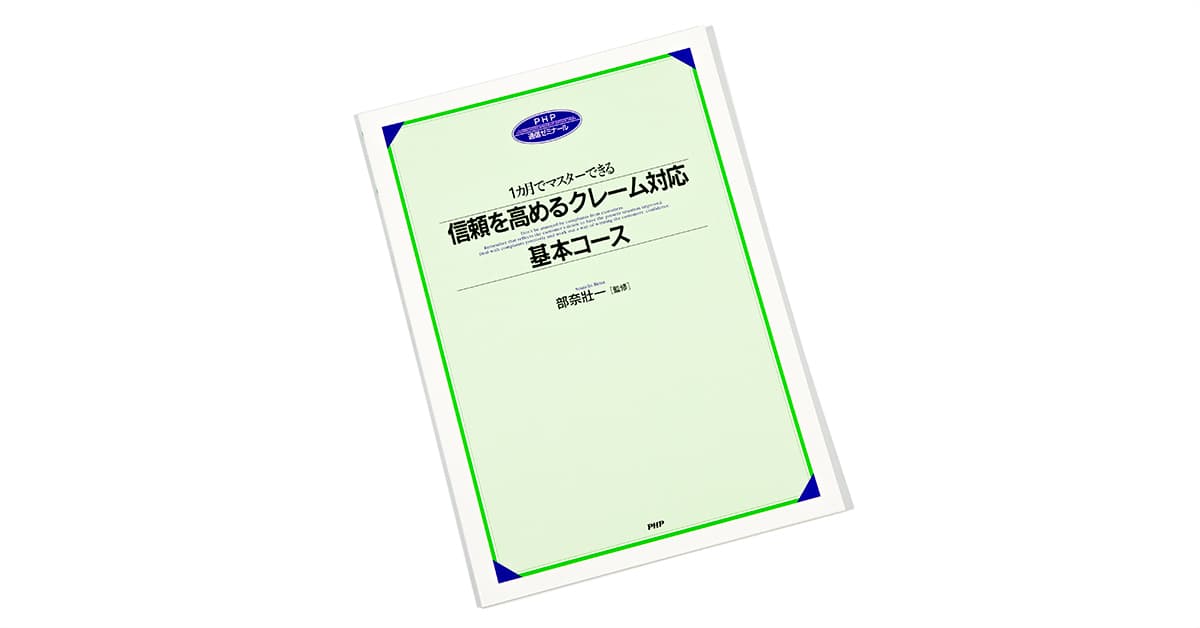





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)
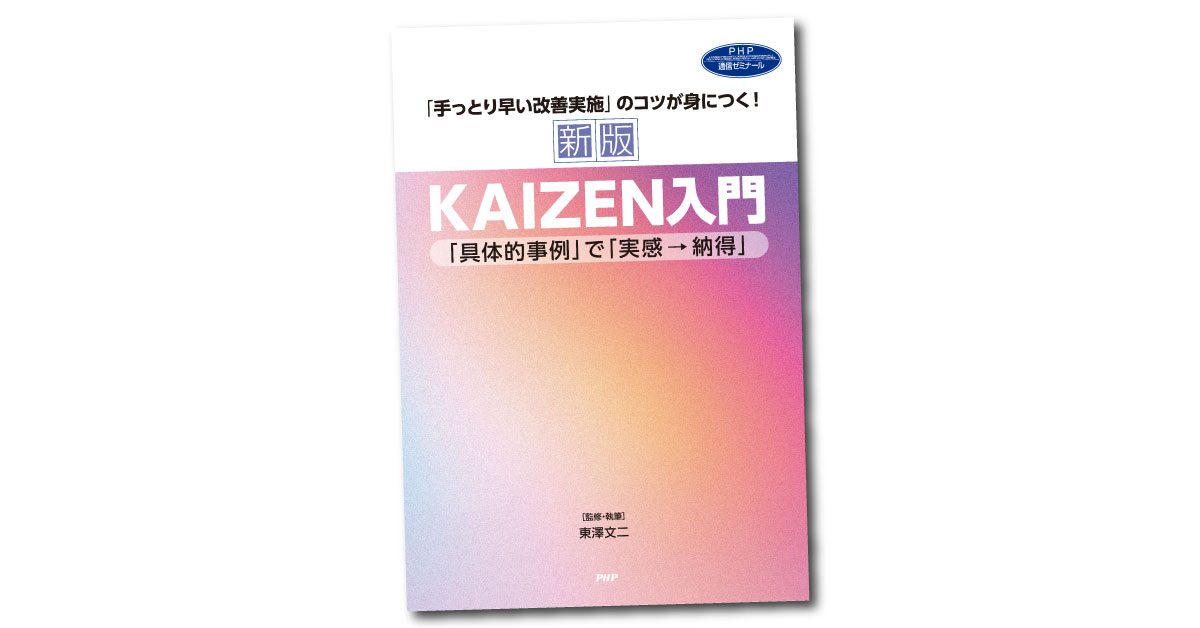











![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


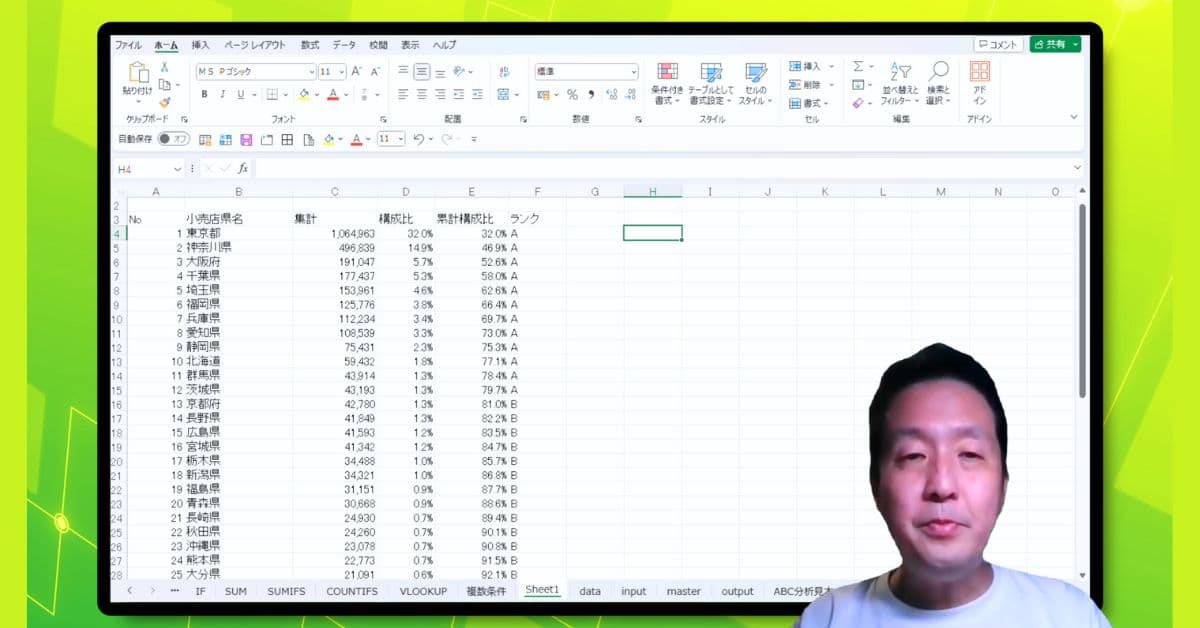
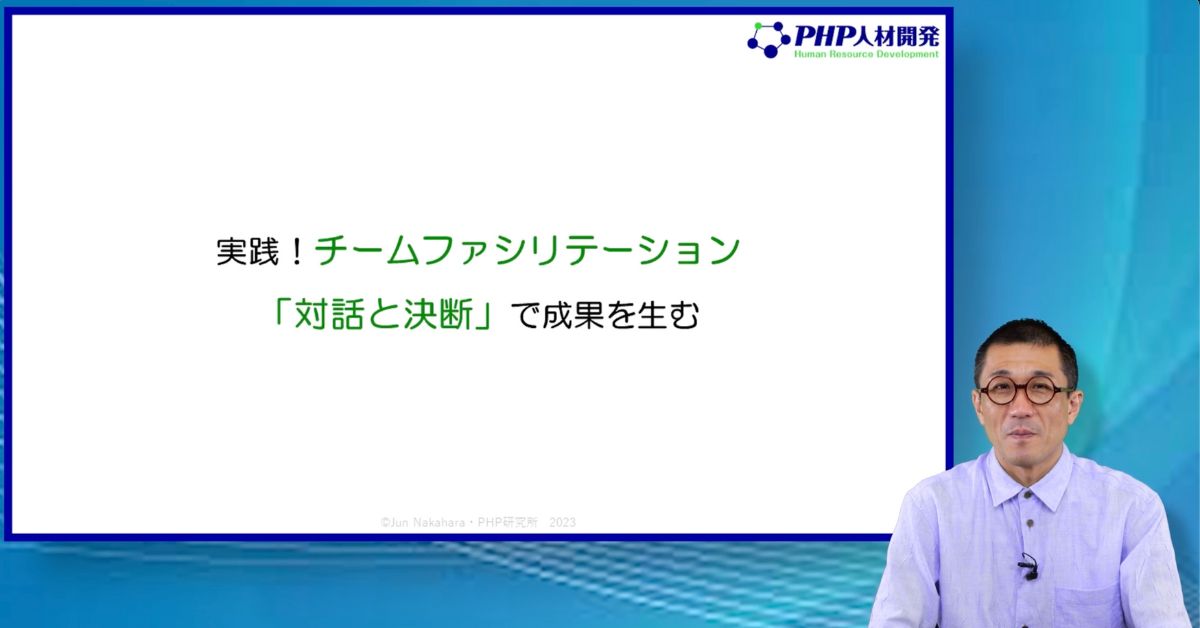
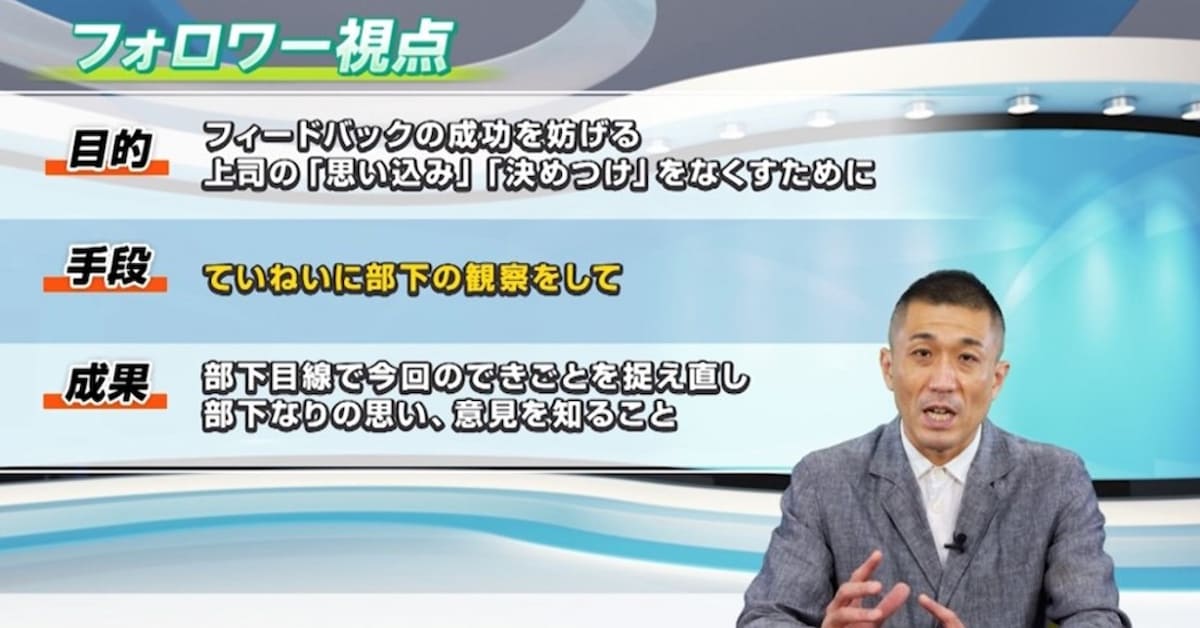


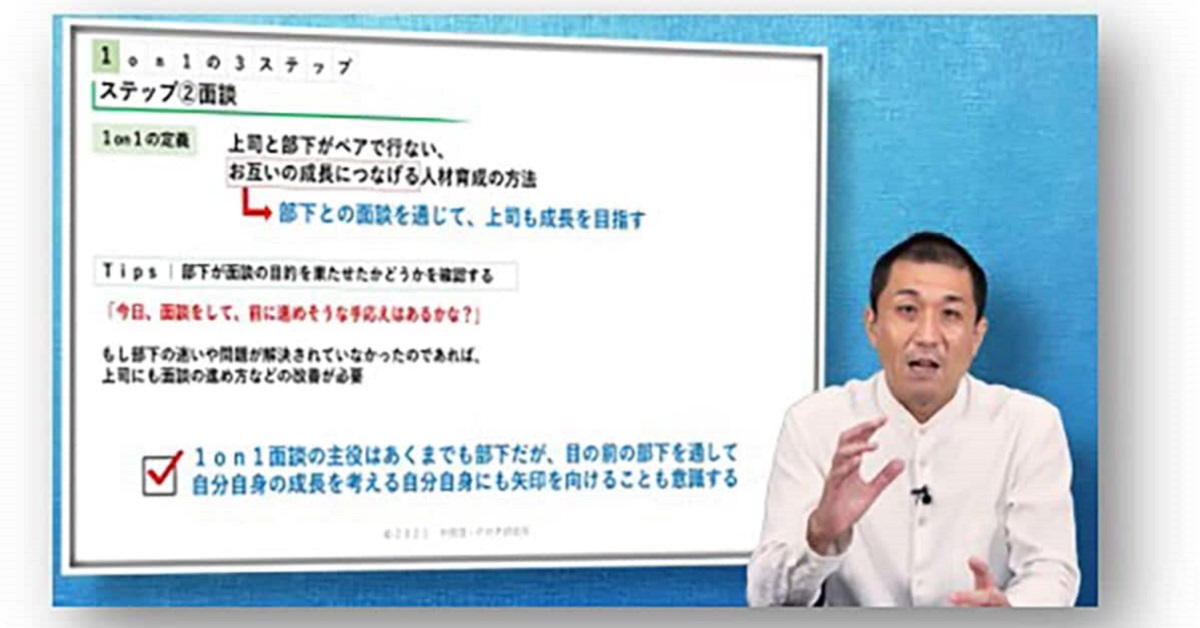

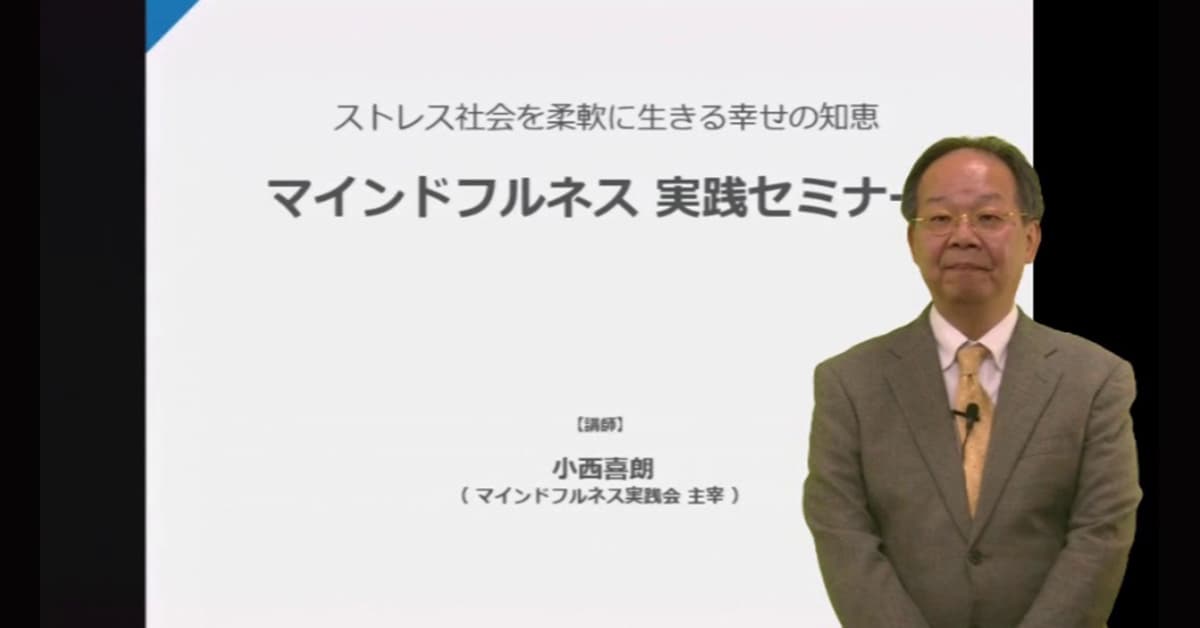

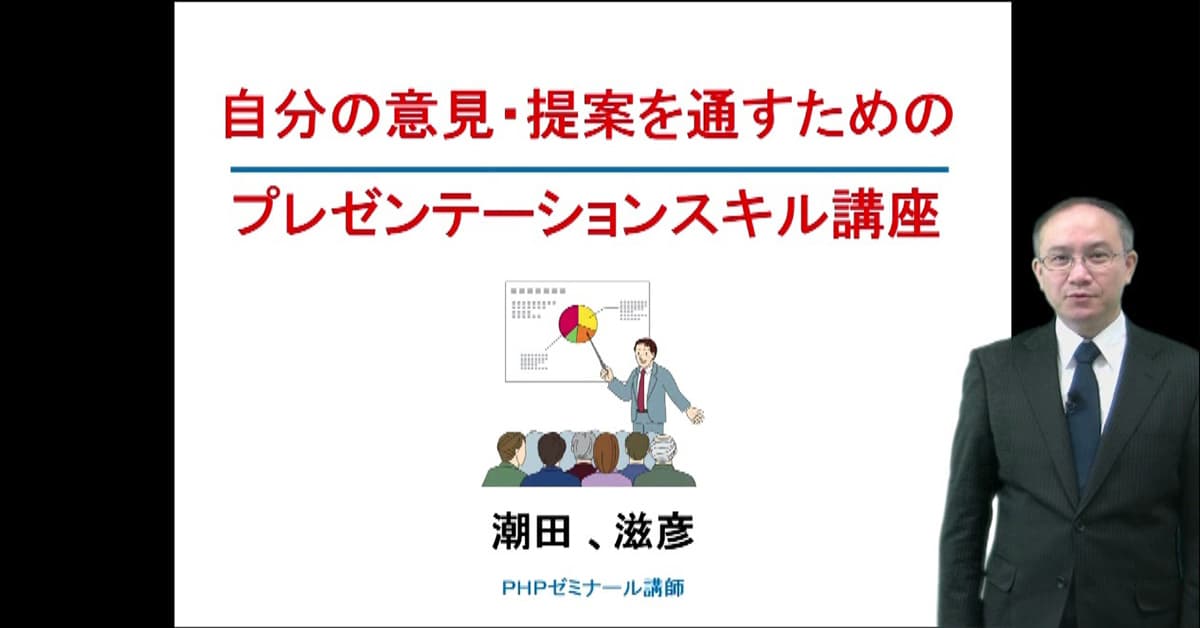
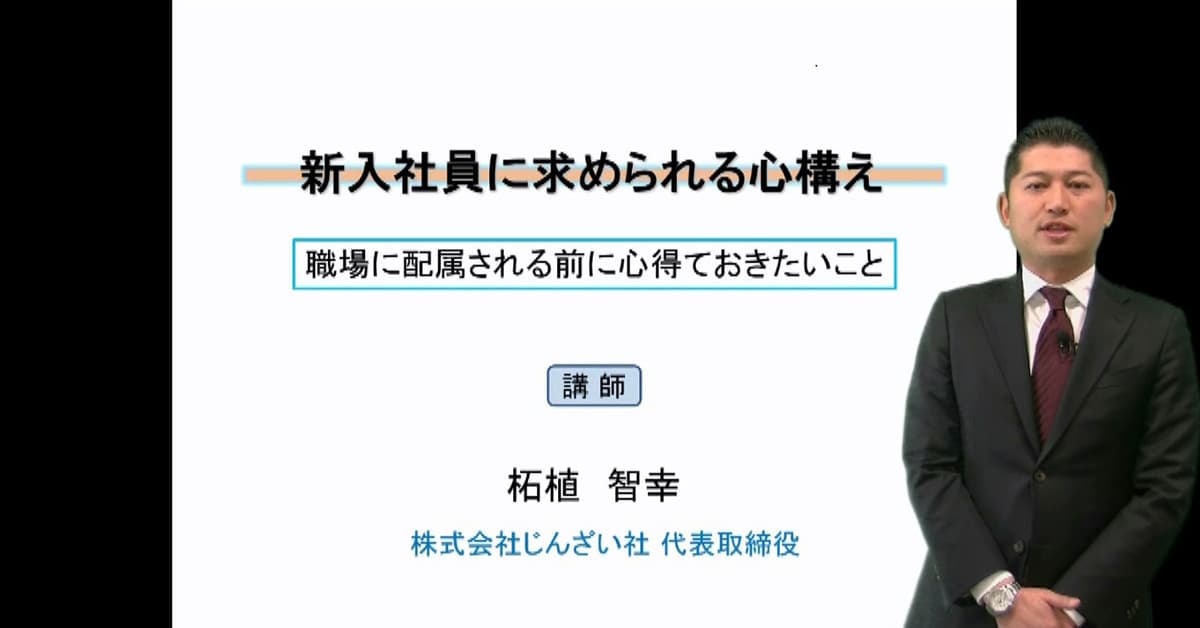
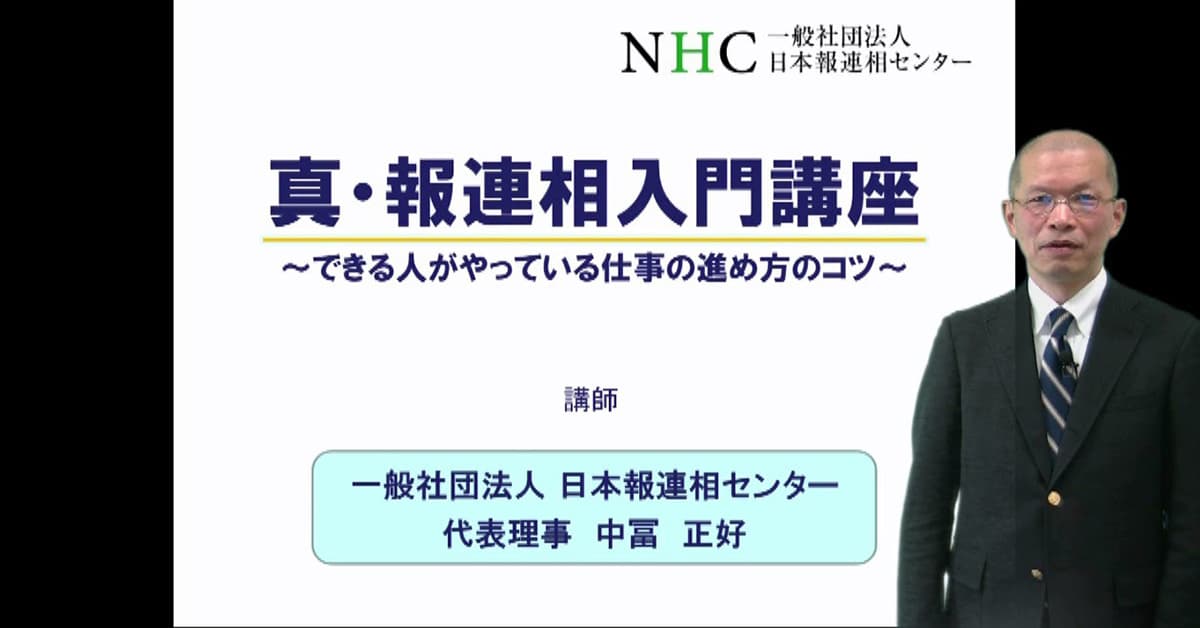
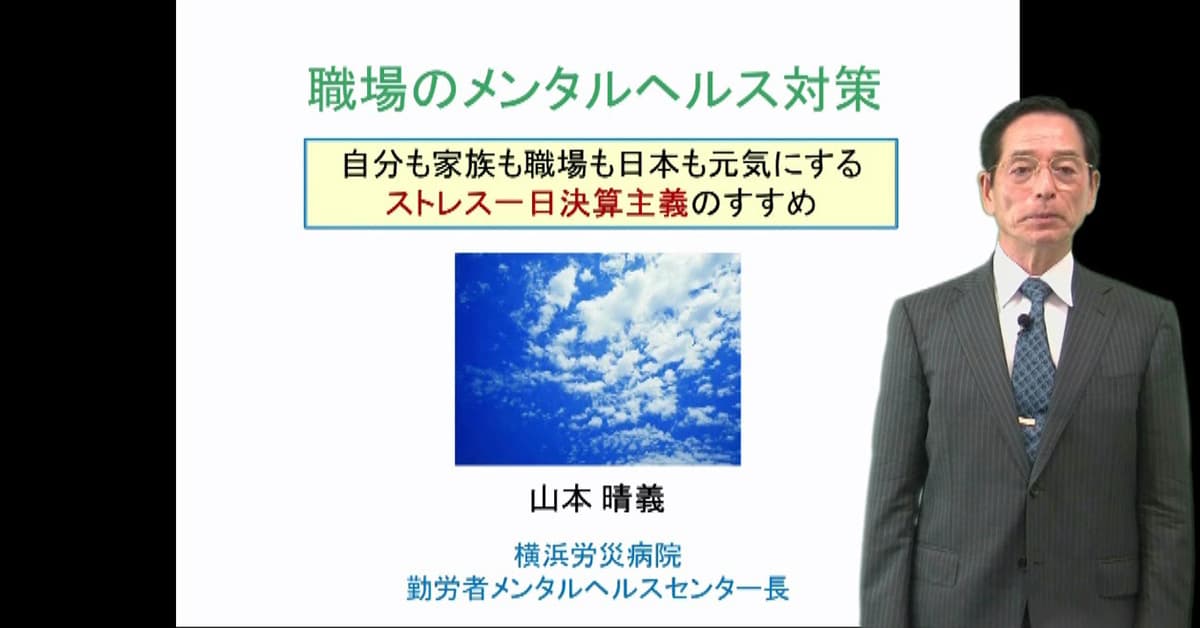
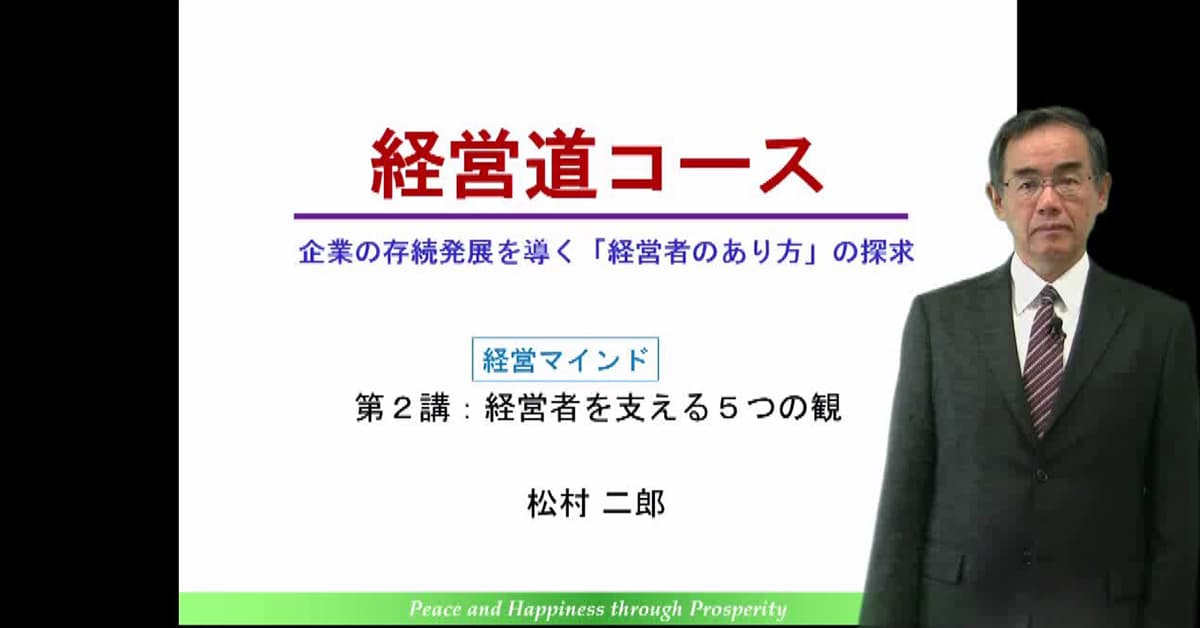
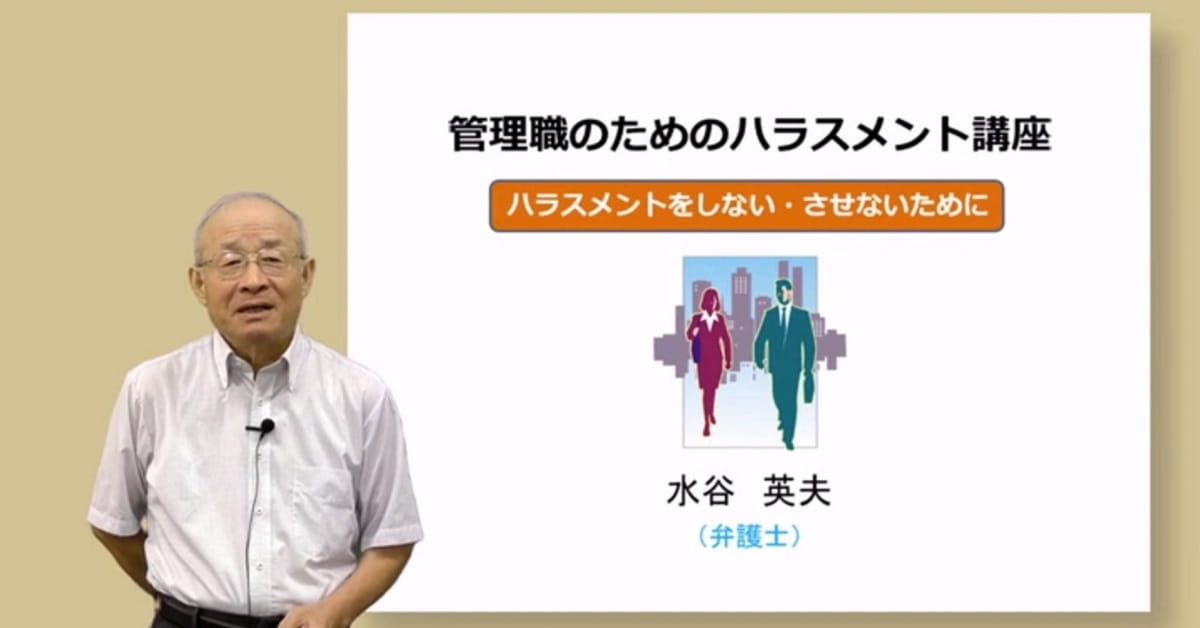

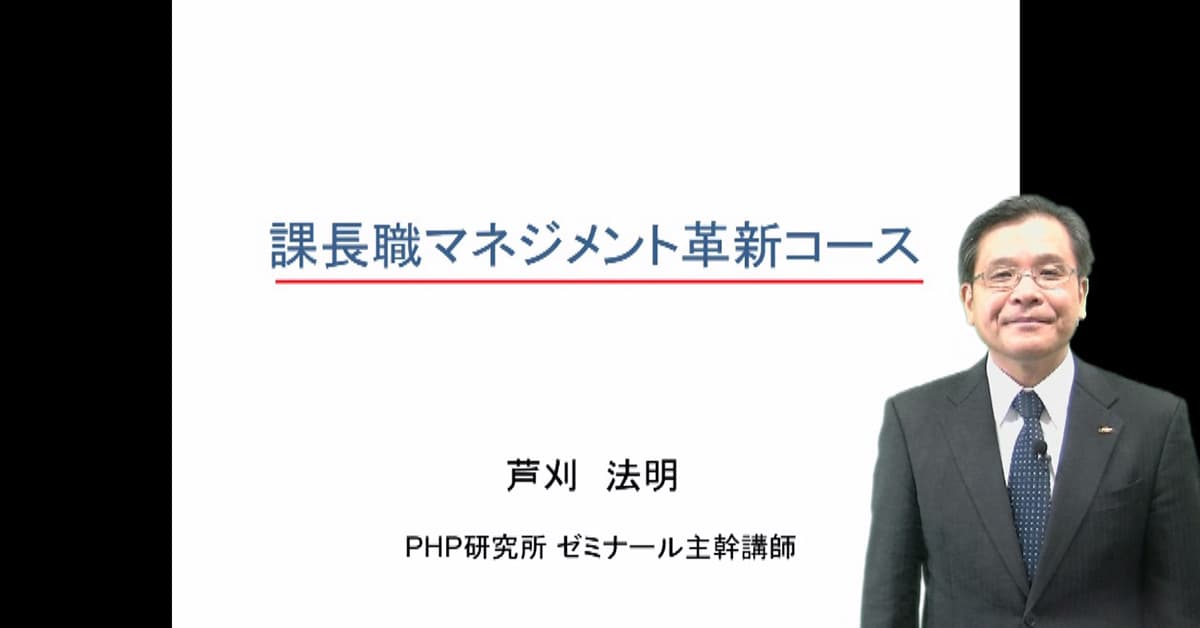


![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)


















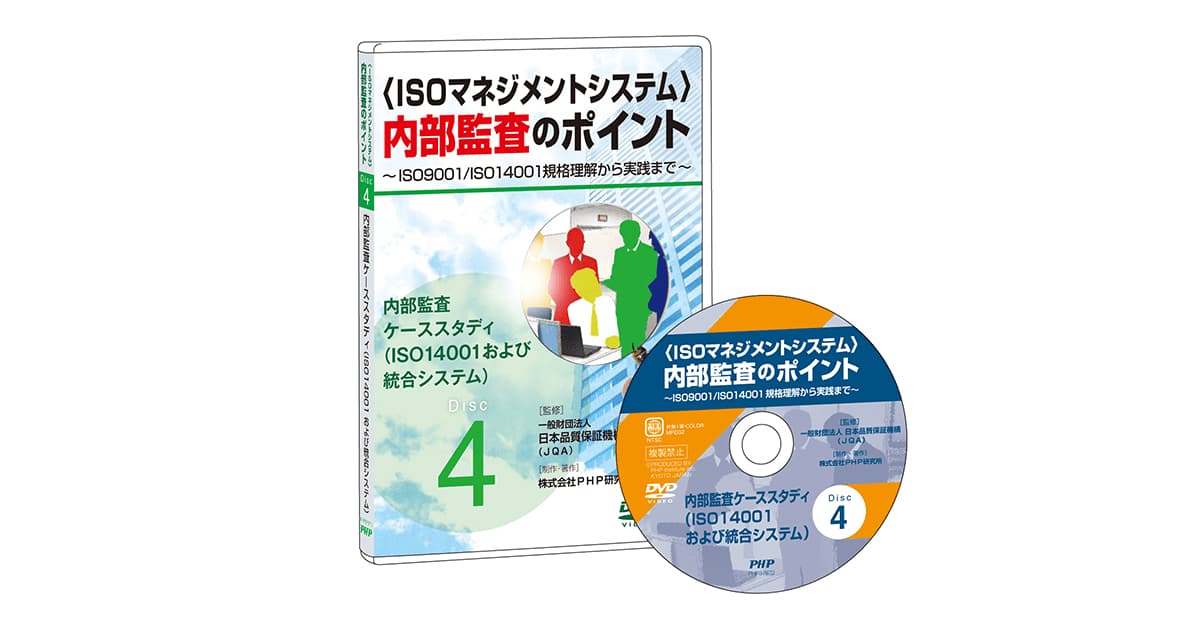





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
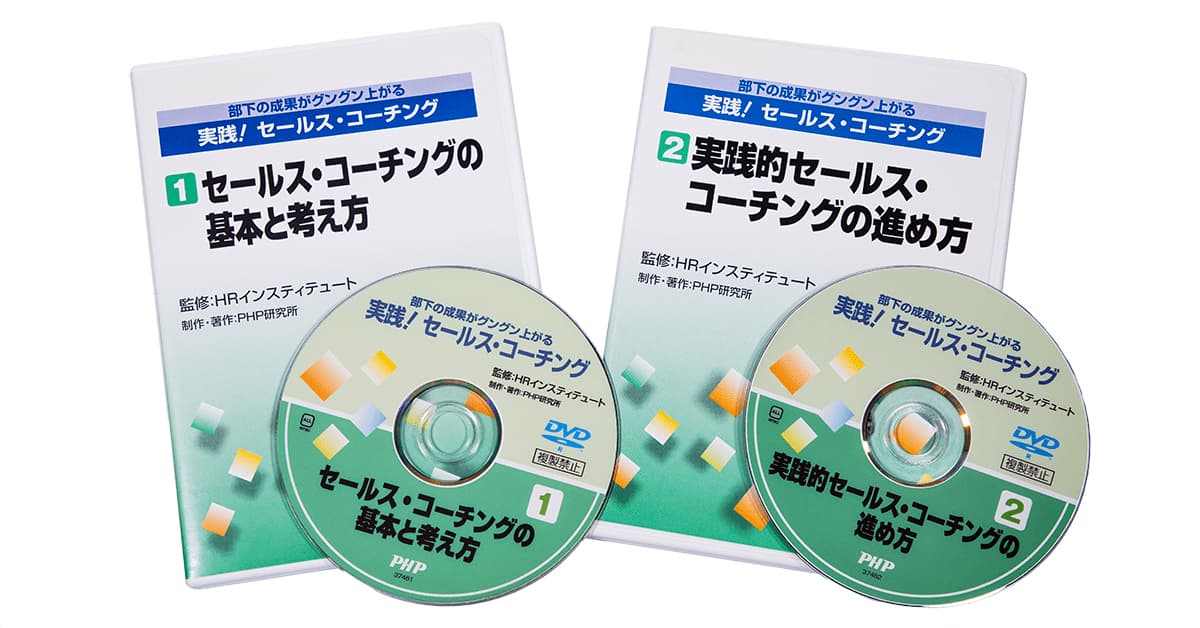

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)










![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)