残業削減と有給休暇取得への仕組み
2014年10月15日更新

* * *
参考になる欧州の法律の安全管理基準
フランスの「労働日数上限」は究極の時短手段
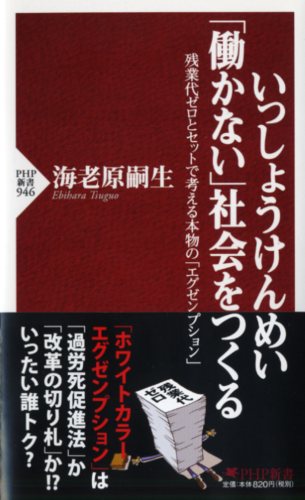
松下幸之助創設・PHP研究所の人材育成サポート
階層別教育のご提案
経営者/幹部育成
管理職(マネジメント)研修・教育
中堅/若手社員研修・教育
2024 新入社員研修・教育
内定者フォロー/研修・教育
公開セミナー・講師派遣
階層別コース

PHP経営道コース~松下幸之助に学ぶ

田村潤の実践経営塾

取締役実践講座

部長研修 部長力強化コース(2日)

【オンライン限定】部長研修 部長力強化コース(1日)

人間力強化研修~部長・課長のためのパワーアップ講座

課長研修 マネジメント革新コース(2日)

【オンライン限定】課長研修 マネジメント革新コース(1日)

プレイングマネジャーのための目標達成マネジメントコース(1日)

係長研修 行動革新コース(2日)

【オンライン限定】係長研修 行動革新コース(1日)

中堅社員研修 意識革新コース(2日)

【オンライン限定】中堅社員研修 意識革新コース(1日)

若手社員研修 仕事力アップコース(2日)

【オンライン限定】若手社員研修 仕事力アップコース(1日)

《セット受講》新入社員研修 フォローアップコース

新入社員研修 フォローアップコース

2024 新入社員研修 「愛される」社会人になるために(3日)

【オンライン限定】2024 新入社員研修(2日)
テーマ別コース
長期コース
講師派遣/研修コンサル
ビジネスコーチ養成・資格
通信教育・オンライン
内定者/新入社員
若手/中堅社員
管理職/リーダー
ビジネス全般
営業/販売/サービス
製造/技術
食品
《法人対象》社員研修・教育
《個人受講》ビジネススキル
DVD・テキスト他
新入社員
若手/中堅社員
管理職/リーダー
製造/改善/安全
営業/サービス/CS
コンプライアンス/ハラスメント
経営
メンタルヘルス/健康
食品衛生
事例・カタログ
2014年10月15日更新

* * *
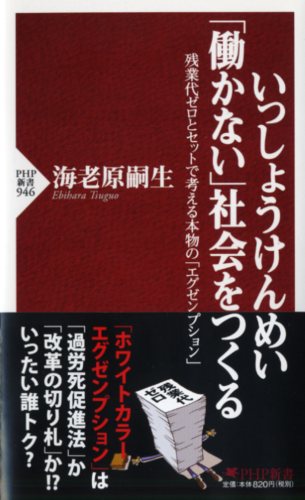

コンプライアンス研修の内容、ネタはどうする? 効果的な実施方...

人的資本経営とは? そのメリットや推進方法を具体的に解説

自己認識(セルフアウェアネス)とは? 意味やメリットを解説
階層別教育のご提案
×
当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は以下をご覧ください。
クッキーポリシー





