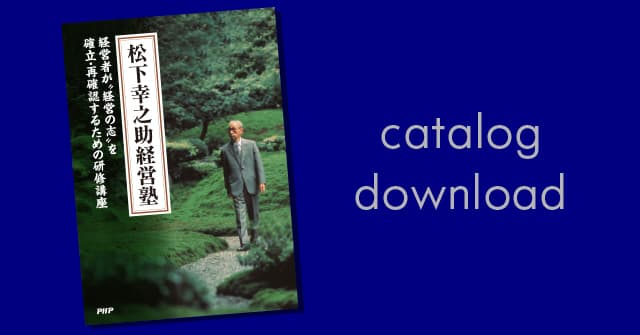大河内正敏の決断~科学者の楽園・理研コンツェルンを創造
2012年2月 9日更新

資金不足や内紛で混乱を極めた財団法人理化学研究所を、「科学者の楽園」と呼ばれるほどの環境に変え、さらには、特許や技術を自らの手によって事業化して「理研コンツェルン」と称される企業群を設立した大河内正敏。"殿様"のDNAが可能にした、その決断の背景に迫る。
明治維新以来、欧米に追いつき、追い越せと精進してきた近代日本の科学界。大正期に入って、国家の威信をかけた飛躍のためには、さらなる基礎科学力こそ必要だとして設立されたのが、財団法人理化学研究所である。
しかし、その運営は大正六(一九一七)年の設立当初から資金不足や、それに伴う物理部と化学部の対立等によって内紛が続くなど課題山積であった。第二代所長は職を辞し、混迷を極めたなかで登場したのが、東京帝国大学工学部教授で四十二歳の工学博士、子爵貴族院議員の大河内正敏であった。第三代所長となった彼は、優れた政治力を発揮して、研究所を「科学者の楽園」と呼ばれるほどの自由な環境に整えた。
大河内のもっとも画期的な決断は、研究者の発明によって工業化が期待される特許や技術を、自らの手によって事業化し、矢継ぎ早に「理研コンツェルン」と称される企業群を設立したことである。類を見ないコンツェルンを創造した大河内の決断の背景とは何だったのだろうか。
ベンチャー企業の元祖
理化学研究所がいかに優れたシンクタンクであったかは、所属した科学者の名前を挙げ連ねただけでも理解できる。世界で初めてビタミンを発見した鈴木梅太郎、原子モデルの世界的物理学者長岡半太郎、強力磁石鋼の権威本多光太郎、いずれも世界的な科学者として文化勲章を得た彼らは"理研の三太郎"と呼ばれた。また異色の実験物理学者であり名随筆家としても知られる寺田寅彦、雪の研究者中谷宇吉郎、原子核の世界的権威者仁科芳雄、のちにノーベル賞を受賞する朝永振一郎ら多士済々であり、大河内自身も造兵学科で弾道学の権威だった。
もともと理化学研究所は、アメリカから帰国したジアスターゼの発見者高峰譲吉が、科学立国の必要性から国民科学研究所構想を提唱し、それに賛同した政財界の補助金、寄付金、また皇室からの御下賜金により資金的基礎を得て財団法人として実現したものであった。ところが、初代所長菊池大麓は就任五カ月で病没、そこへ第一次世界大戦による不況と、財政難、内紛が重なり、二代目所長古市公威も早々に心労からか体調不良を以て辞表を提出し、運営はますます窮地に立たされた。
ここで第三代所長として起用されたのが大河内正敏である。設立の翌年大正七(一九一八)年に入所していた大河内は、大正十(一九二一)年に所長に就任するや、研究員総会を開き、研究者の結束を呼びかけた。そして、政府に対して国庫補助金増額を申請して財政難の解決を図る一方、研究体制の確立のために、大正十一(一九二二)年、「主任研究員制度」を導入した。これは各研究室を独立させ、研究テーマ、予算、人事までも主任研究員職の裁量にすべて委ねるという画期的なものであった。他の大学教職との兼務、研究室を外部に求めることさえ自由だった。理化学研究所が「研究者の楽園」といわれたのもこうした制度によるもので、これにより懸案だった研究員間の対立は雲散霧消した。健全な意味での研究者同士の競争心は残り、プラス効果に転じた。
しかし、こうした自由、とくに研究費の自由を認めたとあっては、補助金の増額など何の解決にもならず、ふたたび深刻な資金難に陥った。ここで、大河内は重要な経営的決断をする。
すなわち、基礎研究の成果となる諸々の特許や技術を民間企業に委託せず、理化学研究所自らの手で工業化し、研究資金を得ようとしたのである。これが理化学興業をはじめとする理研コンツェルンの始まりである。先端技術を事業化するのは今日的なベンチャー企業の走りであろう。
さて、ここで重要な疑問が二つ生じる。大河内はなぜ研究所自らの手で事業化を図ったかということである。そして、もう一つの疑問は、もしそれが大河内しか為し得ない企業家精神の発露と位置づけられるものならば、人間大河内のどのような部分がそうした決断を後押ししたかということである。
大河内の華麗な出自
そもそも大河内正敏とはどのような出自の人間か。
大河内は明治十一(一八七八)年、旧大多喜藩主大河内正質の長男に生まれ、明治三十一(一八九八)年に本家にあたる旧吉田藩子爵大河内信好の妹一子と結婚し、養嗣子となっている。大河内家は島原の乱を平定した松平伊豆守信綱の子孫であり、華族であった大河内はまさしく"殿様"で自邸内でもそのように呼ばれていた。幼少時には大正天皇のご学友に選ばれ、利発だった大河内は明治天皇に愛され、膝の上で何度も抱かれたという。
東京帝国大学工科大学を首席で卒業し、母校の講師に就任。その後、子爵、教授昇格、工学博士号取得、貴族院議員当選と、華麗な経歴は続く。しかも貴公子然としていて一八〇センチの長身である。のちにリコー・三愛グループを創業する市村清は、大河内の知遇を得て理研の代理店を託されたことから実業家として大成したが、彼による大河内評は、「何が不幸であったかといえば、何一つ不幸がなかったということが一番の不幸だったのではなかろうか」というものであった。
その上、芸術家として陶磁器の目利きと研究にかけては一流であり、著書は十冊以上、古九谷、鍋島、柿右衛門の芸術性は大河内の評価によって確立されたという。また日本画家でもあった。趣味人としても当代きっての食通である。たとえば美術雑誌に鰻についてこう書いている。
「店先で先客の注文を燒いてゐる、先づその奥で味覚をそゝられ、待つ間に聞こへて來るばたばたといふうちわの音で、今燒いてゐるのだなと二度目の味覺を思ひ起させ、さんざん待ったあとでやきたての熱いのを喰べるから、そこに云ひ知れぬ味があつたものだが、何人前かの蒲焼が大きなすし皿のやうなものに盛られ、店先きの硝子戸棚に出されてゐたのでは、いくら冷えずにいたとしても、うまさ加減に大きな違ひがある」(「色鍋島と鰻の大串」)
戦後A級戦犯容疑で逮捕され、巣鴨拘置所にいた間に、無聊を慰めつつ獄中メモも資料もないなかで著書『味覚』を書いたのも頷ける。当然のことながら料理の腕も玄人はだしであった。
大河内のこうした人となりが、理化学研究所の運営と理研コンツェルンの創成に大きく寄与したことは言うまでもない。理化学研究所の科学者たちには、絶大の信頼があった。何しろ研究費は自由自在、また発明に対しては多額の報奨金を与えたのである。大河内は日々各研究室を訪れ、研究経過を聞きたがった。実験を重視し、重要な実験を重ねる部屋には一日に何度も訪れたという。現場主義・現実主義、それは大河内の行動原理の重要な特性だったようである。
理研コンツェルンの発展
理研コンツェルンの創成は、昭和二(一九二七)年に三菱、住友財閥の出資を得て設立された理化学興業の誕生からはじまった。大河内が会長に就任し、財団法人たる理研が筆頭株主であった。理化学興業は、理化学研究所の発明・発見・考案を工業化し、生まれた製品を販売し、特許や許諾の仲介をするなど、理化学研究所のための会社であり、その利益もほとんどが研究所に還元された。もちろん大河内の意向によるものである。
大河内の企業家としての手腕はさまざまな面で見られた。
最初のヒット商品は、鈴木梅太郎研究室が肝油からビタミンを抽出したことによって誕生した「理研ビタミンA」であったが、大いに売れた。途中、警視庁から「ビタミンA」は学名であって商品として不適格との横槍が入った。すると大河内は動じることなく、「ならばAを取ろう」とすぐに「理研ビタミン」と商品名を変え、商品力はかえって高まった。こうした難局を打開する機転は見事であった。
また、鈴木梅太郎が開発した、米を必要としない合成酒の開発・製造、そして自らの研究室からも航空機産業に不可欠なマグネシウムの工業化、さらに内燃機関の主要な構成部品であるピストンリングの開発のために、理研マグネシウムと理研ピストンリングを設立するなど、理化学興業の事業拡大は急速に展開された。新たな企業群の設立は「芋蔓式経営」と呼ばれるに至った。すなわち、高度な技術は生み出す成果が農業なり工業なりに芋蔓のように繋がって新しい事業を産む。またその真意は、通常大量生産がかなわないことから赤字に陥る事業を、副産物までも工業化する目星をつけ、主製品と副産物の総体で黒字化できるまで拡大して展開しようという意図にあった。
このように拡大した理研コンツェルンは最盛期(昭和十四〔一九三九〕年)には、会社数が六三、工場数は一二一にのぼった。経営センスとリスクを恐れない決断力の賜物であろう。
もう一つ経営力を感じさせるのは、人材のマネジメントである。
大河内自らは理研コンツェルン各社の会長を兼務しながら、理化学研究所の研究員が経営に関わることを禁じた。研究者は研究こそ目的とすればよいのであって、利潤を研究の主眼としてしまうと、理研コンツェルン全体の目的、技術立国に寄与する意義を失うからだという。大河内は入所した新人研究員が「自分の研究は役に立たないかもしれない」としり込みするのに対し、「科学者の良心に基づいて自由に研究すればよい」と励ました。
大河内は専門経営者の発掘においても経営者ぶりを見せ、人材抜擢を重ねている。先にふれた市村清の例がある。市村は熊本で保険の外交員をしていたが、ふとした縁で理化学興業が製造する理研感光紙のことを知り、その将来性を見込んで代理店としても関わろうと近づいた。そして、実績を積んで理化学興業の九州総代理店を請負うまで成長したにもかかわらず、契約時における理研側の消極的な姿勢に不満がつのった。そこで市村は上京し、総帥たる大河内に直談判に及んだ。出張中の大河内に近づき車中に相乗りして、熱弁をふるったという。
大河内は無礼な訴えを黙って聞いたあと、市村の要求をすべて呑み、事業を任せるどころか理化学興業本社に招き、挙句の果ては新設の理研感光紙株式会社の事実上のトップ、専務に抜擢する。キャリアによらず人材を登用する度量を持っていたのである。その一方で、コンツェルン内で不正を働いた経営幹部に対しては手紙一本で首を切った。失敗もあったがこうした峻別ある決断と実行は明らかに経営者の本領発揮であろう。ただ、大河内がこうした強い権限を発揮したことが、グループ企業の経営管理上の人材確保や経営判断につねに大きな不安を残したのも事実であった。
科学主義工業
さて、理化学興業をはじめ理研コンツェルンの誕生は、大河内しか成し得なかった企業家精神の成果という印象が強い。ならば、なぜ大河内がそうした決断を下すことができたかをもう少し深く捉える必要がある。大河内が理化学研究所を自ら事業化させた理由は、民間企業に任せたくない何かの信念があったのではないだろうか。
その答えの一つとして忘れてはならないのは、大河内が自らの経営思想として「科学主義工業」を表明しているところである。社内誌の月報に大河内はこう書いている。
「理化学研究所の理論科学が生む発明と発見、之が工業化を担当する生産工学、之が経営を担当する経営工学、之等を総称して我等は科学主義と呼ぶ。科学主義工業は理論ではなく実践である。実行の伴はない理論こそ科学主義工業の最も排斥する所である。資本の安泰と蓄積のみ希ってその果敢なる利用を好まない資本主義工業に挑戦する科学主義工業は、たゞ科学の命ずる所に向って驀進する。......」
日本は資源の少ない国である。そのハンディを科学技術によって資源を極限までに有効利用することができれば、補って余りある国家的発展も可能になる。大河内のめざすところは、いわゆる科学技術立国である。また科学の発明・発見は連鎖的であることを以て「芋蔓式経営」も正当性があると主張するのである。
そして、文面から窺えるのは、当時の日本の資本主義体制に対する不満である。資本家は科学のもたらす工業化の優位性を理解していない。科学技術の発展を生かす工業経営が確立されなくして、国力は高まらないというわけである。
理化学研究所の悲劇と真のベンチャーとは?
この「科学主義工業」の主張を見てもわかるとおり、大河内のめざした理化学研究所の興隆ならびに理研コンツェルンの成長は、国益、国家的視座に立ったもの。さらに大河内の専門造兵学からすれば、国防意識が強く反映しているとされている。愛国心である。当時の指導者が共有していた国益志向として愛国心を挙げるほか、大河内の決断の理由を考えるとすると、やはり彼のアイデンティティに結論づけざるを得なくなってくる。なぜなら理化学研究所と理研コンツェルンの発展は日本の経営史上でも稀有な現象であり、その特異性を突き詰めると、一個の人間としての大河内正敏のリーダーシップ以外に説明がつかなくなってくるからである。もし別人が第三代所長であったとしたら、理化学研究所はまずシンクタンクの域を出ず、巨大な産業団が生まれることはなかったであろう。
大河内のDNAの本質はやはり"殿様"しかも名君であったということになるのだろうか。人の上に立つことが当然だという気質、華族であることの自負は潜在的に大きく影響していたかもしれない。同じく久留米藩主の子孫であった作家の有馬頼義はいかなる会合でも上座に座るクセがあったという例もある。また愛国心、国粋的な姿勢というのは、やはり明治天皇の寵愛を含め、彼の生育した環境と無縁ではないだろう。この点、彼の企業家精神について新しい議論が必要だと思われる。
大河内の活動は、戦時、高い技術性を有したゆえに、戦時体制のあおりを受けてしまい、理化学研究所は悲劇をたどる。実験物理学の権威・仁科芳雄研究室は軍部から原子爆弾の研究を依頼されたことから、実験施設サイクロトロンを有するに至る。終戦後、このサイクロトロンは米軍に没収され、東京湾に投棄される。同時に、軍事に近かったがために理化学研究所も理研コンツェルンも解体されることになった。この有能な機関が時代の徒花と消えたのは残念なことであった(現在の理化学研究所は昭和三十三〔一九五八〕年に特殊法人として発足)。
また、戦犯の疑いをかけられた大河内は巣鴨拘置所に拘束される。昭和二十一(一九四六)年に釈放されたが、所長の座を追われ、不遇な余生が残った。父正質が鳥羽伏見の戦で幕軍にあったがために幽閉の憂き目に遭ったが、息子もまた同じ経験をしたのは運命的である。
理研コンツェルン各社をベンチャー企業の草分けと見るのは当然であろう。しかし、あくまで研究本位であったという点で大きく異なる。CSR(企業の社会的責任)の欠如が社会問題化されている現代の資本主義のなかで、一攫千金を求めての技術経営など、大河内の目からすればきわめて意義の小さなものに映るに違いない。大河内の前にもうしろにも同じ光彩を放つ経営者がいないことは寂しい限りである。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。










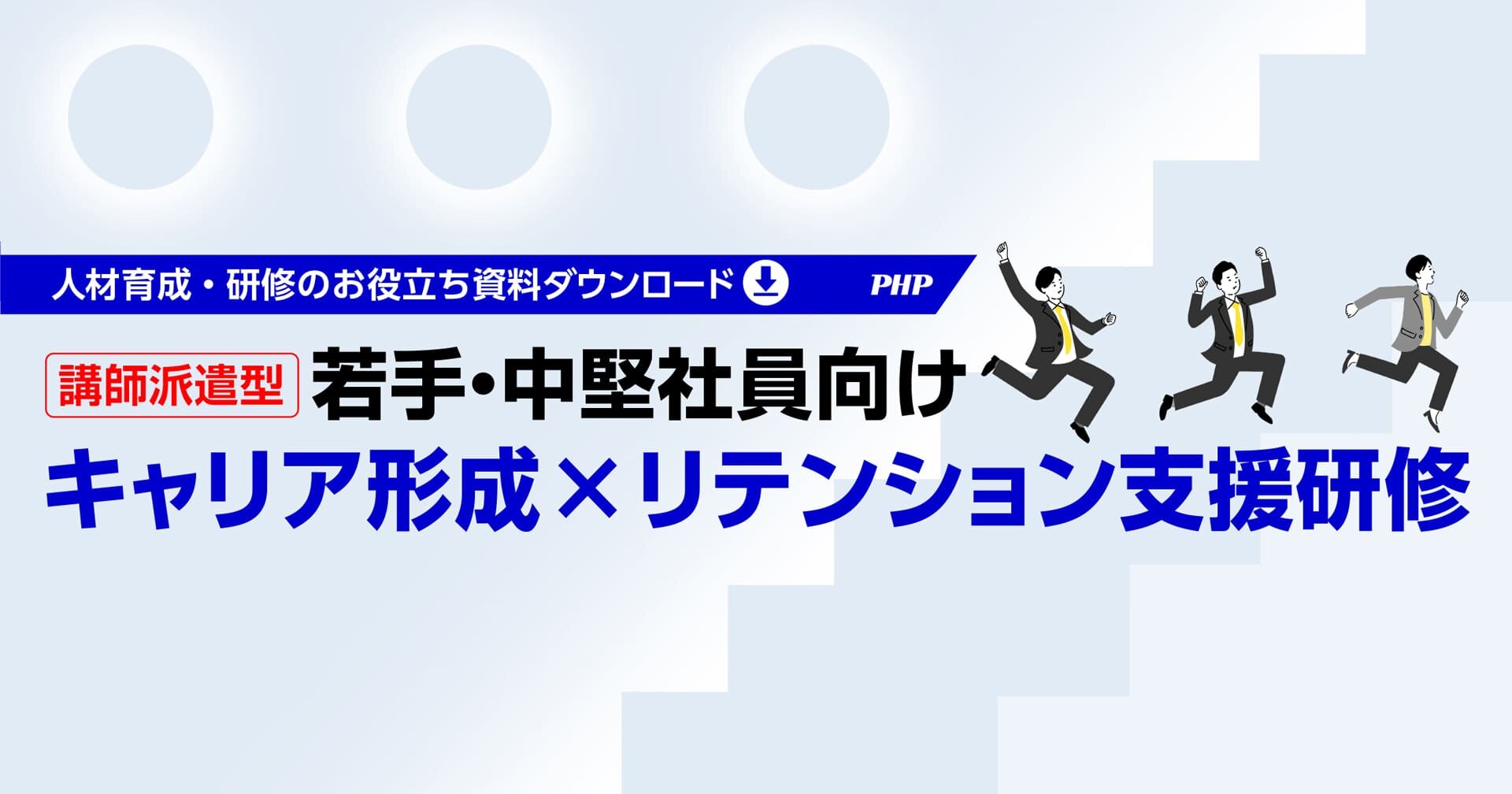















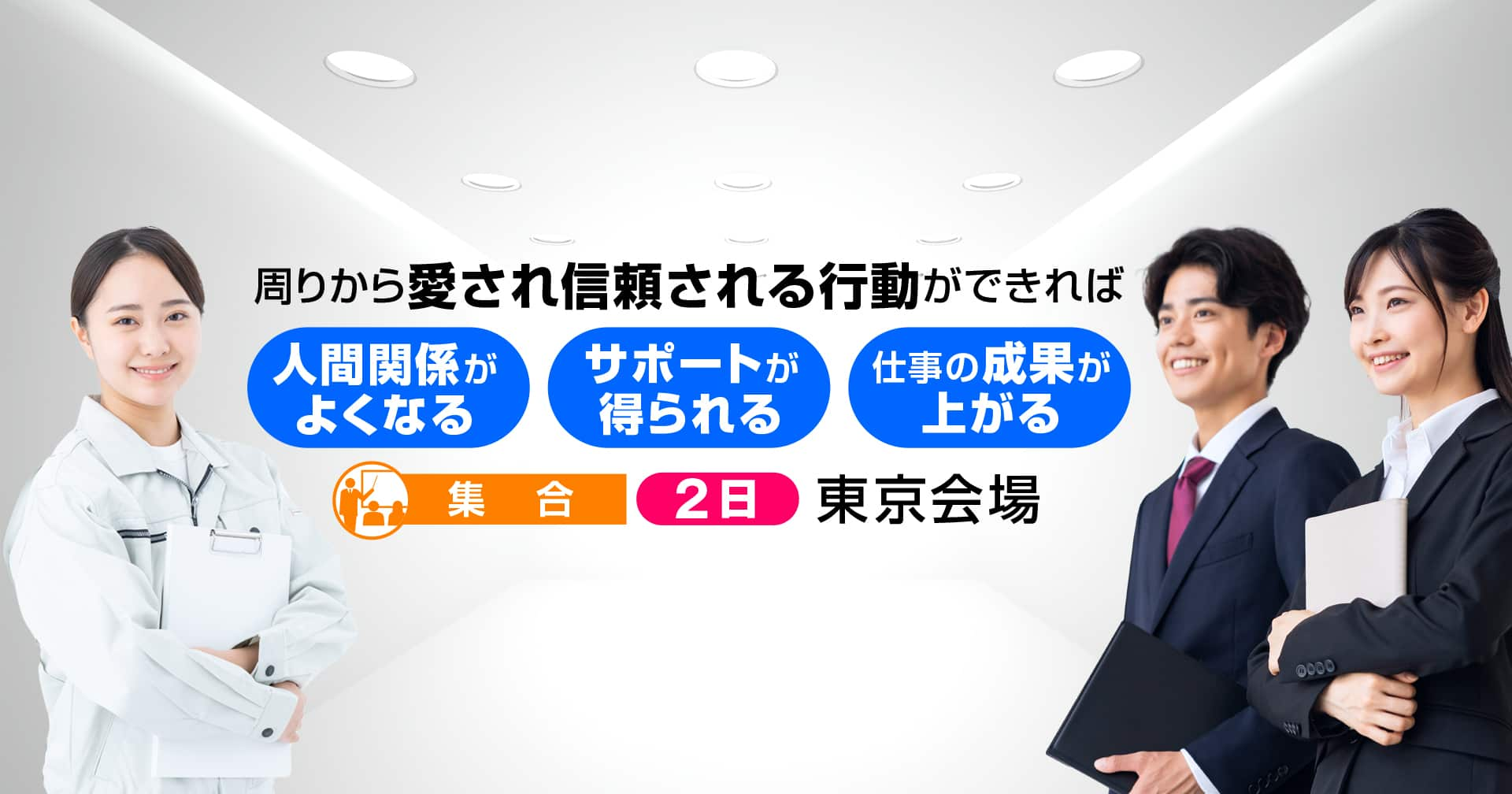










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







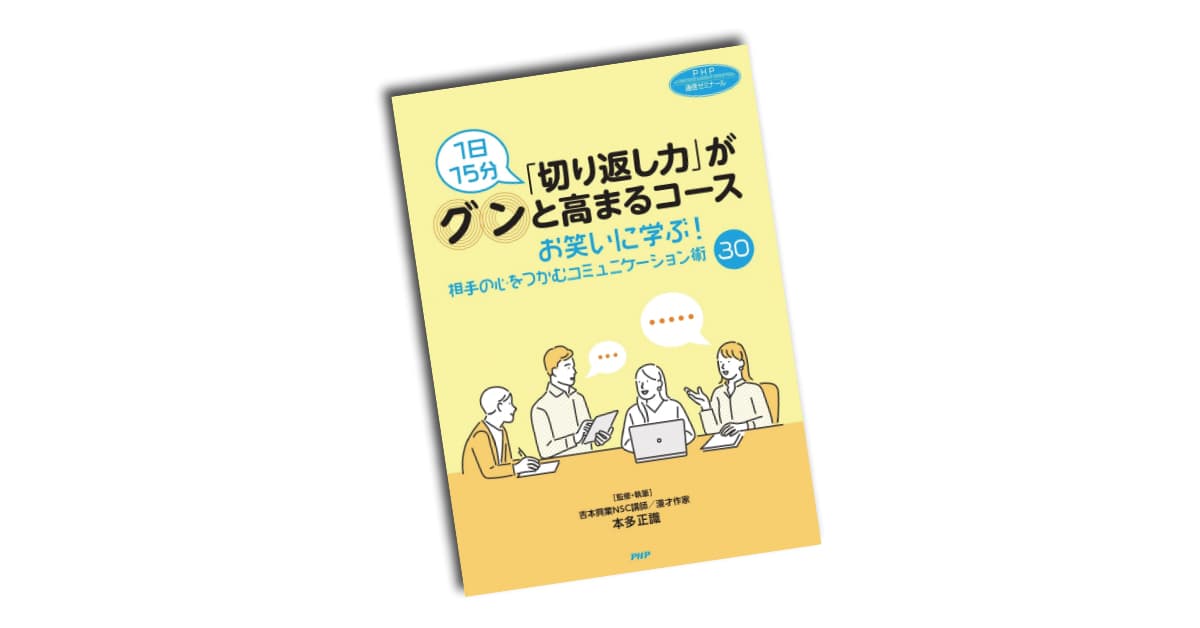






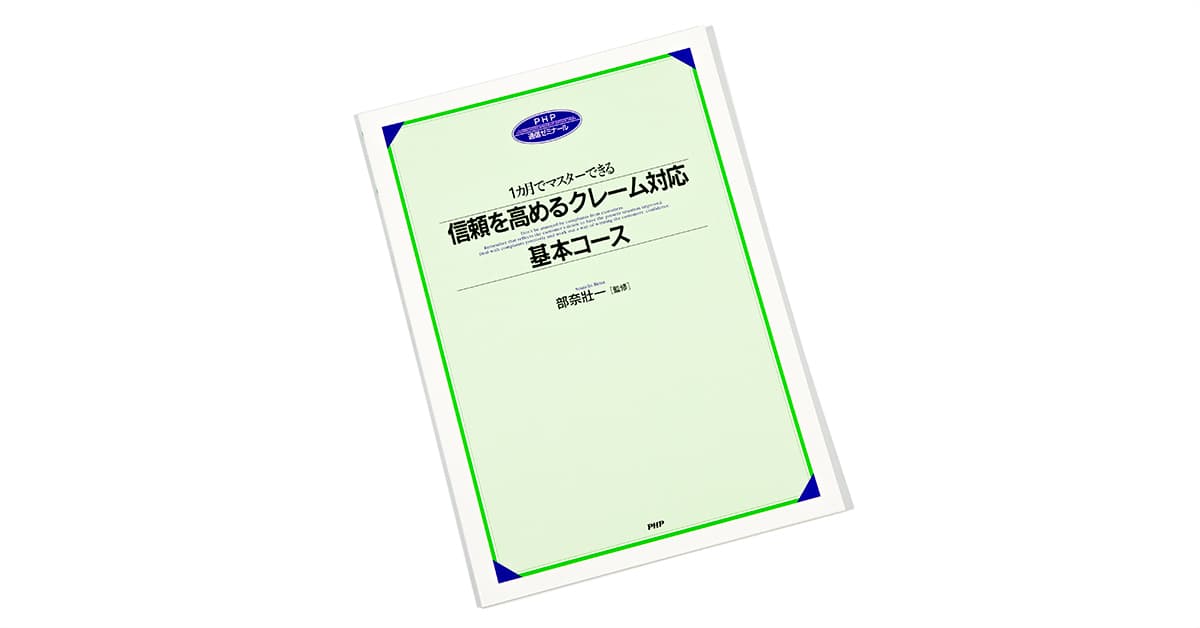





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

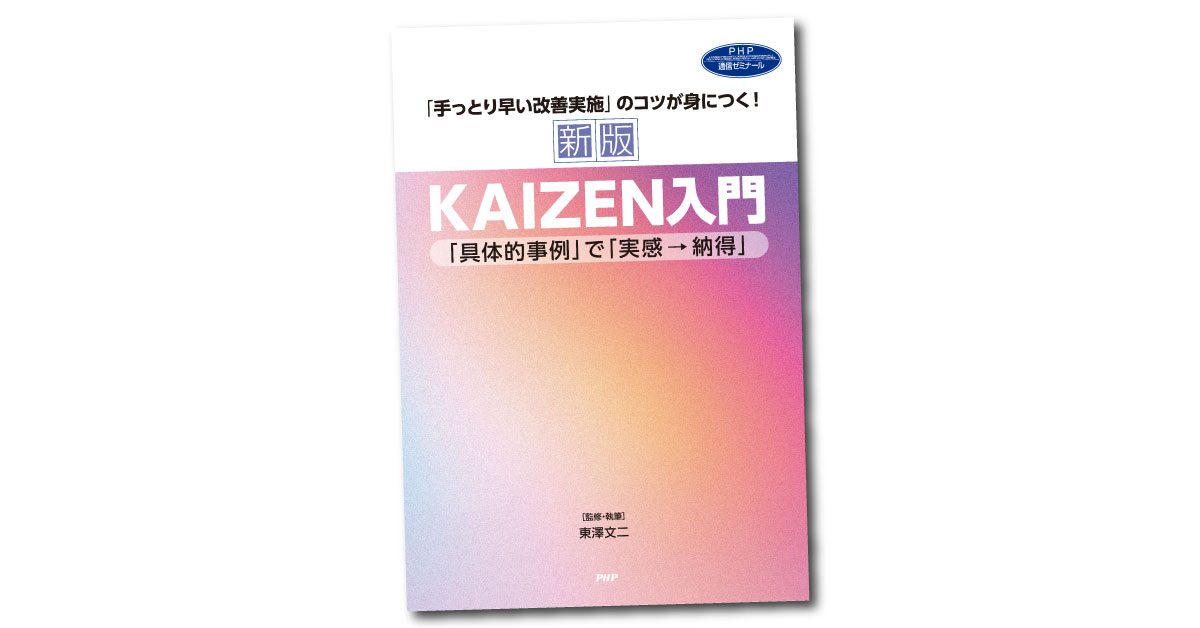










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


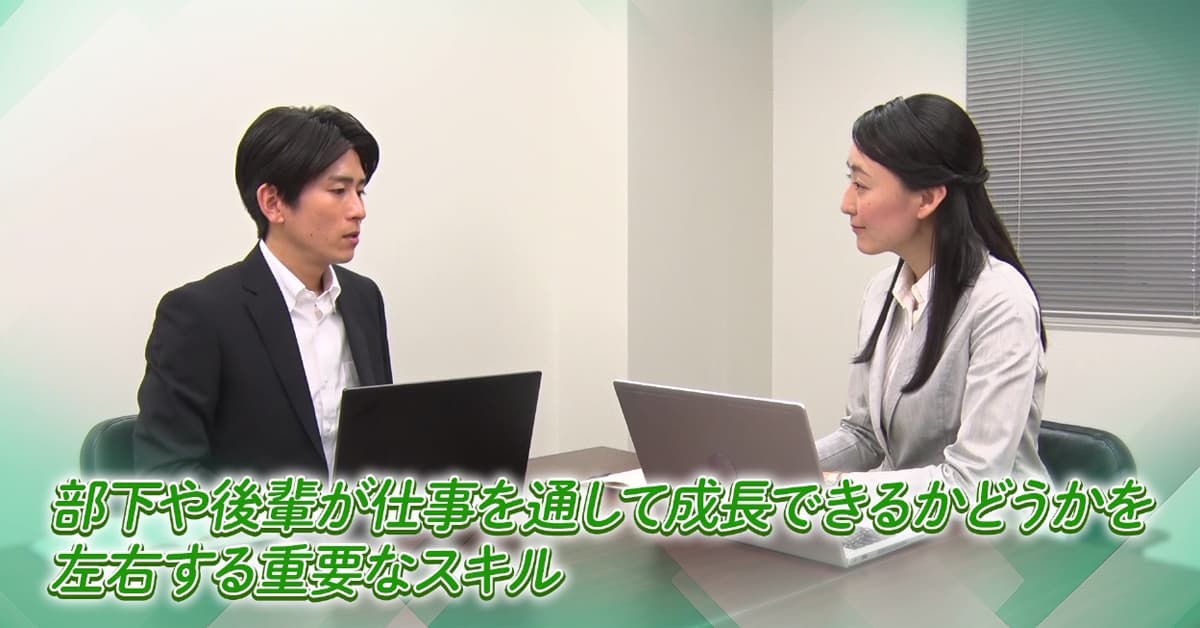
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
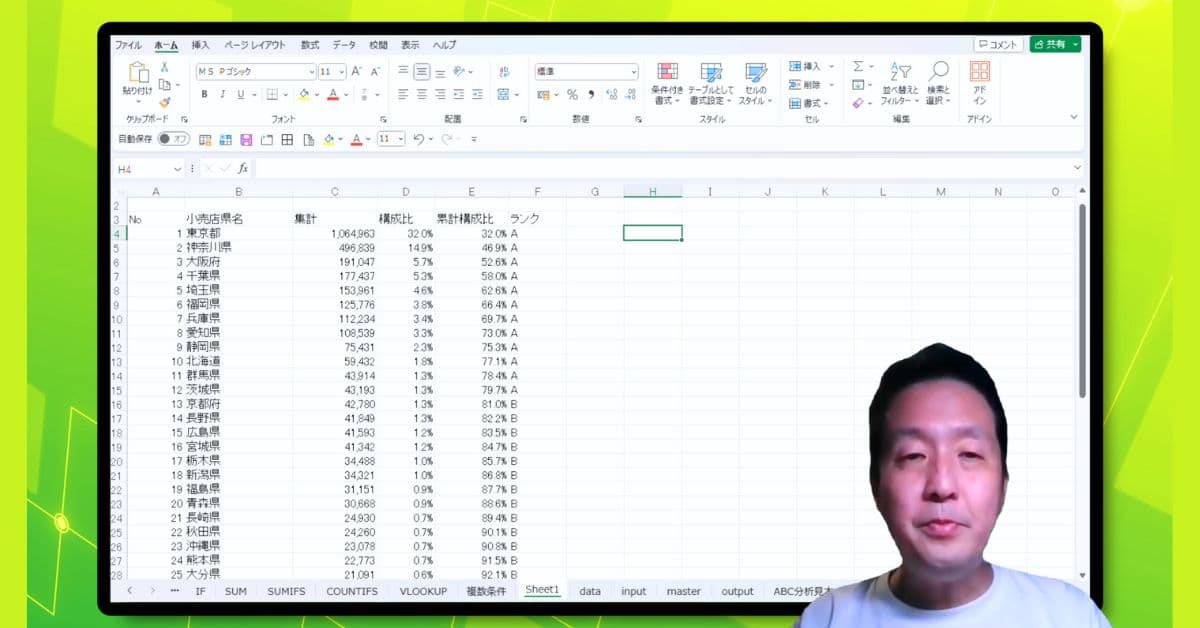
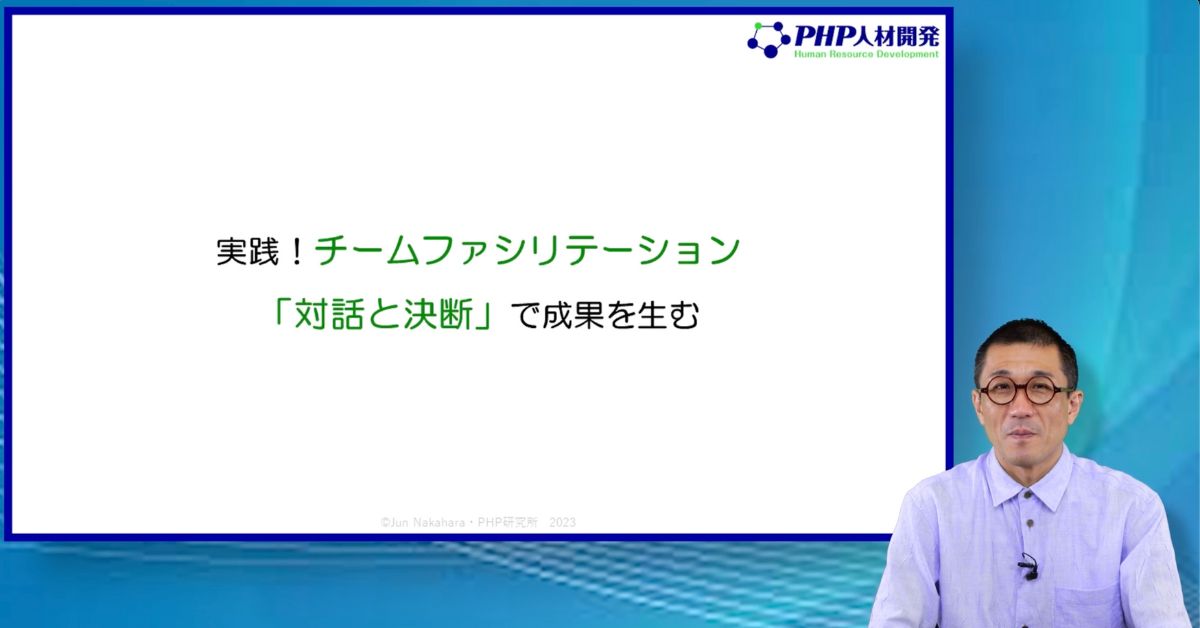
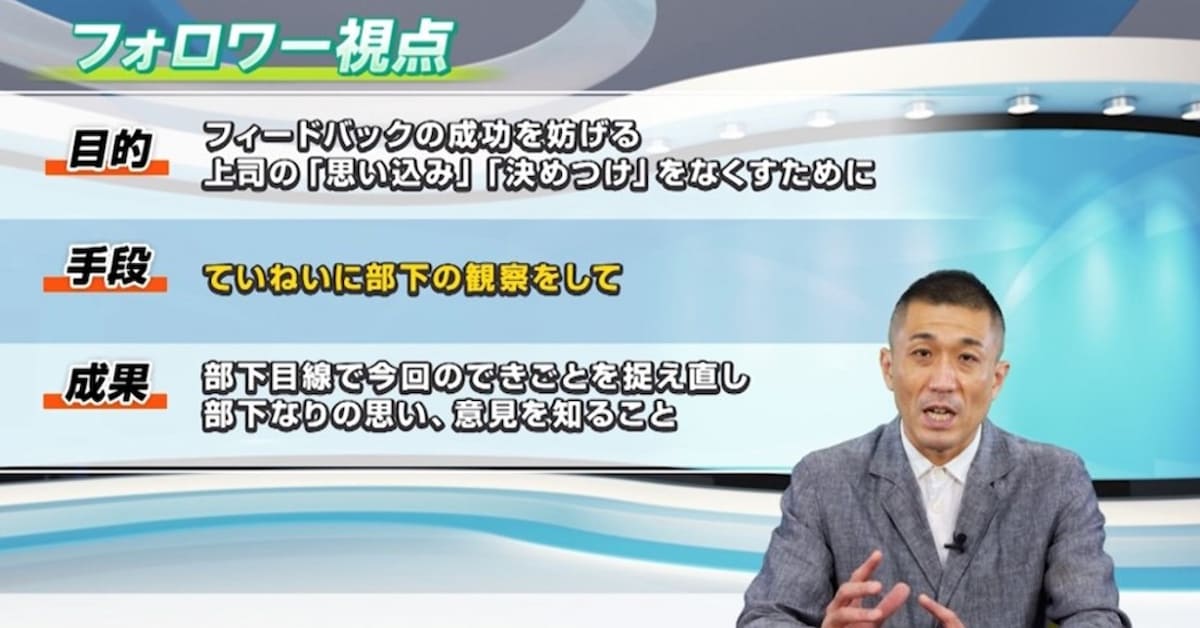

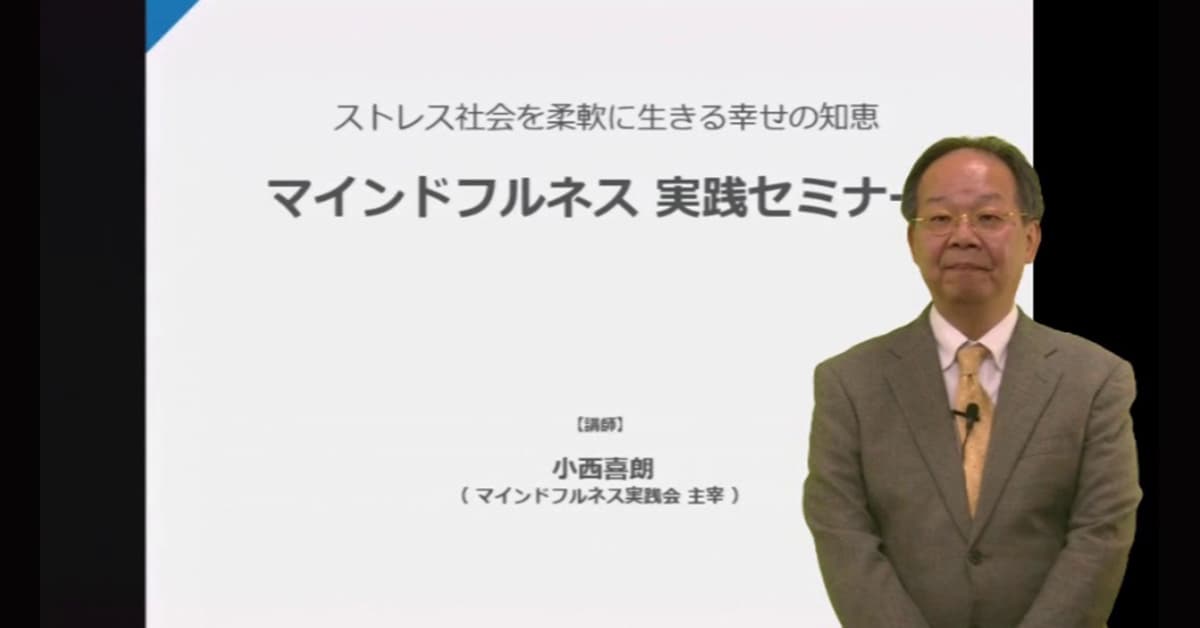

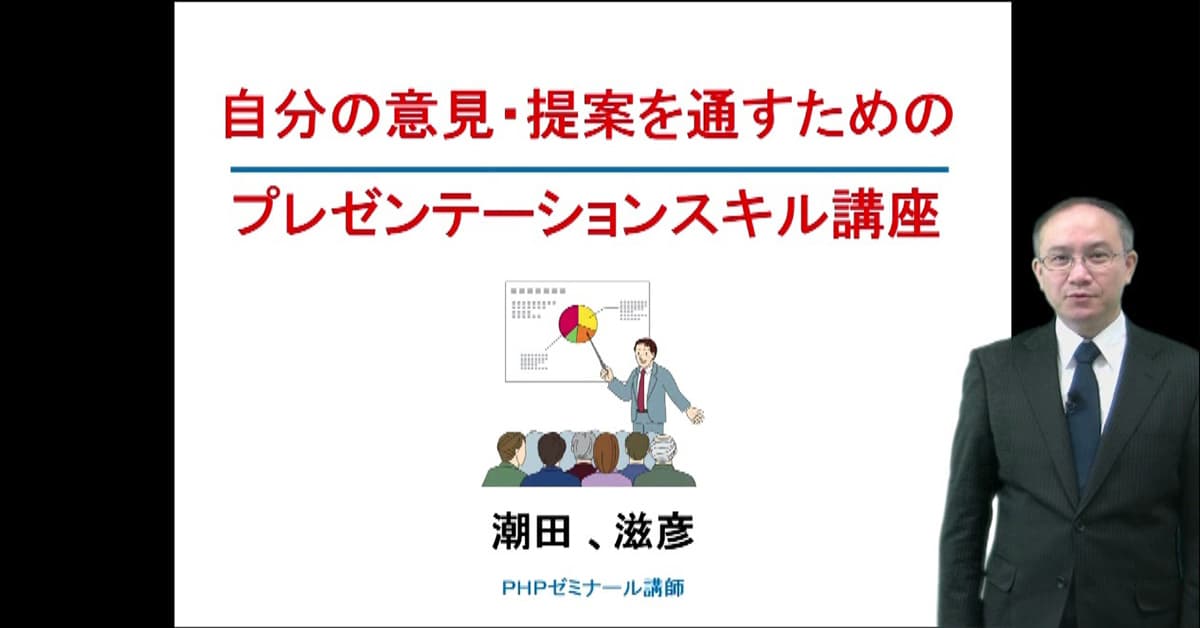
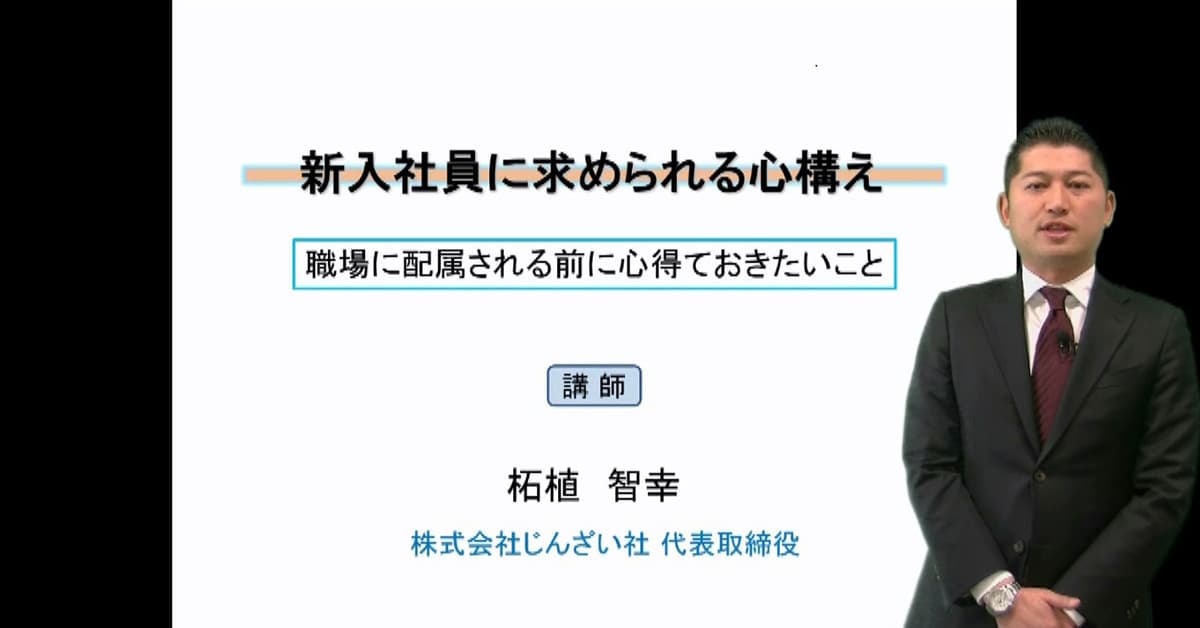
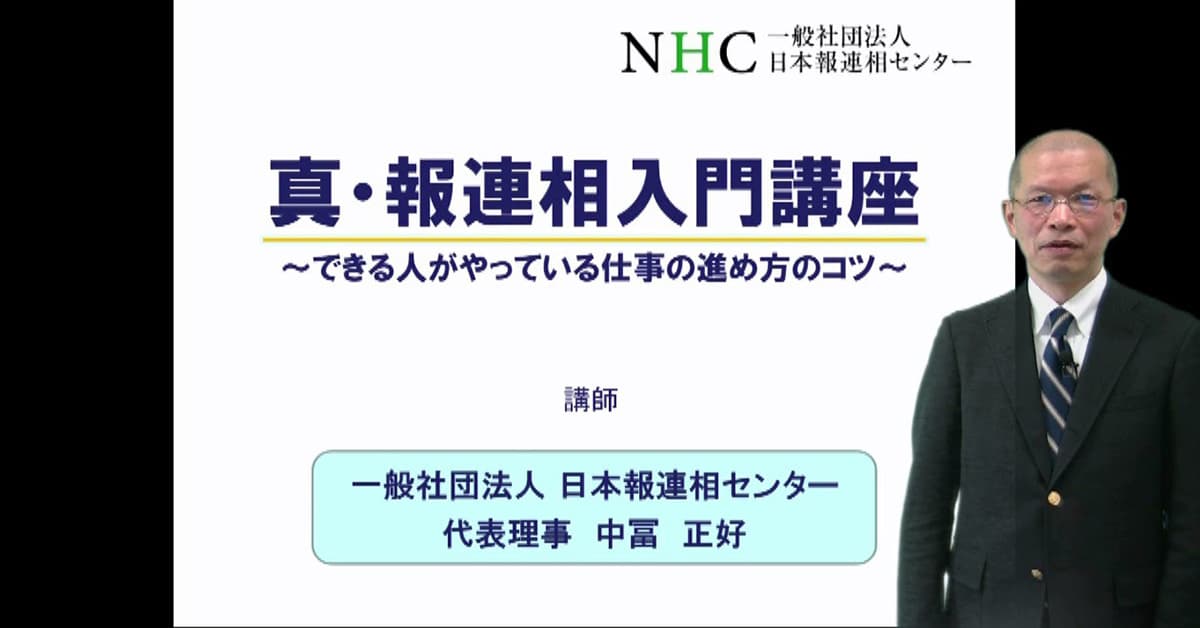
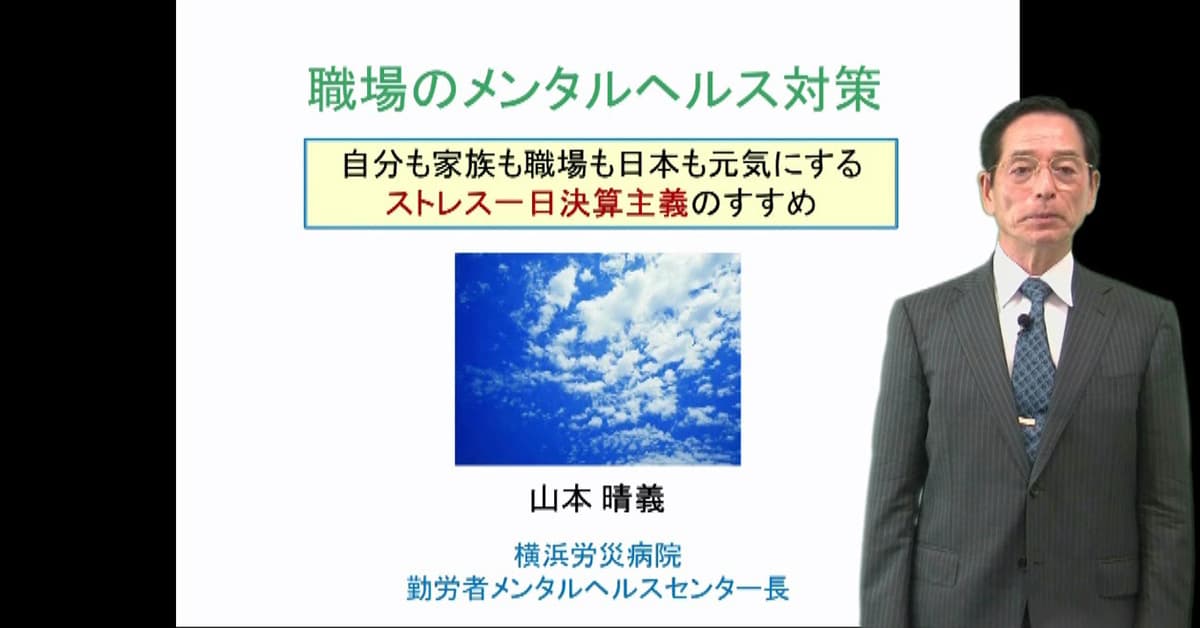
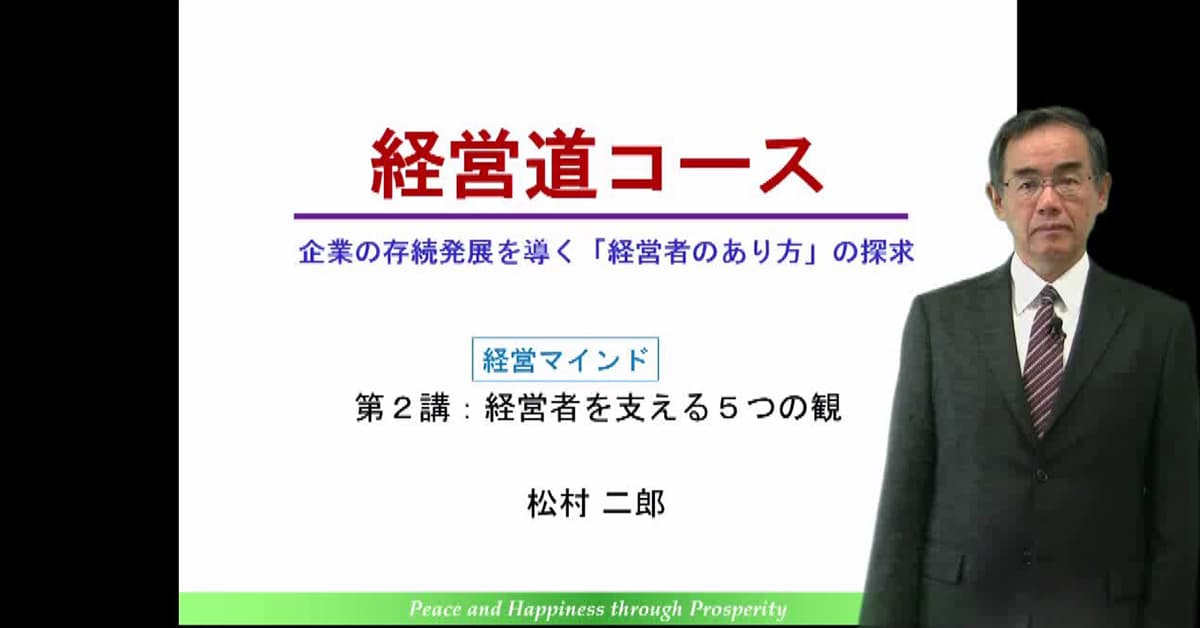
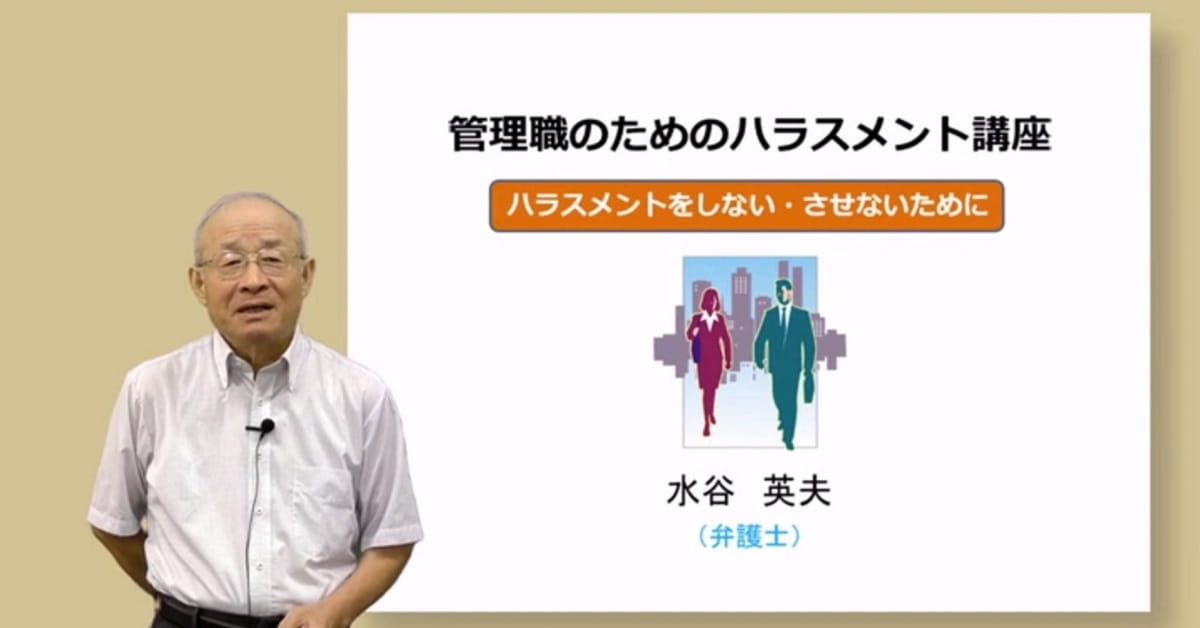

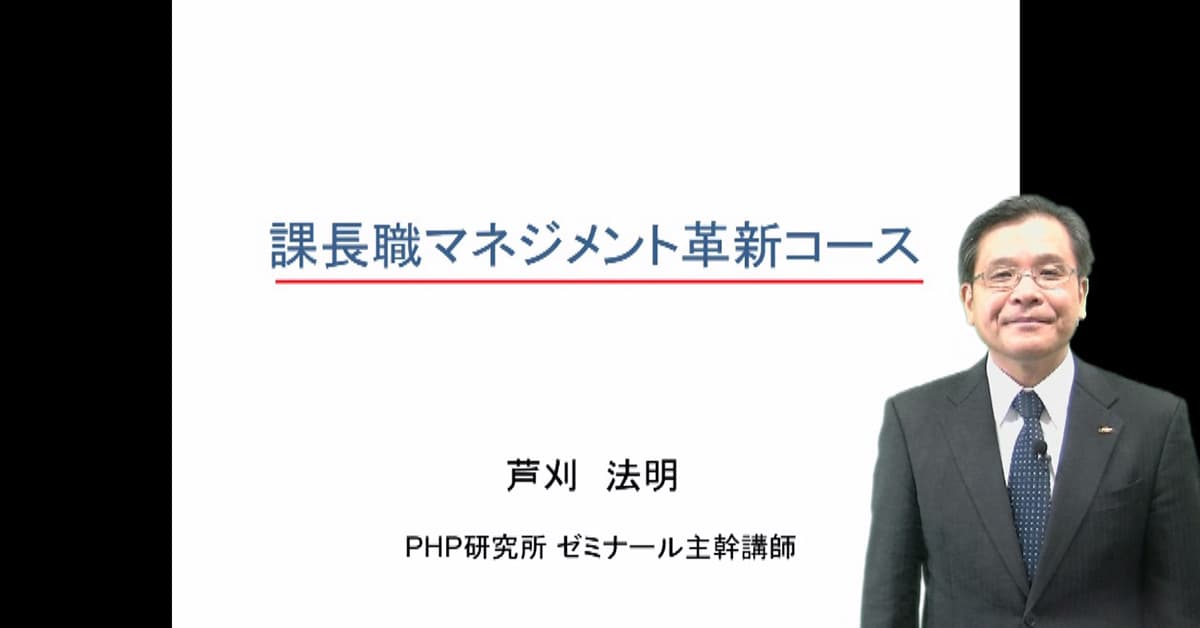



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















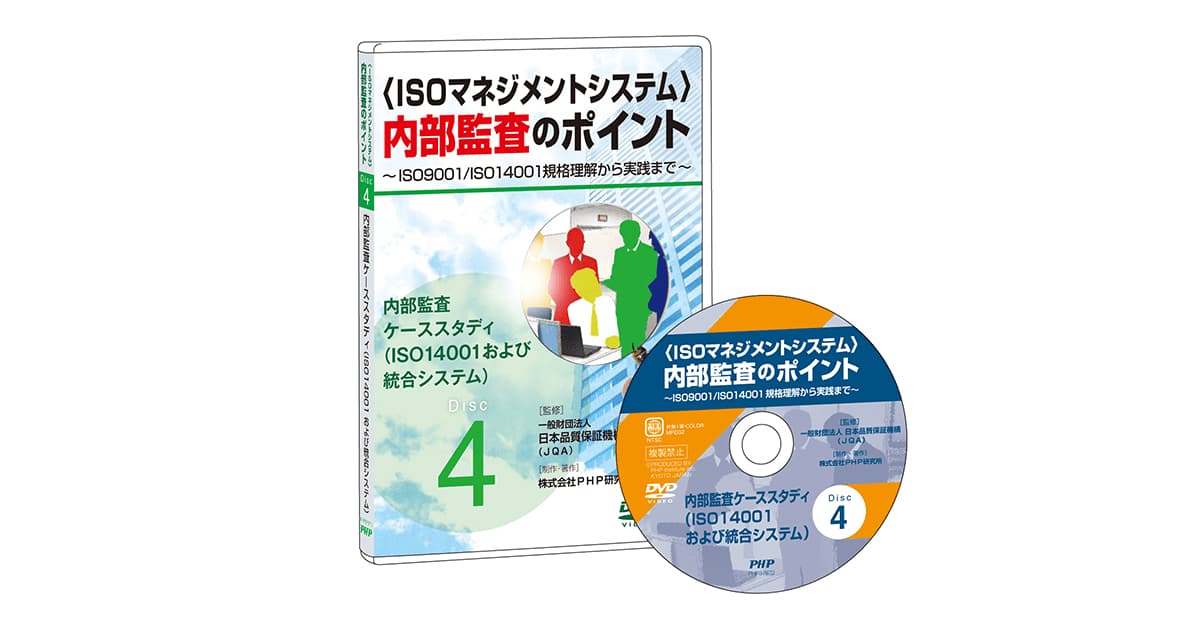





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
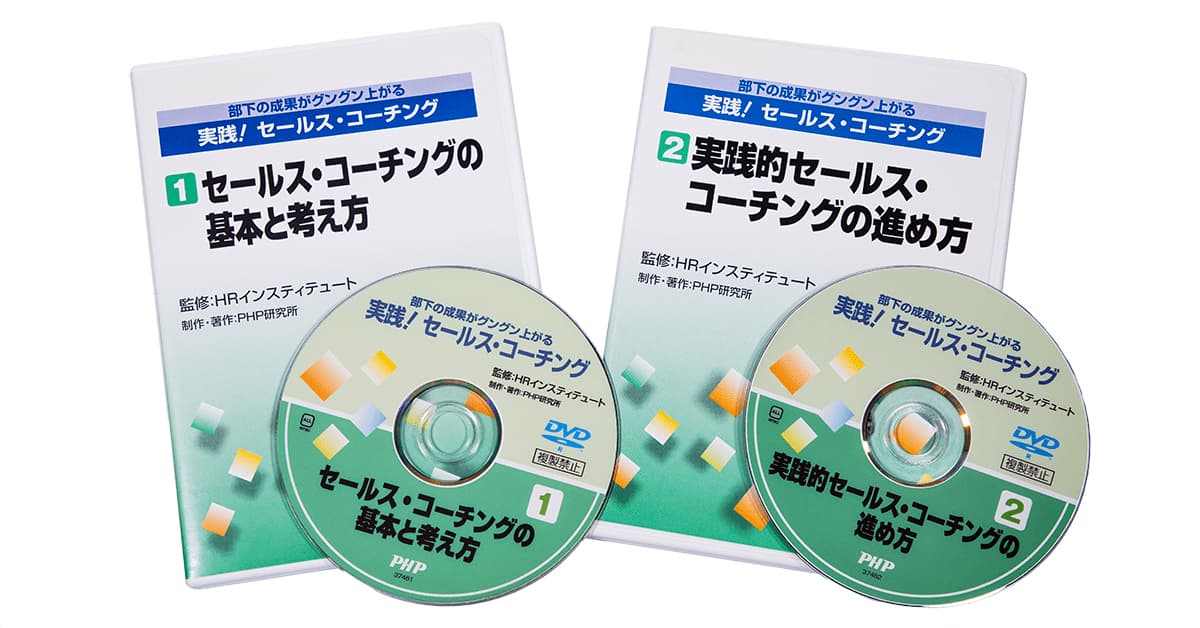




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)