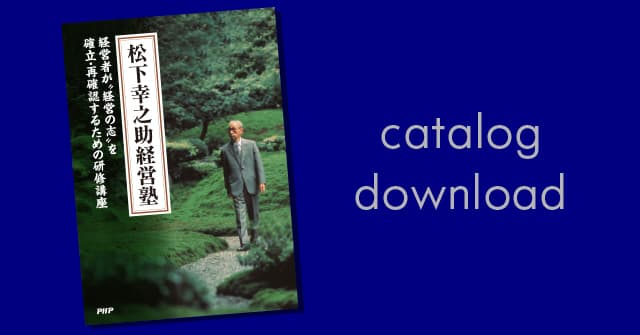伊庭貞剛の決断~存亡の危機にトップはいかに行動すべきか
2015年3月24日更新

存亡の危機が訪れたとき、経営トップはいかなる決断をし、いかなる行動を取るべきか。選択を誤れば事態をさらに悪化させる。
住友財閥の第二代総理事伊庭貞剛は、明治27(1894)年に起こった住友史上最大ともいわれる別子銅山での騒乱の危機を見事に克服し、逆に発展の礎を築くという稀有の成果を収めた。そこで示された決断の背景にはどのような信念が込められていたのだろうか。
別子銅山の内憂外患
伊庭貞剛が下した決断。それは、大阪の本店から新居浜・別子へ単身で赴任するという決断である。テロによる生命の危険がある中、現地で陣頭指揮をとるという、一見蛮勇とも奇異とも見える決断であったが、それが結果として、住友の人心を結集し、のちの改革を成功に導く基となったのである。
明治27(1894)年、当時、別子では二つの問題によって大きな紛争が生じていた。一つは、住友の初代総理事広瀬宰平の独裁経営に対する反発、もう一つは銅の製錬が及ぼす環境問題であった。
異様な状況である。「広瀬反対!」というのが別子での社内の気勢。一方社外では「煙害を何とかしろ!」と訴える地元農民たちのデモ。
広瀬宰平という人物は、別子銅山の一奉公人から出世した才人であった。幕末維新期の住友の財政危機を切り抜けたこと、外国人鉱山技師を雇って銅山を近代化したのも広瀬の功績である。しかし、初代総理事となり、経営の全権を掌握すると、自らの戦略への固執や人事の専横など、その豪腕経営が次第に度をすぎるようになった。そしてついに事業の中心たる別子銅山で、現地幹部社員が広瀬批判の弾劾書を住友の家長あてに提出するに至って、銅山経営は麻痺状態となった。
社外においては、火力確保のために銅山周辺の木々は伐採され、山肌から緑が消えつつあった。加えて、製錬により生じる亜硫酸ガスが新居浜・別子の人びとの健康や作物に重大な影響を与えはじめていた。ところが、その被害が刻々拡大しているにもかかわらず、総理事広瀬は「煙害など存在せぬ」と請け合わない。
住友の不誠実に対して、一部の農民は暴徒化し、ここに別子は内にあっては内ゲバ、外にあってはデモや打ちこわしの危機に見舞われていたのである。
事態の打開のために、本来もっともリーダーシップを発揮すべきは、住友家の家長もしくは総理事の広瀬であったろう。しかし、家長に経営の指導力はなく、総理事は事態の当事者として適任ではなかった。広瀬に次ぐ経営責任者である支配人の伊庭におのずと衆目が集まった。
伊庭は形勢を察して、「私が新居浜へ行きましょう」と志願した。
伊庭の決断の背景にあったもの
自薦したというものの、伊庭にどれだけの成算があったのかは疑問である。現地に歓迎されて行くのではない。さらに悪い条件なのは伊庭が広瀬の実の甥であったことだ。広瀬は近親者を多数引き上げ、公私混同を批判されていた。伊庭も裁判官だったところを、その器量を見込まれ、広瀬の説得によって住友入りしており、憤激している者にとっては、伊庭こそ広瀬の分身として憎しみの対象にもなり得る。
テロに遭う可能性は多分にあった。伊庭は、妻の梅子に別子行きを伝えるなり、「わしの身に何が起こるかわからんから、子供のことは万事よろしく頼む」と言い残していた。
したがって、伊庭の決断の背景にまずあるのは、死を恐れぬ勇気が具わっていたことである。また客観的に伊庭でなくてはならなかった理由はまだある。それは広瀬と並ぶ権限を有し、即断即決ができる責任者の資格があったことである。現場は急を告げている。そこに赴任したものの何の権限もなく、いちいち本店に伺いを立てなければ判断ができないということなら、現地の憤りは増すばかりである。さらに、この重大な危機は住友内部の問題だけではなく、社会的に配慮のある対処をしなければならないという点で、たいへんな見識が必要であった。関東では足尾鉱毒問題がすでに社会問題化していた。別子を足尾のようにしては、全住友にとっても大打撃である。その点でも、大阪の上等裁判所判事であった伊庭の経歴は住友にとって僥倖だったのかもしれない。
伊庭は、周囲の期待と自らの適性に準じて、別子行きを決めたわけである。
大いなる決断
明治27(1894)年7月4日、木綿の質素な着物に羽織、袴という姿で、袂に『臨済録』を忍ばせ、四十八歳の伊庭は船上の人となり、瀬戸内の海を越えた。無聊を慰めるために連れてきた顔なじみの謡曲師との二人旅である。とても大住友の支配人一行には見えなかった。
新居浜入りした伊庭はまったく驕る風もなく着任し、居宅も四畳半の質素な草堂に起臥した。それでも現地従業員の態度は敵意に満ちたものだった。廊下ですれ違っても挨拶さえしない。歓迎の酒宴では伊庭の前にあぐらをかき、「支配人、山の宴会は大阪とは違って手荒いぜ」とうそぶく始末だった。
別子の幹部たちにとっても荒くれた坑夫や人足たちにとっても、本店支配人の伊庭は広瀬の分身であり、諸悪の根源に見えたであろう。もしも、有無を言わさず担当者の更迭や大量の馘首をするならば、暴力沙汰に及んでもと、彼らは激昂していた。
険悪な情勢のなか、伊庭がはじめたのは、わらじ履きで銅山通いをすることだった。
坑夫たちは伊庭の態度に当惑した。会えば殴りつけてやろうと思っていた相手が、質素な格好でやってきては、「ご苦労なことだのう」「体の調子はどうかね」といたわりの言葉をかけてくれる。しかも危険な坑内を平気で巡検し、帰れば連れの謡曲師と曲を唸る。
人心の収拾こそ改革の第一歩と、伊庭は己の捨て身の態度を示そうとしたのである。その融和的な姿勢は現地従業員たちを次第に軟化させていった。日を追って伊庭の周りに職員や坑夫たちが集うようになり、ともに謡曲をうたうまでになっていた。暴徒が出る恐れなど、いつの間にかすっかり消えていた。
こうして人心が落ち着いた時分、広瀬は家長友純の命により、依願解雇の形で総理事を退き、まず内なる問題は解決した。
事実上、総理事を継いだ伊庭(正式には六年後)は、残った煙害問題に身を挺して尽力した。製錬所に、煙害の被害をこうむっている周辺の農民たちが、手に手に棍棒や竹槍を持って、「支配人の伊庭に会わせろ」と押しかけてくる。四畳半の草堂にも上がりこんでくる。しかし、伊庭は毅然とした態度で臨み、脅しには屈さず、しかも追い返すようなこともせず徹底して対話を続けた。
まず伊庭は失われた山林のために、大規模な植林を命じた。「自然にお詫びをして緑をお返しするのだ」という信念のもと、この植林事業は明治28(1895)年から昭和25(1950)年まで継承され、広大な山林が蘇った。のちにここから住友林業という専門企業が誕生する。
次は煙害そのものの解決である。本店の家長友純に別子赴任の挨拶をしたとき、伊庭は、「銅山をつぶす覚悟で参ります」と決意のほどを示したという。最悪の場合には、事業廃止を決断する覚悟もあったのかもしれない。
伊庭はかつて広瀬との意見の相違から住友を離れ、古河鉱山に移っていた技師の塩野門之助を別子に呼び戻して技師長とした。優秀かつ必要な人材を得るのに逡巡はなかった。塩野も伊庭の熱意に打たれてこれに応じた。調査のあと、塩野は煙害を解決する抜本策として製錬所の移転を提案した。
これは、製錬所をそのまま瀬戸内海に浮かぶ無人島四阪島に移転することで煙害を根本からなくすという、前例を見ないスケールの大きなものだった。伊庭は塩野とともに釣り船に乗り、ざっと島の見分をして即断した。伊庭が現地に来たことがここでも生きた。伊庭は買収に際して余計な横槍が入らないよう、四阪島を個人名義で地主の言い値のままどんどん買い取っていった。四阪島製錬所は伊庭が赴任した十一年後の明治38(1905)年から操業を開始する。
こうして、住友は新鋭設備を持つ大規模製錬所を有し、しかも煙害を大幅に軽減することに成功したのである。大規模な植林運動と製錬所の全面移転。煙害を地域住民と無縁のものにするためのこの二つの策は、企業の社会的責任に準じた、時代を先取りする誠意ある対応だったと評価されている。
伊庭貞剛に学ぶ、決断のポイント
伊庭は、弘化4(1847)年、近江国蒲生に生まれたが、十代の青春期には勤王倒幕に燃えて京都を奔走した熱血漢であった。それが新政府に至って司法家となり、のち官界に嫌気がさして農業に転じようとする。それを叔父の広瀬に報告に行ったところを説得され、住友入りしたという異色の履歴をたどった。
そういった経歴からか、伊庭の経営決断は、大局的見地に立って公正が貫かれている印象が非常に強い。それにいったん下された決断が後々ブレないところも特徴的である。
かの四阪島の買収過程で、ある部下が、「買収が終わってから、やはり製錬所に不向きだとわかったらいかがいたしましょう」と弱音を吐いたとき、伊庭は、「そのときには本当にわしの私有地にして、桃でも植えて名所にするよ。君たちも見物に来ておくれ」と笑って、部下たちを安心させたという。
決断がブレないのはなぜか。
それは何がどうあるべきかという解決へのビジョンがつねに確固としており、部下に対しても明快に示されていたからではないだろうか。
それは、キャリアのゆえか、もしくは本来司法家に適した資質が、伊庭の恬淡とした性格から引き出されるのかもしれない。伊庭は実業人でありながら、大阪府立商船学校や大阪市立商業学校の校長に推され、代議士にもなった。司法界に教育界、政界と種々の要請があったこと自体、その篤実な人間性を証明しているといえよう。
別子にいること五年間、解決の道筋をつけると、伊庭は独裁を生まないよう、重役会議による戦略決定を定式化、経営の意思決定の合理化を図った。そして自らの進退も潔く五十八歳で総理事を辞する。「事業の発展にもっとも害をなすのは、青年の過失ではなく、老人の出しゃばりである」というのが退任の弁。最後の決断も鮮やかだった。
退任後は、近江石山の邸宅・活機園に悠々と老いを養い、大正15(1926)年10月23日、行年八十歳にて死去した。
伊庭は幽翁と称されるが、その号は最晩年、八十歳の新年を迎えたときに、自ら選びなおしたものである。禅を好んでいた伊庭は、「幽」の意味する、自然で優雅な、そして私心を忘れる境地をその生涯を通じて願っていた。
友人の禅僧に、「七十はまだ娑婆くさし歳の暮。八十の耳あらたなり初からす。幽翁と名もあらためて御慶かな。などと申し出し候」とその心境に至った喜びを綴っている。
無欲恬淡とした生涯が当時の財界人の尊敬を集めたのも頷ける。










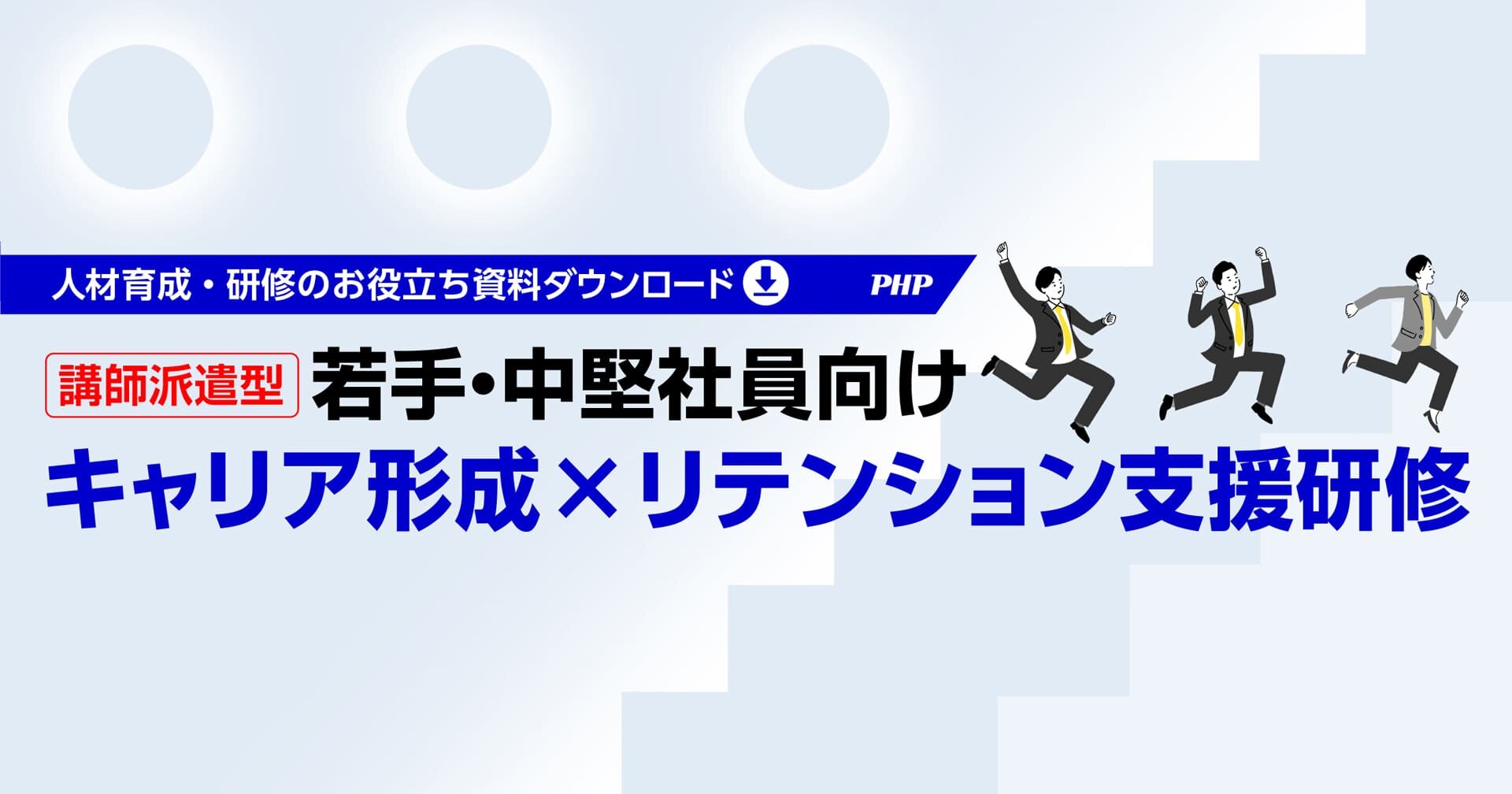















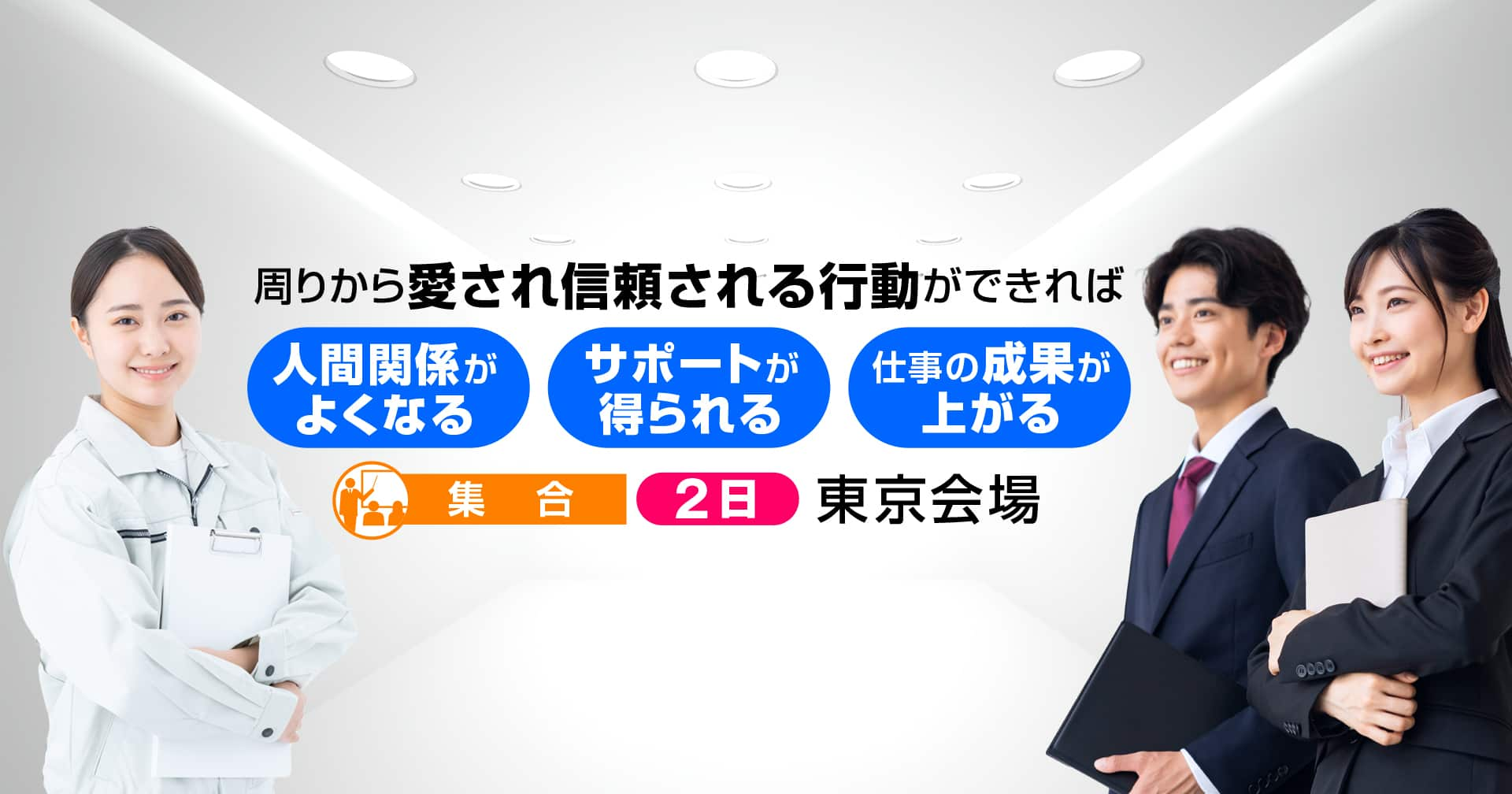










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







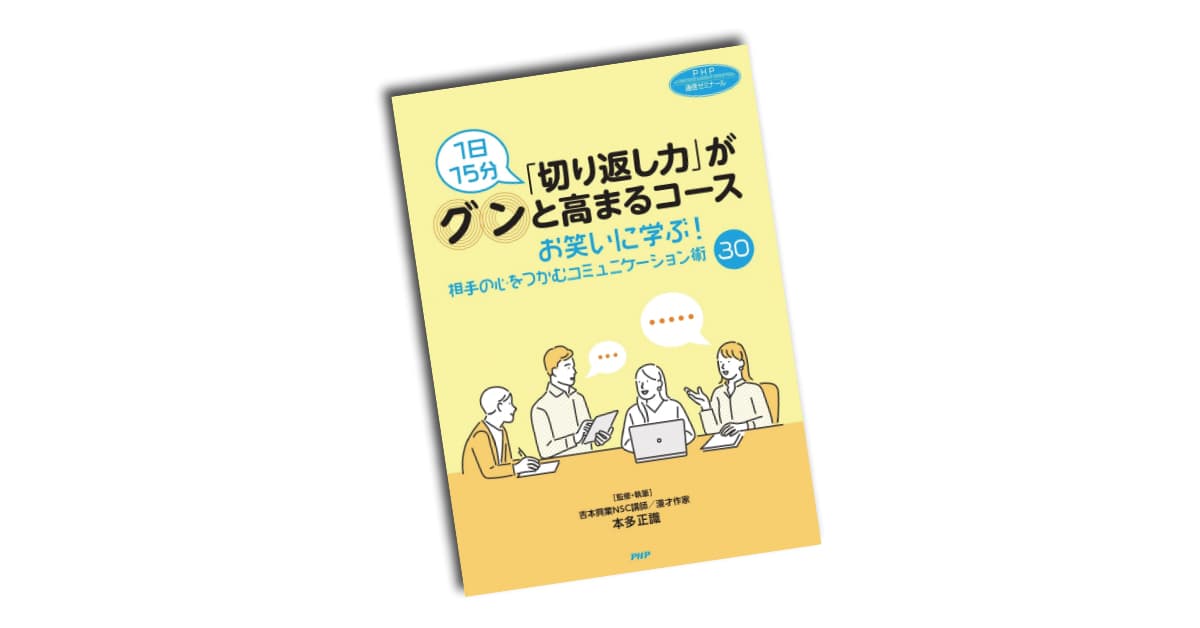






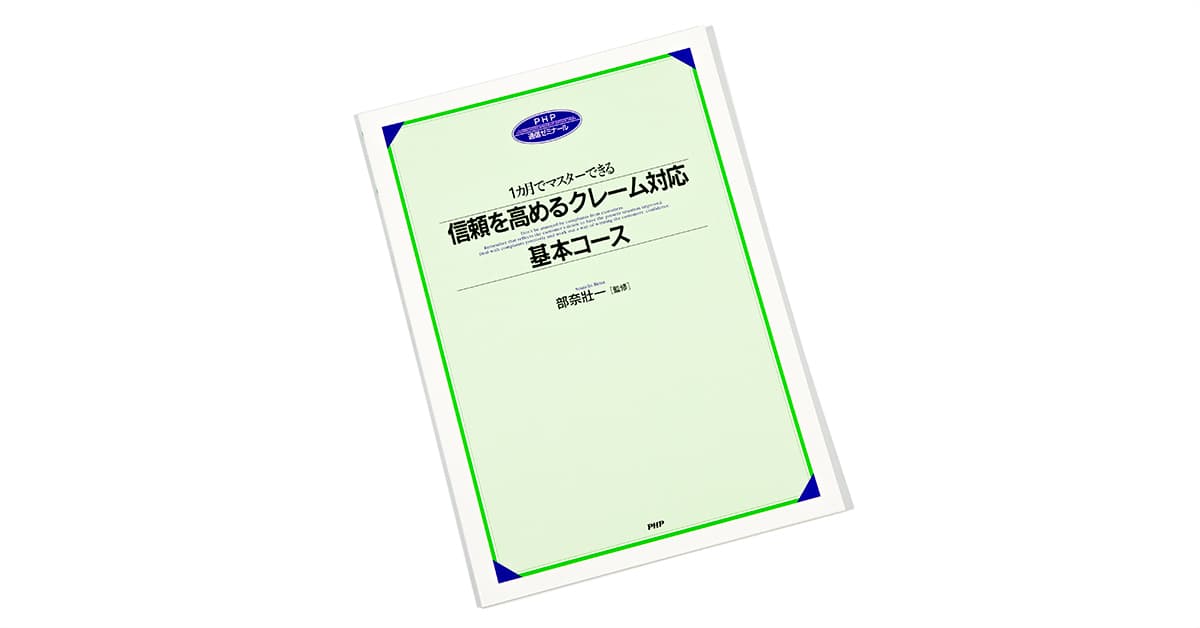





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

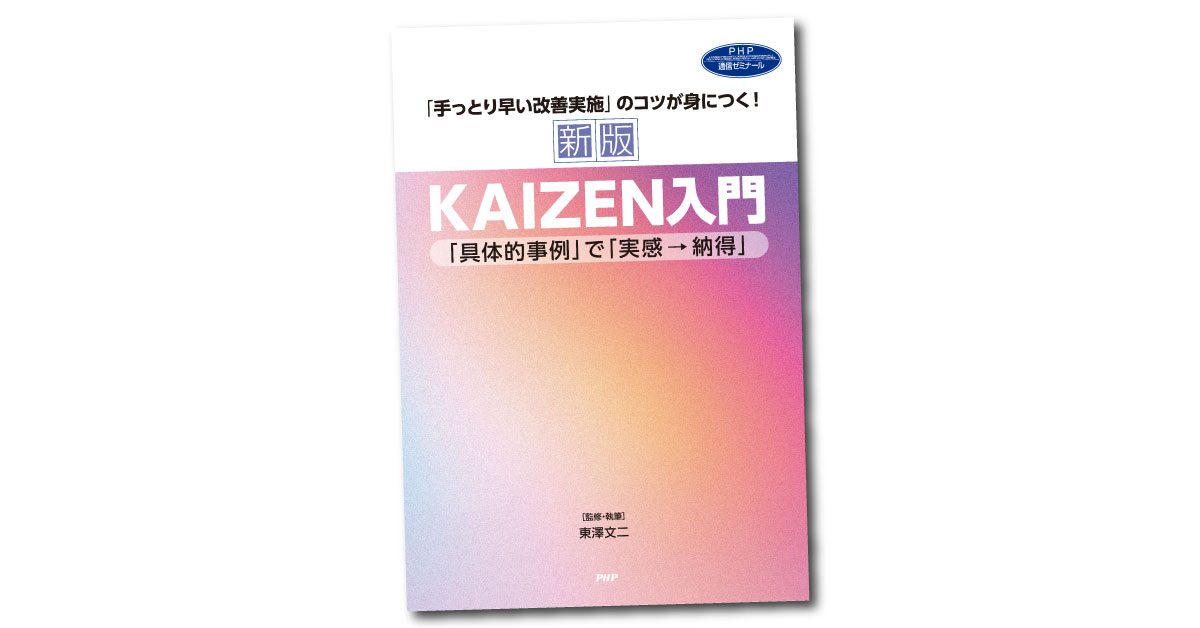










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


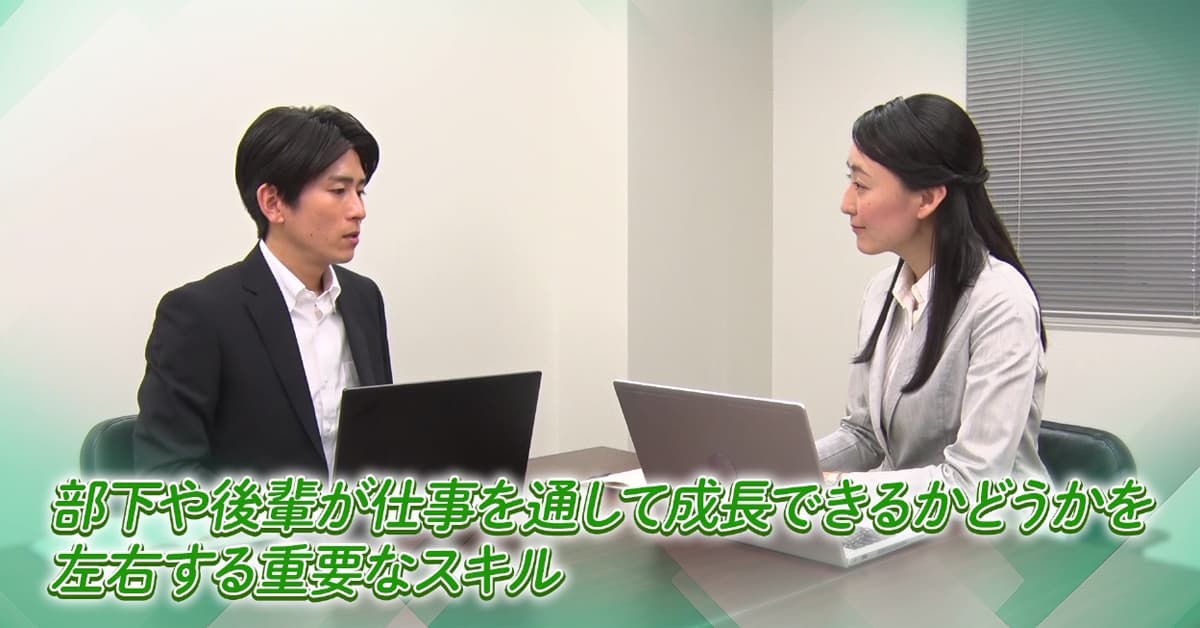
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
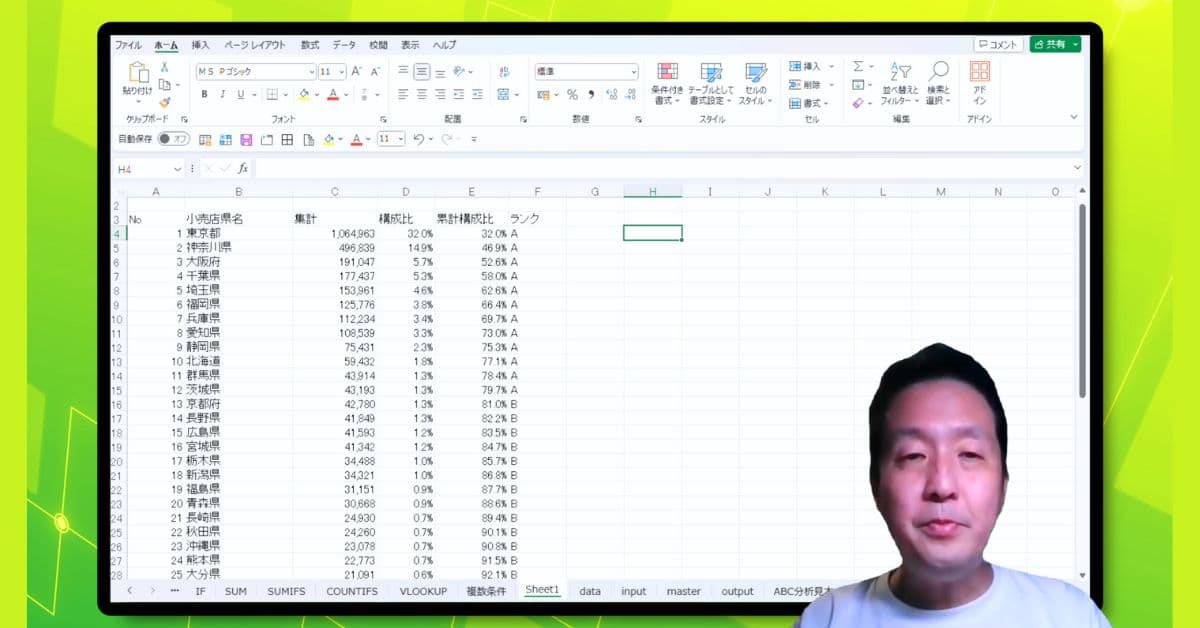
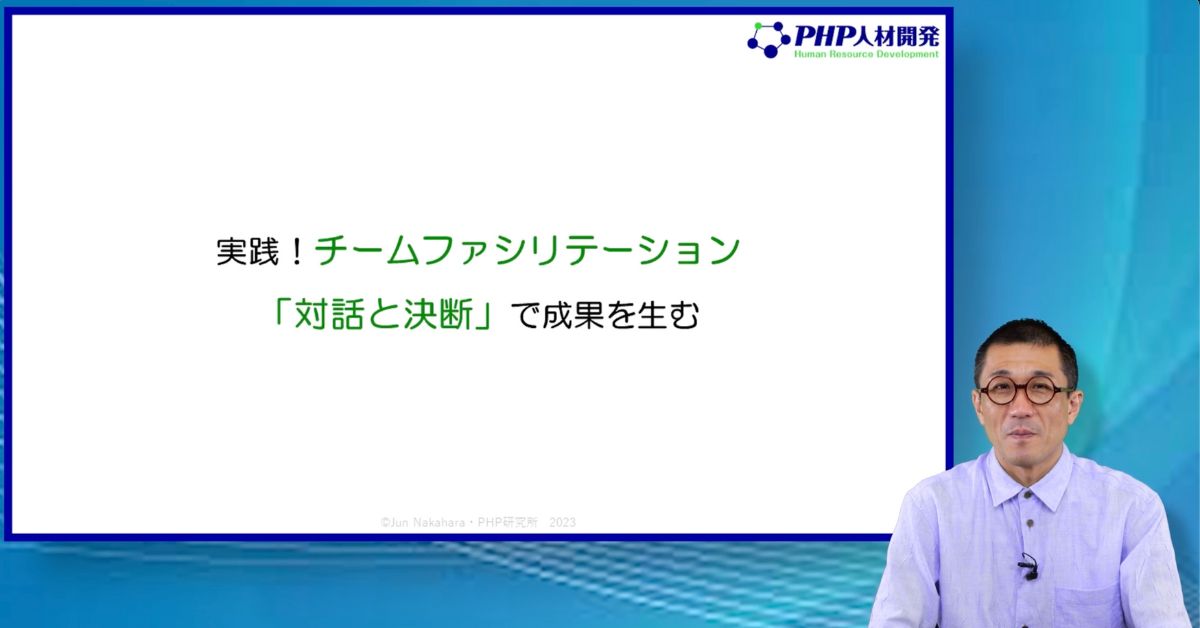
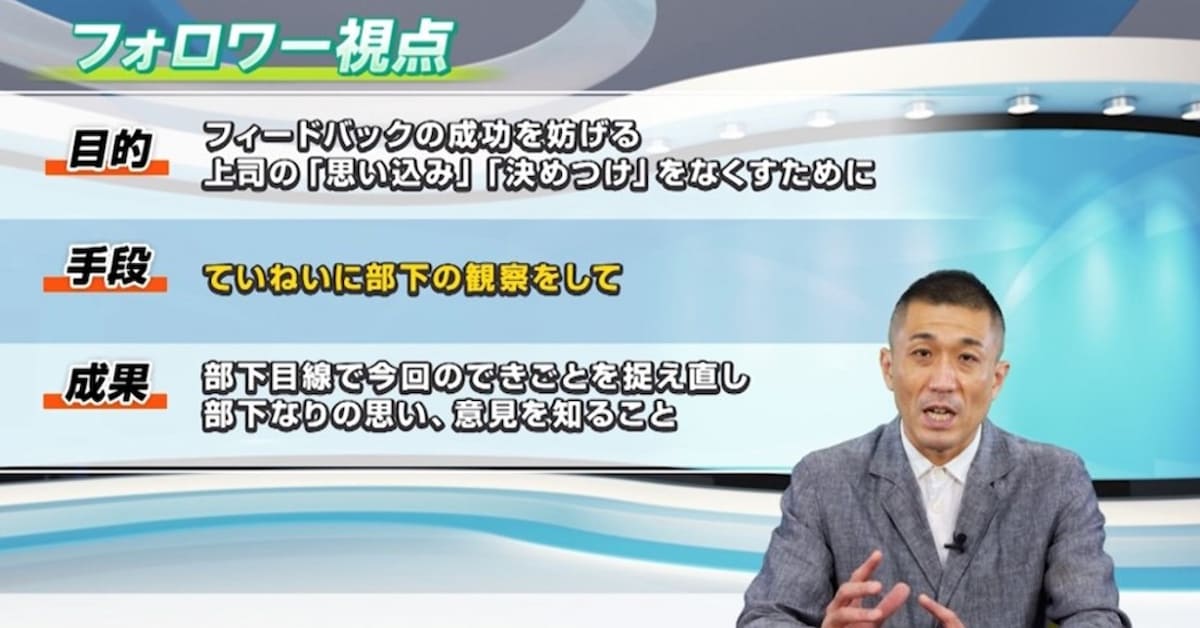

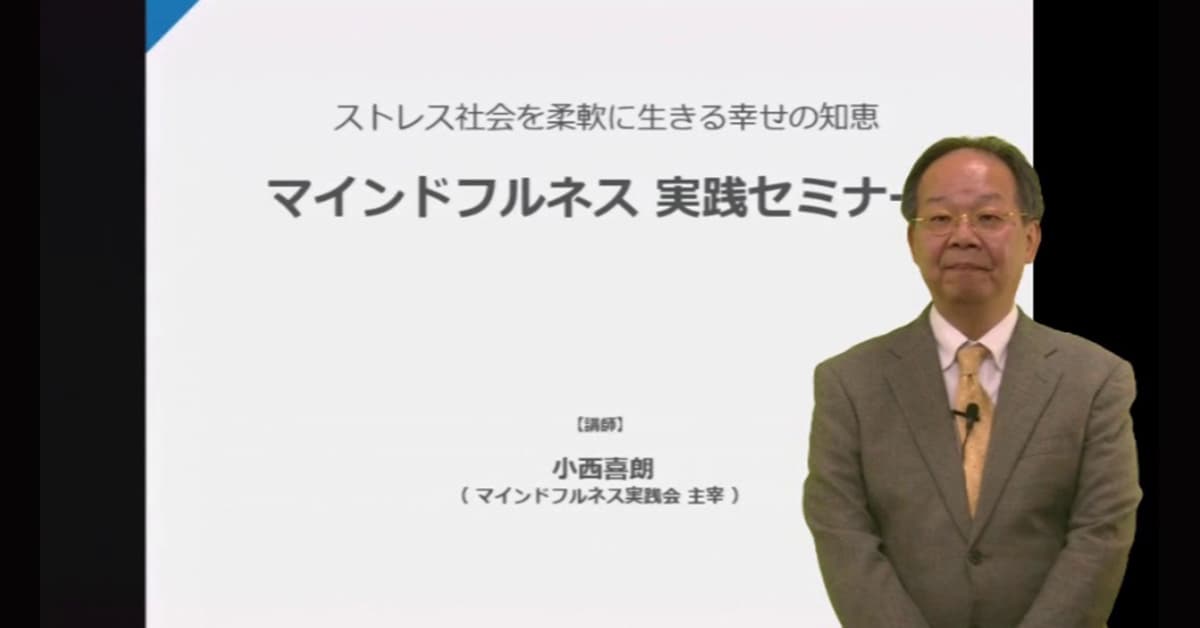

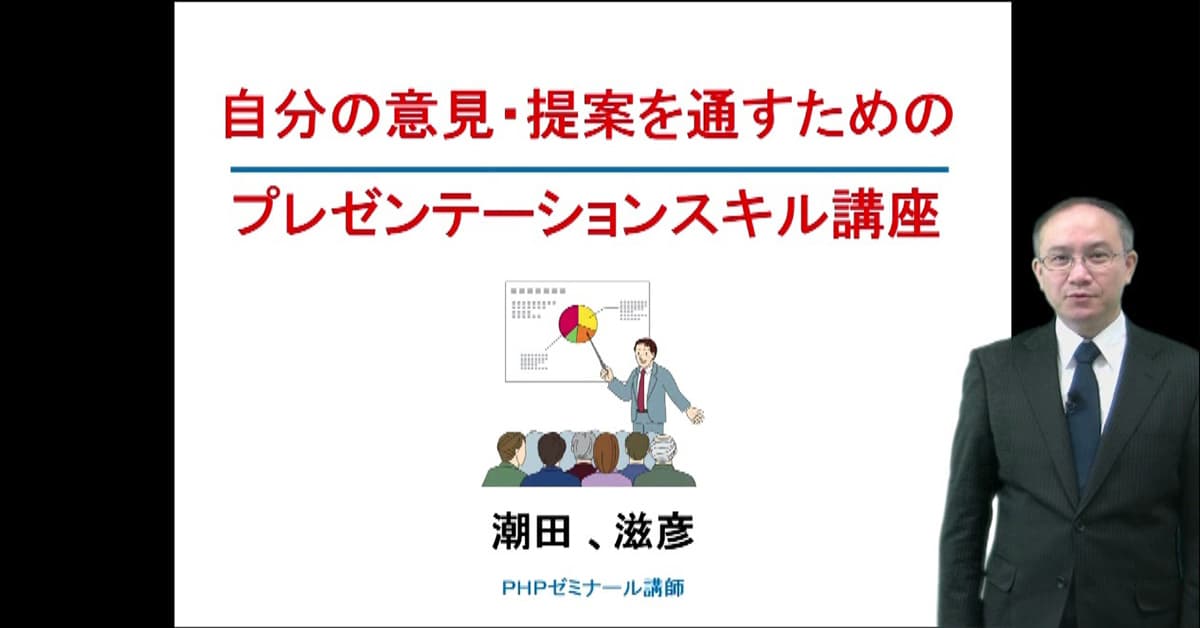
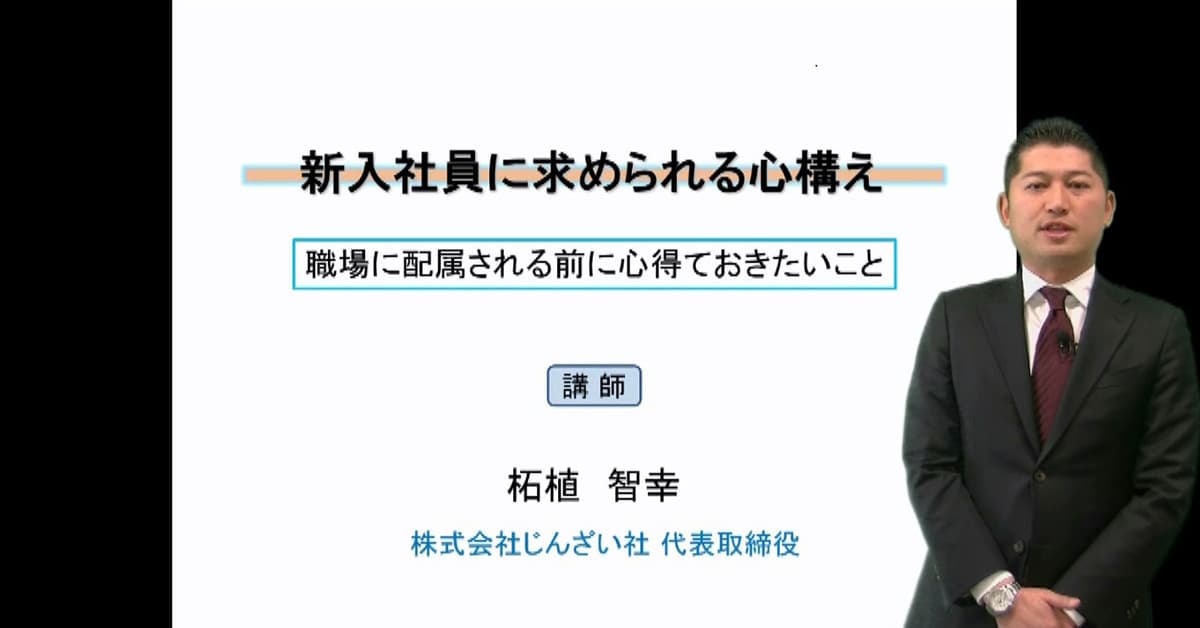
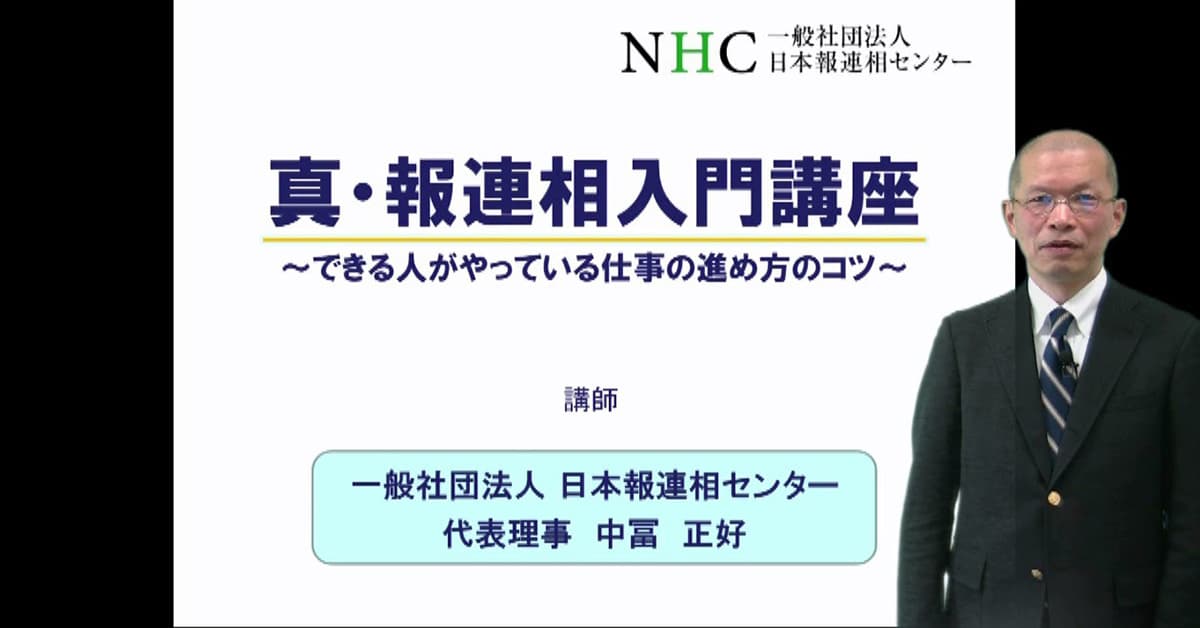
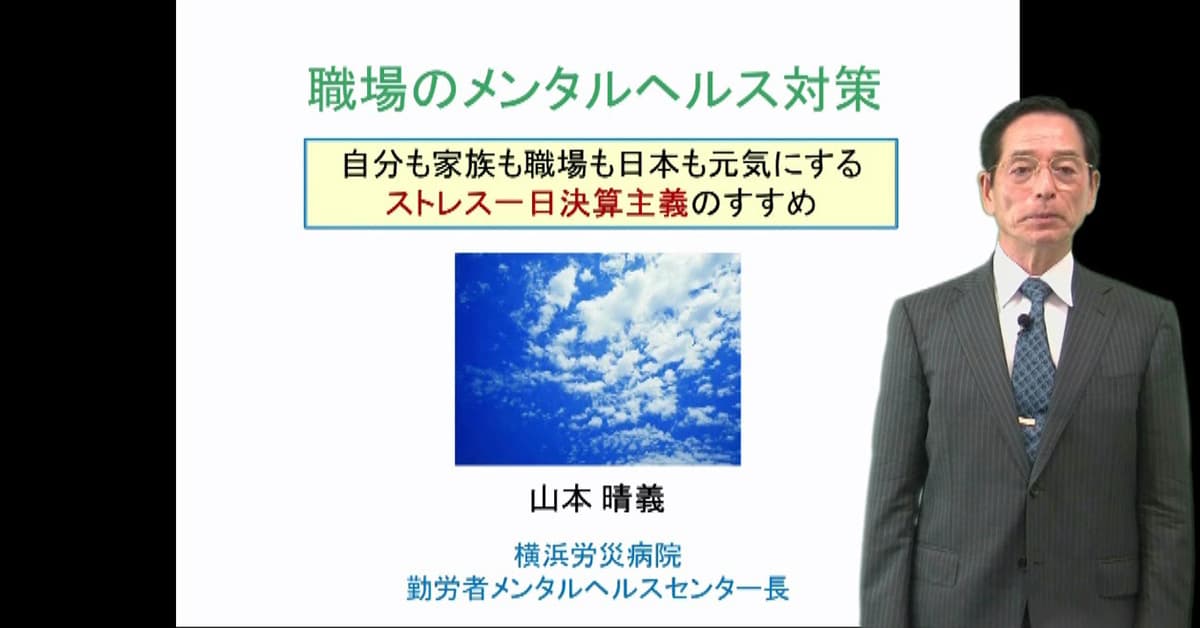
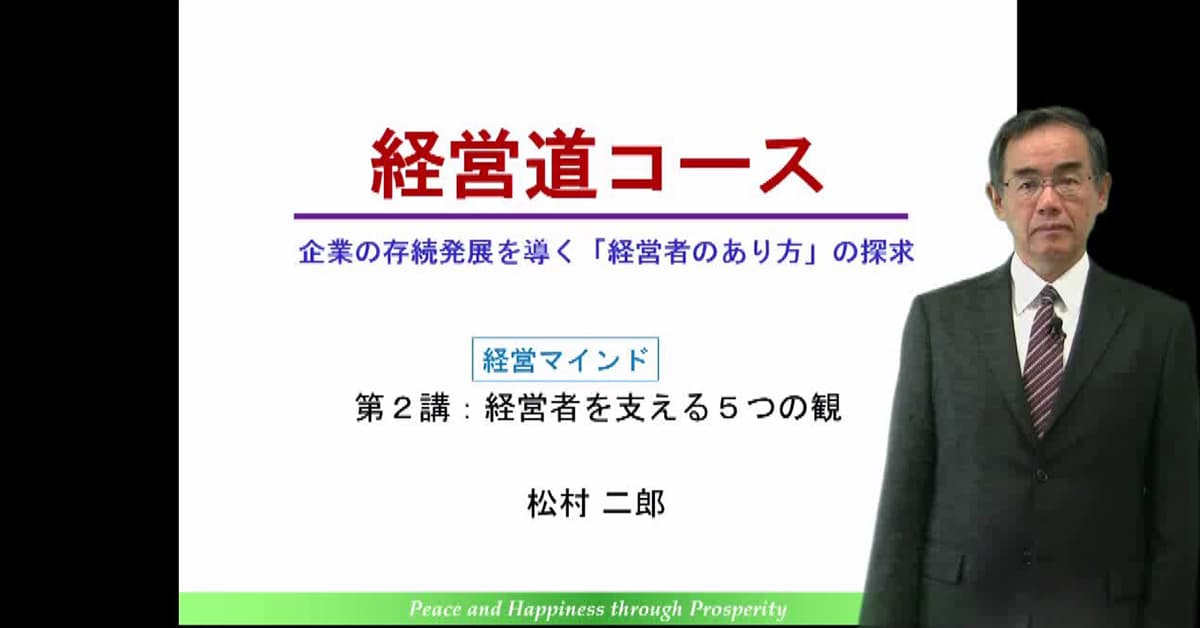
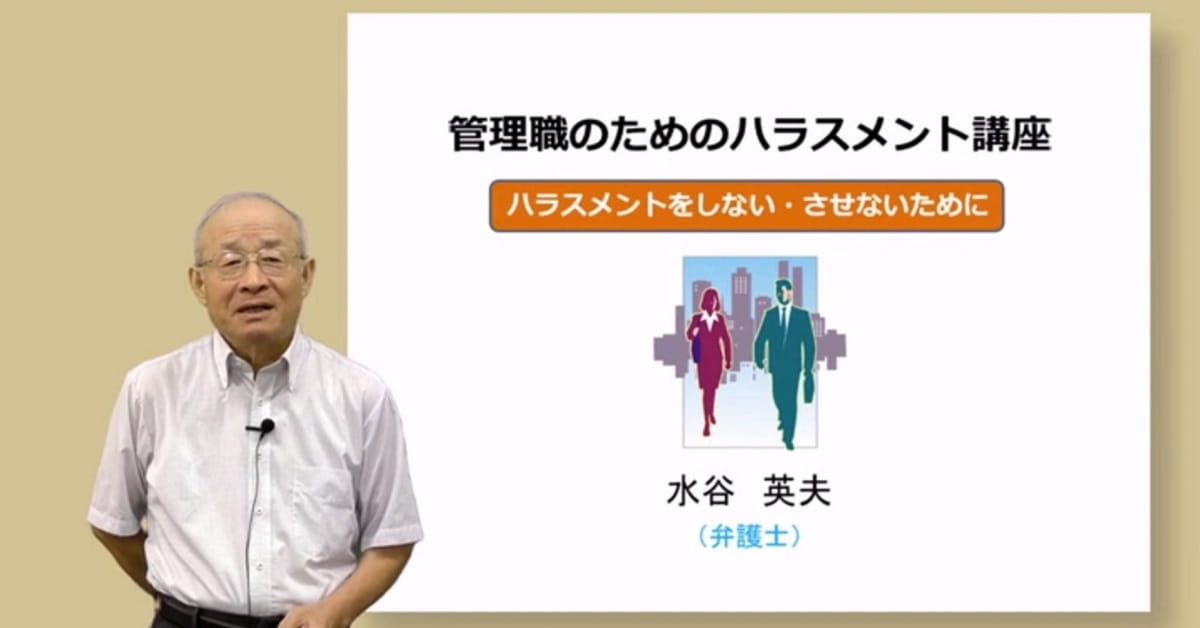

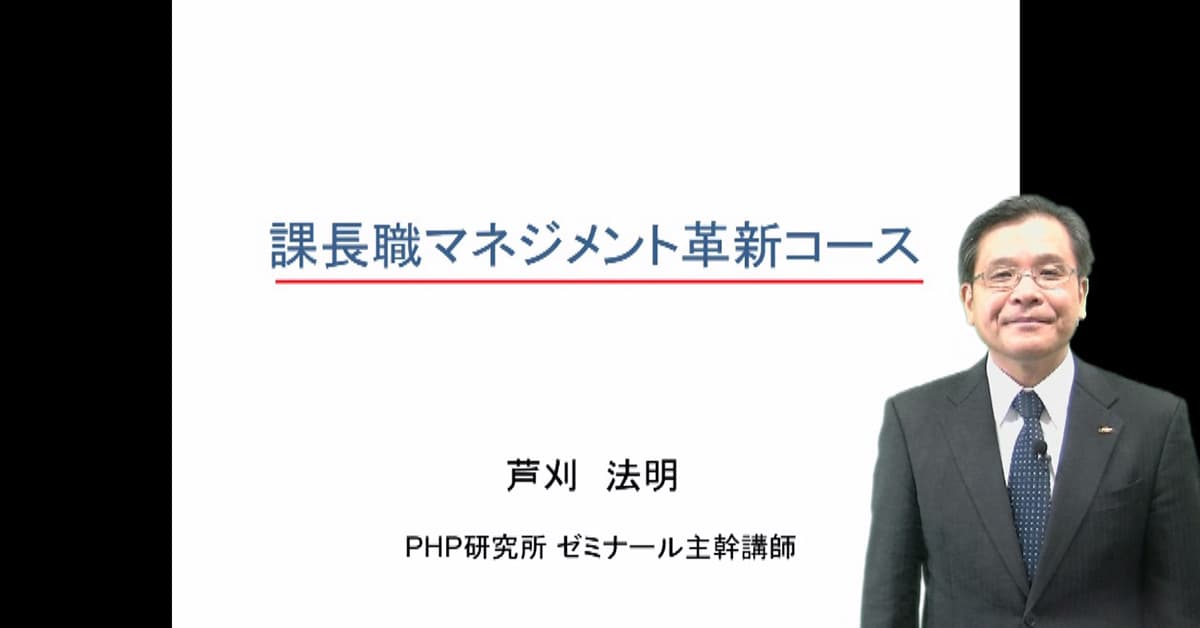



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















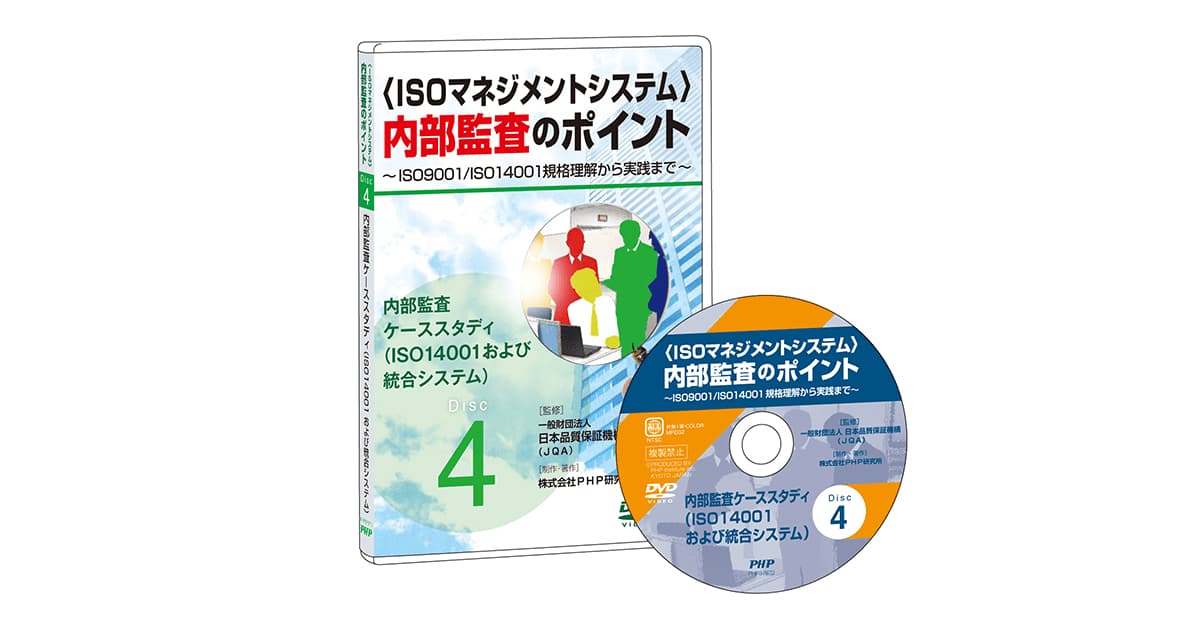





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
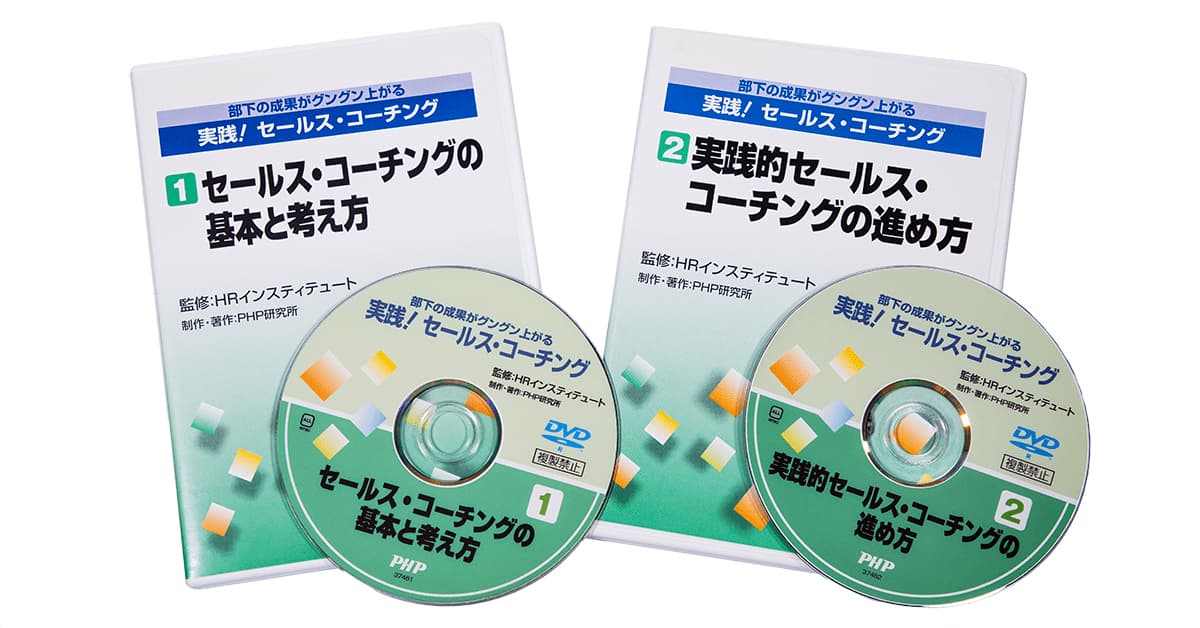




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)