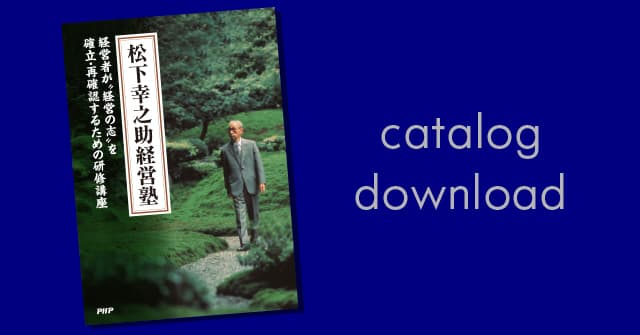十河信二の決断~先見力と執念で実現させた新幹線
2015年12月21日更新

執念で新幹線を実現させた十河信二。組織と社会を動かした、その強い意志と行動力の背景に迫る。
開業式を翌日に控えた昭和三十九(一九六四)年九月三十日、朝野の名士やマスコミを招待して新幹線試乗会が行なわれた。さりげなく席に着いた国鉄前総裁の十河信二は中継するアナウンサーから「あなたの席はあっちです」と告げられた。
そこは特別招待席であって、「あなたの席ではない」というのだ。
総裁就任以来新幹線を発想し、かつ八年にわたってその実現のため粉骨砕身してきた功労者に割り当てられていた席は、一般招待者の席だった。
去る昭和三十(一九五五)年、国鉄が経営する宇高と青函連絡船の相次ぐ大事故により世間の批判にさらされ、国鉄総裁になり手はなかった。そんななか、白羽の矢が立てられたのが七十一歳の十河であった。難問山積の国鉄経営において、ひそかに十河が企図していたのは、夢の超特急・東海道新幹線の建設である。しかし当時は、これからはアメリカのように飛行機と自動車の時代になるのだから、鉄道は斜陽化の典型だというのがすべてのマスコミの論調だった。十河は孤立無援のなか、新幹線建設に動きはじめた。
新幹線の生みの親
十河信二が自らの人生を語った『私の履歴書』(日本経済新聞社)、ならびに十河の伝記第一号といえる中島幸三郎『風雲児・十河信二伝』(交通協同出版社)の頁を開くとはっと気づくことがある。いずれもその巻末は、十河の昭和三十(一九五五)年の国鉄総裁就任を以て大団円としていることだ。総裁就任後二期八年で新幹線開通という大事業を行なうというのに......。
昭和二十一(一九四六)年、愛媛県西条市長を辞し、次いで鉄道弘済会会長を経たあと、十河は人生何度目かの浪人生活を送っていた。すでに古希を迎え、当時の定年を考えればそこで過去の人となってもおかしくない。それが、多くの死者を出した宇高と青函の両連絡船の大事故によって、国鉄第三代総裁の長崎惣之助が引責辞任したため二十九年ぶりに古巣に復帰するとは、十河自身、予想もつかないことだったであろう。
ところで、十河が世間の意表をついて総裁に就任したのはなぜか。直接的には同じ四国人の政治家三木武吉らの推挙によるものだったが、三つの要因が考えられる。
一つは先述のように、不祥事が続いて国鉄総裁に対する風当たりが強いため、国鉄内から総裁を望む者はいなかった、いわば天の時が十河に向いていた。二つには、日本の復興につれてふえはじめた旅客・貨物が大動脈である東海道本線に集中し、輸送容量は飽和状態となり、これを解決するための抜本的な対策立案が迫られていた。この課題に対処できる力量の持ち主としては、実績面で十河しかいなかった。最後は、十河自身の人間的資質に対する評価であろう。剛毅で面構えも野武士のごとく骨太、しかしながら、至誠の人柄である。
総じていえば、浪人暮らしが長かろうと、七十の坂を越えていようと、十河の人間力はなおだれもが認めるところだったのである。
孤立無援のなかから
現代から見れば意外なことがある。新幹線をつくろうと十河が意図したとき、有識者、政治家、それにマスコミもこぞってそれを"非常識な夢"としたことである。その背景には、日本の鉄道政策上に長くのしかかっていた「狭軌―広軌」論争があった。すなわち線路の幅の規格のことである。
明治初期、日本に初めて鉄道がもたらされたとき、イギリス人技師は、山が多く、川と谷が複雑に入りくむ日本の地形と貧しい予算を考慮し、先進欧米国では標準であった広軌ではなく、狭軌を採用した。当時の日本は刀とまげをやっと捨てた極東の小国、たしかに迅速に鉄道網を整えるには、狭軌は正しい選択であったが、世界の大国に急成長したあとはスピードや輸送力においてたちまち限界が生ずる。そのためにできるだけ早い段階で、すべての線路を広軌に変更すべきという議論が明治末期からあった。ところが、そのためにはかなり長い区間を一挙に切り換えるという技術的課題と莫大な予算が必要となるために、計画が浮上しては消えるといった状況がくり返されていた。
十河が総裁に就任した当時でも、焦眉の急であった東海道本線の輸送力増強案については、狭軌派が圧倒的であった。
増強案は狭軌のままで東海道本線を複々線化する案、あるいは今の新幹線ルートに狭軌を敷く案、それと広軌で別線を敷く三つの案があったが、狭軌案を採用すれば、線路容量が不足する区間から逐次線路を増設でき、輸送力増強の即効性と経営の安全性からすればこの案が当然とされた。十河がひそかに広軌別線を決断しながらも、総裁就任当初、新幹線の「し」の字も述べなかったのは、国鉄内部の専門家も外部の政治家もこぞって広軌別線をきわめて非現実的な"老人の妄想"として捉えていたからだった。
したがって、十河の新幹線建設の決断は、何よりも、その先見性が評価される。七十一歳という国鉄内で最長老の総裁が遠い日本の将来を見据え、高速鉄道の可能性に夢を馳せていたのである。また十河の指示により、東海道新幹線の開通二年前の昭和三十七(一九六二)年には、鉄道技術研究所は次代の鉄道としてリニアモーターカーの研究開発をはじめていた。その見識は驚くばかりである。
険しい道のり
実を言えば、新幹線が時速二〇〇キロを超える高速鉄道になり得るかどうかは、十河自身見通しはなかった。起工した昭和三十四(一九五九)年当時、高速化実験でもやっと時速一二〇キロに達した程度だったからである。
新幹線という大事業が、政治的決定を見ることにおいても、技術的な課題を克服することにおいても、いかに険しい道を歩んだかが想像されるが、これらの課題を信念、説得力とねばりによって十河はすべて解決し、夢の超特急を現実のものとしたのである。
十河はまず、昭和三十(一九五五)年五月の就任直後、
副総裁と技師長に、東海道広軌新幹線の検討を要請した。ところが何日か経って十河に届いたレポートはお茶を濁したような怠慢な内容だったので、十河はレポートを叩きつけて激怒した。技師長を呼び出し、「技師長にはもっと広い視野の人を頼みたいから、君、替わってくれ」と言うと、広軌新幹線反対派だった技師長は、「私もそう思います。替えてください」と答えたという。
それならば、と十河は総裁審議室の若手技師五人に検討を命じた。彼らは自分たちの調査にたびたび口を出す十河を"うるさい爺さんだ"と思いつつも、直属の上司に隠れて自宅に資料を持ち帰って作業をした。そして、昭和三十年の暮れ、彼らは鉄道技術研究所・車両構造研究室長が前年に発表していた「狭軌ならば東京~大阪間を四時間四十五分で運転可能」と題する論文を再検討し、広軌ならば平均速度二〇〇キロ、東京~大阪間を二時間四十分で可能とはじき出した。しかし、総裁の意を受けていたとしてもなお、うかつに表明できない。反対派から潰されてしまう危険性があったからである。それほど当時の国鉄の官僚機構は天下り総裁の意向をはねつけていた。
一方で十河は、国鉄理事であった島秀雄を十二月に新しい技師長に据えることに成功した。島は名蒸気機関車「D51」の設計を手がけた名うての技師で、広軌提唱者、高速列車研究の第一人者であった。島は十河以前の組織が硬直化した国鉄に嫌気がさし、住友金属工業取締役に転出していたが、熱心な十河の懇請に折れ、復帰を決めたのである。
さらに十河は、鳩山一郎首相、岸信介自由民主党幹事長ら政治家に新幹線への理解と支援を求めて歩いた。そのうちの何人かは助力を約束してくれたが、大勢は無関心だった。多くの政治家は、新幹線の意義がわからず票に結びつかないと思っていたからである。
昭和三十一(一九五六)年一月に総裁審議室の五人は十河の指示により検討結果を「東海道広軌鉄道計画」として国鉄の常務理事会に提出する。しかし、理事会の反応は冷たいものだった。
時には策士となって
四月になって理事会は、「東海道線増強調査会」を設置する。名前のとおり「東海道線をいかに増強するか」が目的であるが、十河と島はこの会を、経営幹部に新幹線建設の説得を図るための場とした。この調査会は五回で終了したが、この時点でも「広軌新幹線建設」という結論は出なかった。二人の前には依然理事たちが反対のスクラムを組む厚い組織の壁があった。しかし、二人はいつか風向きが変わることを信じ、くじけずに次の機会を窺い続けた。
大きな転換点は、調査会から五カ月経った昭和三十二(一九五七)年五月二十五日に開催された鉄道技術研究所の創立五十周年記念講演会だった。「東京~大阪間三時間への可能性」と題して鉄道の可能性を一般市民にPRしたところマスコミは大きく報道し、一躍社会の脚光を浴びたのである。
当時の鉄道技術研究所は、国鉄内では主流の組織から外れた傍系の一機関にすぎなかった。しかし、各研究室の技師たちは十河らの活動とは別個に、車両・軌道・信号などの超高速鉄道技術の開発に励んでいた。そして、五十周年を機に互いの技術を集大成し、鉄道が果たすべき使命感を共にして、その実現をめざし世間に大きくアピールしたのである。
実はこの催しは、十河や島が新幹線を大衆にしかけた"お祭り"だったという説もある。
講演会を催した鉄道技術研究所の技師たちを処分すべきだと言い張った理事もいたが、十河はそれを逆手にとって、理事会の場に四人の技師を呼び、その講演会を再現させた。そして技術的根拠をテコに、一気に広軌新幹線建設への流れを引きよせたのである。
これによって十河は運輸大臣に東海道本線の増強を申請、国鉄本社内に「幹線調査室」を設置し、新幹線を具体的に計画する組織がようやくできあがった。また、運輸省も十河の陳情を受けて「日本国有鉄道幹線調査会」の設置を決定し、ほぼ同時に新幹線を国家プロジェクトとするための舞台が整えられた。これら一連の円滑な進行の背景には、国鉄内のみならず、政治の場においても十河の類まれな折衝力が発揮されていたのは言うまでもない。
このように、十河は時には策士のごとくにふるまって、この難航するプロジェクトを最後は詰め将棋のように完成させた。そして、技術陣も十河の期待に応え、開業を一年後に控えた昭和三十八(一九六三)年三月三十日、試作車両が世界最高時速二五六キロを記録、成功を確実なものとした。
その先見性にあったもの
ソニー創業者の井深大は、友人であった十河自身から新幹線プロジェクトの成功理由を聞いている。それは次の六点であった。
1)住友金属工業社長に何回も頼んで島秀雄を獲得したこと
2)広軌新幹線のために政治家を説得できたこと
3)工事費に三千億円かかることを理解しながら、国会を通すために度胸よく約千九百億円に削除したこと
4)技研の講演会により、東京~大阪三時間の可能性を宣伝、ジャーナリズムをうまく利用したこと
5)むずかしい委員会(「東海道線増強調査会」)で、狭軌にこだわる口やかましい人たちを説得できたこと
6)世界銀行の借款を得られたこと
井深は、十河が説得に次ぐ説得によって総合的に新幹線を実現させた手腕について"説得工学"だと評した。十河の進め方が、地道に論理に徹して人間を説得した点を考えれば、合点がいく命名といえよう。ただ、それを推進したのは、「まったく執念によってできた仕事」と断じている。
十河の人間力によって新幹線が実現できたのは事実のこととして、あらためて評価すべきは、当初から広軌新幹線こそ国家百年の計と決断できていた十河の先見力である。その拠り所はどこにあったのであろうか。
十河は新しい機械好きだった。大正九(一九二〇)年頃、鉄道省の会計課長時代に、当時アメリカでも購入が困難であったIBMの機械をリースで手に入れ、それまでカードによって分類整理していた統計処理業務を一気に高速処理できるように改善したことがある。集計に一年かかっていた業務を数日で処理できたため、鉄道省内でも機械化を評価する声が高まった。それでもあきたらず十河は外国人技師の招聘を訴え、実現した。
十河は当時をこうふりかえっている。
「一介の会計課長だった私のところに米人顧問がいて、何かと相談し合い、よその官庁、会社などでは、到底買うこともできないような機械をいろいろ整え、思い切った機械化を断行し得たのだから、まことに愉快だった」(有賀宗吉『十河信二』)
このように、元来科学技術に対する偏見を持たず、本質的によいことは即座に実行するという優れた資質を若い頃から発揮していたのである。また昭和元(一九二六)年、経理局長となっていた十河は、収賄の疑惑を得て拘留され、そのために失職する。冤罪であったのだが、官僚としては拭い切れない汚点である。しかしまたこの経験こそが、ねばり強い人間性を育んだともいえるわけである。
後年十河は、大事を成すには三つのポイントがある、と常々言っていた。それは、
1)志を大きく立てて、ビジョンを持て
2)実現可能な科学的な根拠を持て
3)実現のためには政治的な策略も必要
ということであった(笹季興「十河信二さん 私の昭和史」)
こうした自己能力分析からも、十河の決断力と実行力はすなわち、センスとたしかな見識、人間的器量の融合によるものだったといえよう。
業績は不滅
昭和三十八(一九六三)年五月、新幹線建設に関わる予算超過がにわかに取りざたされ、開業を目前にしながら十河は任期満了で辞職、開業式にさえ招待されなかった。国家のために比類ないプロジェクトを達成しながら、後継の国鉄幹部はただその一事を以て瑕疵と捉え、開業式において遇する配慮をしなかった。まさに狭量、汚点ともいうべき仕打ちであった。
その後、新幹線が経営的にも活況を呈し、国民に大きな誇りを与えたという評価によって、あらためて十河の顕彰が検討された。しかし十河は、「賞をあげるなら、島君にあげてくれ。島君が顕彰されないうちは、ぼくはいっさい何もいらない」と言った。昭和四十六(一九七一)年、島秀雄は文化功労者として表されるが、十河の部下を思う気持ちが反映されたのであろう(さらに島は九十三歳にしてエンジニアとして井深大に続いて文化勲章を受章する)。
十河については、東京駅十八・十九番ホームの新橋よりにレンガ造りのささやかなレリーフがつくられた。ややいかめしい顔つきをしている。日々何万人もの利用客が行き来するがめったに気づく人はいない。できあがった自分のレリーフを眺めて、十河はにこりともせずただ一言こうつぶやいたという。「似とらん」。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。










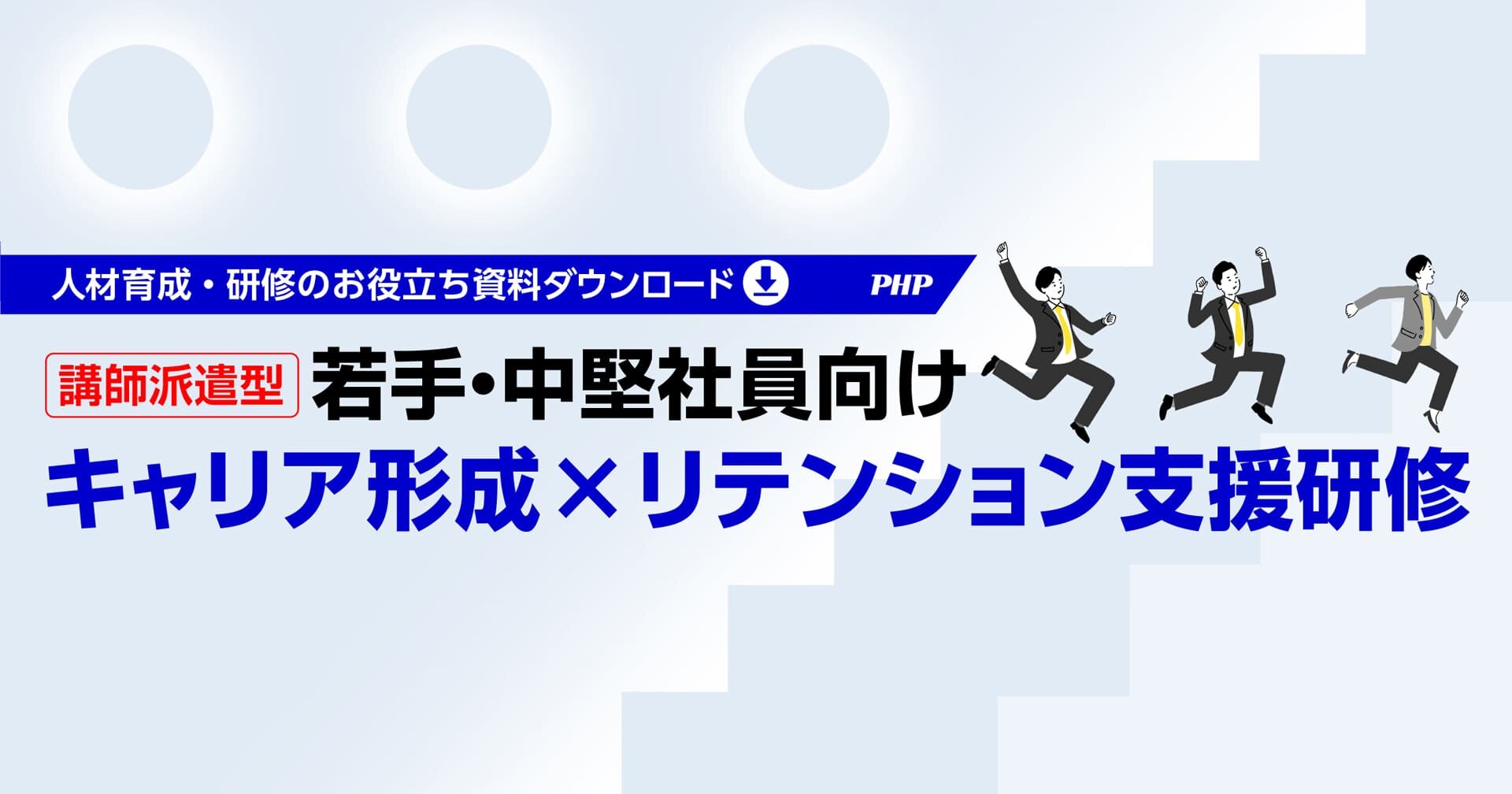















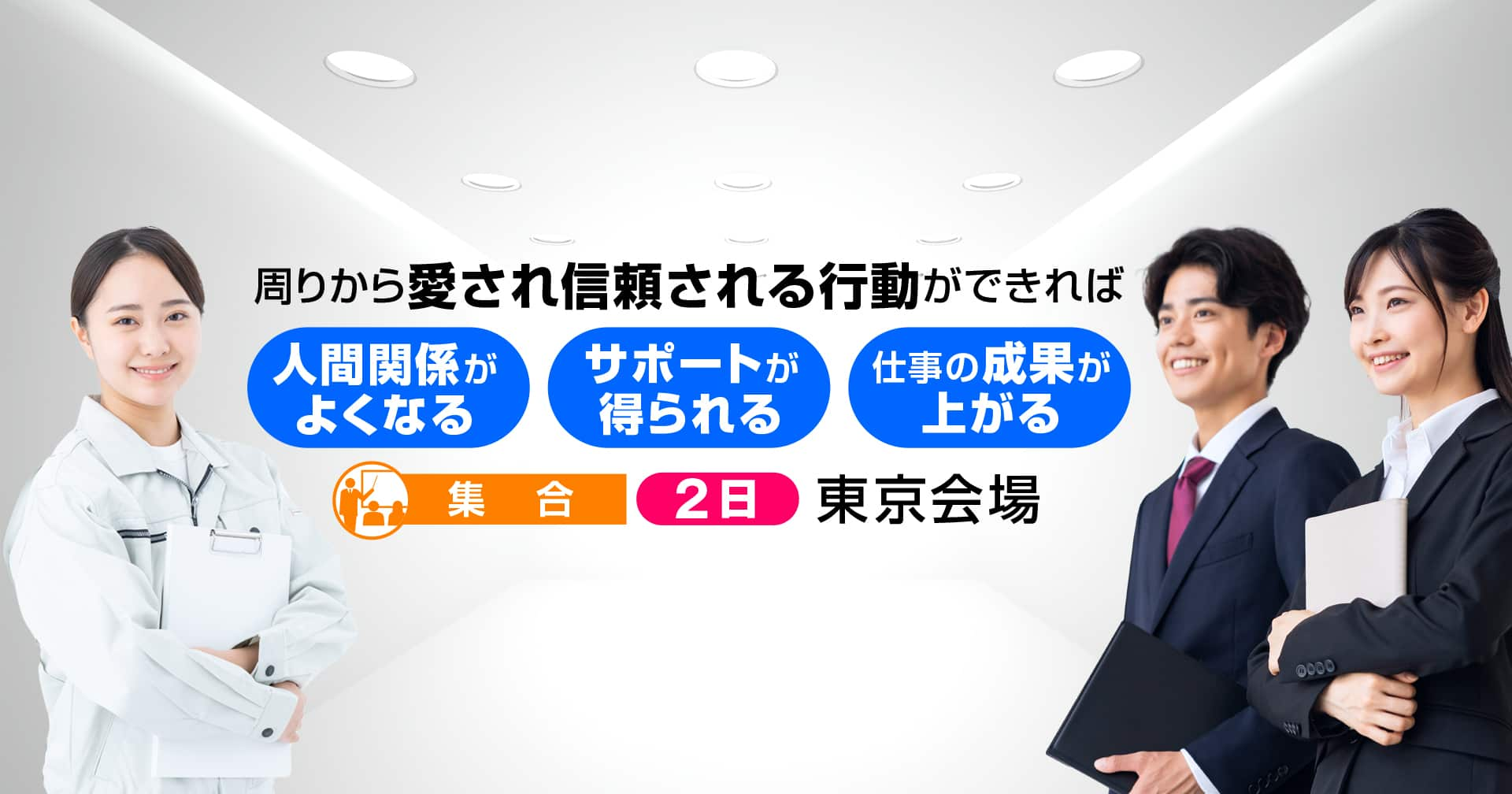










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







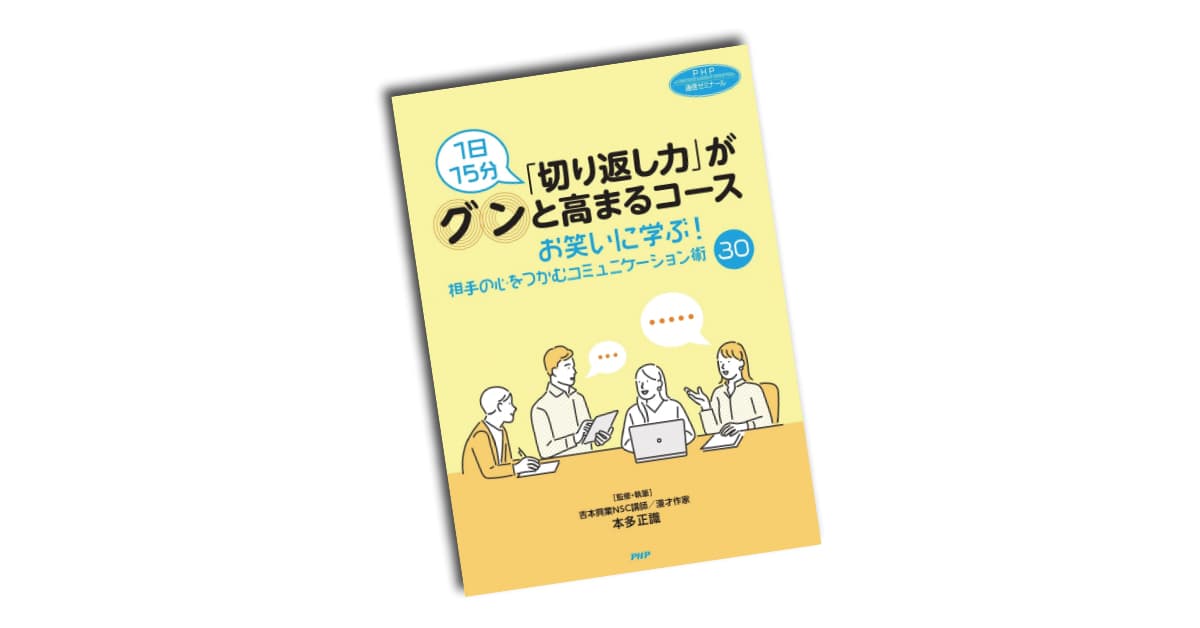






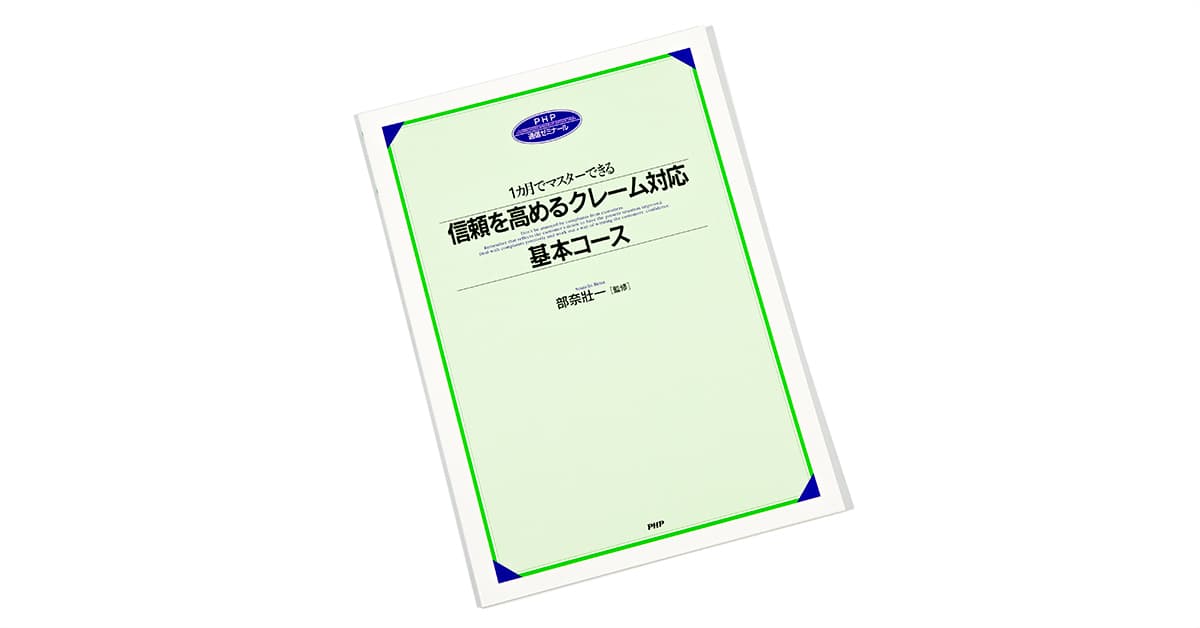





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

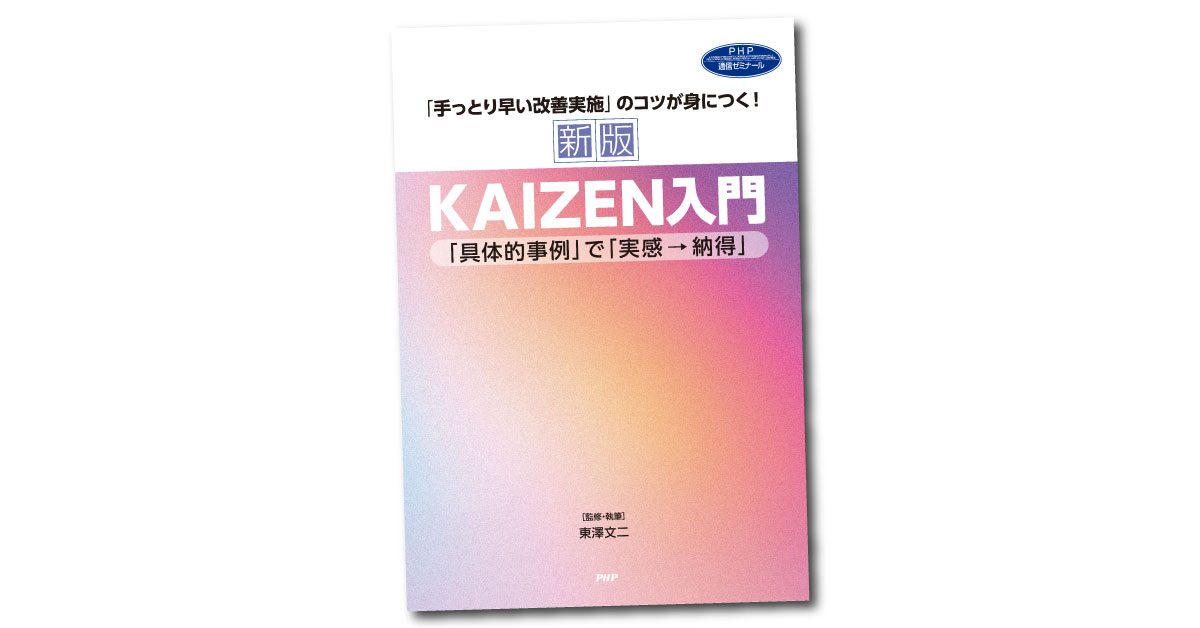










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


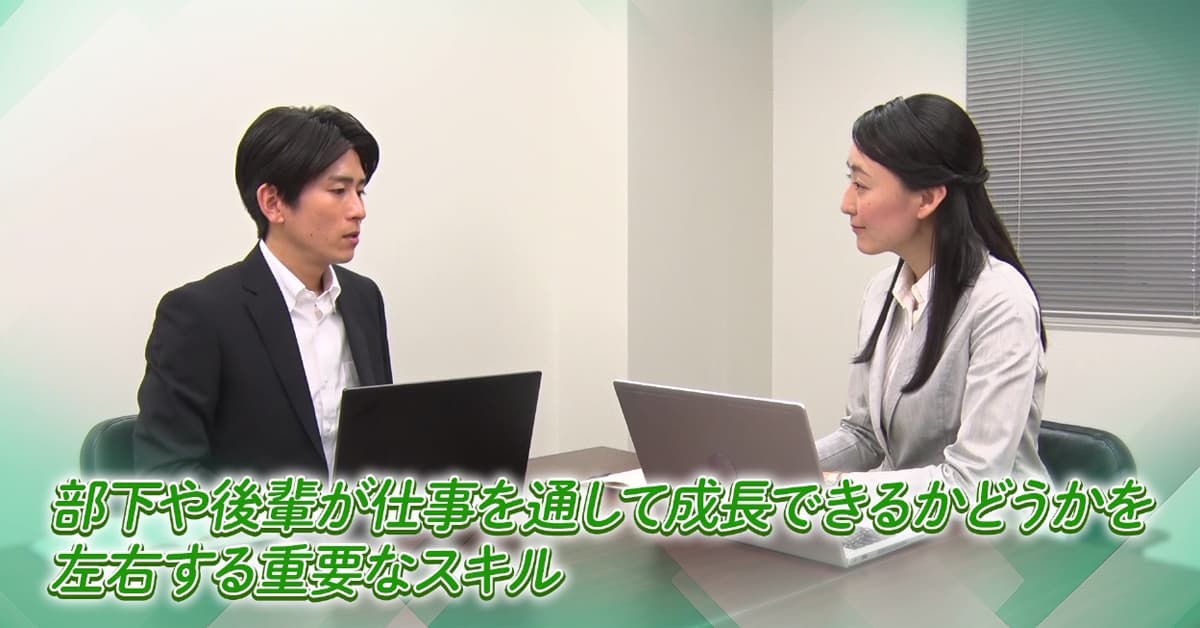
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
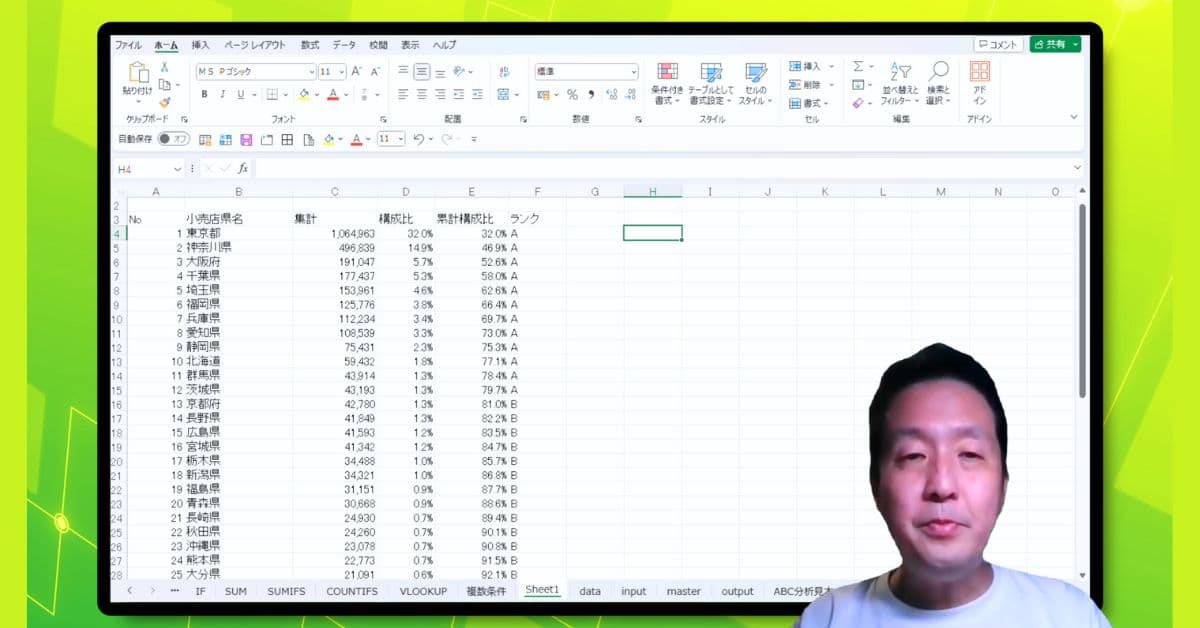
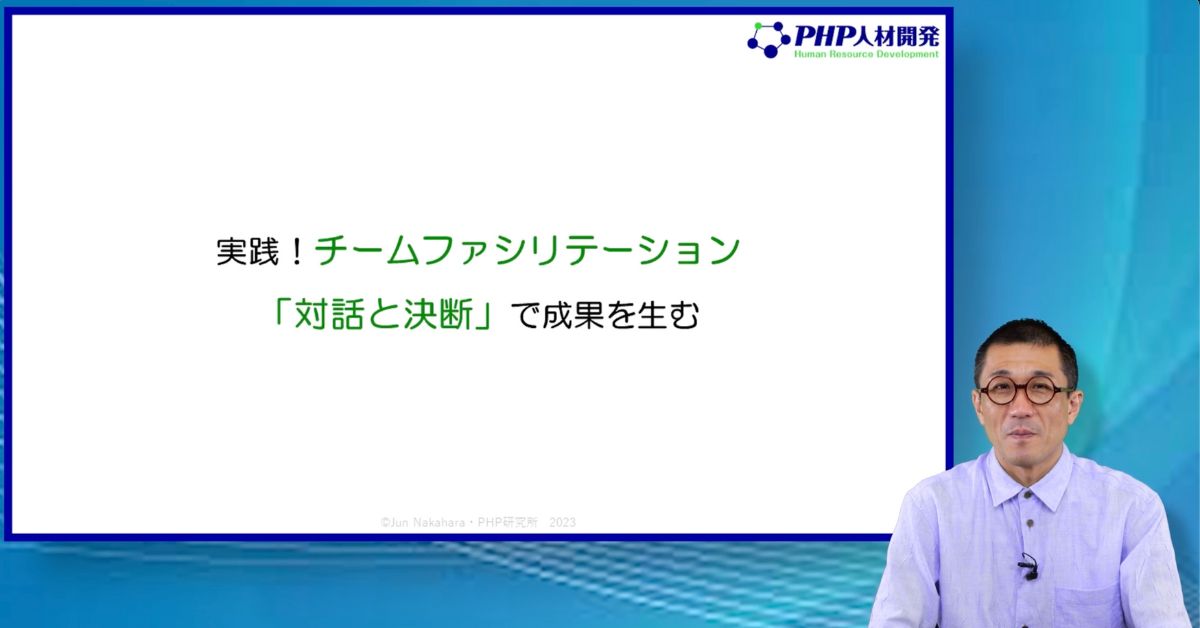
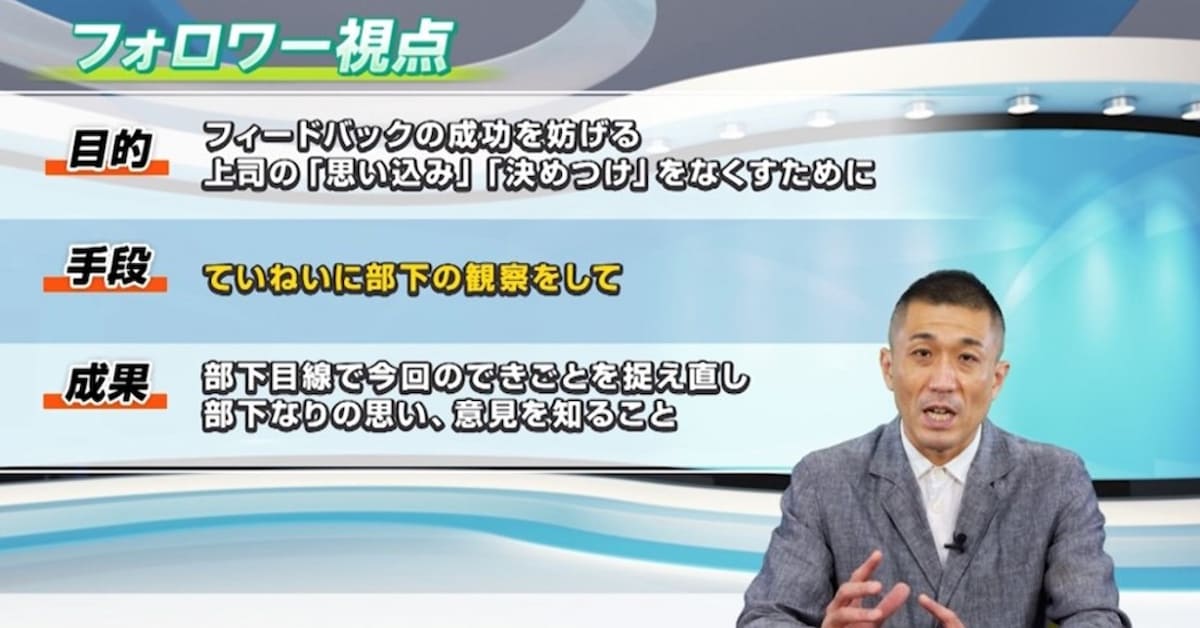

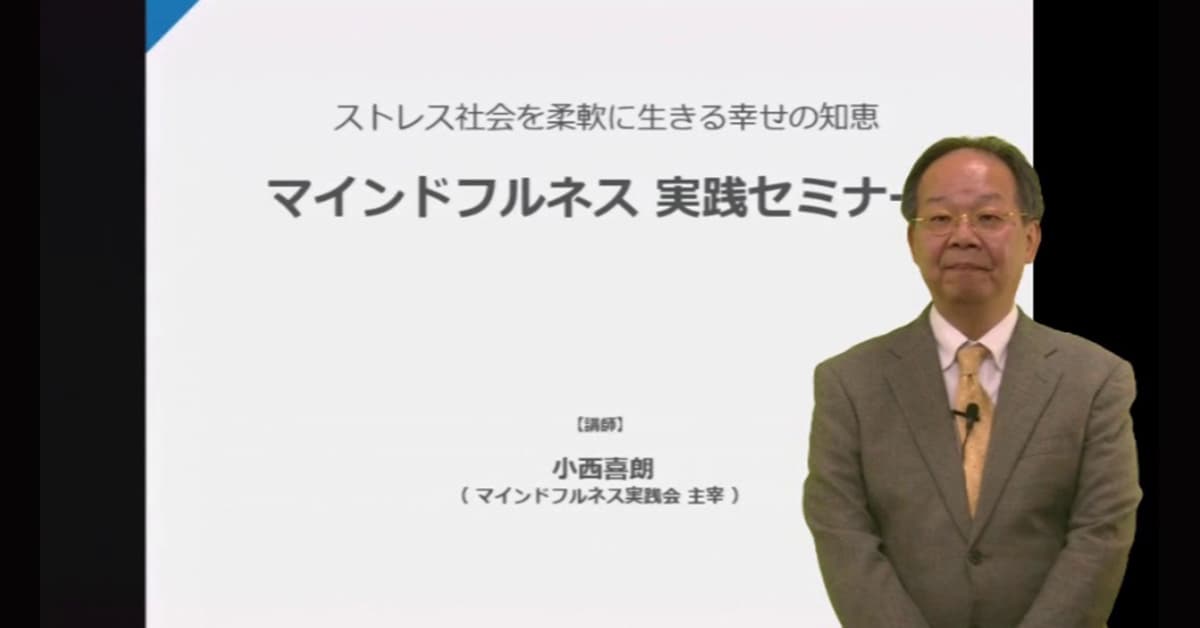

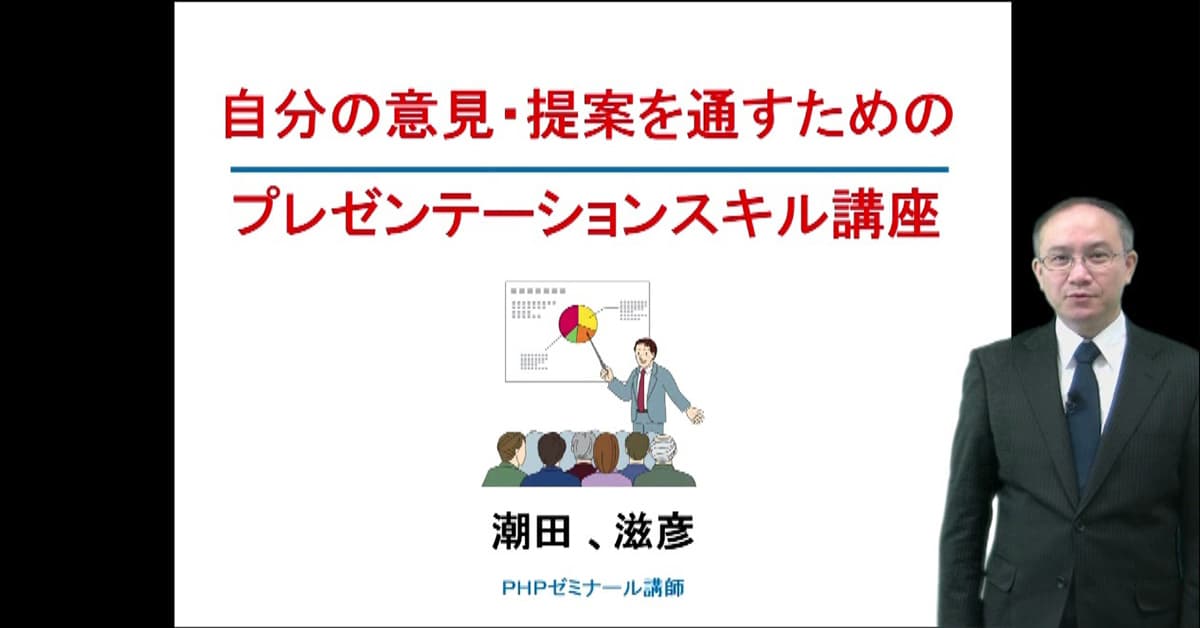
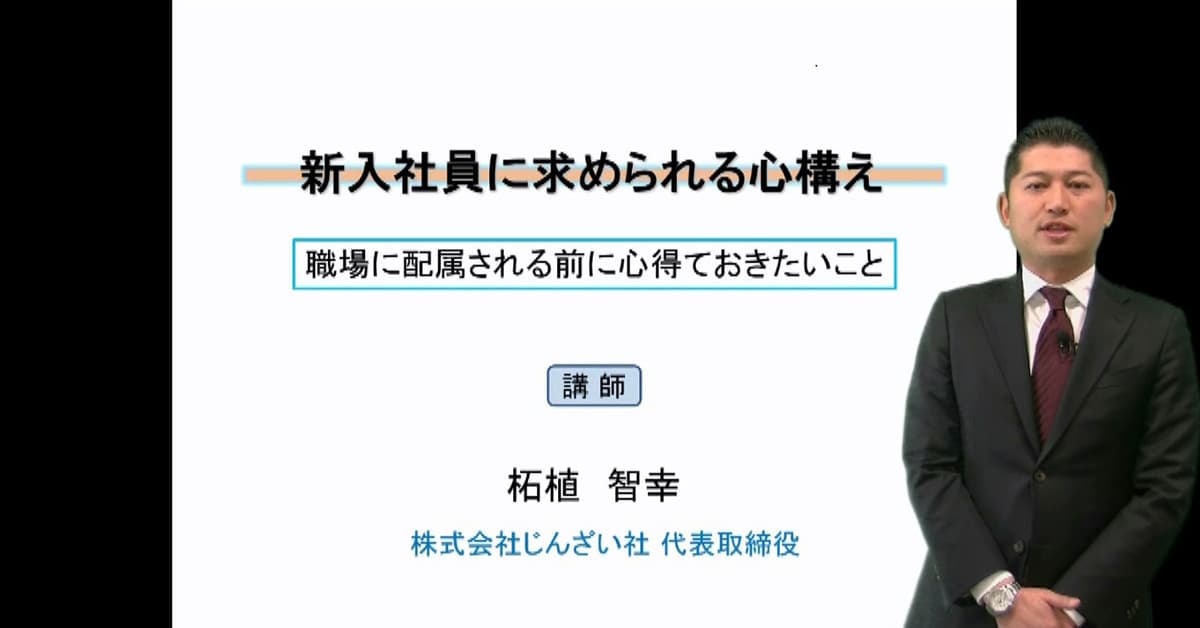
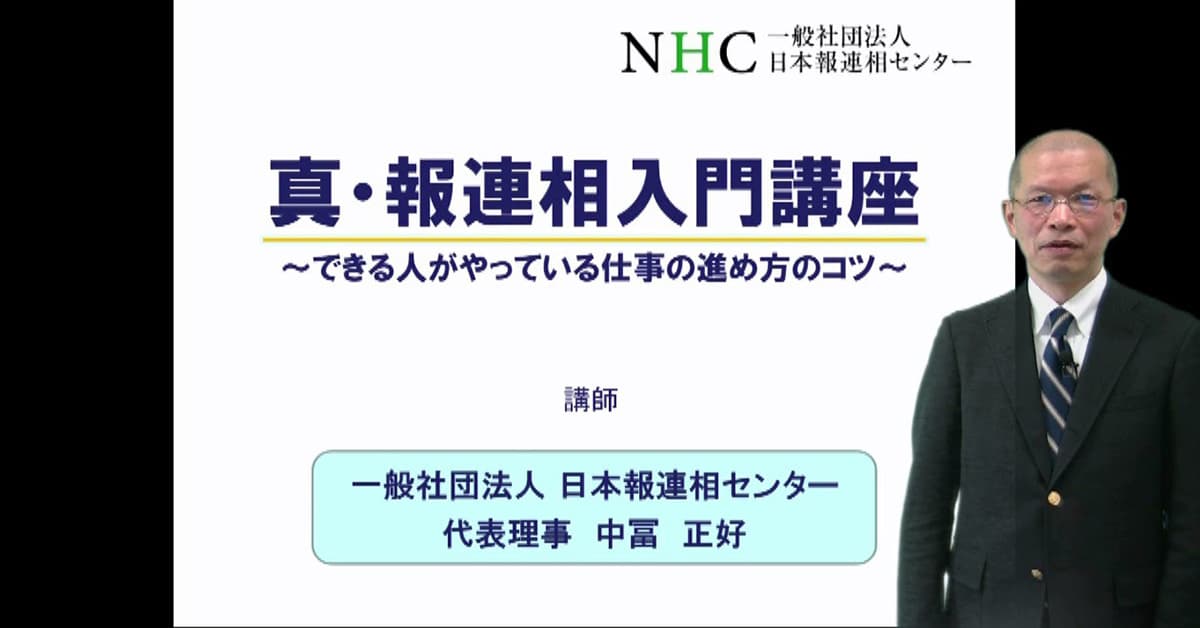
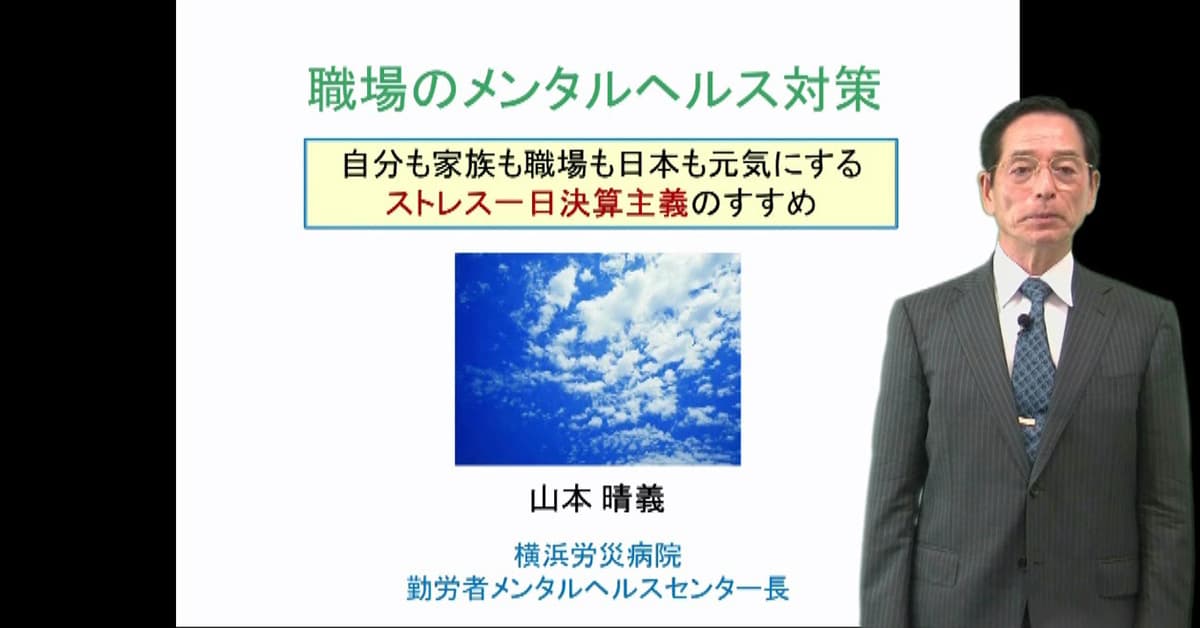
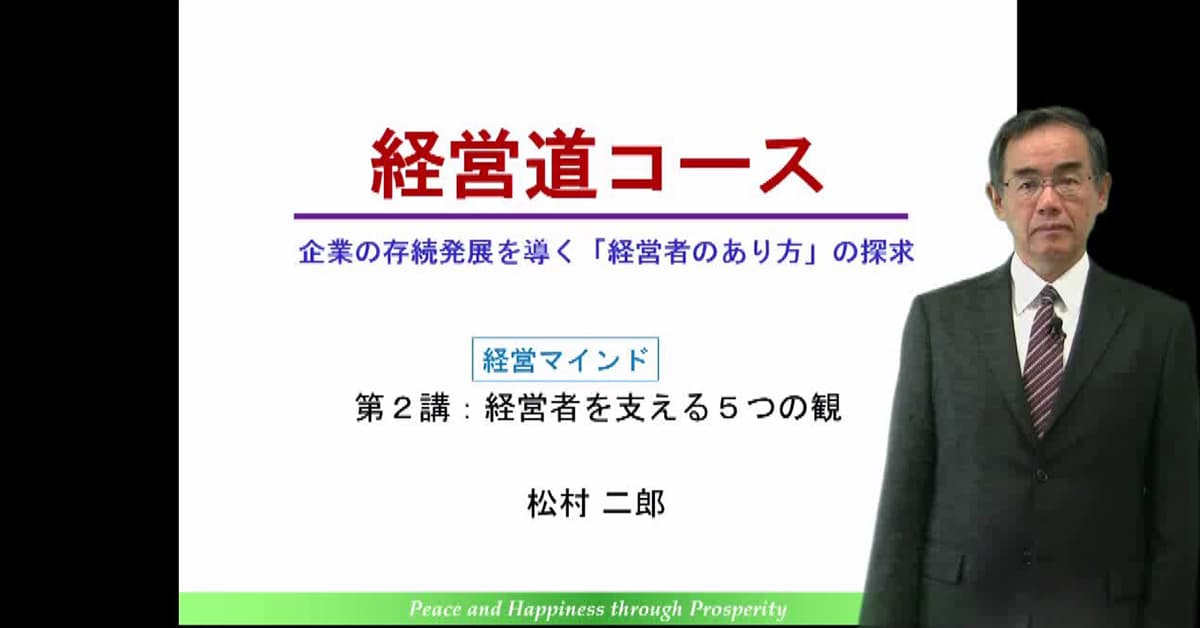
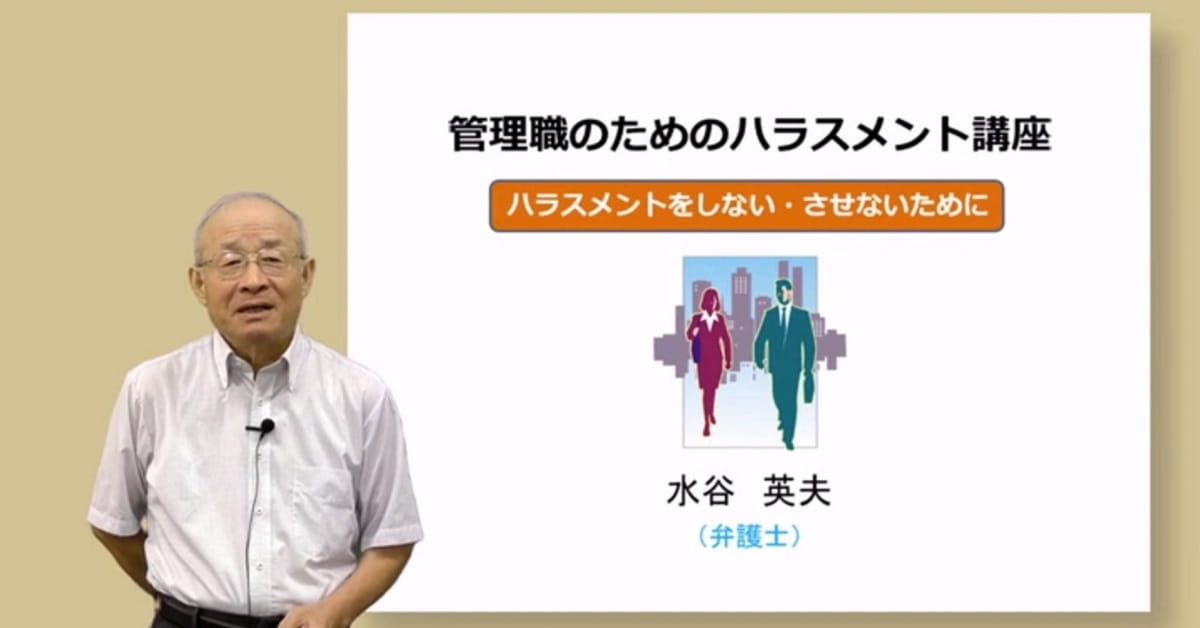

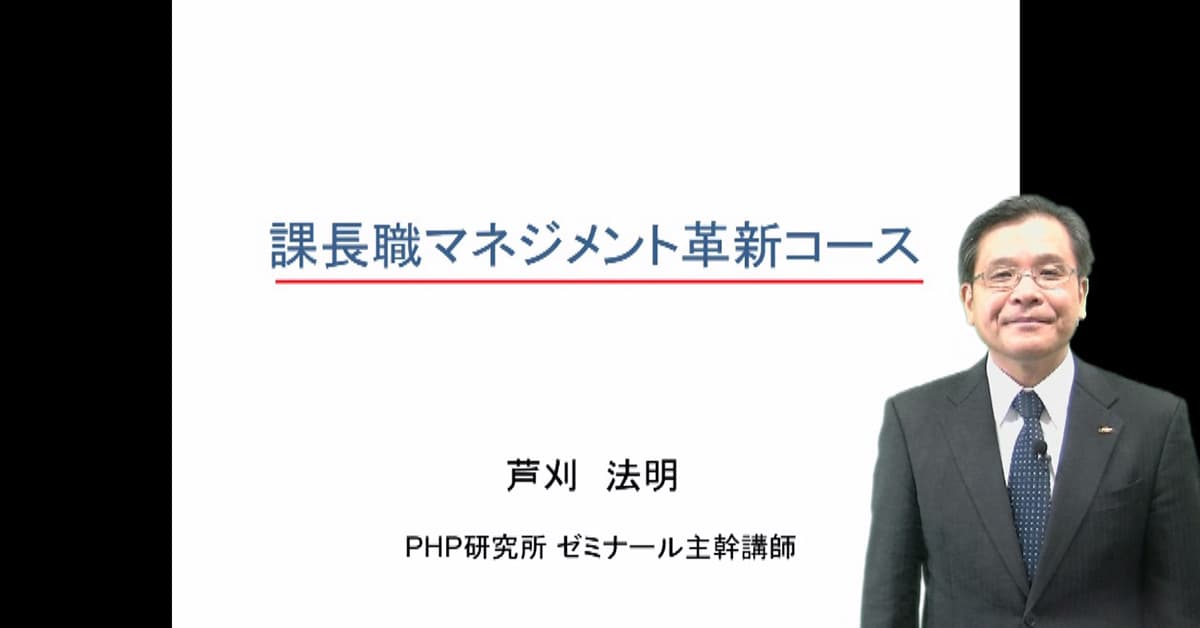



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















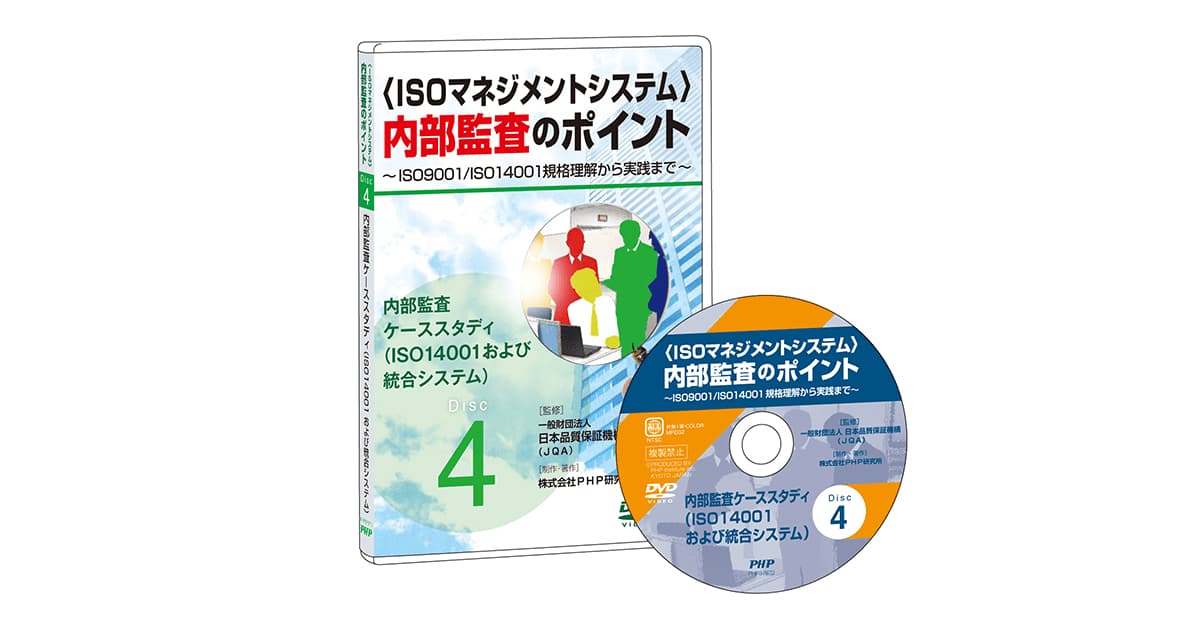





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
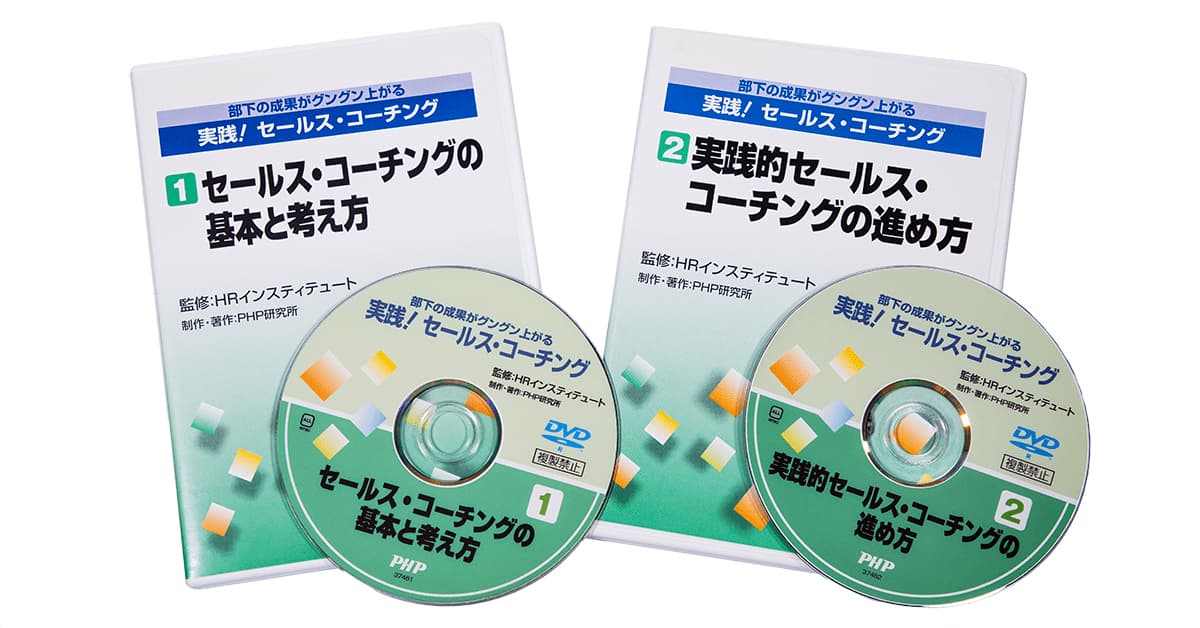




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)