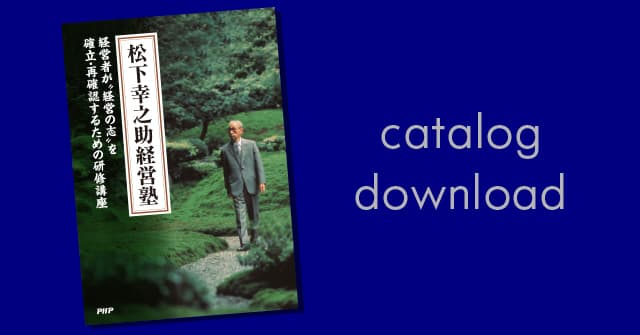松下幸之助の決断~業界首位を呼び込んだフィリップス社からの技術導入
2020年10月 5日更新

オランダのフィリップス社との技術提携で、業界首位に立った"経営の神様"松下幸之助。企業DNAを信じて共存共栄の道を目指した、その決断の背景に迫る。
昭和三十年代に予想される、来るべき家電需要に対して、万全の備えをしておかなければならない。しかし、会社は敗戦の痛手からようやく再建の手ごたえをつかんだ程度で、時代の寵児と期待されるテレビやラジオの開発において、技術力が覚束なかった。真空管をはじめ電子管技術の立ち遅れは、外国企業との技術提携により補完しなければならない。
一方、日本のテレビ研究の標準は次第にアメリカ方式へと定まっていく。そうした趨勢にもかかわらず、欧米への視察を終え、松下幸之助が社運を賭けるに足る提携先に選んだのはオランダのフィリップス社であった。交渉は難航し、その意義を何度も問い直した末での決断であった。しかし、結果的に同社との技術提携によって、松下電器はテレビ開発競争の勝者となったのである。松下幸之助はどのような思惑のもとにフィリップス社を選んだのであろうか。
技術提携が成功した稀有の決断
現代人の生活においてテレビは、市場に出回って以来、現在ももっとも重要な家電製品であることに変わりはないであろう。そして日本のテレビ産業は今や世界市場を牽引している。敗戦によってテレビ研究が欧米よりも遅れていた日本のテレビ産業が、昭和四十二(一九六七)年にアメリカの生産を上回って以降、現在の地位を築いたのは、国家産業の見地からも日本の誇りといえよう。
その輝かしい業界のなかで、今も旗頭となっているのが松下電器産業である。同社は高度成長期に生産シェア首位になるが、遅れていた日本のテレビ産業にあって、第二次世界大戦後のテレビ研究の再開時には、ライバル社の開発よりなお遅れていたという。そこから首位の座をつかむまでには、製造からマーケティングまで、さまざまな分野における工夫と努力が結集されたと見られる。ことに品質面で劇的な向上を促したのが、オランダのフィリップス社との技術提携であった。この技術提携が、同社の家電産業としての飛躍に大きな役割を果たしたことは衆目の一致するところである。
この社運を賭けるほどの決断は、その技術提携の交渉が生半可なものではなかったこともあって、松下幸之助をサイン直前まで悩ませたという。
松下は何を以て決断できたのであろうか。
その前にまずテレビ研究の歴史を少しふりかえっておく必要があろう。そもそも日本のテレビ技術は大正十五(一九二六)年に当時浜松高等工業の高柳健次郎がブラウン管による電送・受像の実験に成功して以来、世界水準で推移していたといわれる。"テレビの父"といわれた高柳の活躍で昭和十(一九三五)年頃には、電子式テレビの技術的課題はかなり解決されており、あとはいかに実験を重ねていくかが開発のポイントであった。
折しも、昭和十五(一九四〇)年に東京オリンピックが予定されていたこともあり、その放映と受信がすべてのテレビ技術関係者の目標となるに及んで、第二次世界大戦開戦前夜のテレビ研究はかなりの熱気をはらんでいた。
ところが日本が戦争に突入したことで、テレビ研究は大きく停滞することになる。戦時中、民需向けのテレビ研究は、軍需面中心の研究に移行してしまったし、何にも増して敗戦の打撃がテレビ研究に与えた影響は大きかった。GHQが昭和二十(一九四五)年十月から翌年六月までテレビ研究を禁止。この停滞や物資の不足もあって、テレビの技術開発は欧米と比べると七年から十年遅れたといわれる。
したがって研究が再開されたとき、業界各社は市場にいち早く製品を投入するためには、先行している欧米企業からの技術導入が不可欠、と考えるようになった。
松下幸之助の選択
戦後の松下電器におけるテレビ研究の再開は早いものではなかった。東芝が昭和二十四(一九四九)年五月に再開したのに対し、松下電器は昭和二十六(一九五一)年七月。発足したテレビ課はわずか三人からのスタートであった。ことに重要な部品である真空管こそ戦時中から自社生産によって調達できるようになっていたが、ブラウン管についてはライバル社の日本電気製を使用するか、アメリカ製のブラウン管を購入するしかなかった。
この状態のままでは追いつくことはできても追い越すことはできない。どの企業と提携するか。それは家電企業として飛躍しようとする松下電器にとって大きな転機となるはずであり、社運を決定づける重要な決断であった。その決断のために松下幸之助が最初に外国を訪問したのは昭和二十六(一九五一)年一月のことで、行き先はアメリカであった。次いで十月には、再びアメリカを訪れたあと、オランダ、ドイツ、フランス、イギリスを回った。二度目の外遊の目的は欧米の優れた会社を見聞し、実質的には、技術提携および経営の提携先を探すことであったといえよう。そして、この重要な選択で、松下幸之助が選んだのがオランダのフィリップス社だったのである。
フィリップス社は、当時で社業六十年、全世界に三〇〇近い工場と販売拠点を持ち、製品の八〇パーセントを海外へ輸出する世界有数の電子機器メーカーであった。フィリップス社の要請により提携の受け皿となる会社として、昭和二十七(一九五二)年十月、松下電器との合弁によって松下電子工業が設立されたのである。
フィリップス社との交渉
その決断は見事な成果を生み出した。技術提携によって管球部門の品質は向上し、市場におけるテレビ部門のシェアも大きく躍進した。昭和二十九(一九五四)年八月発売の一四T―五四九はフィリップス社のトランスレス方式による一四インチテレビで大ヒットを記録。これによりテレビの生産シェアで松下電器は第三位になった。その翌年六月発売のT―一四二二によって十万円を切ることに成功し、さらに安定した競争力を持つ。そして昭和三十三(一九五八)年二月発売のT―一四C一は価格、品質、デザインにおいて好評を博し、翌年にかけてついに松下電器はシェア第一位を獲得したのである。
フィリップス社との技術提携は、その交渉過程において非常に難航したことはよく知られている。フィリップス社が技術提携に応じる条件は、提携の受け皿となる新会社の資本金の七〇パーセントを松下側が持ち、フィリップス社の負担は三〇パーセントとすること、しかもその出資分は松下側が支払う技術援助料を充当するというものだったから、結局全額松下側の負担であり、松下電器にとってかなり不利な内容であった。その上、技術援助料は七パーセントという高率を要求された。アメリカの会社なら通常三パーセントだったのである。さらに合弁によって設立する松下電子工業の資本金は六億六千万円。親会社の松下電器の資本金五億円を上回るもので、その出資規模を考えれば決断の重さは尋常ではない。技術提携がはっきりした成果を見せなければ、新会社も松下電器本体も存続に関わる打撃をこうむるであろう。
この投資が成功するのかどうか、松下幸之助は悩み抜いた。そしてまたこの提携条件がはたして適切かどうかも。この交渉過程で有名になったのは、松下幸之助がフィリップス社の高額な技術援助料に対して、「経営指導料」というものを主張し、認めさせたところである。これは、「フィリップス社の技術援助に価値があるならば、松下電器の経営指導にも価値がある」と確信して要求したもので、前例のない画期的な発想であった。「相手は非常に困った顔をしたが、結局それを承諾した」と松下幸之助は回想している。この結果、フィリップス社の技術援助料は四・五パーセント、松下電器の経営指導料が三パーセントということで合意に達した。
技術以外の決断要素
さて、ここで大きな疑問が出てくる。設計をはじめとする標準がアメリカ方式にあったにもかかわらず、なぜ松下幸之助はアメリカの企業ではなく、あえてオランダのフィリップス社を選んだのであろうか。
テレビの基本特許をたくさん持つアメリカのRCA社も候補にあったという。この決断について松下幸之助は後日雑誌で、「技術提携のロイヤリティがアメリカの会社は三パーセント、フィリップス社は七パーセントである。なぜこんなに差があるのかと調べてみると、フィリップスの方があらゆる点において優れている。私はなるほど七パーセントの価値はあると思った」と話している(「難局を切り抜ける条件」『実業之日本』一九六二年七月十五日号)。
松下が認知したフィリップス社の価値とは、提携する技術のことだけではなかった。
とくに重視していた点は、フィリップス社の社歴や置かれた環境が松下電器と似通っていたことである。創業者アントン・フィリップスが電球製造からはじめて、一代で成長した会社であること。そして日本よりなお国土が狭く、資源も乏しいオランダにありながら世界的企業に成長した実績を持つこと。けっして恵まれていない条件ながら、同社が努力と工夫を頼りに発展してきたところに、松下幸之助は共通点が多いと感じたのである。
経営手法についても、昭和三十九(一九六四)年に刊行された伝記『アントン・フィリップス』(紀伊國屋書店)の冒頭で、推薦文を執筆した松下幸之助はこんな一節を記している。
「私がフィリップス社に対して非常に敬服し、感心している点の一つは、この会社が、急速な発展をとげたにもかかわらず、あらゆる点において、実にうまいバランスがとれているという点である。言いかえれば、つねにバランスある姿において、成長発展をつづけてきたということである。その大きなものの一つが、技術と販売のバランスである。何れも兄たり難く弟たり難しというわけで、優れた技術と優れた販売が実にうまく調和されている......」
この指摘もまた、松下電器が家庭電器事業においていち早く流通網を整備して成長した経営手法を思えば納得がいく。
また経営に臨む姿勢も然りだった。松下幸之助が何よりも評価していたのが、フィリップス社が社の発展のために、つねに自主独立の信念のもと不屈の志を以て海外展開に挑み続けてきたことであった。自主独立の経営もまた松下幸之助の信条である。こうした総合的な見方のもとに、決断は下されたのであった。
「結婚」といえるまでの共鳴
フィリップス社も松下電器も厳しい提携交渉を経ながら、互いにこの提携を「結婚」と呼び、信頼関係を強調した。その意味するところは、たんなる契約関係にとどまることがなかったことからも窺える。松下幸之助は、松下電子工業の責任者に、「最初の五年間は黙ってフィリップス社に教えてもらえ。言いたいことがあれば五年経過してから言うように」と諭していたという。そして、フィリップス社も基礎技術から最新情報まで、誠実に対応していった。技術開発・設備面だけではなく、「バゼットシステム」といった生産・経営の管理手法、またマウンター(組立作業者)の訓練を行なう「マウントスクール」といった人材教育、アフターサービスのプロフェッショナルを招いての勉強会に至るまで、時に提携契約の範囲云々を問わず、現場における細かなアドバイスのレベルにも及んだという。
「ルーペイズム」もその一例である。フィリップス社から派遣されてきた技術顧問F・J・セーが松下電子工業の現場を巡回し、ルーペの使い方や本来あるべき美しいマウント(図面どおりつくる電極組立部)の姿を指導した。すると、七〇パーセントが限界であった真空管製造の歩留まりが九五パーセントまで急上昇したのである。これはルーペの使用法という技術上のことではなく、彼らに共通する一つのものづくり哲学、先入観なしに素直に物を見、その本質を見抜くという考え方で、同社の現場現物主義の基本になる考え方に根ざしていたことだった。
松下幸之助が企業家の修養として自己観照に努め、社員にも素直なものの考え方をするよう提唱していたことは知られるとおりである。割符を合わせたような価値観の共鳴が「結婚」と言うにふさわしい濃密な協力関係を生むに至ったのであろう。
フィリップス社とは、その後、昭和三十五(一九六〇)年から定期的に技術連絡会議(コンタクトミーティング)が行なわれるなど、関係を深め、昭和四十二(一九六七)年には契約期間が満了したが、さらに十年間の延長が決定した。このとき、技術援助料と経営指導料は二・五パーセントずつとなり、昭和六十二(一九八七)年には二・四パーセントずつに、そして平成五(一九九三)年、松下電子工業の海外展開を含む事業拡大に伴い、所期の目的を十二分に達したとのことで提携は解消されるに至ったのである。技術の導入だけが目的であれば、おそらくもっと早くに提携は不要になっていたであろう。それがかくも長期にわたったのは、松下電器の「恩を大切にする風土」があってのことに違いあるまい。
志と哲学あってこその決断
今、ますますさまざまな技術の融合、コラボレーションこそが企業の将来性を決定する重要なポイントとなっている。そこで問われるものはいったい何であろうか。
先に述べたように、松下電器のテレビ躍進を支えたのは、昭和二十九(一九五四)年八月、フィリップス社の技術を生かした一四インチテレビ一四T―五四九の成功であった。
しかし、この開発時において松下電器は、彼らの技術をそのまま単純に受容したわけではなかった。フィリップス式テレビの最大の特徴は、簡略な製造が可能なトランスレス方式というものであったが、ヒット商品一四T―五四九の開発は、電子管こそ同社製を使用したものの、設計はアメリカ式に近いものを採用し、独自に部品数を減らすことに成功したからこそ、高品質にして廉価な商品の開発を実現できた。
すなわち、フィリップス社の技術をただ導入するのではなく、彼らの誇りとする自主独立の気概を持って、新しい技術を生み出したところに見事な成果を上げることができたわけである。大事なことは、技術を導入しつつも、いかに独自の開発をめざすかということであろう。
画期的だといわれる経営指導料の発想も、当初フィリップス社は当惑したというが、"その心意気やよし"と認めたのは、やはり両社に共鳴し認め合う土壌があったからに違いない。社運を賭すほどの大きな提携というものは、ないものをただ補い合うという安直な理屈ではなく、提携する企業同士の志の高さ、そして哲学の相性によって大きく成果が分かれるものではないだろうか。松下幸之助のフィリップス社との技術提携の決断はその意味で、実に企業家らしさに満ちた最高の事例であったといえよう。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。










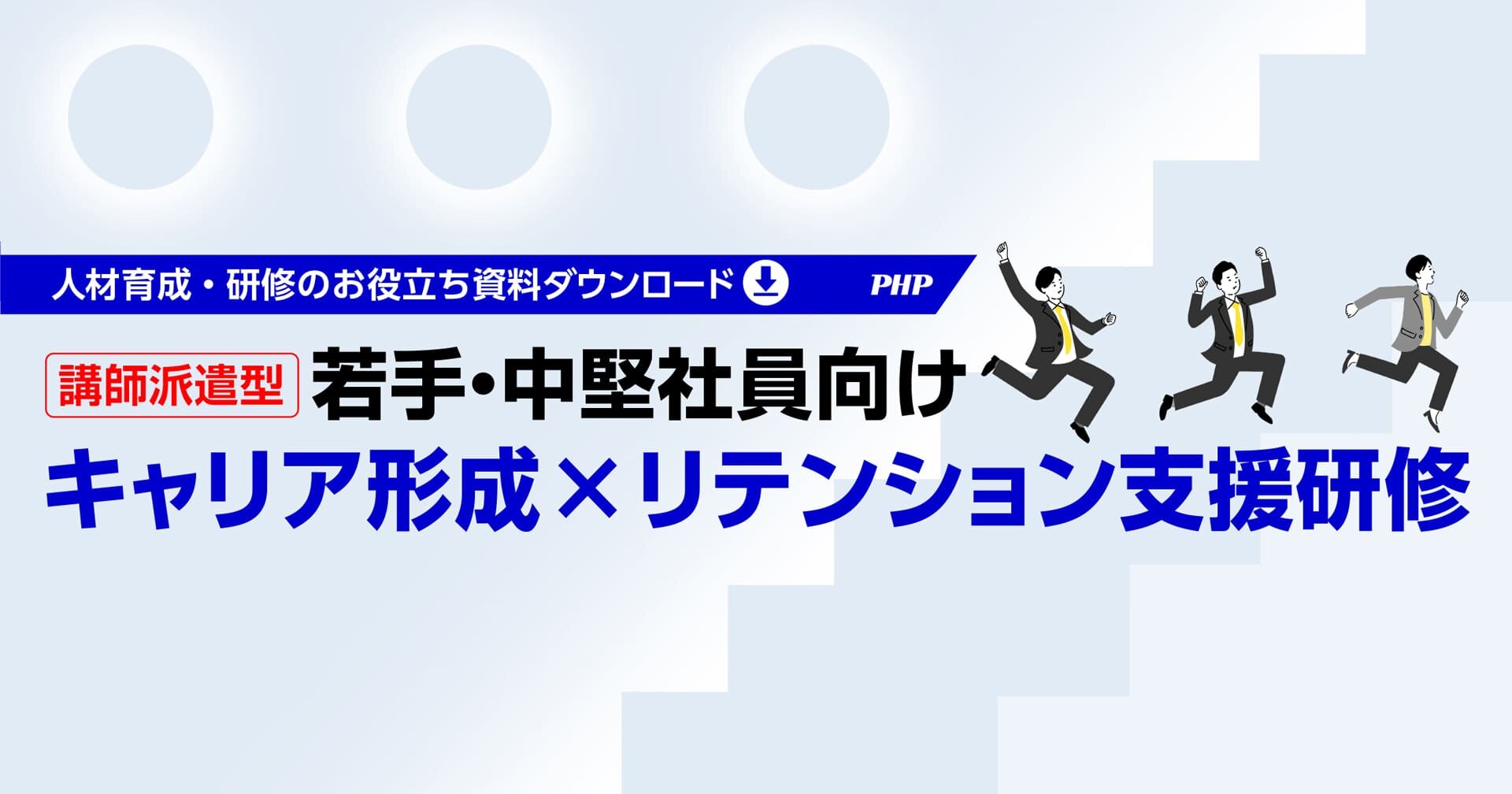















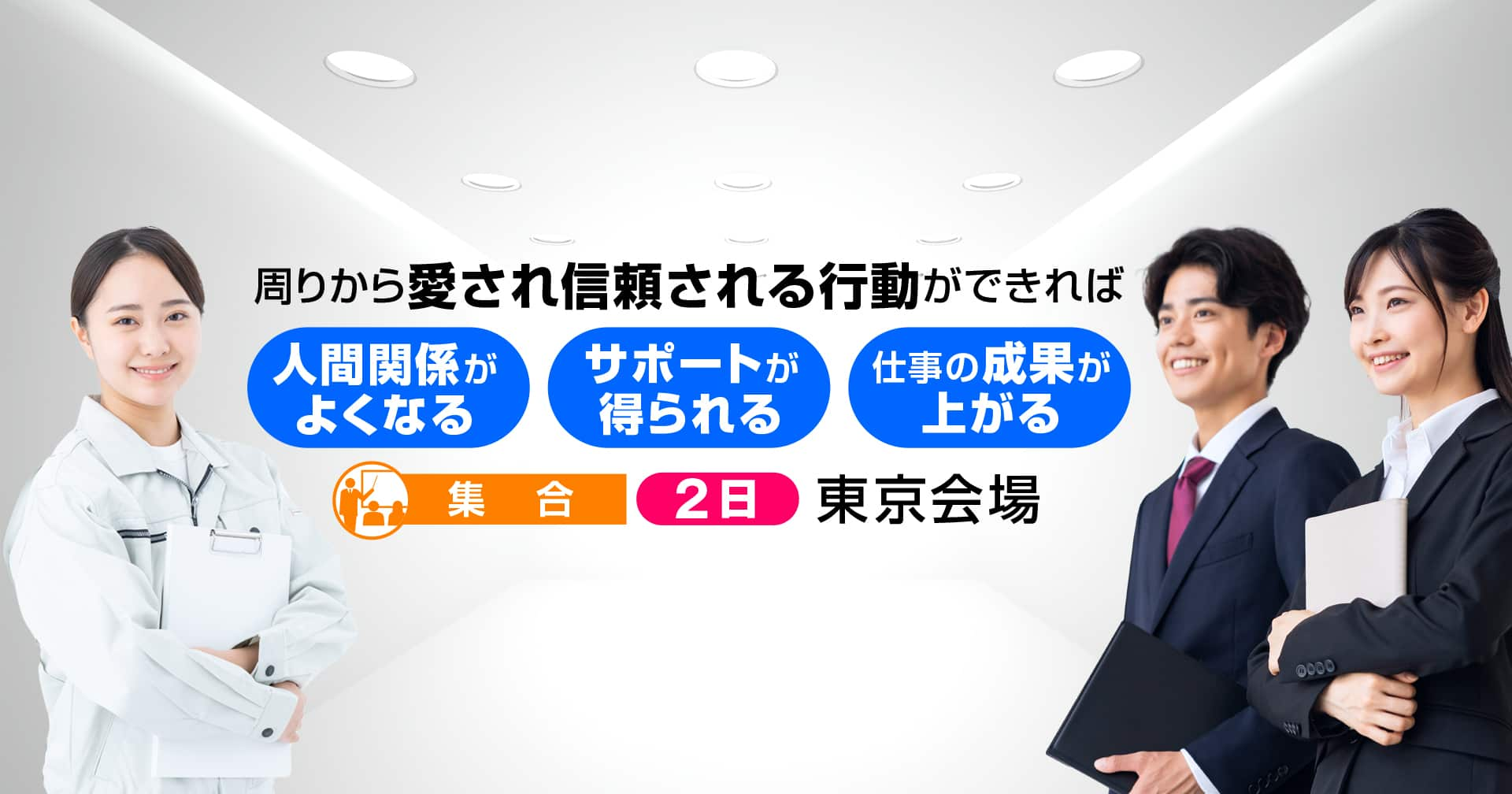










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







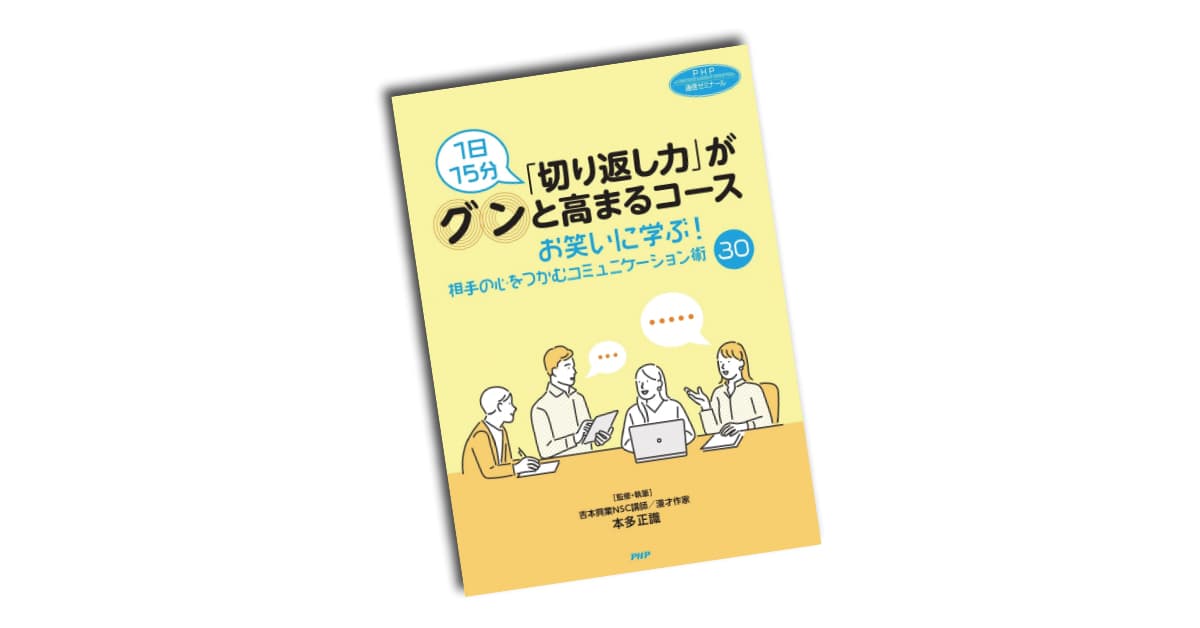






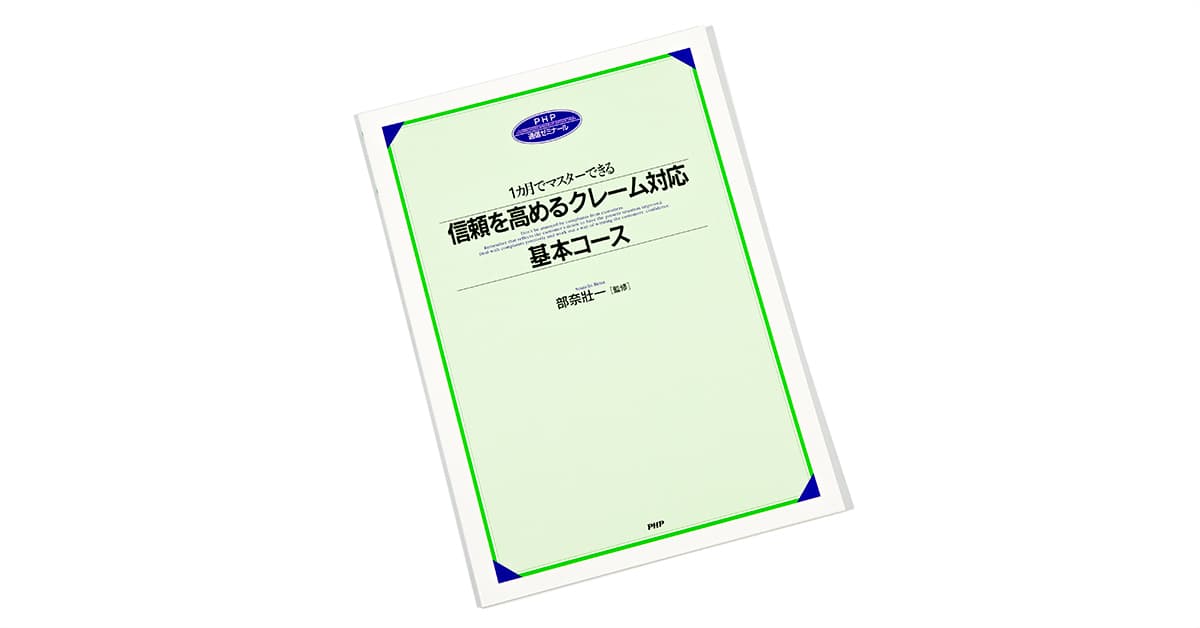





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

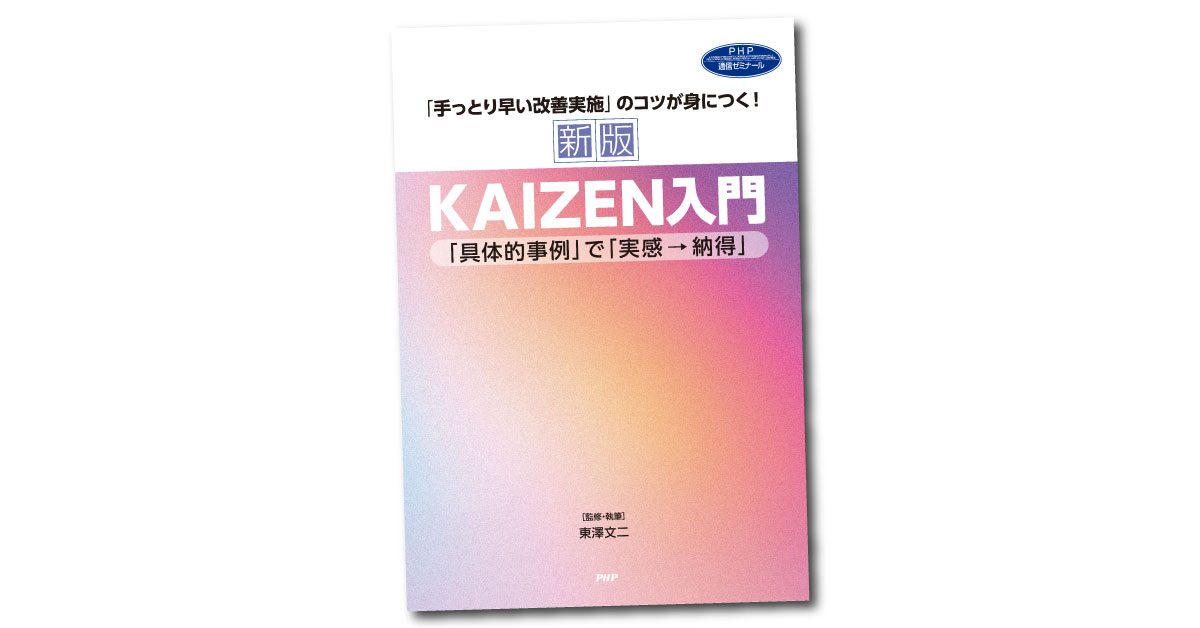










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


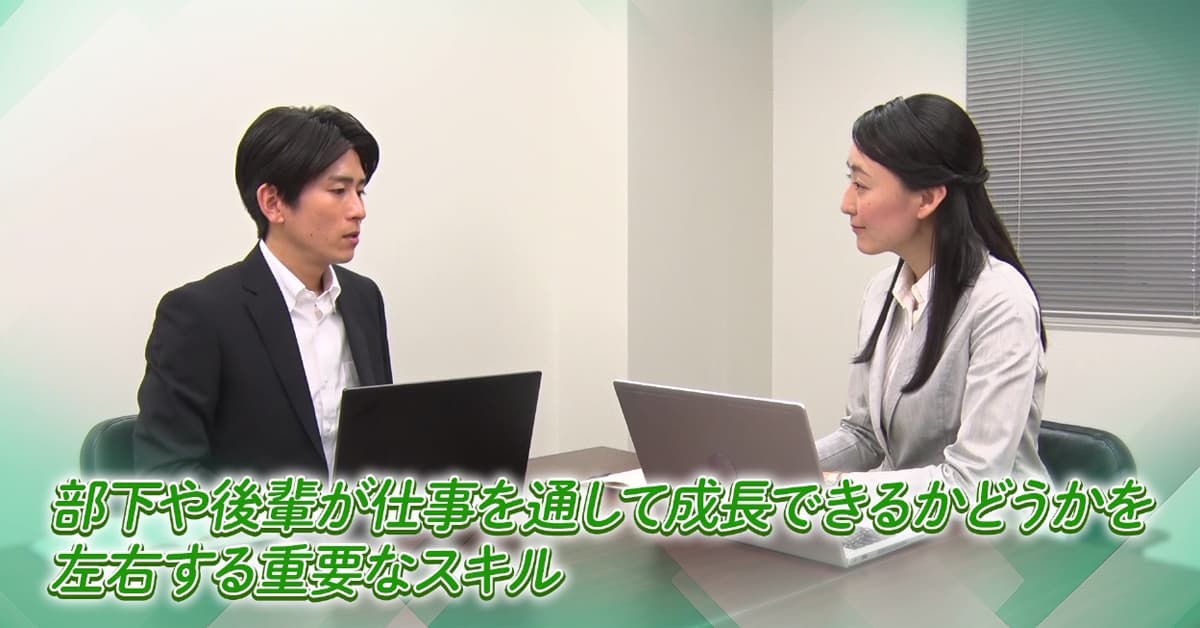
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
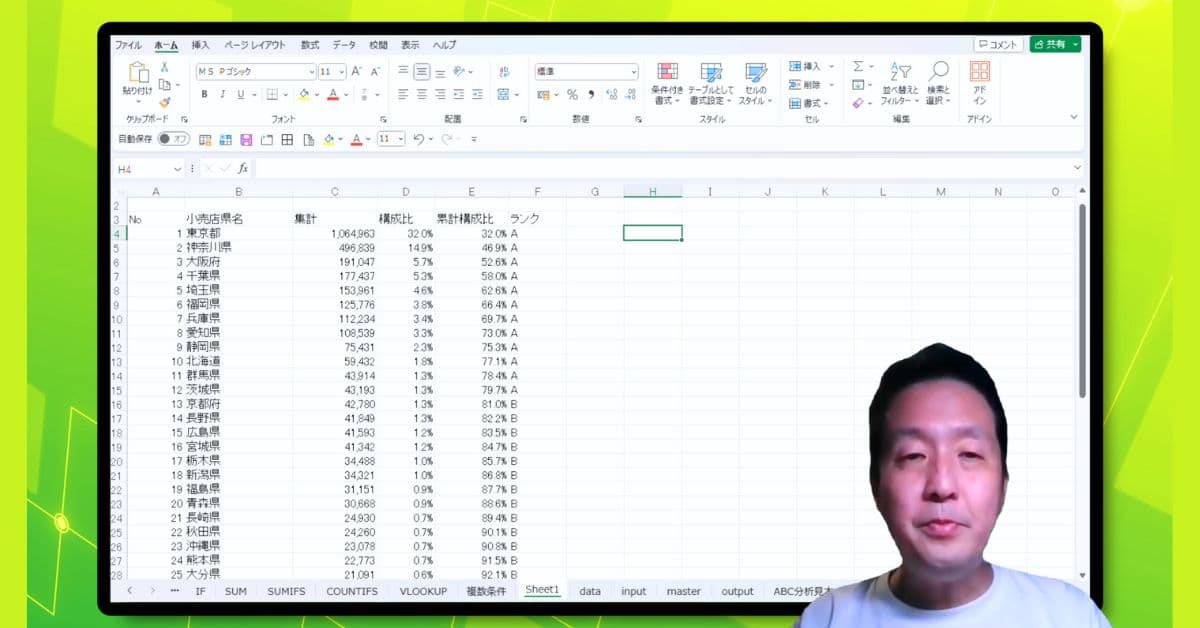
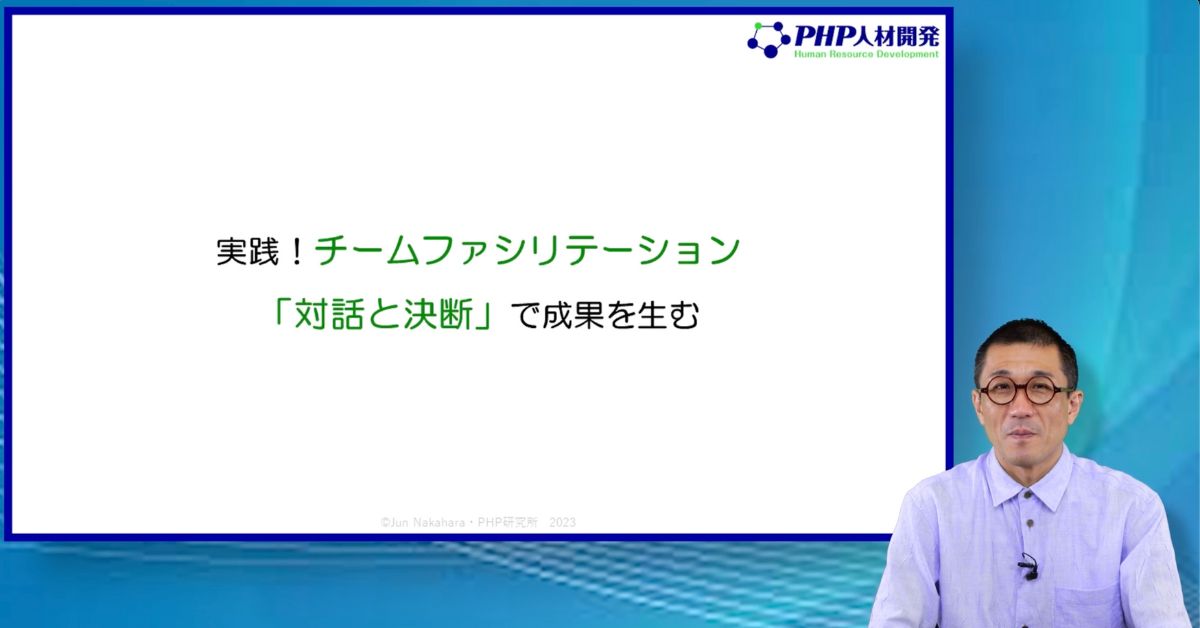
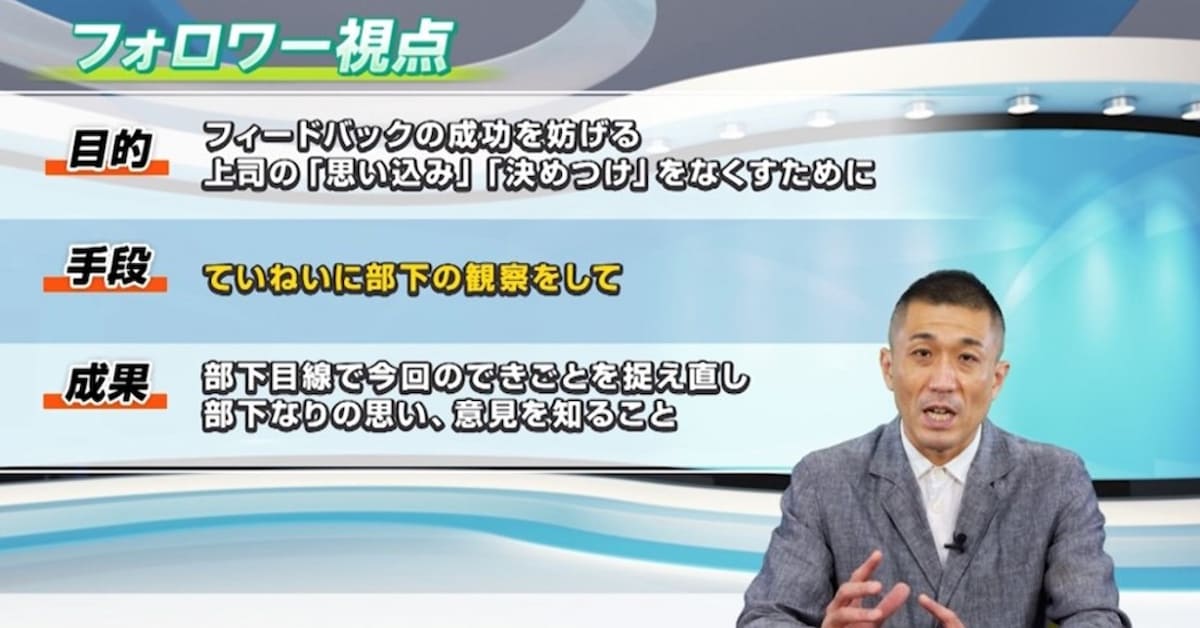

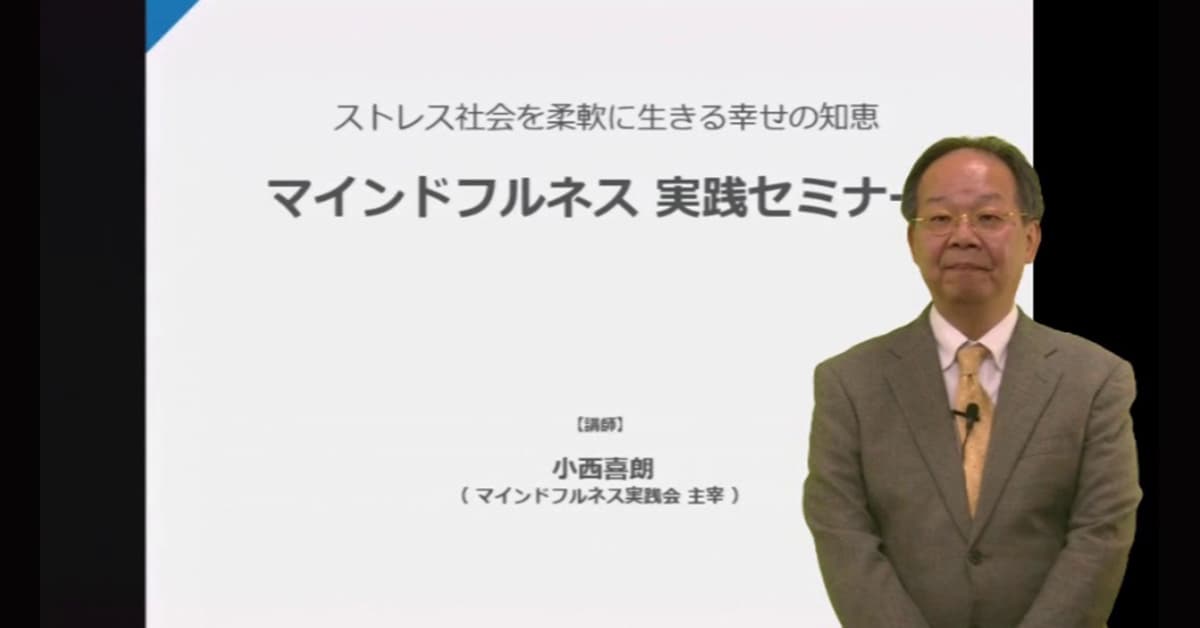

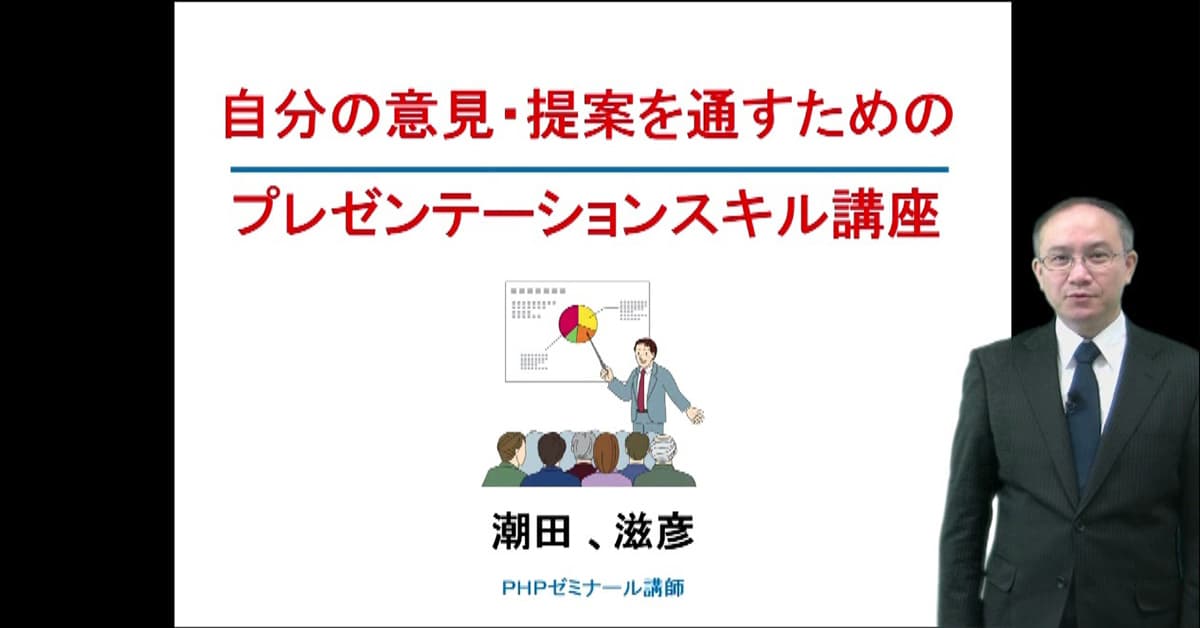
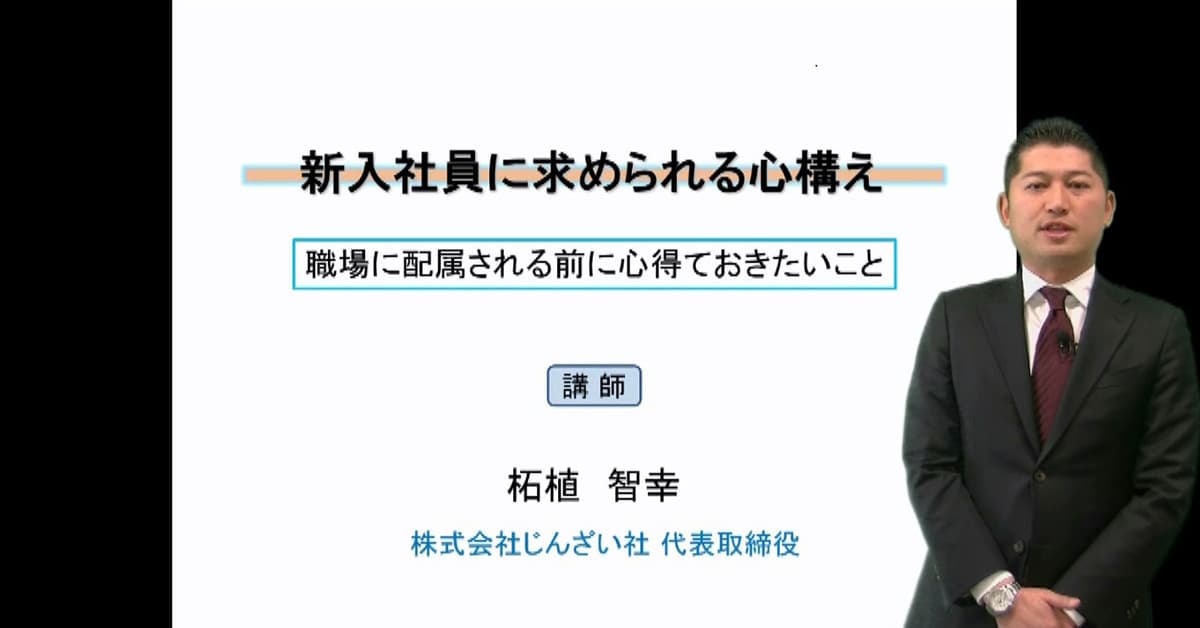
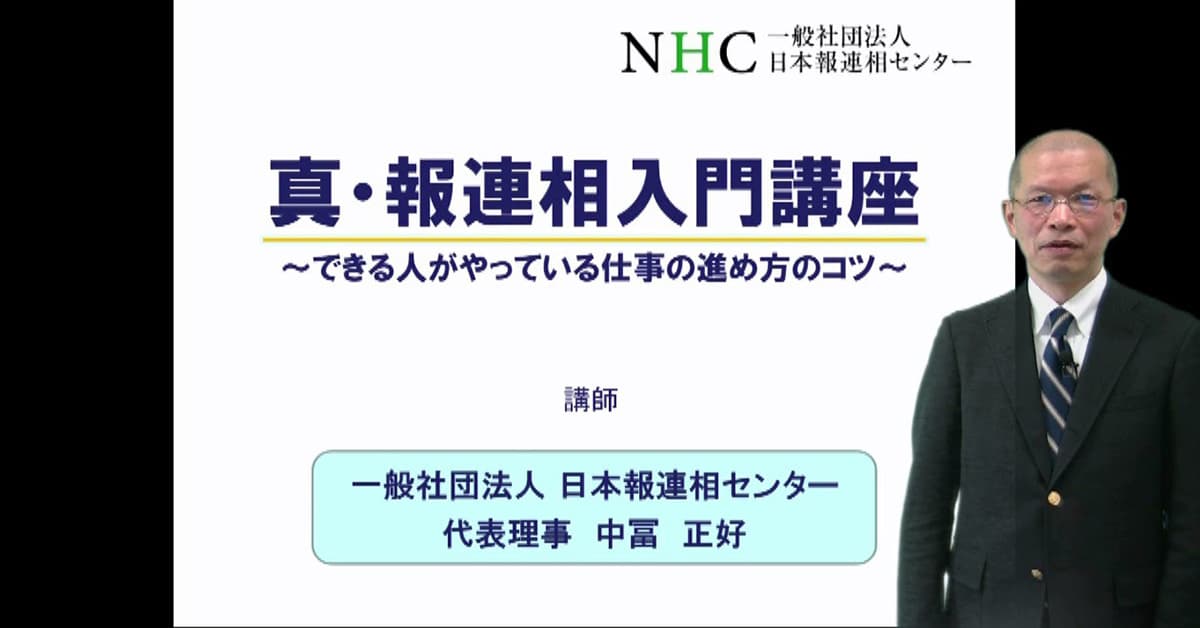
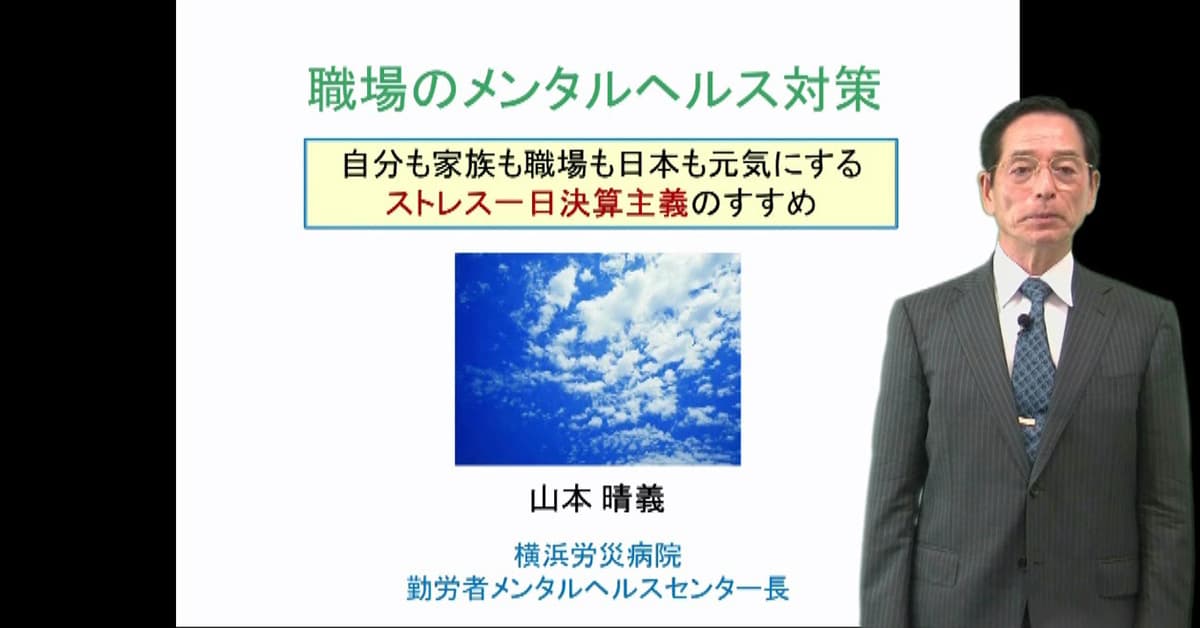
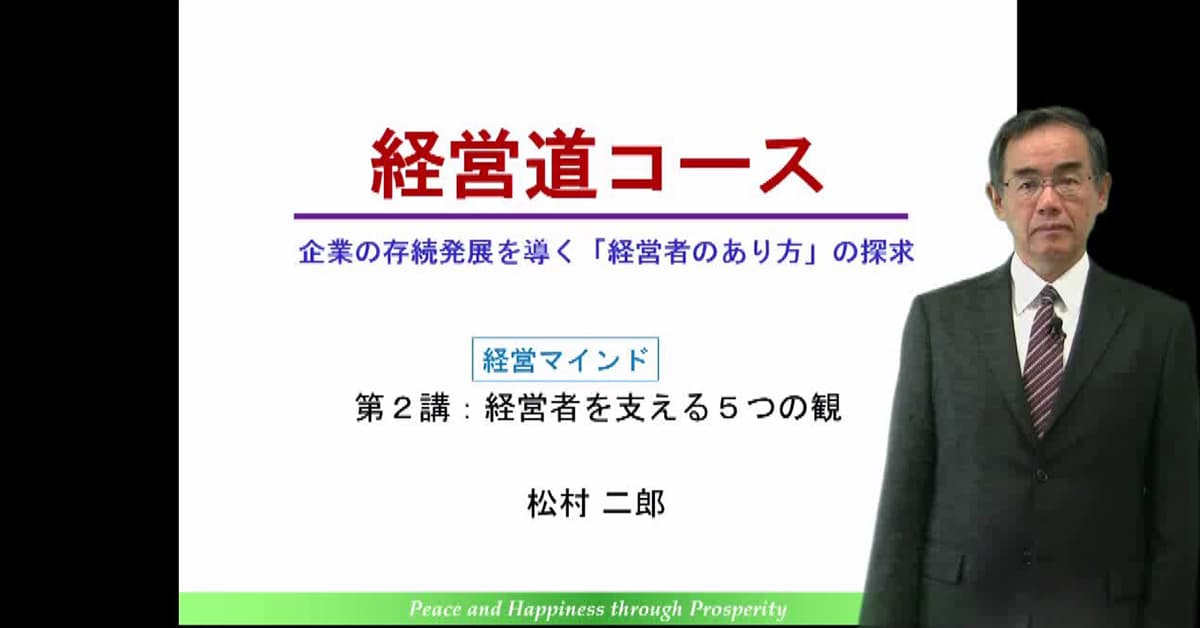
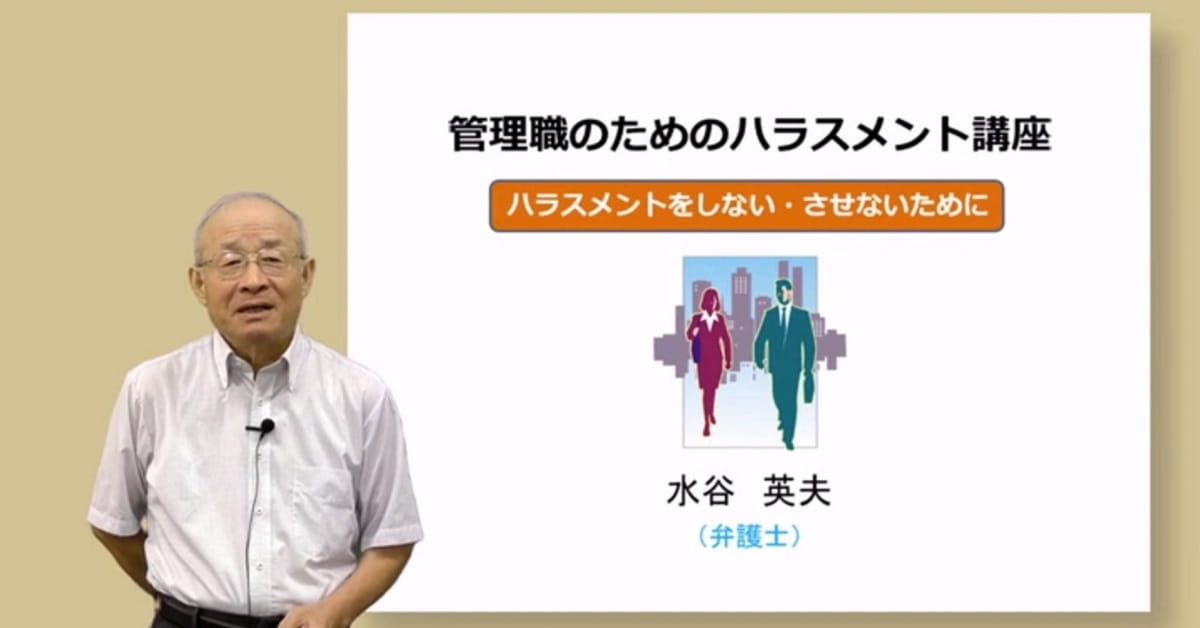

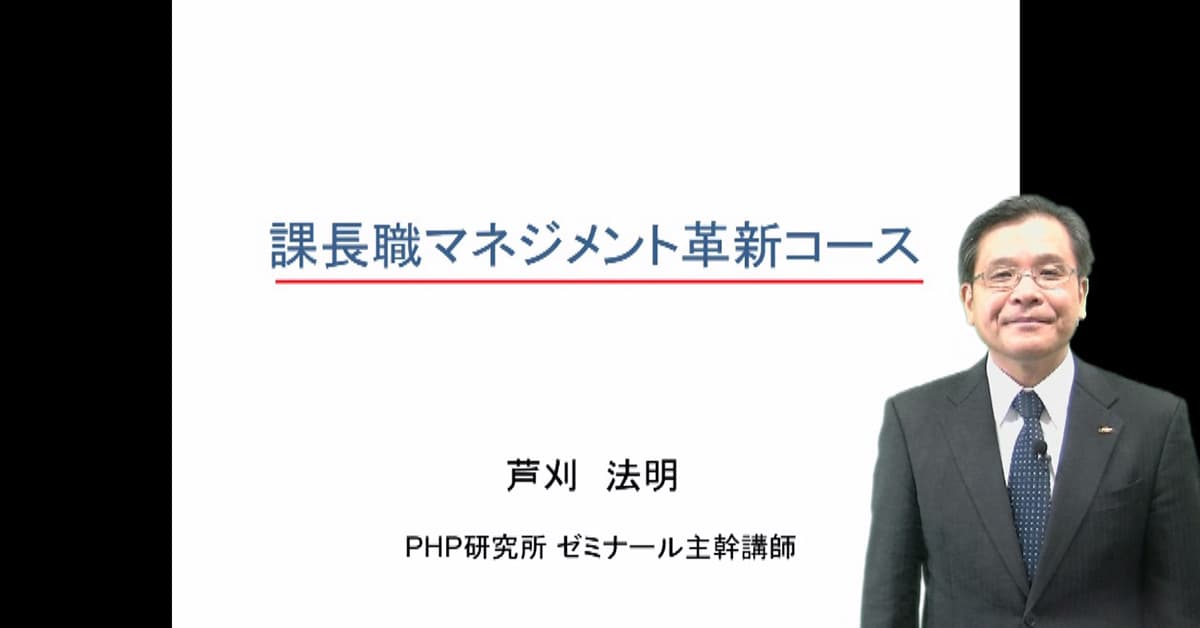



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















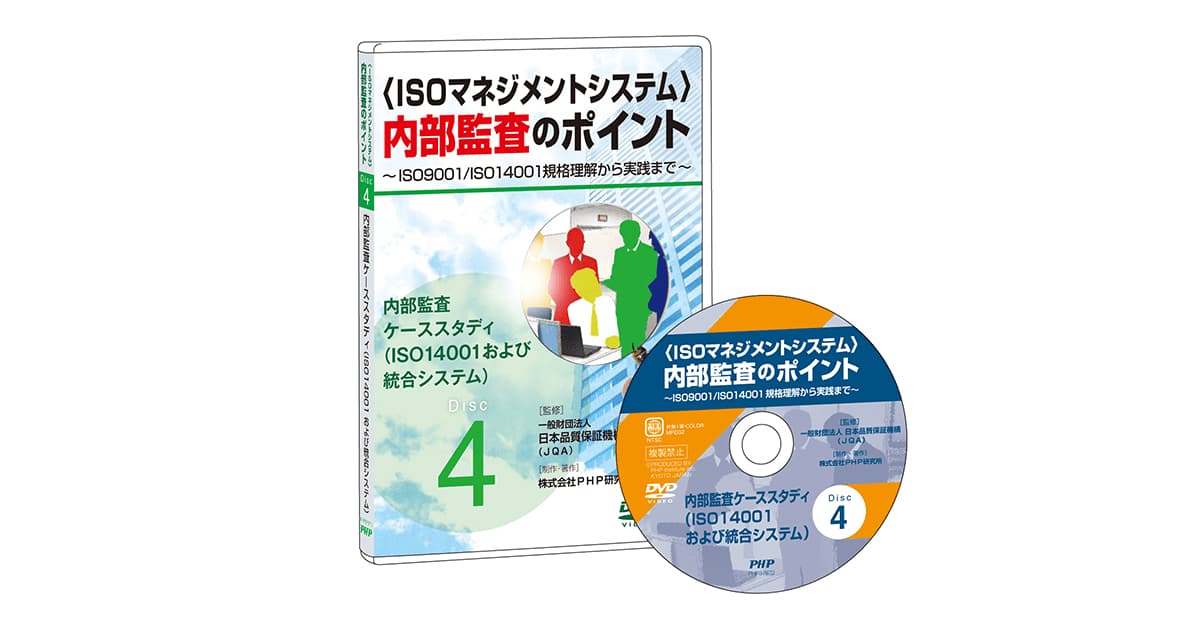





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
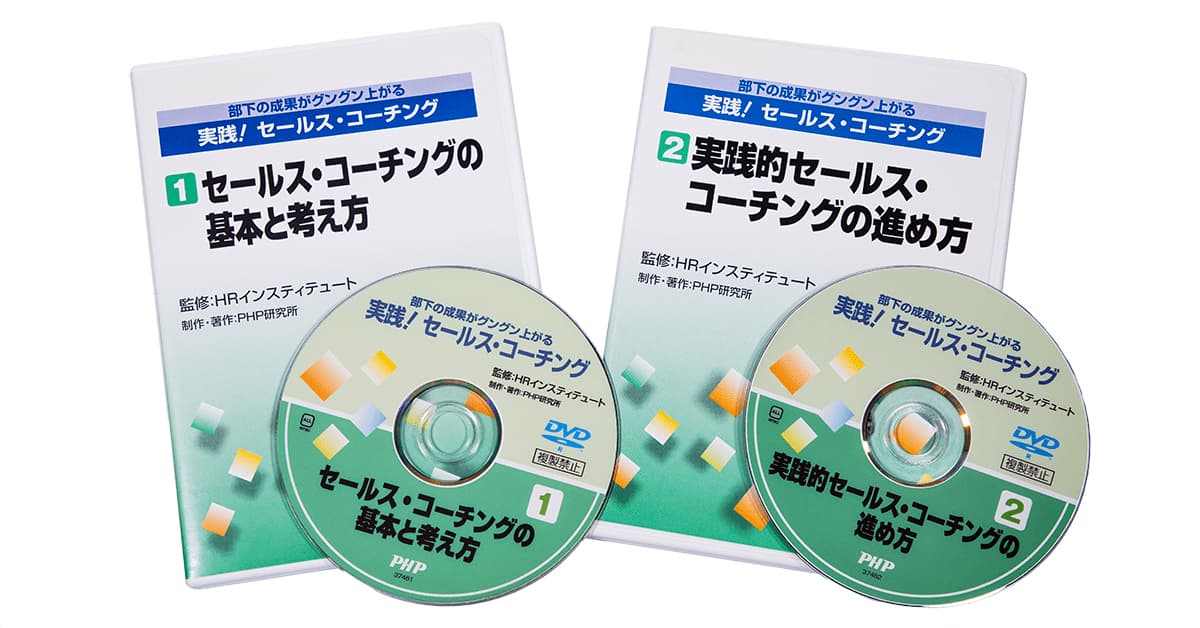




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)