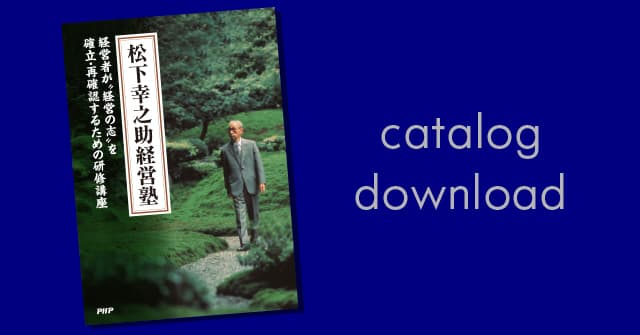本田宗一郎の決断~四輪車への挑戦
2019年4月19日更新

創業から二十年で世界のHONDAをつくりあげた本田宗一郎。その決断の背景に迫る。
天才的技術、そして強烈な個性とバイタリティーで、創業から二十年で世界に冠たる企業に成長させた本田宗一郎。二輪車において世界の頂点に立ち、新たな発展をめざして四輪車に参入した。
軽トラック、軽自動車を発表し、上々のスタートを切り、ついに大衆車と位置づける本格的小型乗用車を発表。しかし、その開発をめぐる頃から、水冷エンジンを推す部下と空冷エンジンを推す本田との間の葛藤が深まっていった。
二輪車の空冷エンジンにおいて抜群の実績を持つ本田は、副社長の藤澤武夫のぎりぎりの説得で水冷エンジン開発を認めた。本田自身の限界が取りざたされ、大きな波紋を呼んだこの決断において、本田が異様なまでにこだわったのは、いったい何であったのだろうか。
藤澤武夫の説得
副社長の藤澤武夫が、和光(埼玉県)の技術研究所にある社長室に本田宗一郎を訪ねたのは、昭和四十四(一九六九)年七月のことだった。目的は研究員が希望する水冷エンジン開発を本田に認めさせることだった。
本田技研(以下、ホンダ)という会社が「ツーマン経営」というのは知られているとおりである。本田は創業者だが、もっぱら製造・技術・開発の人。本田が卓越した開発力でつくった商品を、巧みに流通に乗せ、営業その他の経営全般を切り盛りするのが藤澤の役目。分担は徹底されていた。ただ、今は本田が推す空冷エンジンと研究員らが推す水冷エンジンの選択を決着させなければ、喫緊のテーマとなりつつある低公害車開発に大きな支障をきたす恐れがある。
研究員の現場の声を聞かされた藤澤は、自らの見識としても、あえて役割分担の域を越えなければならないと考え、説得をはじめた。
「本田さん、水冷エンジンを試しにつくってみませんか」
さりげなく切り出したが、やはり、本田は拒否した。予想されたことである。
そこで藤澤はこんな言い回しをしたという。
「私と最初に出会ったとき、あなたはこと技術に関して、他人からの指図は受けたくないと言った。私も技術はくわしくないからそうしてきたし、これからもするつもりはありません。ただ、今は一つだけお聞きしておきたいのです。本田さん、あなたはホンダの社長としての道をとられるのか、それとも技術者としてホンダにいるべきだと思っておられるのか。その辺りをそろそろはっきりさせなければならない時期にさしかかっていると思うのです」
この言葉に本田は沈黙した。この間、本田はどれだけのことを考えたのであろう。しばらくのち、本田の口から出たのは、「やはり、おれは社長としているべきだろうな」という言葉だった。
ホンダとして重要な技術戦略上の決断。藤澤の説得は成功したというわけである。ただそれは、本田自身にとっても実に重みのある決断でもあった。なぜ、こうした構図になったのだろうか。ホンダの四輪車開発史をたどる中から考えてみよう。
四輪車への挑戦
「子供のころに、T型フォードが走っているあとを追いかけながら、地面にこぼれたオイルに鼻をくっつけて、においをかいで刺激されたことが、今日のクルマづくりにつながっているんだ」
日本人として初めてアメリカの自動車殿堂入りを果たした平成元(一九八九)年、本田は自動車への愛着をこう語っていた。その思いからすれば、二輪車で世界的成功を収めたあと、その新たな発展の糧を本田の長年の夢であった四輪車の参入に求めたのは当然のことだった。
昭和三十(一九五五)年に、政府は「定員四人、時速一〇〇キロ、価格二五万円」等々の国民車育成構想を打ち上げる。自動車業界への追い風が吹いていた。
ホンダがこの国民車構想に応じるべく四輪車開発のための部署・第三研究課を新設したのは、昭和三十三(一九五八)年のことであった。ただ四輪車参入というのは、ホンダの二輪車の実績をもってしても、たやすいものではなかった。四輪開発のための技術者が足らなかった。開発を命じられたメンバー七名の中に旧飛行機会社出身者や三輪車開発経験がある中途採用者を含んでいたのがそれを証明している。
昭和三十四(一九五九)年に試作車第一号XA170、第二号XA190が完成。その後も研究が続けられた。
昭和三十七(一九六二)年六月五日、建設中の鈴鹿サーキットで行なわれた第十一回全国ホンダ会総会の製品展示・試走会で、軽四輪スポーツカーのS360と軽四輪トラックT360がホンダ初の四輪車としてお目見えとなった。本田は自らS360を運転してメーンスタンド前を駆け抜け、関係者にPRした。そして十月の第九回全日本自動車ショーには、先のS360、T360のほかS500が出展され、四輪進出が高らかに謳われた。
昭和四十一(一九六六)年、軽自動車N360が誕生し、大ヒットした。大衆車と位置づけた本格的小型乗用車H1300が発表されたのは昭和四十三(一九六八)年であった。
「空冷vs水冷エンジン論争」とN360までの開発
「空冷vs水冷エンジン論争」は、空冷エンジン搭載のH1300開発過程からくすぶりはじめ、同車が営業不振に終わったこと、F1でも初の試みとした空冷エンジン搭載車がレースで事故を起こしたこと、といったいくつかの事情が重なって表面化する。
ここで気をつけなければいけないのは、「空冷vs水冷エンジン論争」に至るまで、試作車も含め四輪車はなべて本田の指示で空冷エンジンを採用し、そこに不備が出て水冷エンジンになった、という単純な図式ではないことである。
昭和三十四(一九五九)年に最初に造ったXA170、XA190はたしかに空冷エンジンであったが、翌三十五(一九六〇)年の後継試作車AS250やAK250は水冷エンジンである。この変更は、やはりテストしていた空冷エンジンに限界が出たからだという(『語りつぎたいこと チャレンジの50年』)。そして、先に述べた後継のS360、S500、T360も水冷エンジンを採用しているのである。
ただ、ヒットした軽自動車N360もそのあとのH1300も空冷エンジンであったからそう見られがちだが、本田はけっして当初から水冷エンジンを否定していたわけでもなかった。
では、なぜN360やH1300においては空冷エンジンを採用したか、ということが大きな鍵となってくる。
そこには試作車一台一台の開発においては、たんに技術上の課題にとどまらないさまざまな思惑や制約が働くからである。
とくにこれら四輪車の開発は政治的な影響を多分に受けるものでもあった。
昭和三十六(一九六一)年五月、自動車行政の基本方針(後の特定産業振興臨時措置法案:通称・特振法案)が、通産省から示された。
これは貿易の自由化を二年後として、それまでに国際競争力の弱い自動車、特殊鋼、石油化学の三分野を特殊産業に指定し、行政主導のもとに強化しようというものであった。
自動車産業においては、既存メーカーを①量産車グループ、②特殊車グループ、③軽自動車グループに分け、統廃合を促す。新規参入は許可制にする、という統制色の強い政策だった。
新規参入をめざすホンダにとっては、背水の陣を布かざるを得なくなったも同然だった。法案成立までに生産実績を上げなければ四輪業界へ進出する機会が失われるのである。この政策に本田が猛反対であったのは言うまでもない。
S360やS500、T360開発が急がれた背景には、こんな切迫した状況があったのだ。また量産体制の構築や、営業体制、販売店育成なども急ピッチで進められた。
最終的には、乗用車(大衆車)生産を前提としなければならないが、現状では先行メーカーが激しい競争をしており、ホンダがいきなりこの市場に入るにはリスクがあった。それにくらべ、軽自動車市場は、ホンダの従来の技術でも対抗でき、投資金額も抑えられる。その上で、他社にない新しい軽自動車を提供すれば成功できる。
営業的にヒットとなったN360の場合は、何よりもマーケティングが優先して開発されたといってもよいだろう。
N360は新聞広告で「このクルマは客室から設計をはじめました」と打ち出した。居住性に優れ、斬新なデザイン、スポーツカー並みの出足、廉価が大評判となって、業界トップの売行きを記録したのである。N360のルーツは試作車XA170で、軽自動車の範囲ではエンジンが空冷式であっても、ファンを付けて冷却力を強化することで対応できたのだった。
H1300の失敗
最初の試作車から九年、いよいよ念願の普通車として、小型乗用車H1300が開発された。本田がこの車に求めた使命は、「やるからには、先に行くトヨタ、日産の鼻をあかすクルマでなくてはならないんだ」ということだった(『語りつぎたいこと チャレンジの50年』)。
その鼻をあかす具体的選択の一つが「独創的空冷エンジン」となったのである。本田にとってはN360が成功したのであるから、この選択は奇異でもなかったのであろう。ただ、部下の研究員らは、軽自動車と普通乗用車の違いを別世界だと感じていた。本田の陣頭指揮におけるたび重なる設計変更も、本田と彼らの溝を深めるものだったらしい。
そもそも空冷エンジンと水冷エンジンの違いは、文字通りエンジンの冷却方法にある。空冷エンジンは走っているときの空気をエンジンに当てて冷却する。水冷エンジンはエンジンの周りに水を循環させて冷却する。二輪車は空冷エンジンが主流だが、四輪車は水冷エンジンが基本とされている。なぜなら四輪車のエンジン排気量が大きくなればなるほど、機能的に空冷の不利が際立ってくるからだ。
もちろん、本田も空冷の課題を理解し、水冷エンジンにくらべ大きくなる騒音の軽減とかさを小さくする努力を続けた。そして、DDAC(一体構造二重壁空冷方式)という新エンジンにたどり着いたのである。
努力の甲斐あってH1300は高い性能を誇り、ライバル社を驚かせた。トヨタ自動車工業・豊田英二社長(当時)は、自社の技術者に対して、「ホンダは1300ccで百馬力を出している。なぜウチではできないのだ」と雷を落としたという。技術的にはたしかに鼻をあかすクルマが誕生したのであった。
しかしそれでも結果的に、H1300は営業的に失敗に終わってしまった。いろいろな見方があるなかでも、とくに政治的な要因が大きかった。アメリカの新聞が輸入していた日本車の欠陥を報じたことがきっかけとなって、日本のマスコミも欠陥車キャンペーンを展開、業界各社それぞれに欠陥車が指摘され、ホンダではN360が標的となった。このため同車の売行きは激減した。さらにこうした報道がもたらした消費者心理の影響から、高性能、高馬力のH1300はその品質の高さにもかかわらず、消費者に顧みられなくなってしまった。
当時の開発担当者は反省の弁として、「お客様の視点というものを意識していたつもりだったが、結果としては技術というものが前面に出てきてしまって、このクルマが最終的に、・どんな人たちに、どんなふうに乗ってもらうか・ということが不明確になってしまっていた」と述べている(同前 )。
問題はそれをどう修正するかであり、その焦点が「空冷vs水冷エンジン論争」となったのである。
昭和四十四(一九六九)年七月、軽井沢で本田技術研究所の研究員六十人が集まって「なぜ、H1300は売れないのか」をテーマに集会を開いたとき、総括されたことは――空冷エンジンにこだわったことで、ほかの部分に問題を生んだということ。そして、一般のお客様が日常使われる、普通の道具として成り立たせるために、さらにアメリカの排ガス規制対策に至急対応しなければ輸出ができなくなるという事態を打開するには、水冷エンジン開発に絞るしかない――ということだった。
本田はH1300の失敗にもかかわらず、なお空冷エンジンにこだわっていた。排ガス規制に対しても空冷エンジンで乗り切ろうと考えていた。ここに研究員との葛藤が頂点となり、藤澤がその調整に当たった。
冒頭の藤澤の説得劇に向かっていったというわけである。
遺伝子継承のためのエポック
「空冷vs水冷エンジン論争」とは、どのように評価できるであろうか。
偉大な創業者は意地に捉われず、最後には経営者としての自覚が上回って危機を打開した。そうした捉え方をして、本田を賞讃するだけでももちろん大きな意義はあろう。ただ、もう少し考えるならば、本田が空冷エンジンを通してこだわっていたのは何であったのか、ということである。
空冷エンジンが得意だったから、というのではけっしてない。
本田が自らに課し、また部下にも求めていたのは、まず・ホンダらしさ・すなわちオリジナリティであり、そして、もう一つ"世界を視野に"であった。だからこそ、あえて難度の高い道を選んでいたのである。
本田が当初から水冷エンジンを採用していたら、たしかにこの決断の機会は必要なかったことだろう。しかし、そんな本田だったらホンダ神話もなかったのではないだろうか。無謀と偉大な革新は紙一重なのかもしれない。しかし、本田はこれまでいつもその危険な挑戦に勝ってきた。
今まで通用していた自らのリーダーシップの限界を悟り、あとを部下に託すという大きな決断。そこで託された側も、この一技術の選択から、"ホンダらしさ"と"世界を視野に"を追求し、開発力の遺伝子を証明する責任が課せられた、という見方ができよう。
したがって、この論争の二年後、昭和四十六(一九七一)年、世界初の低公害エンジン「CVCC」が発表されたということは、それこそ本田の決断が正しかったことを見事に証明したものではなかったか。
昭和四十八(一九七三)年八月、本田はCVCCエンジンの成果に関してこう述懐している。
「CVCCの開発に際して、私が低公害エンジンの開発こそが先発四輪メーカーと同じスタートラインに並ぶ絶好のチャンスだと、言ったとき、研究所の若い人は、排気ガス対策は企業本位の問題ではなく、自動車産業の社会的責任の上からなすべき義務であると主張して、私の眼を開かせ、心から感激させてくれた」(『本田宗一郎 夢を力に』)
自分よりも新しい価値観を身につけていた世代に、本田は安心して任せる気持ちになったのではないだろうか。
結局、「空冷―水冷エンジン論争」の決断は、遺伝子継承のためのエポックという位置づけになるのではないだろうか。
昭和四十八(一九七三)年、本田と藤澤はそろって、社長、副社長を退いた。クライマックスのあとのさわやかな幕切れだったといえよう。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。










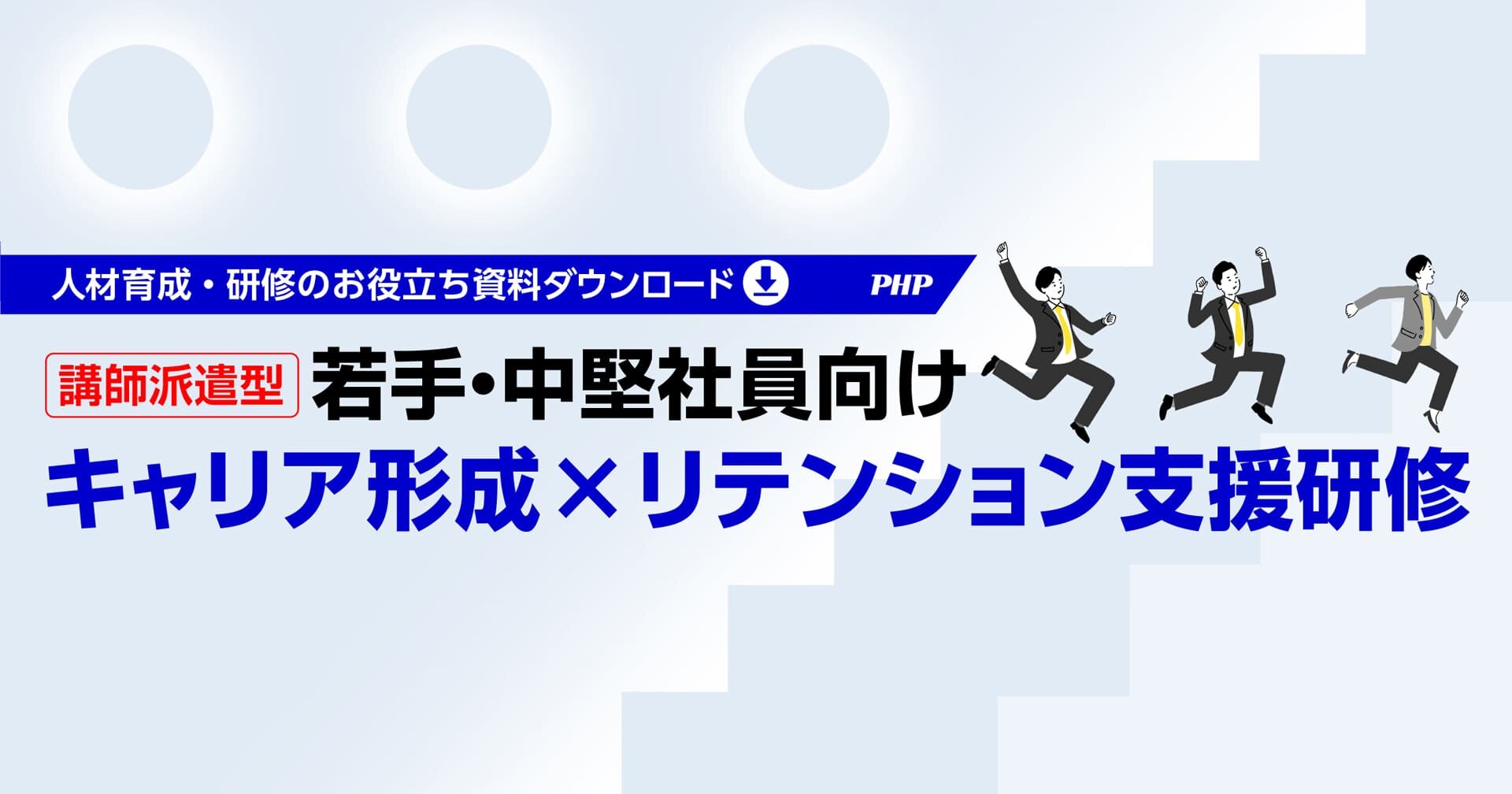















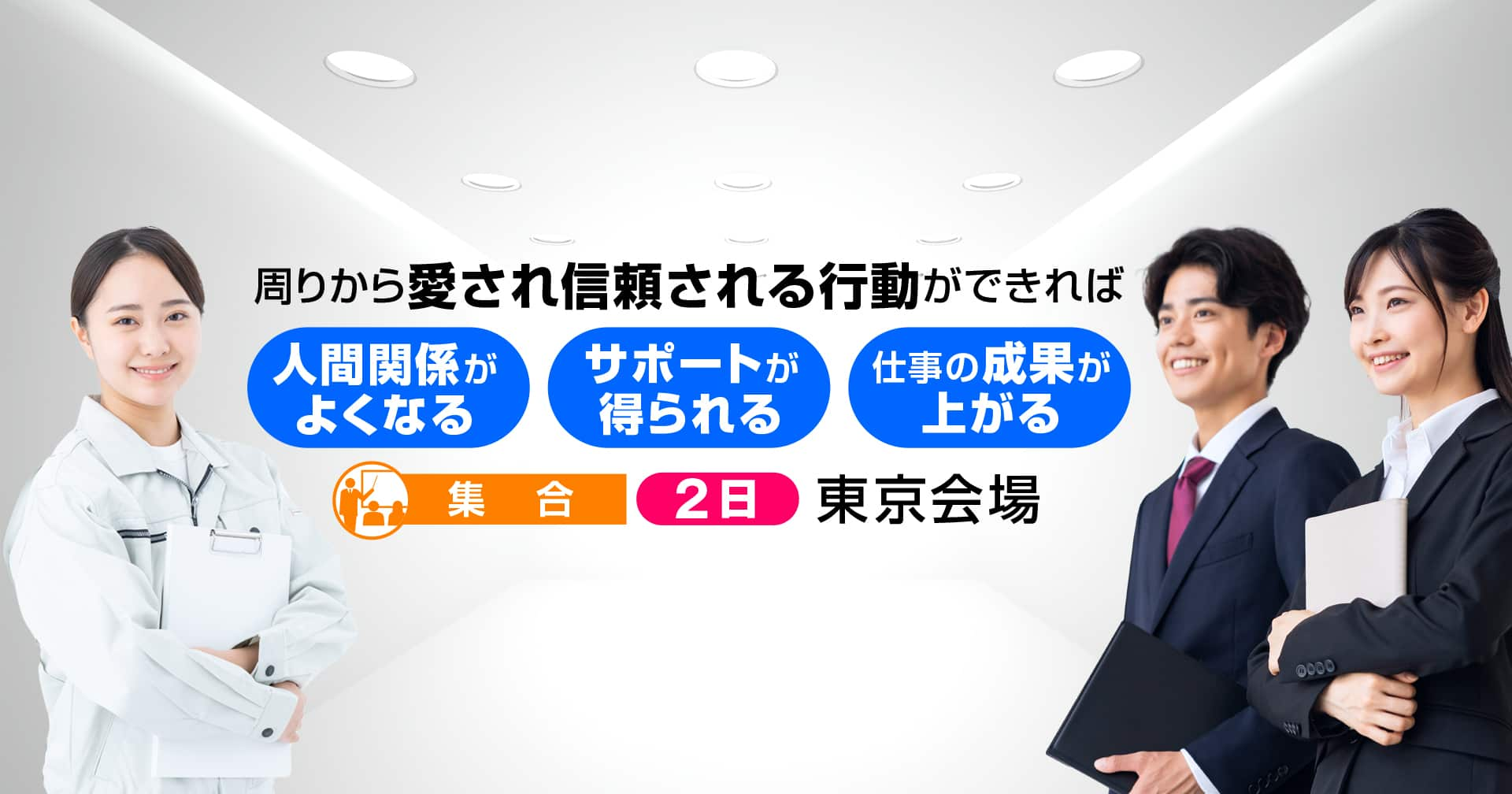










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







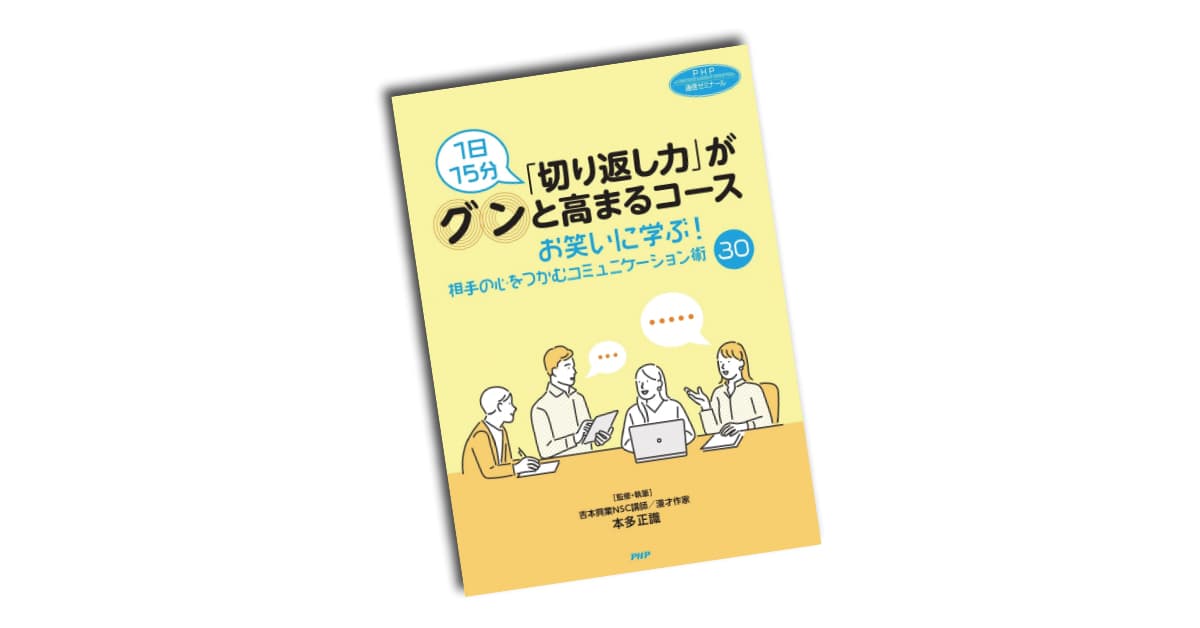






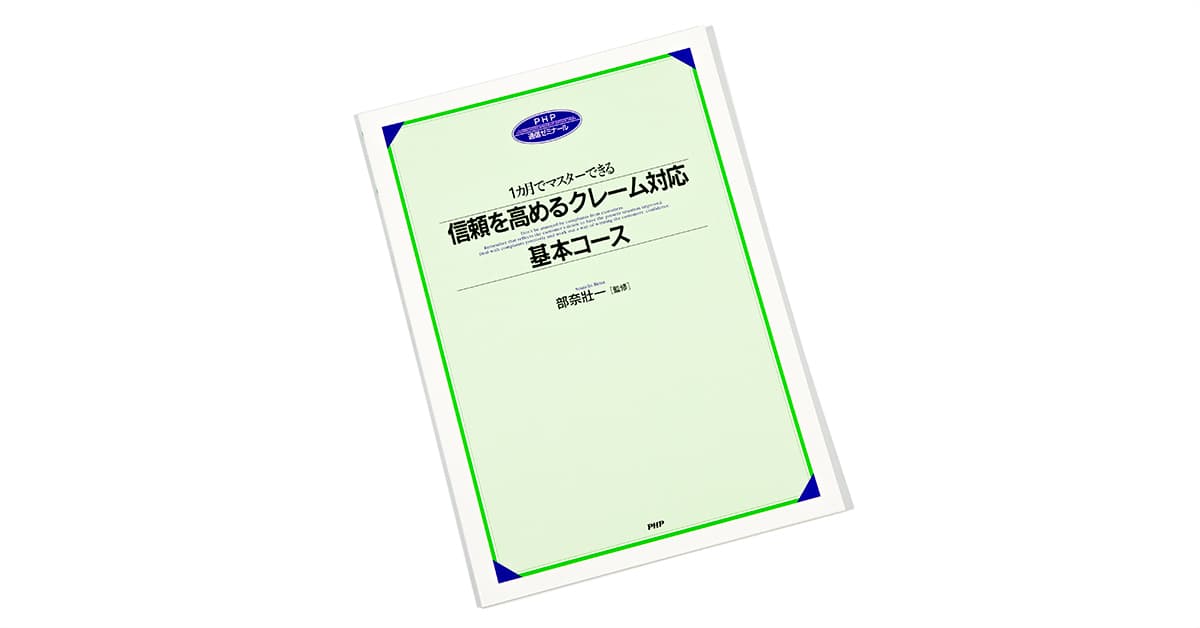





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

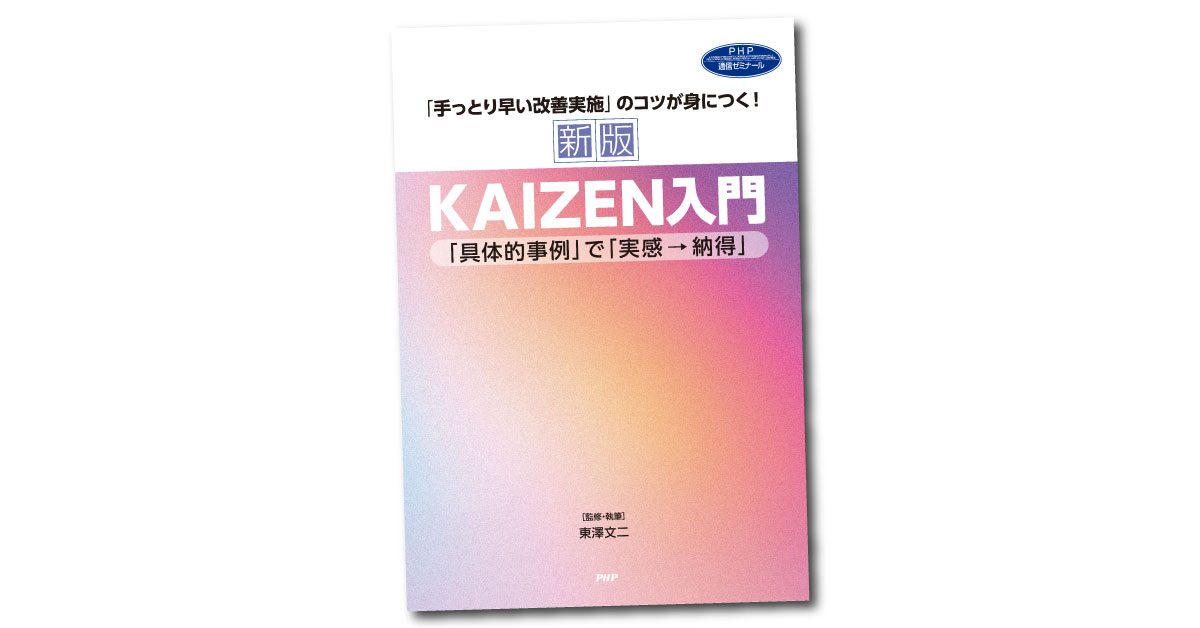










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


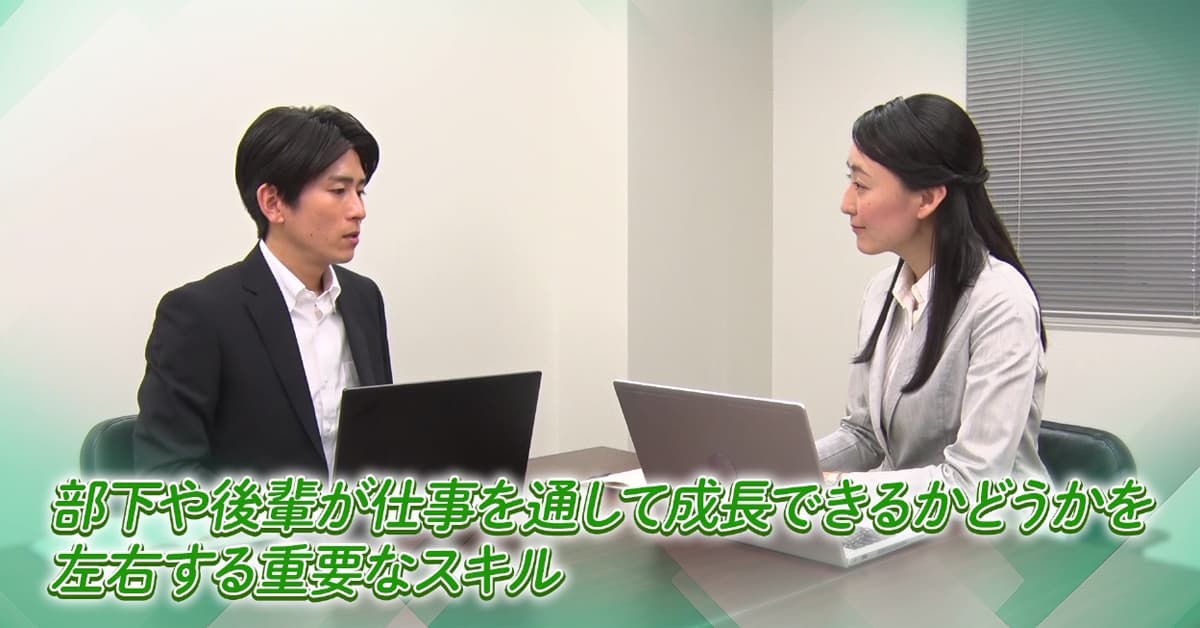
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
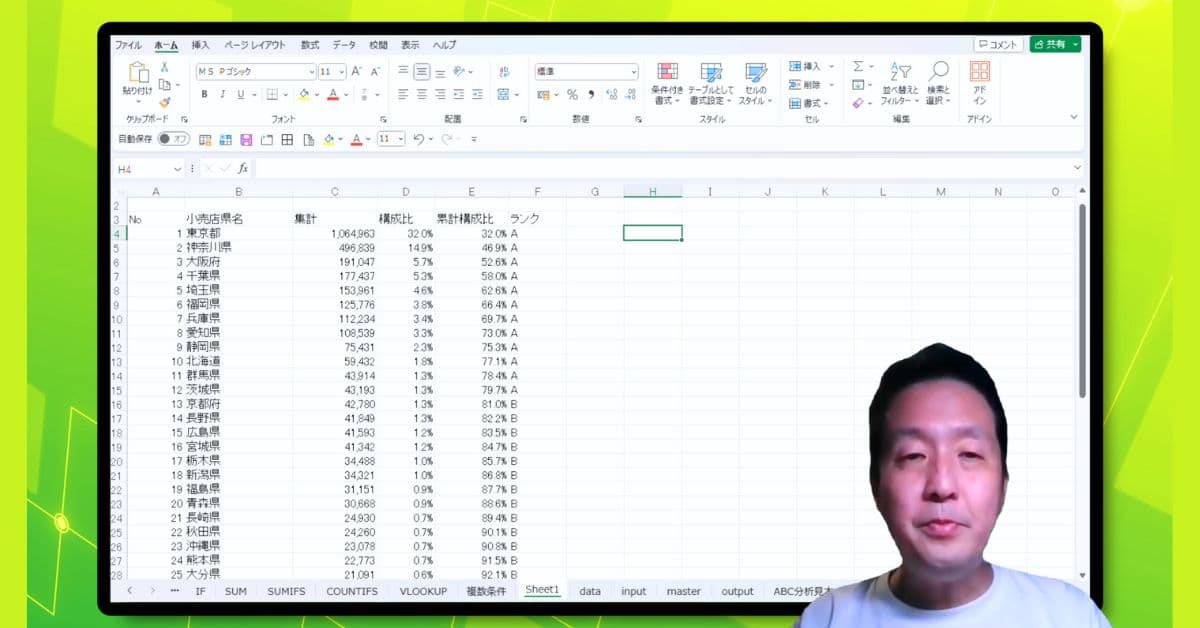
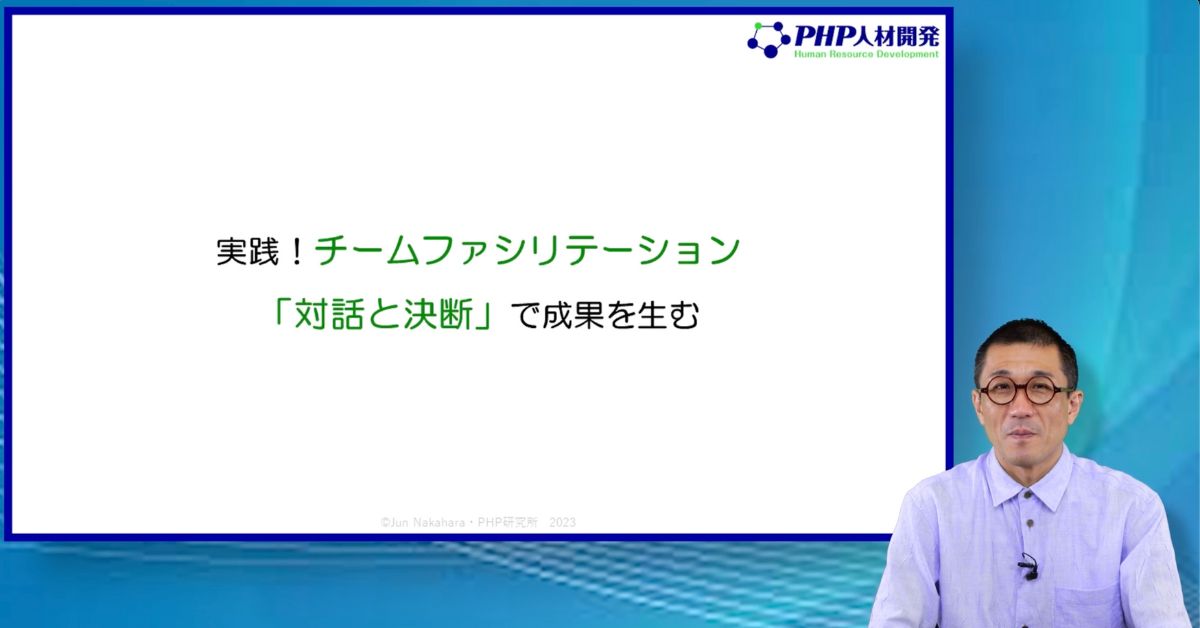
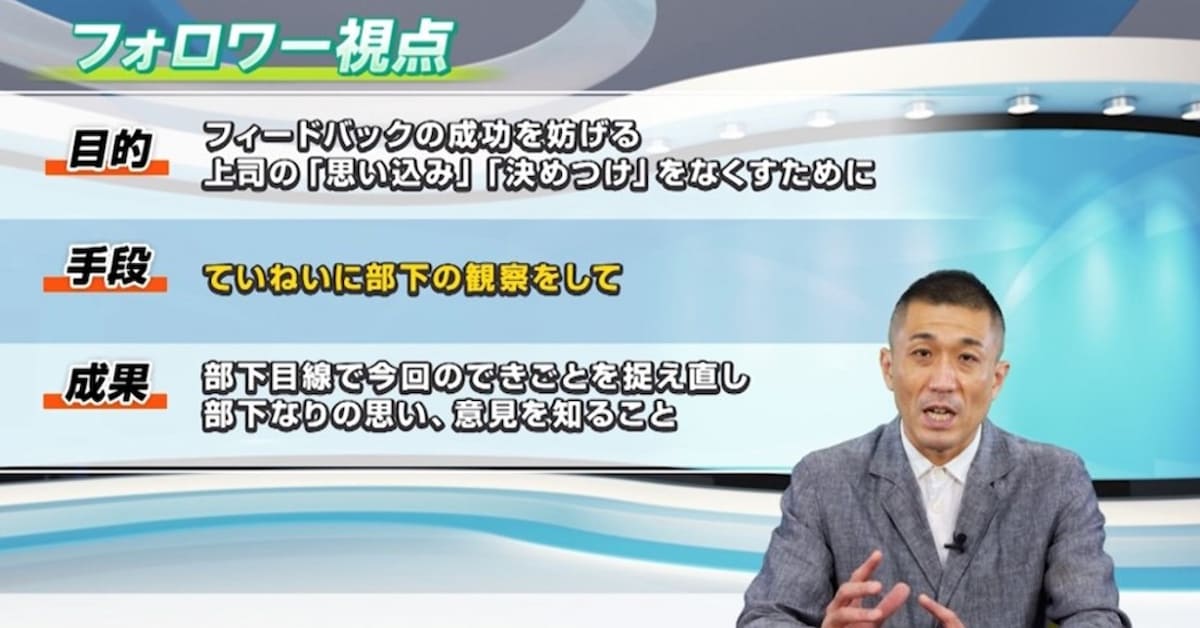

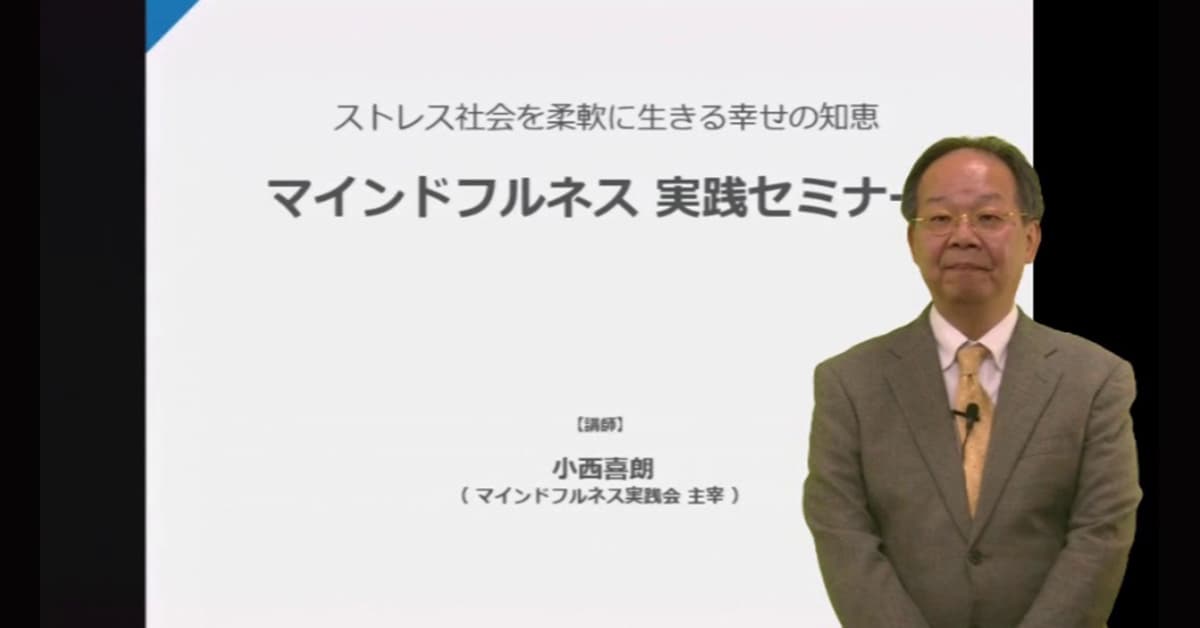

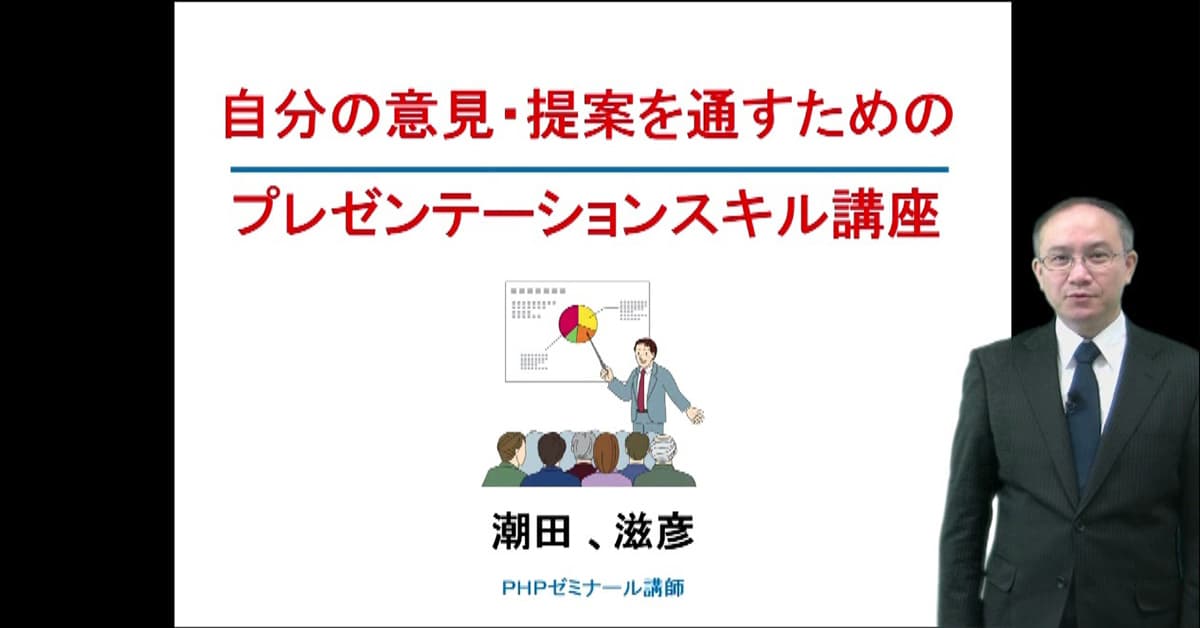
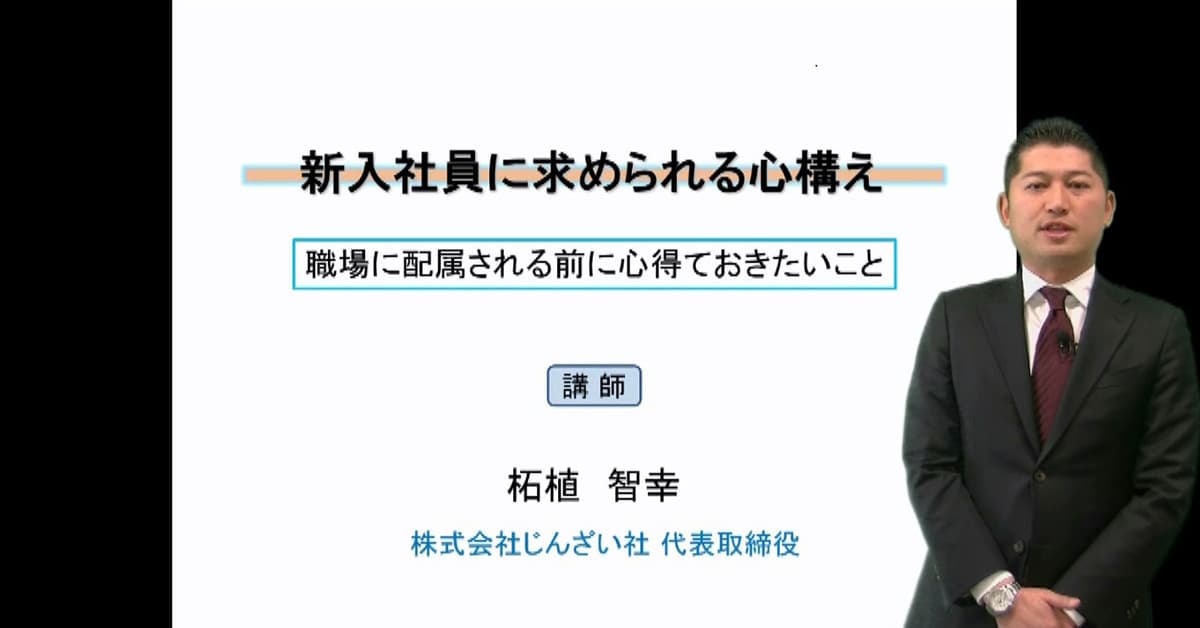
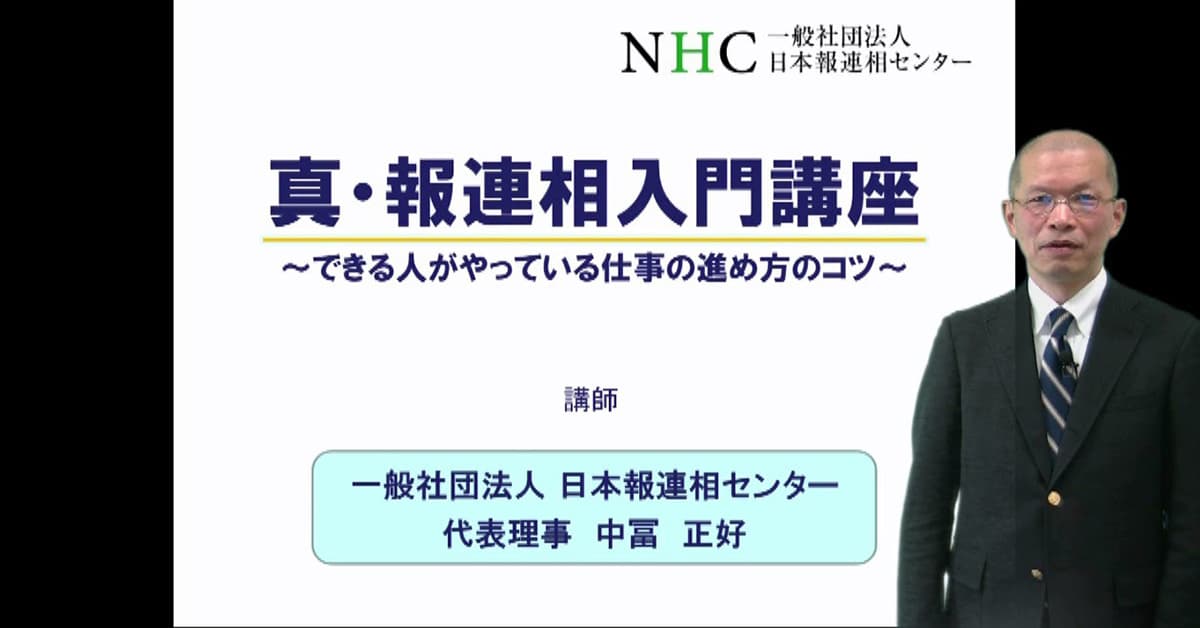
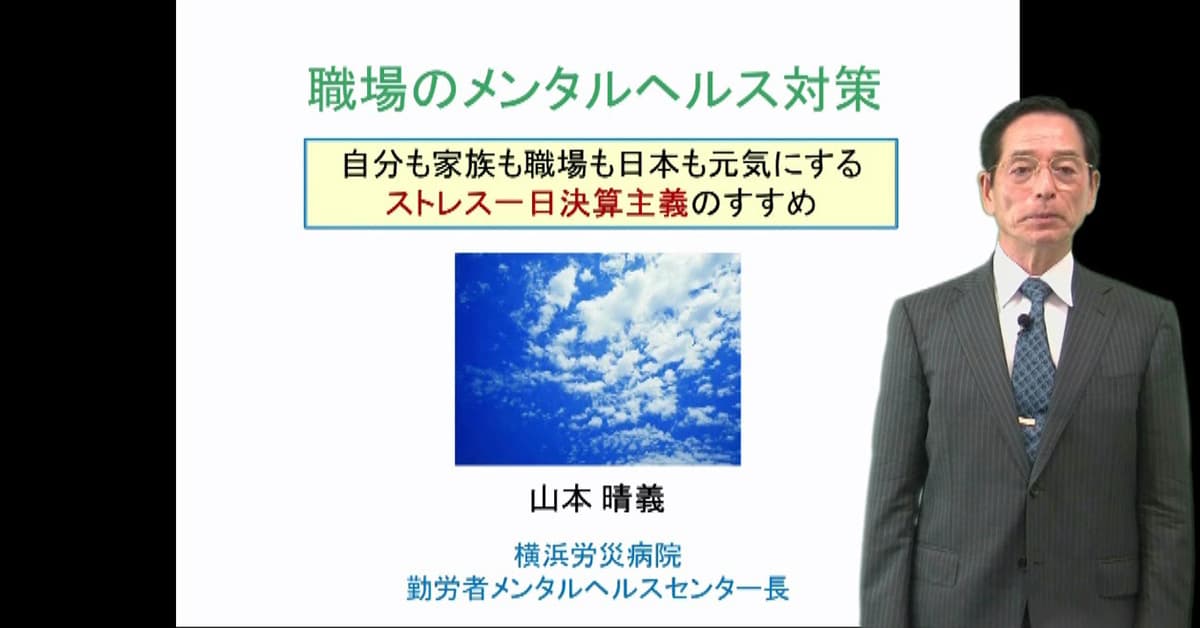
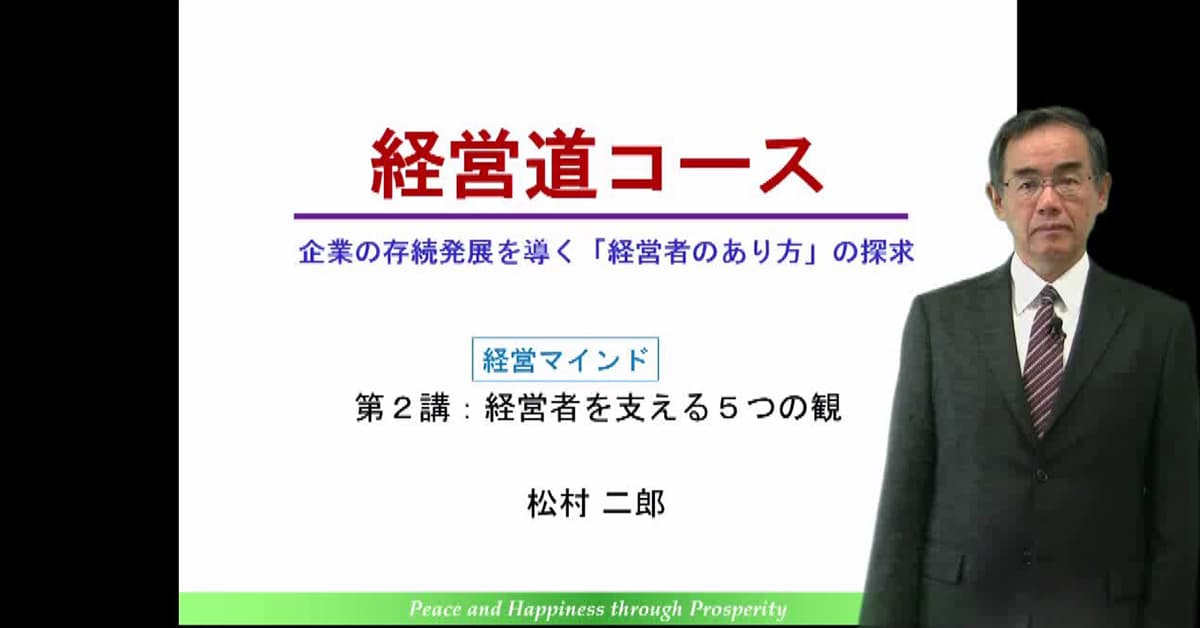
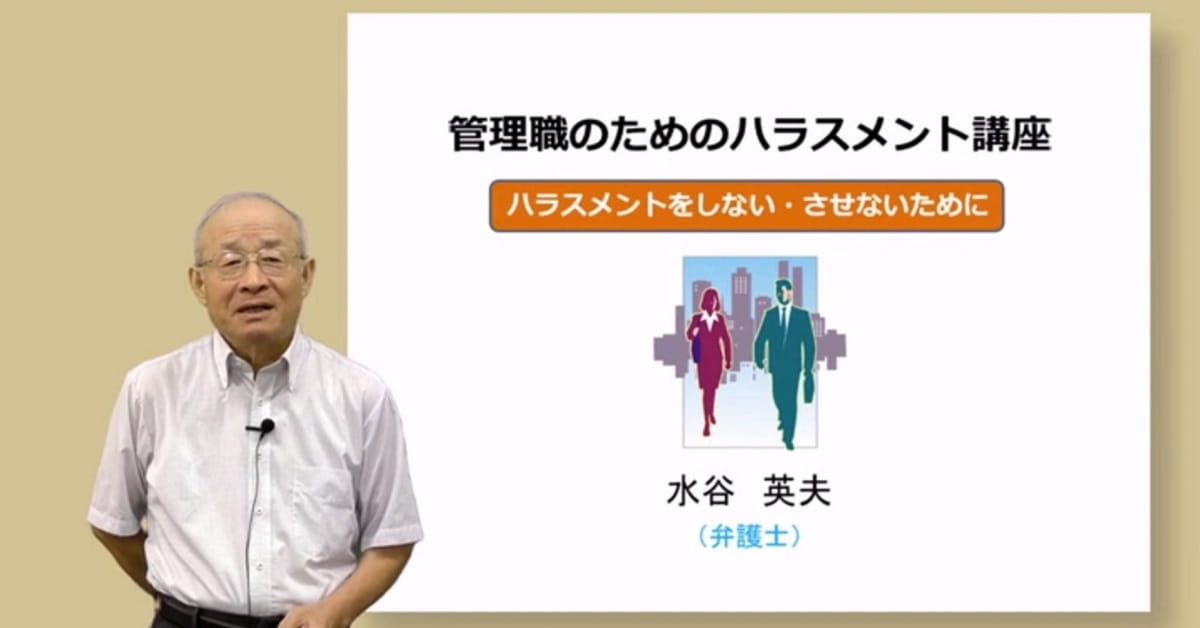

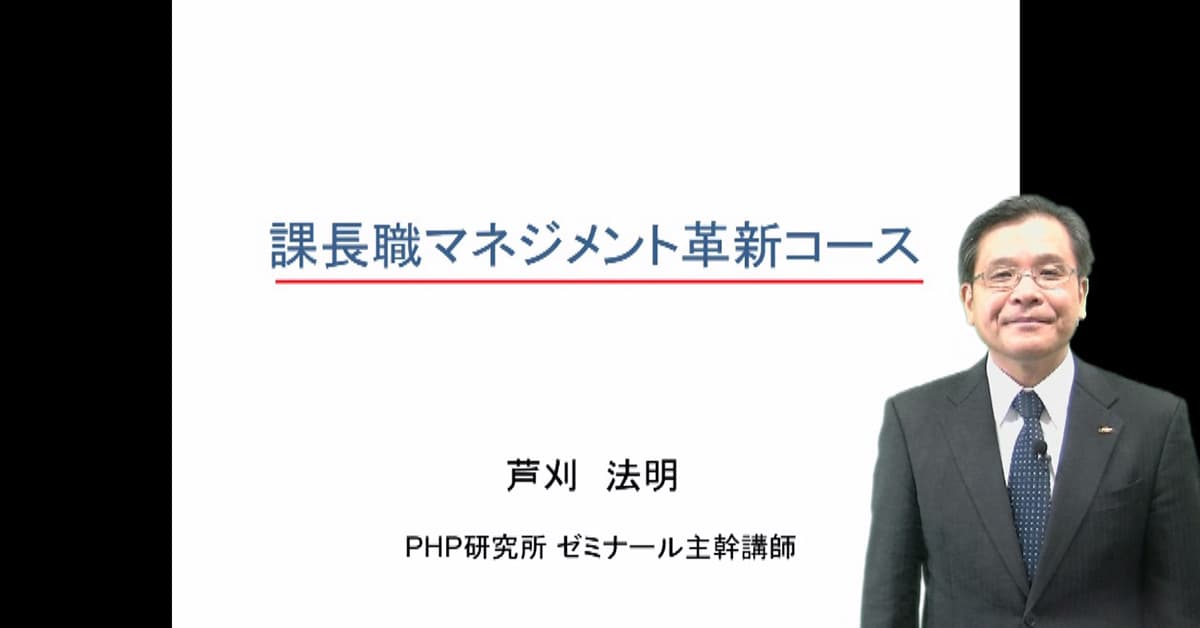



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















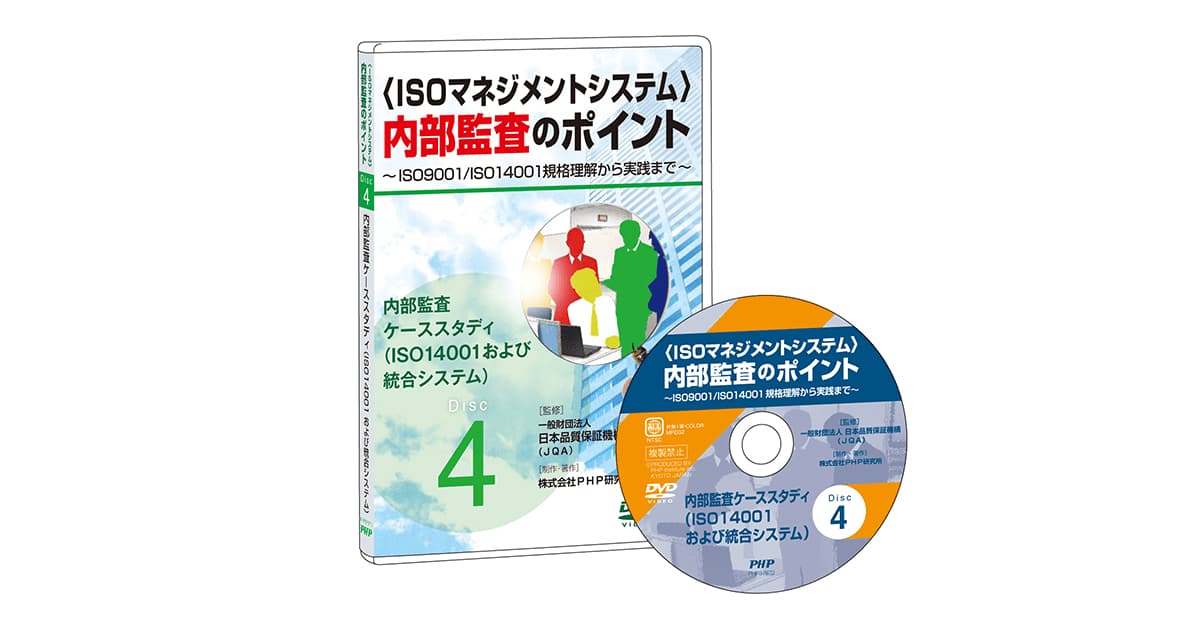





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
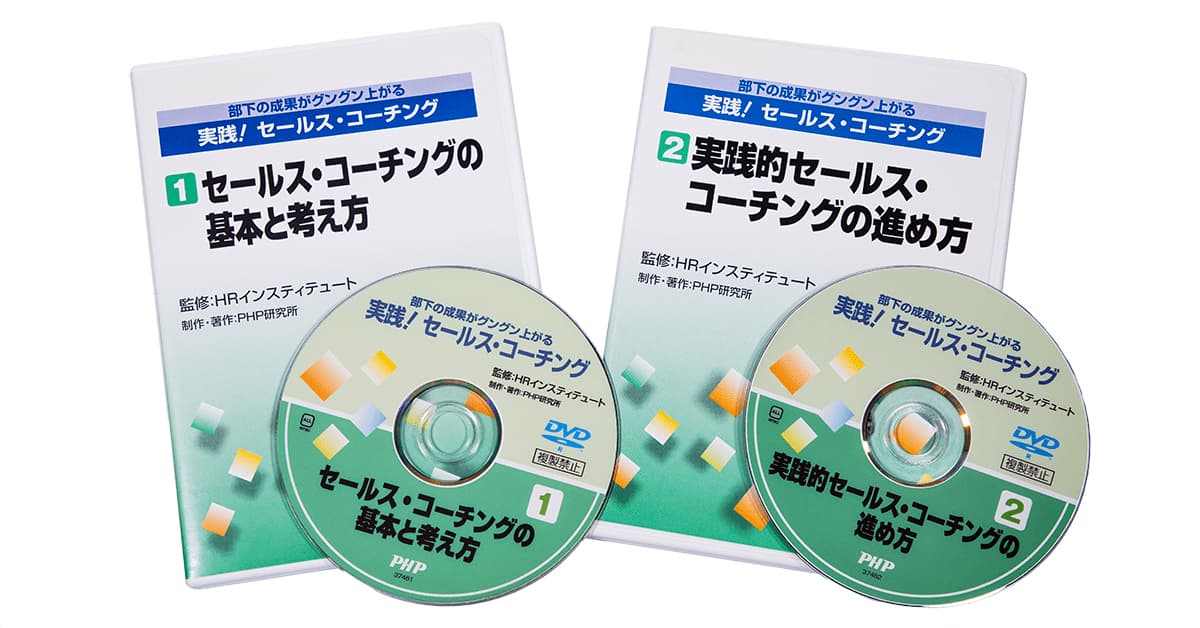




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)