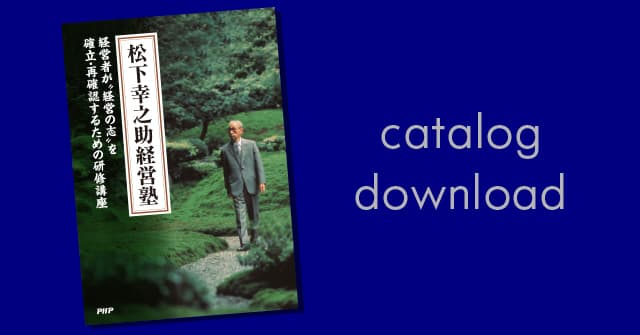土光敏夫の決断~石川島重工業と播磨造船所の合併
2019年1月13日更新

合併――それは企業が成長するための飛躍的な手段である。大が小を資本の論理で強引に併せ呑む合併が主流の中、石川島重工業と播磨造船所の合併は、マスコミも驚く電撃的かつ・恋愛結婚・と称されるほど理想的なものであった。
その演出者・土光敏夫は、のちに東芝の再建、経団連会長、臨時行政調査会会長となって常に世直しの先頭に立った。
世間が頼り続けた経営手腕の原点は、やはり石川島播磨重工業の誕生劇にあったといえよう。人間味あふれる土光の決断の背景にあったものとは......。
意表をついた発表
昭和35(1960)年7月1日、午後2時、東京会館で行なわれた記者会見はざわついた。石川島重工業の土光敏夫と播磨造船所の六岡周三の両社長が雛壇に並び、両社の合併が唐突に発表されたのである。
会見で土光は言った。
「貿易の自由化に対処して企業の合理化を推進するのが、この合併の狙いであります。不況にある造船部門も必ず近いうちに立ち直ります。この合併によって一プラス一を二にするだけではなく、核融合を起こして三にも四にもしてみせます」
それは断固たる、しかも確信に満ちた声明だった。資本金で見れば、52億円と40億円。従業員は約9千人と約6千人。年間生産能力は約4百億円と約2百億円の大型合併であった。
誕生する新会社の名は石川島播磨重工業株式会社、略称はIHIである。
「まさに寝耳に水」(『毎日新聞』昭和35年7月2日付朝刊)と書かれた合併劇は、マスコミのみならず、造船造機業界にも大きな波紋を呼んだ。
しかし、だれよりも驚いたのは、従業員だった。石川島では、部課長、労組に合併の合意が伝わったのは記者発表当日の午前8時、全従業員に伝わったのはそれからのことである。労組委員長が思わず叫んだ。
「社長、発表の直前に知らせるとは何事ですか。事前に労組に意向を打診するのが筋ではないですか!」
「悪かった。役員にさえ長く秘密にしてきた。そこを理解してもらいたい」
合併論議が騒がしくなれば成るものも成らなくなる。土光があっさり申し開いたので、だれも返す言葉もなかった。合併を交渉した当事者は両社長のほか、3人ずつの担当者、実は計8名にすぎなかったのである。
当時、日本経済の大変動を予見して、製造業界に異変が起こりそうな予感はすでにあった。しかし、造船業界においては、それぞれの思惑が交錯しだれも舵取りをしなかった。それゆえに、土光の合併劇は周囲の逡巡をさしおいて鮮やかに映った。播磨造船所との吸収合併をひそかに企図していた川崎重工専務・砂野仁(のち社長)は、「こちらが半年以上もぐずぐずしているうちに、土光さんはわずか3日で決断してしまった」とくやしがった。
陸と海の結婚
土光が合併を意識しはじめたのはその一年前のことである。造船業界の会合で播磨造船の六岡と会食をした。そのときの六岡のさりげない言葉がきっかけだった。
「播磨造船は造船部門の比率が高すぎて、造船の景気が悪くなると業績を直撃するのです。土光さんのところのように、陸上機械部門が強いとショックを吸収できるんだがなあ」
土光は驚いた。石川島との状況の違いが際立っていたからだ。
朝鮮戦争による米軍からの特需によって、日本の造船業は飛躍を遂げ、世界一の座にかけのぼった。しかし、昭和33(1958)年から世界的に海運業が不況に陥り、造船業もあおりを食っていた。六岡の悩みはそこである。
一方、石川島は全事業のうち造船部門が二割、陸上機械部門が八割だから、造船での影響は深刻ではない。しかし、土光はもっと先を見て別のあせりを感じていた。
(これから世界のエネルギーは石油の時代になる。そうなれば不況は一転し、大型タンカーの需要で好況に転じるのは間違いない。逆にそのときになって船を造るドックがなければ競争に負けるのは必然だ。造船部門の強化を急がねばならない)
昭和34(1959)年に、ブラジルに石川島ブラジル造船所を完成させ社の造船能力を三倍にしたが、それでも三万トン級タンカーの建造しかできない。ライバルの三菱重工、日立造船などは十万トン級タンカーを建造できるドックを持っていた。
(十万トン級の船を造れるドック建設に踏み切るかどうか)
それが土光にとって大きな懸案だった。
「六岡さんのところとは逆に、石川島は造船が弱いのです。大型タンカーの時代が目前に来ているのに、今の石川島のドックや技術では対応できない。せっかくのビジネスチャンスを、指をくわえて見ているしかありません」
正直にそう答え、
「世の中うまくいかないものですなあ」
と二人でこぼし合ったあと別れた。
しかし、このひとときの会話で、「お互いに、成り成りて成り合わざるところと、成り成りて成り余れるところとがある。これならうまくゆくのでは」と、土光は瞬時に合併を意識したのである。社に戻ると、腹心の部下を呼び、指示を出した。それは、「播磨造船所の調査をしてほしい。内密に」というものだった。
播磨造船所に関する調査資料が続々と土光のもとに届けられる。こと造船に関して播磨造船は三菱重工、日立造船に次ぐ第三位。兵庫県の相生にある大型ドックは業界屈指である。合併の意義を確信した土光であったが、それでも資料の吟味にゆっくりと時間をかけ、最終的に意志を固めたときは、六岡との会食から半年が経っていた。
それだけの時間をかけた裏には、おそらく合併に至るまでの土光なりの算段をつけたり、想定され得る事態への対処を思索したり、また合併後の混乱なき事業推進への対策を練ったり、といったことがあったのだろう。
合併という難題の推進に、もっとも大事なのは交渉である。播磨造船の六岡は小唄が得意な都会人。かたや夜の付き合いが苦手な土光は普段料亭に行くことはない。しかし、今はそんなことをいっておれない。土光は六岡社長を赤坂の料理屋に招待し、予定の一時間前に赴いて、玄関で六岡を待った。腹を割って合併の話を切り出すと、同じく技術屋経営者で合理的な六岡はすぐに土光の意向を理解し、話は一夜にしてとんとん拍子に進んだのであった。
改革の申し子
正式合併までの最難関は人事と組織の整備。ここは問題となりやすい。旧社同士の力関係を引きずって、人事に不公平を生むことがよくあるのだ。ことに大が小を併せ呑む合併ではなおさらである。石川島播磨重工業においては、播磨造船が解散という形を取った。どう見ても石川島による吸収合併である。その上両社の社風、給与体系、昇進制度すべてが違う。
しかし、新会社初代社長として土光は、まず役員構成を旧二社出身者同数にして公平を保った。膨張した組織は「産業機械」「原動機化工機」「船舶」「航空エンジン」「汎用機」の五部門に集約、完全事業部制を布き、それぞれの事業部長には大幅な権限委譲を行なって、俊敏な経営形態の構築を図った。驚くべきは個々の人事であった。これは「ミキサー人事」と呼ばれ、賞賛された。全従業員をそのまま本社がいったん預かり、あとは先の事業部へ石川島、播磨の出身にかかわらず適材適所のみに忠実に配置し直したのである。これでは社員同士がお互いに新顔で、どちらの出身かもわからない。こだわりやわだかまりが生じることなく人心が一新された。土光が会見で言った・核融合・は本物だったわけである。
この合併の立役者になったことで、従来地味だった土光の株は一躍上昇した。
その後の土光は・改革・の要あるところに引っ張り出されるようになった。取引関係にあった東芝再建を託され社長に就任。エリート意識だけが高く、お坊っちゃま気質に陥っていた社風に活を入れ、社長専用の華美な浴室を取り壊し、二人の秘書を業務に戻すなど、徹底的にムダを省いてわずかな期間に再建のめどをたてた。
いよいよ引退しようと思ったら、経団連会長に推され、さらに八十四歳にして臨時行政改革推進調査会会長に担ぎ出され、やはり改革を任された。技術者らしい合理的な考え方が、企業の再建や政治の改革にも適役だと見られたのだろう。
こうした活躍から土光についたあだ名も数多い。「財界の荒法師」「ミスター合理化」「行革の鬼」「怒号さん」等々である。
そうした資質が土光の人生において最初にクローズアップされた決断が、この石川島重工業と播磨造船所の合併劇だったと思われる。
では、合併の決断という点において、もっとも評価されるべきはいかなる点であろうか。
合理的であることはもちろんだが、やはり公平無私の精神と強いリーダーシップであろう。従来、資本関係も業務提携もなかった大企業同士の合併が、官庁や金融機関による根回しもなく、企業トップの主体的判断のもとに成立した。こうした例はごく稀なことで、企業家の信念がよほど強固でなければ実現しない。しかも、それが円滑に進んだのは、当事者の土光が、目先の利益、自社の利益といった視点ではなく、長期的視野に立ち、また相手の会社の立場を配慮して、終始紳士的な態度でリードしたからこそであろう。
土光敏夫の原点
こうした土光の信念と公正な気構えはいつ培われたのであろうか。その答えは、母の存在にある。
明治4(1871)年、岡山県御津郡芳田村で土光の母登美は生まれた。登美は18歳で米穀肥料の仲買をしている土光菊次郎と結婚、明治29(1896)年に敏夫を産んだ。
土光は熱心な日蓮宗の信者だが、それはこの父母がそうであったからである。ただ、信仰の姿勢は対照的で、病に関してなど、父菊次郎は薬を拒否し、信仰による治癒を信じた妄信ぶりだったのに対して、母登美は読経をしつつ専門の医学者を探したりした。また、信仰生活や自然を大切にしながら、たえず生活に工夫を取り入れ合理的な考え方をしていた。こうしたことから周囲の曰く、土光はこの登美の気風をそのままに受け継いだという。
登美について驚かされる点は、一主婦の身の上ながら、学校を創設したことである。元来、進取の気性に富んでいた登美は、雑誌『中央公論』『改造』などを読みふけり、社会問題に敏な女性であった。
いつしか信仰のない当時の女子教育に大いに不満を感じるようになった登美は、いつかそのための活動をしたいとひそかに期していたのであろう。菊次郎も登美も土光の就職とともに上京、普通に暮らしていたが、菊次郎が昭和15(1940)年に病没すると、一周忌のその席で余生を女学校の創設にかける、と家族に宣言した。すでに70歳の登美のその宣言には、皆呆気にとられ、当然反対した。
しかし、登美は譲らない。学校創設のためには文部省の認可から、用地買収、教員の確保、生徒募集まで途方もない労力が必要である。資本もない。登美は、資金集めからはじめた。そして、不屈の信念のもと、勤勉の限りを尽くして、本当に女学校創設を実現する。昭和17(1942)年創設の橘学苑(現橘学苑中学校・高等学校、横浜市)がそれである。学苑ができて、登美は法華経の読経をピアノの音で生徒に弾いて聞かせたという。
土光にとって、そうした母の生き方はすべての手本であった。土光は晩年、臨調会長として奮闘する中、質素な生活ぶりが紹介され有名になった。食事はメザシ、散髪も息子の腕に任す。月々の生活費は五万円、といわれた。おそらく大半が残されたであろう月々の給与は、母が創設し、自分が理事長を継いだその橘学苑に多く、可能な限り寄付されていたのである。
母の壮大な目標に対して、当時の土光は石川島の猛烈サラリーマンにすぎず、時間もなければ、給与も協力するには頼むに足りない。登美はすべて自力で邁進したが、亡くなるときには、「頼むよ」と土光に言った。土光は社業を抱えつつ、橘学苑理事長を継ぎ、母の遺志に応え続けた。肝心なときに充分に力になれなかった悔いが終生あったからだろう。
亡くなるまで母がしたように、朝夕法華経を読んで心を清めた。そうしてひとたび仕事に当たれば信念に基づき、合理性を重んじて判断した。よく合理的であることの裏側には、ドライ、冷徹な経営者像がついてまわるが、土光ほどそのイメージがないどころか、求道者的人間像が尊敬を受ける人物もいないのではないだろうか。
「個人の生活は質素に、社会は豊かに」。母登美が口癖にしていた言葉を、土光も信条としていた。土光が亡くなって以降、清貧が似合う経営者などどこにもいなくなった感がある。物心両面の豊かさについて、今の経営者は何らかの思いを抱いているのであろうか。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。










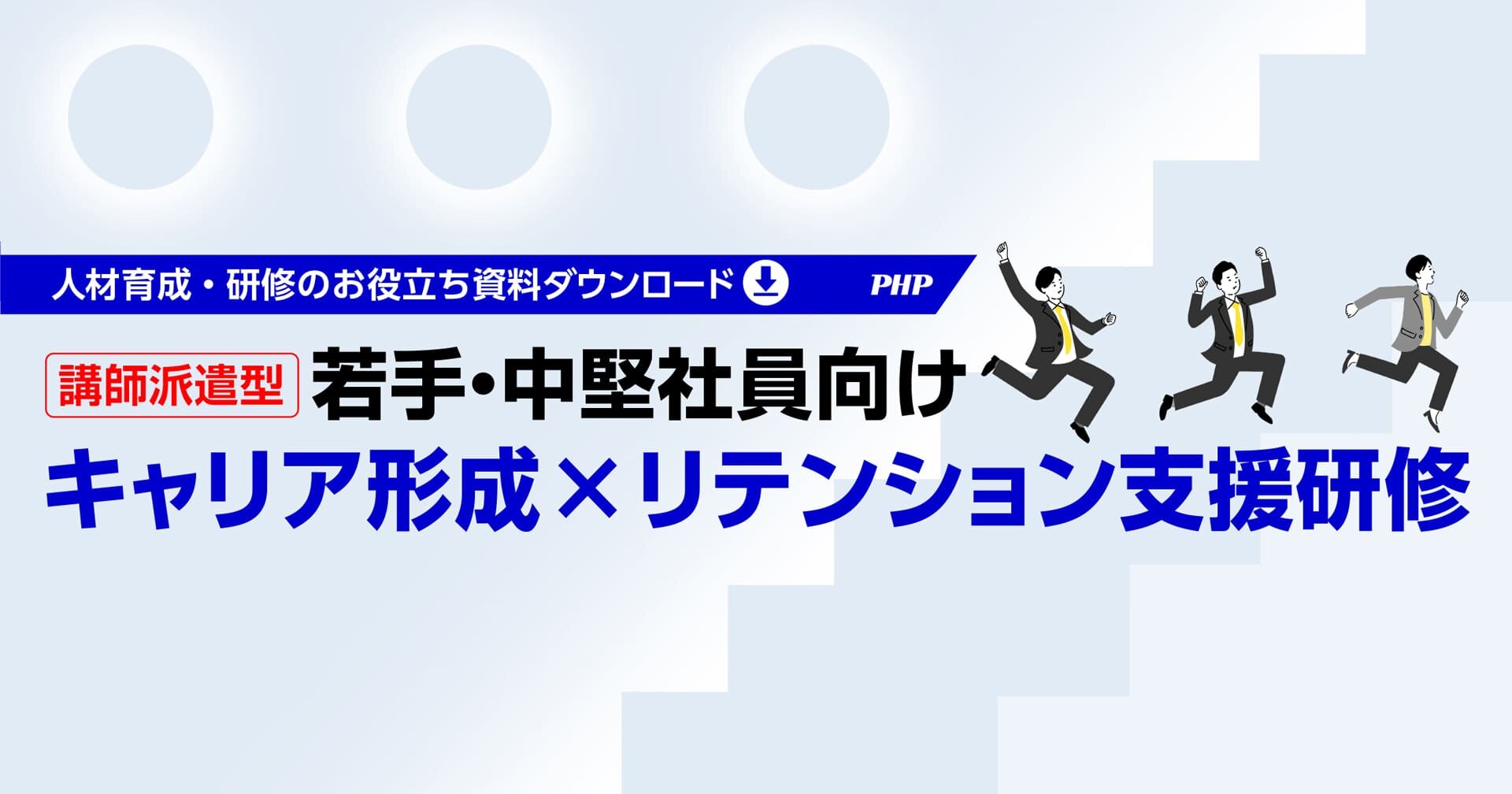





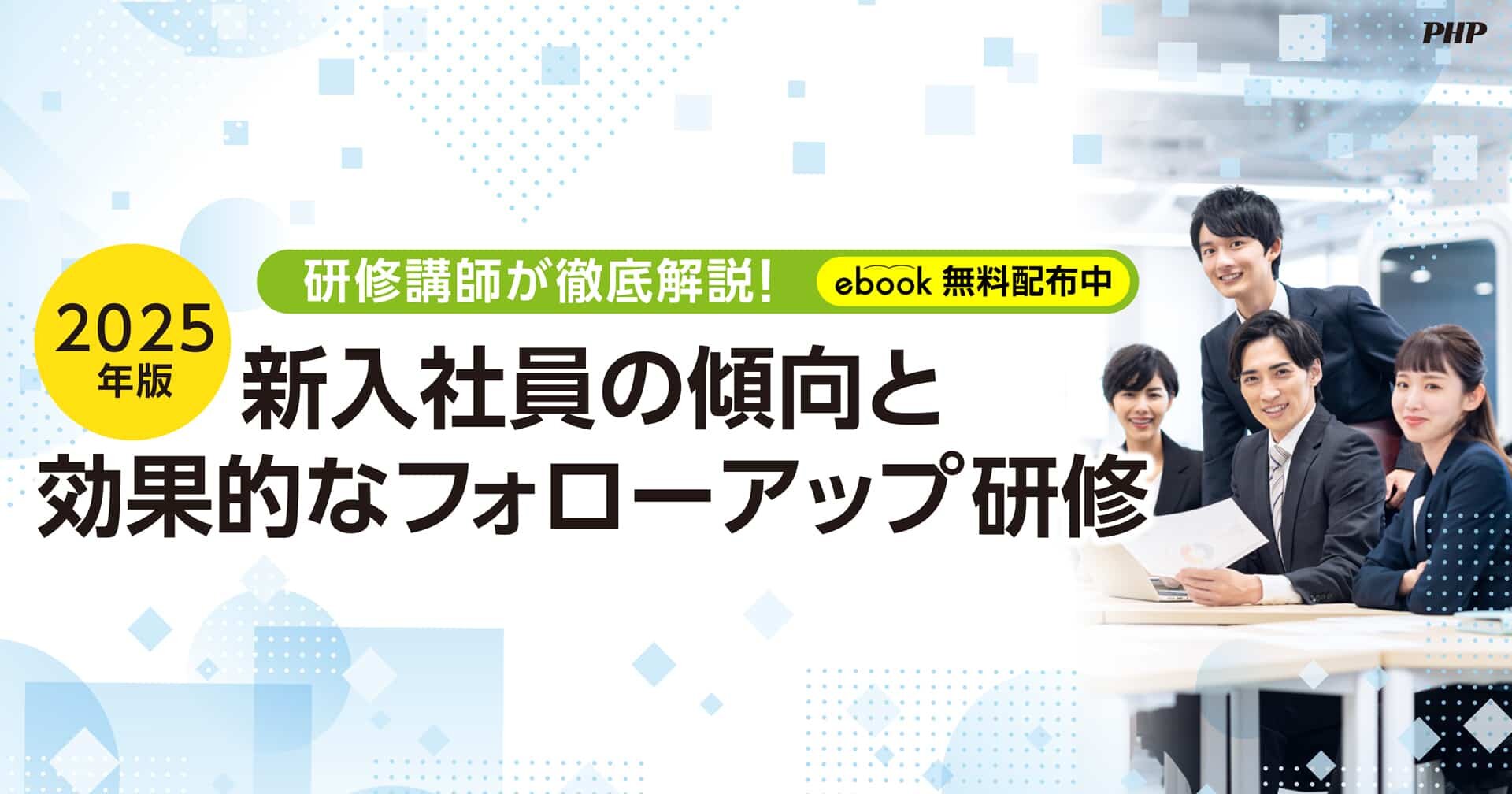









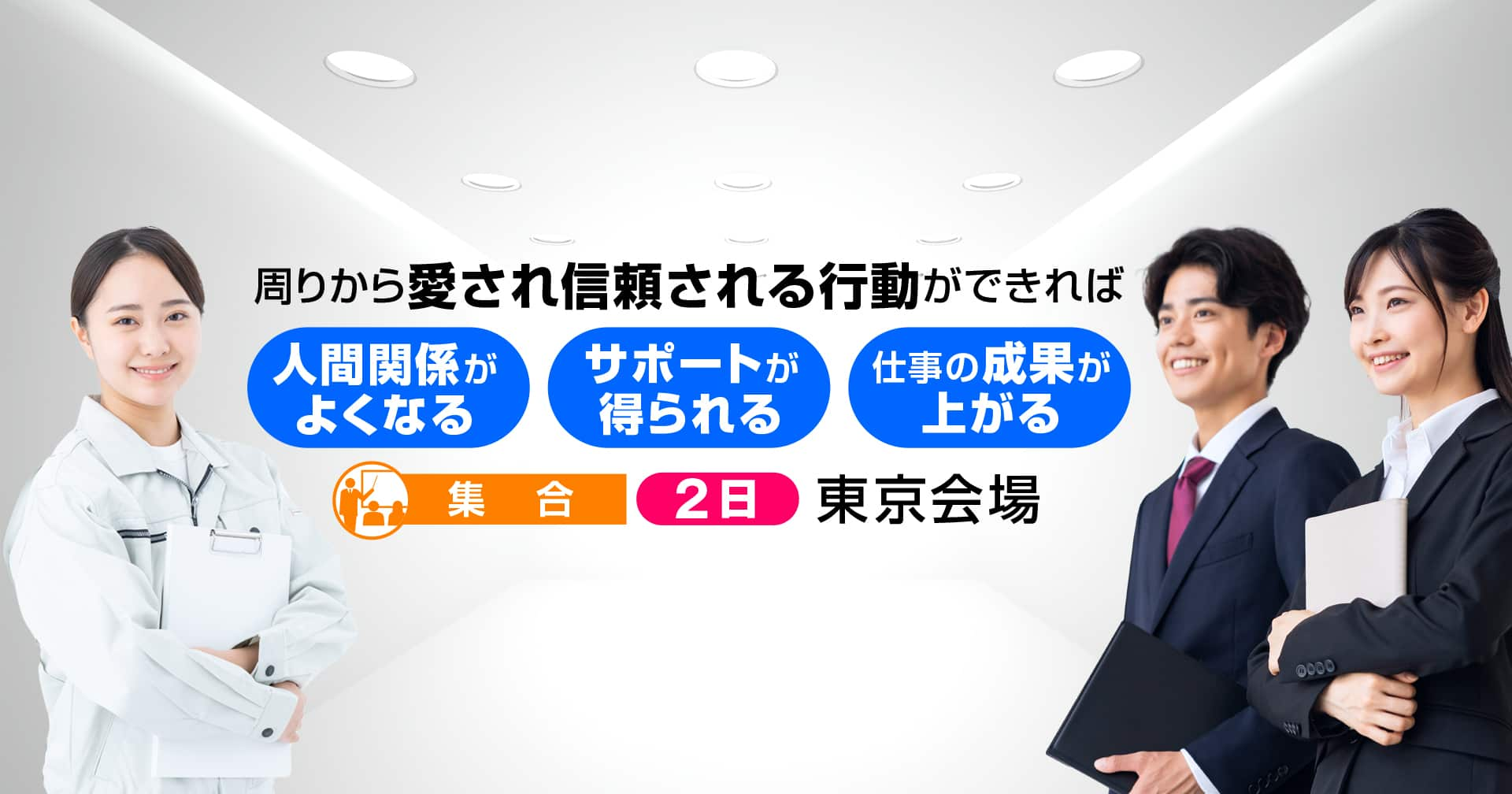










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







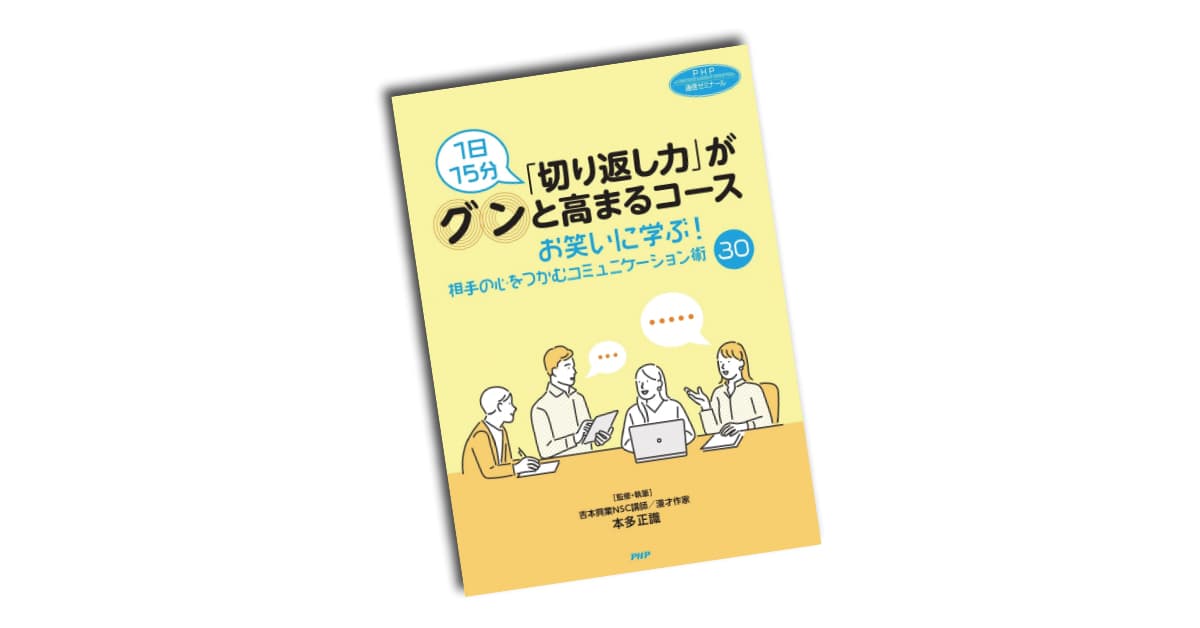






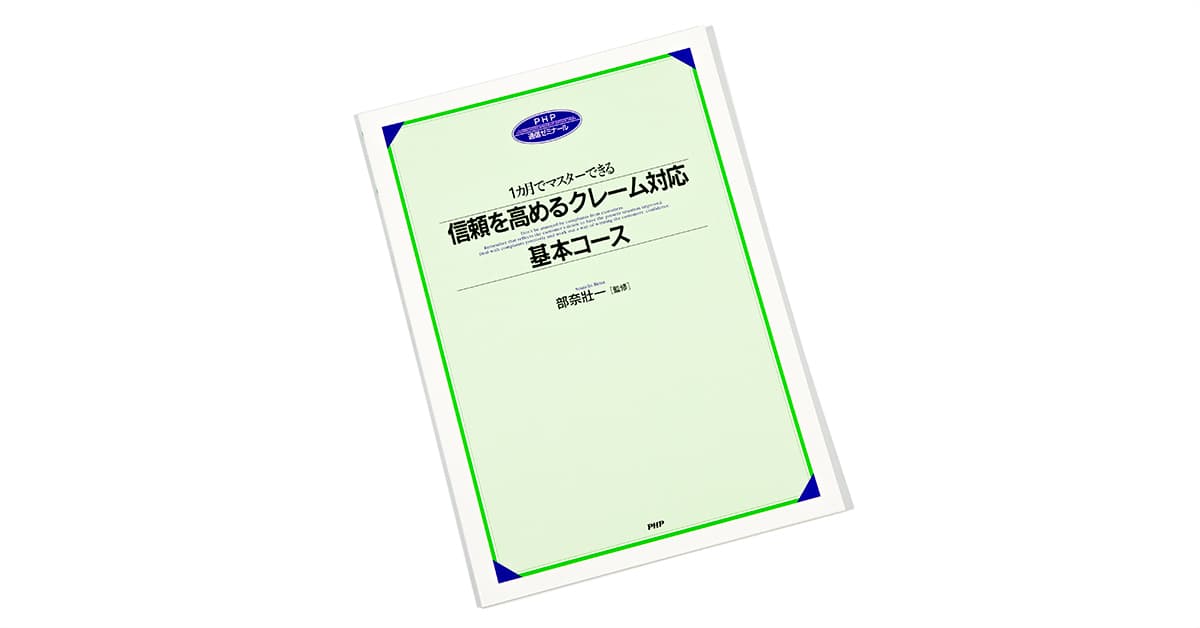





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

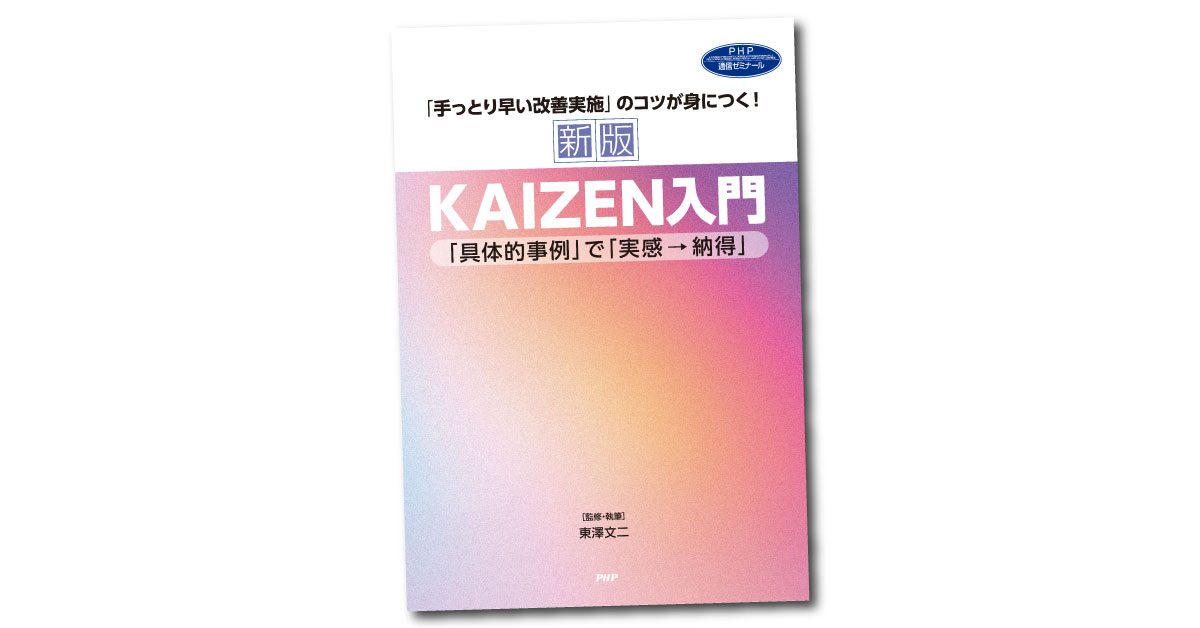










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)



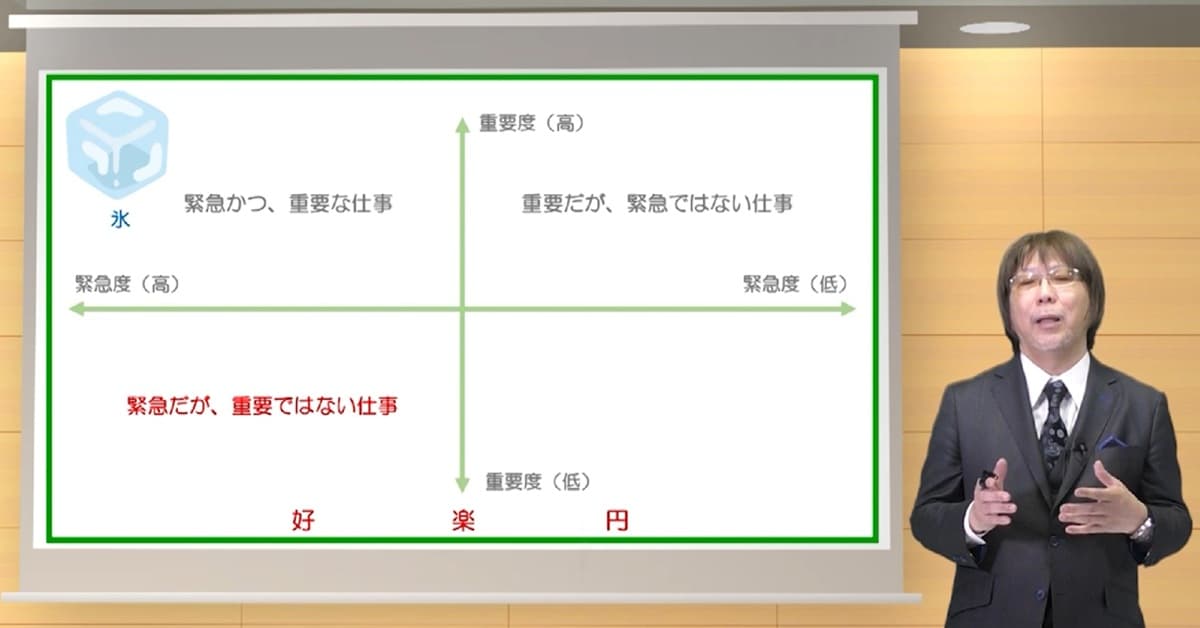
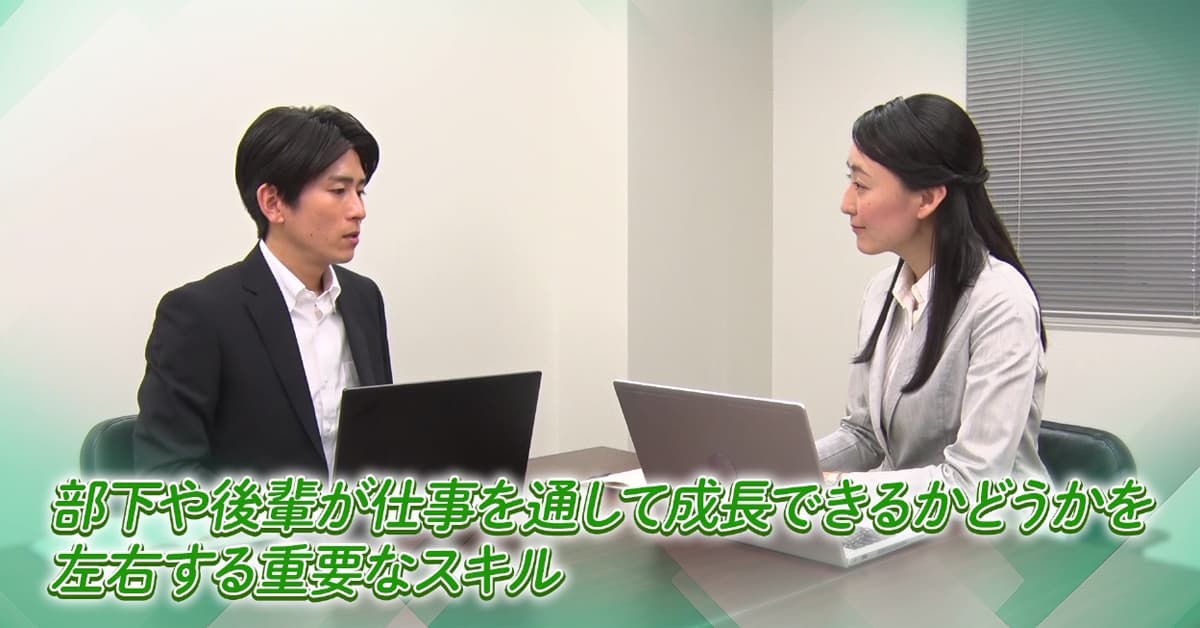
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
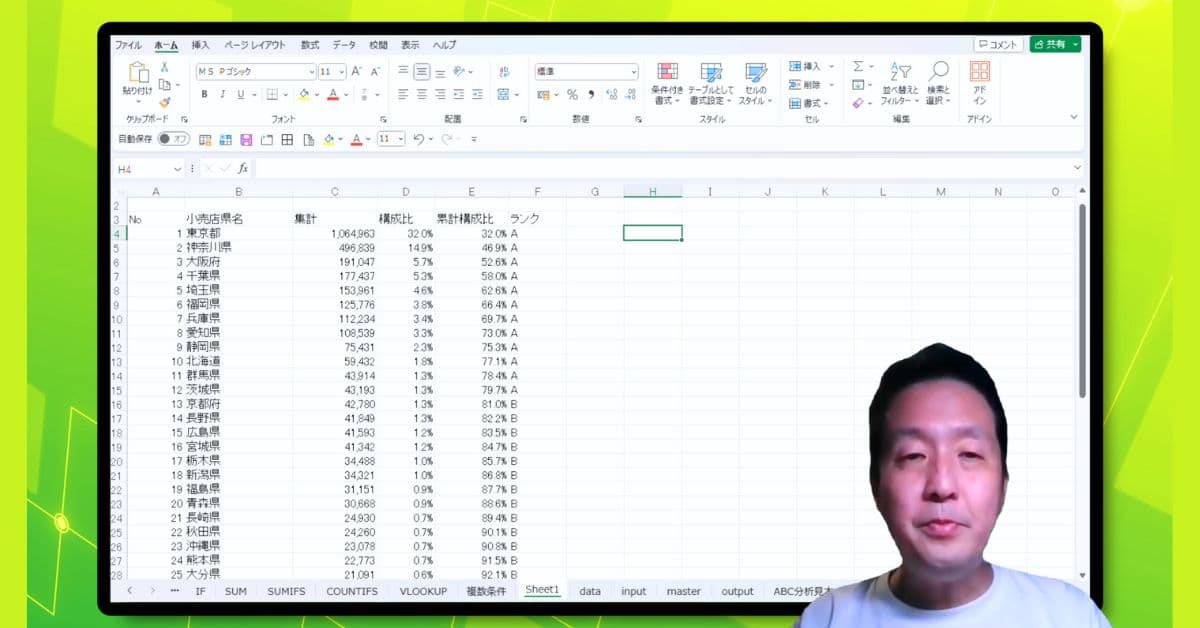

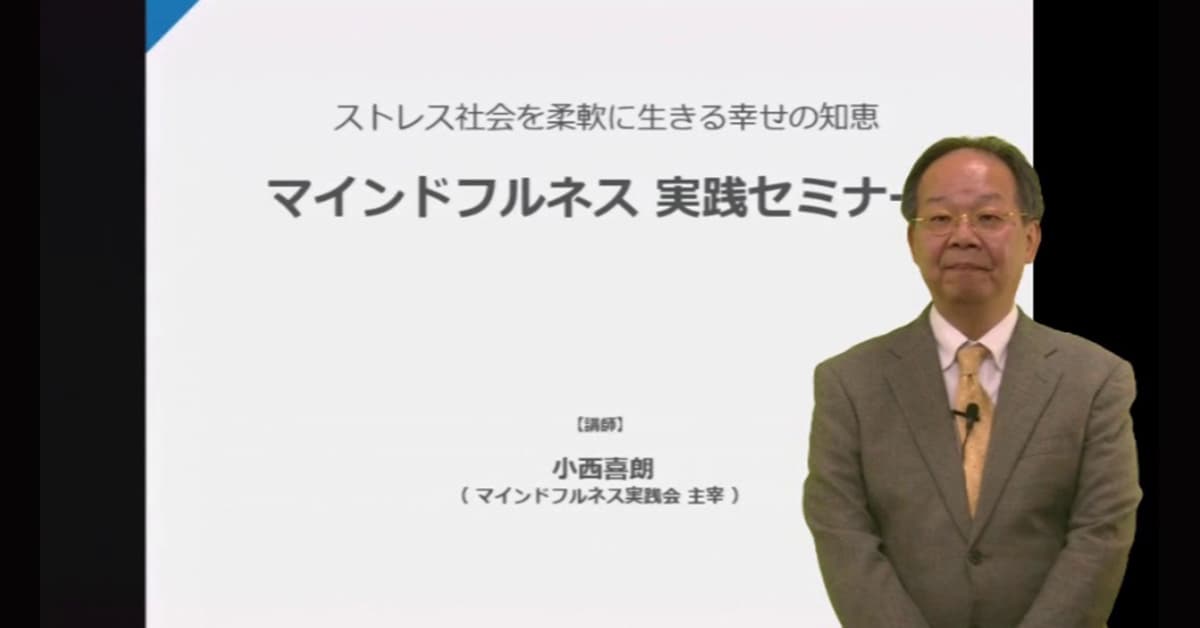

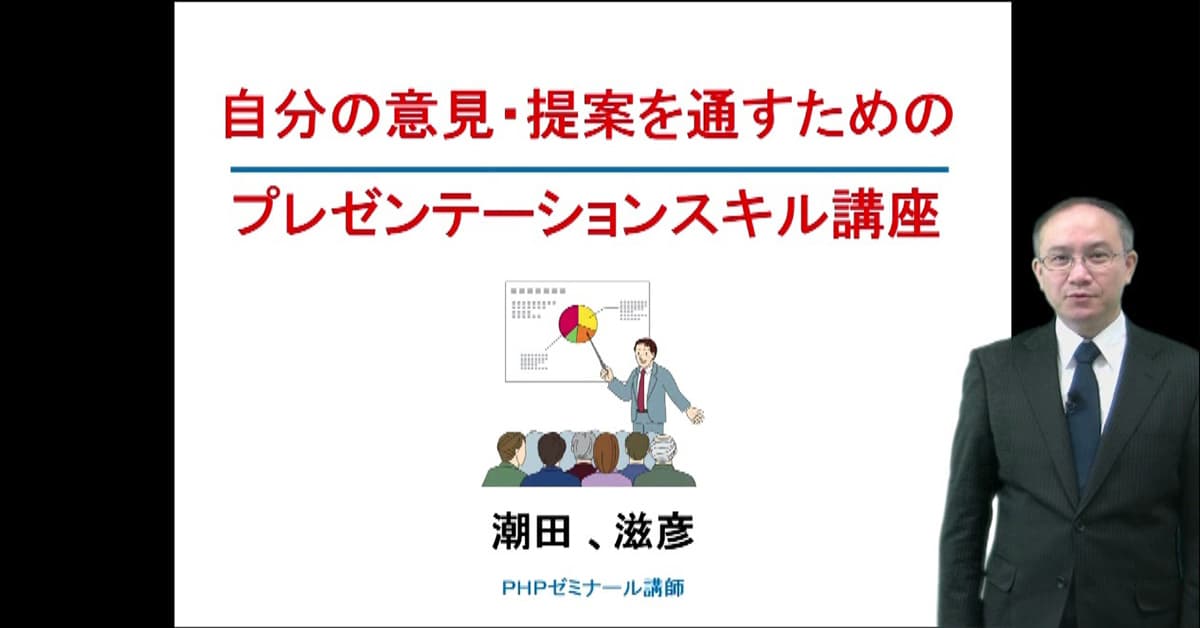
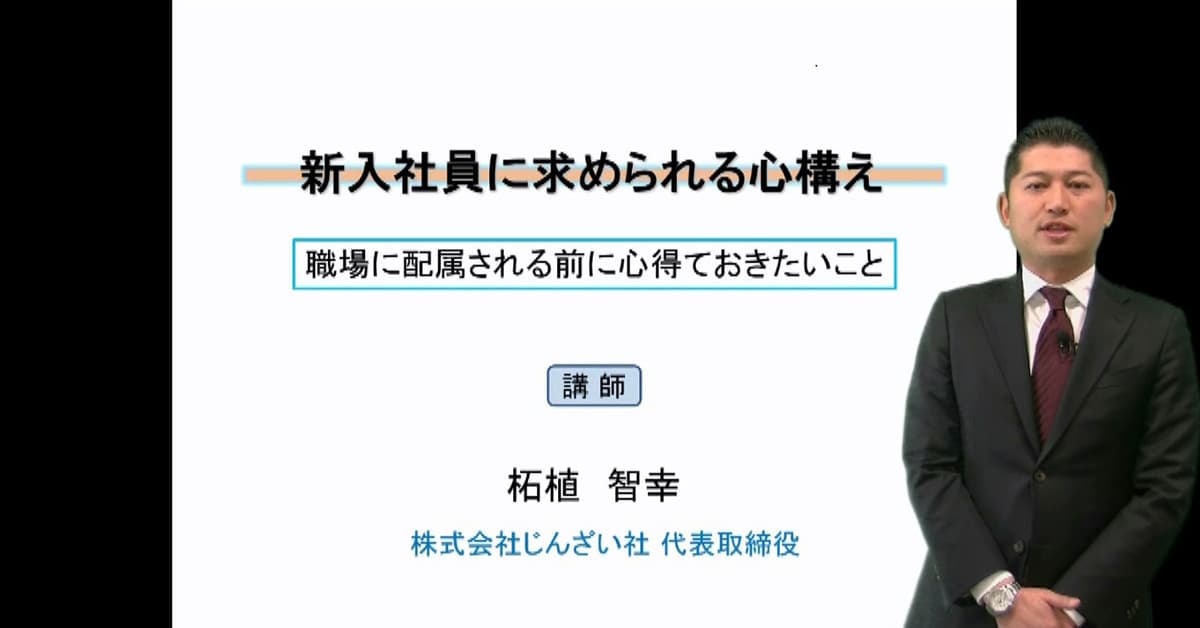
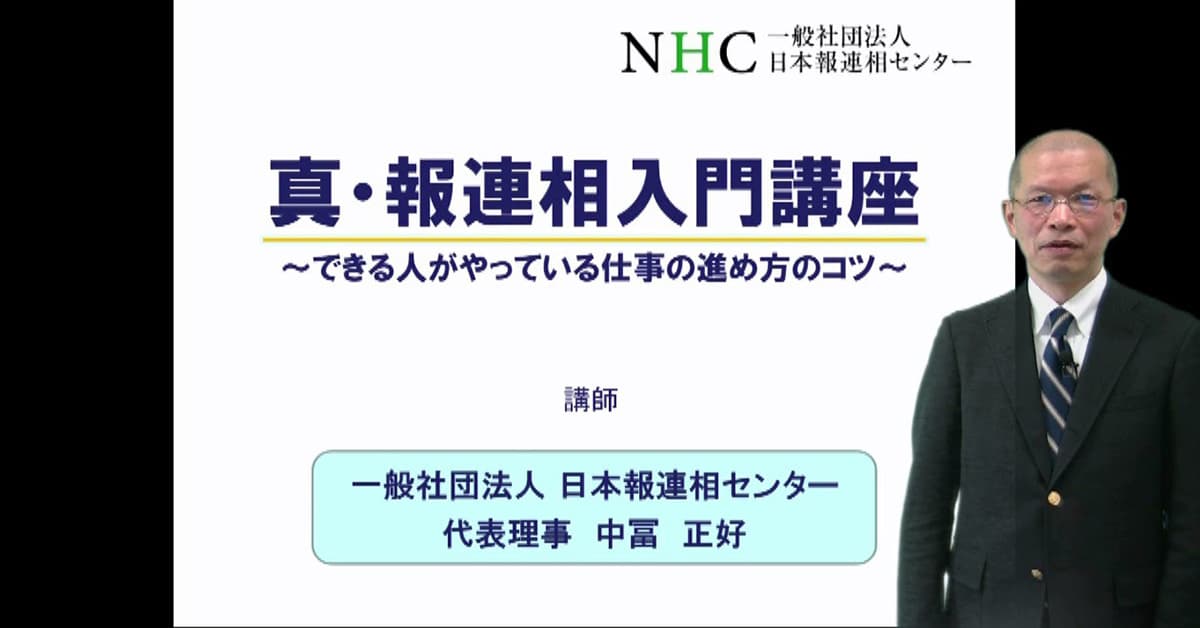
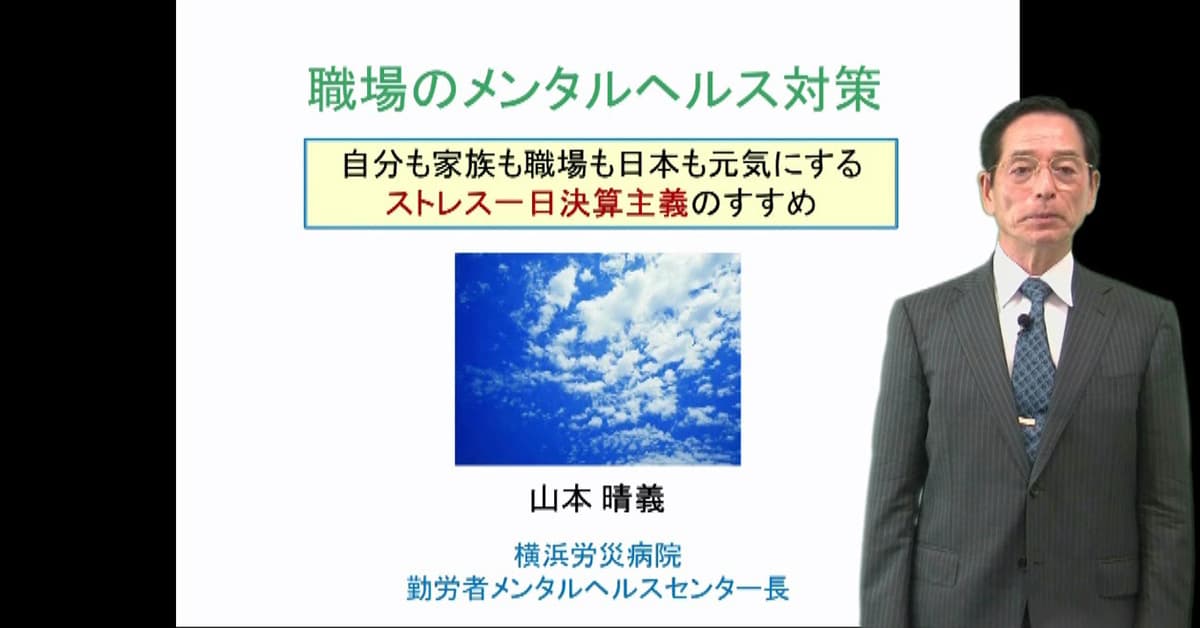
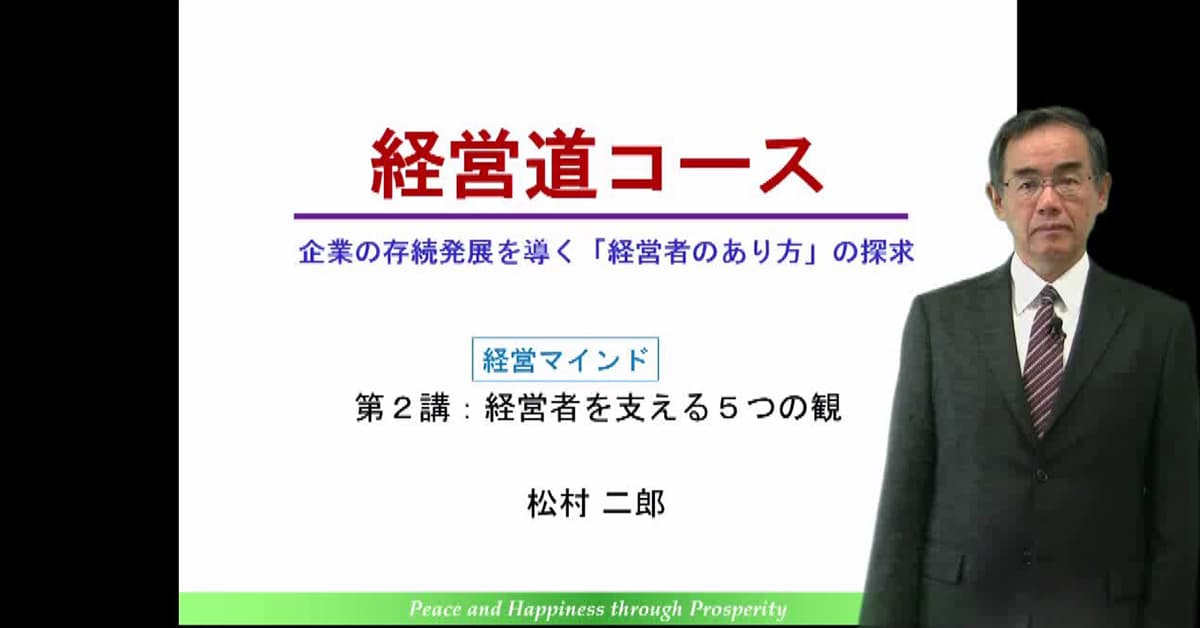
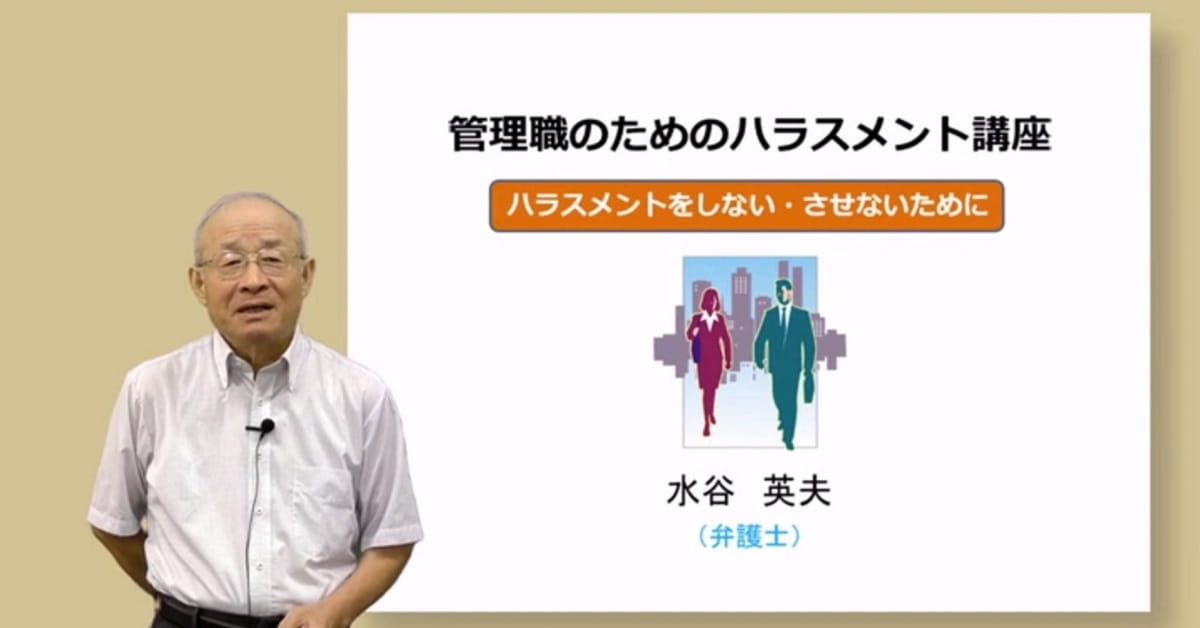

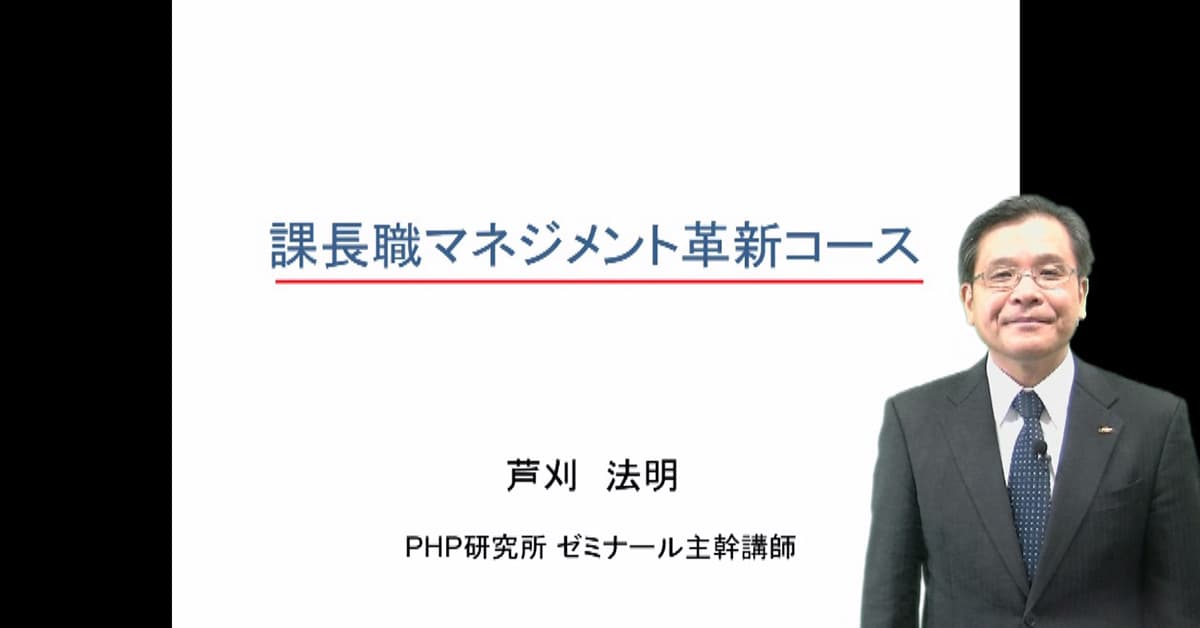



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















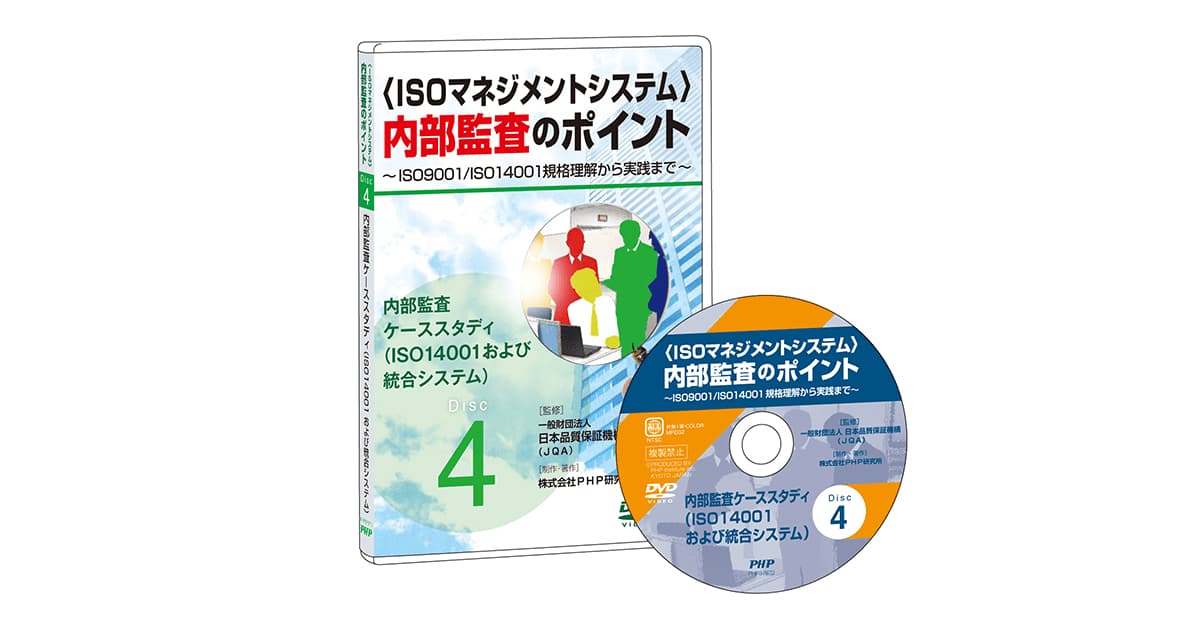





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
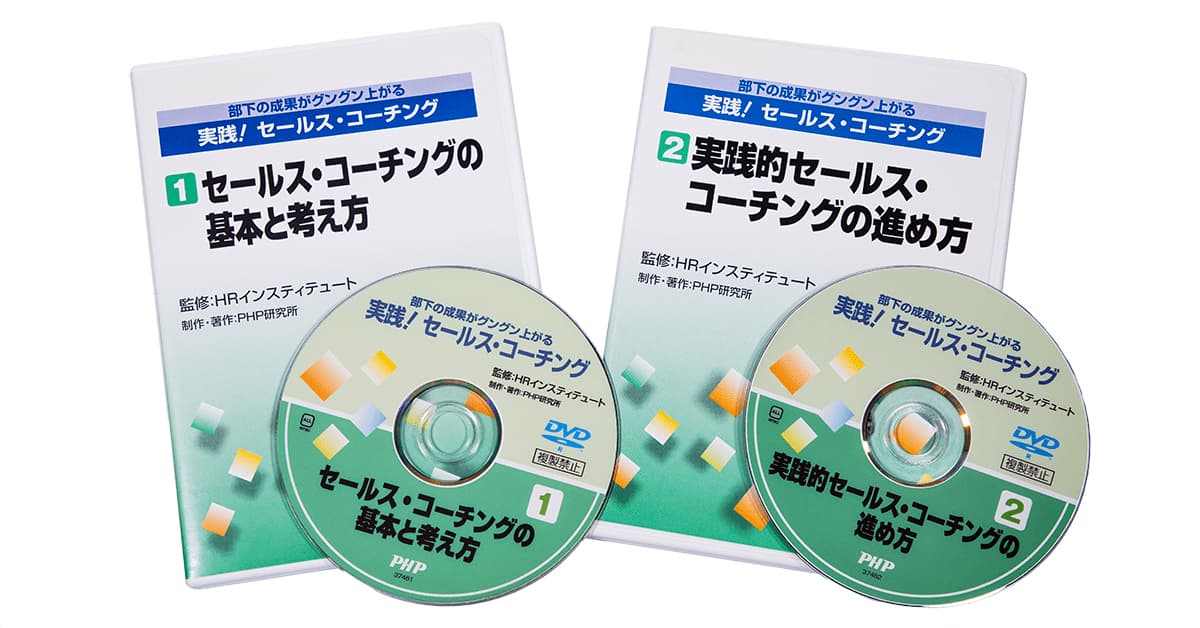




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)