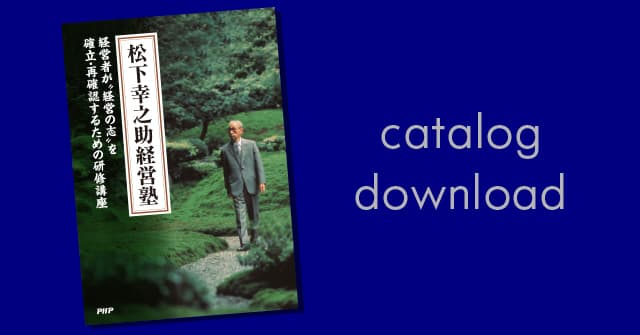金子直吉の決断~鈴木コンツェルンを形成した企業家精神(アントレプレナーシップ)
2015年11月24日更新

戦争特需に乗って、「行け! まっしぐらじゃ」と事業を拡大、神戸の砂糖商を一躍、世界的総合商社にし、なおかつ数多くの製造業を設立して鈴木コンツェルンを形成した男・金子直吉。
学歴もなく、風采も上がらず、自ら「白鼠」と称する男が、狂気に憑かれたごとく事業に邁進したのはなぜだったのか。
「煙突男」「財界のナポレオン」等々、背中につけられた多くの異名は人間・金子の際立った個性を証明している。金子の破天荒な人となりをふまえつつ、空前絶後の事業設立をめざしたその決断の背景を探る。
金子直吉の人となり
金子直吉を名経営者として論じることに異を唱える人がいてもしかたがないかもしれない。というのも金子は自分の会社を潰してしまった企業家であるからだ。神戸の鈴木商店という、三井物産や三菱商事を凌駕したこともある大商社があった、と思いを馳せる人は今や少ないことだろう。
しかし、鈴木商店の栄光と挫折は、金子とともにただ歴史の海に沈んだのではない。鈴木の名こそ消滅したが、金子が心血を注いで傘下に収め、手塩にかけて育てた企業群の一部は、神戸製鋼所、帝人、サッポロビール等、今も確固たる地位を築き活動を続けている。その源というのは、実は「煙突病」と揶揄された金子の常軌を逸したともいえる起業家精神にある。
鈴木商店は戦争特需の波に乗ったものの、その後の景気後退に資金繰りが悪化、ついに昭和初期の金融恐慌に耐え切れず瓦解する。けれども、金子の産んだ事業は親会社が滅びても日本経済の発展に寄与している。
資料や証言による金子直吉という人物は、たいへん個性的である。福沢諭吉の養子だった福沢桃介は金子を、「実業家の風貌も二代三代となると、自然鍍金がのって、綺麗にもなれば品もできるが初代の御面相はお話にならぬ。澁澤栄一、大倉喜八郎、根津嘉一郎等何れも皆然り。金子と来ては抜群なものだ......口大きく鼻低く、眼は小さく、近眼の上、色黒で......人並外れた醜男」と散々に評している。その上、服装にも無関心で破れ帽子に詰襟を着ていたため、大臣官邸の門衛に阻止されたという逸話もある。
その一方、日々の行ないは規律正しく、酒や煙草は一切たしなまず、仕事一筋だった。こんなこともあった。
ある夕方、金子が須磨の自宅に帰ろうと電車に乗った。あいにく車中は混んでおり、金子は立っていた。すると、前に座っていた婦人が席を譲ってくれたので礼を言って座った。そしていつものように事業のことをあれこれ考えていた。駅に着いたので電車を降り、自宅へ向かう坂道を歩いていくと、先ほどの婦人が前にいて、しかもわが家に入ろうとする。はて、と目を見張ってやっとそれが自分の妻であることに気づいた。金子の仕事中毒ぶりを示す逸話である。
慶応2(1866)年、土佐の吾川郡名野川村の貧しい商家に生まれた金子は、小学校すら通えなかった。読み書きも独習だった。十二歳になって高知で丁稚奉公をはじめ、砂糖屋、乾物屋、質屋を転々とした。恵まれない境遇ながら、金子はくさらず商人として身を立てることを誓う。後年、冗談めかして周囲にこう語っていたという。「わしは質屋大学の出身だ。質入れになった本を片っ端から読んだので、法・経・文・理何でもござれの総合大学だから、そう馬鹿にしたもんではないよ」
鈴木入りと精進の日々
金子は二十一歳のときに航路神戸に向かう。立身の望みを土佐にとどまって枯らしてしまってはいけないと思うところへ、神戸の鈴木商店の番頭・柳田富士松が偶然金子のいる店を訪れた。そして運よく金子を気に入ってくれて、鈴木入りの口を利いてくれたのであった。
当時の鈴木商店は初代岩治郎が輸入砂糖の引き取り・販売をしていたが、店員はわずか二名にすぎず、総合商社の片鱗はまだない。単調な貸し金取り立ての毎日、その上岩治郎の躾は、ソロバンの角で頭を殴りつけるという手荒なものであったから、金子は耐えられず一度土佐に帰郷する。しかし、母と岩治郎の妻ヨネが説得、店に戻った。
岩治郎から新しい取扱商品の検討を任された金子は本領を発揮しはじめる。樟脳や薄荷、鰹節を取り扱いに加え、それがいずれも当たったのである。ところが、金子の活躍によって店が個人商店の域を脱しようとしている矢先に、主人岩治郎が急逝する。店じまいも選択肢にあったが、未亡人ヨネは商売をあきらめず、先輩の番頭柳田と番頭になっていた金子の二人に託して事業継続を決定する。二十九歳の金子はヨネの信頼に応えようと事業に精を出した。しかし、思いとは裏腹に金子は大失敗をしてしまう。相場を読み切れず、無茶な樟脳の空売りを続けてしまったのだ。納品の期日が来てもモノはなく、金子はヨネに詫びるしかなかった。
しかし、ヨネは金子を叱らなかった。金子は示談で解決するよう諭され、注文を受けた外国商館に出向いた。ところがいくら釈明しても、厳しく督促されるだけだった。意を決した金子はにわかにその場にひざまずき、九寸五分の短刀を抜く。切腹して謝罪するというわけである。芝居じみた行ないだったが、恐れをなした相手の譲歩を引き出し、どうにか少額の違約金で示談をまとめることができた。
鈴木商店の飛躍は、この金子の逆境をはねかえす精神力が生んだと言っても過言ではないだろう。早々に金子は先輩の柳田に代わって、鈴木商店の全権を任されるようになっていた。拡大路線のために金子が企図したのは、やはり樟脳であった。故郷土佐が樟脳の産地(樟脳が採れる楠が豊富)であり、また防腐剤、火薬の原料として当時、世界的に大きな需要があったことから、金子はまず樟脳に勝負をかけた。樟脳の大産地・台湾に進出するのである。
当時、日本が支配していた台湾で、時の民政長官後藤新平に取り入り、樟脳の政府専売化を献策。そして、明治32(1899)年それが成ったところで、したたかに樟脳および樟脳油の六五パーセントの販売権を獲得した。さらに翌33(1900)年、台湾の現地工場を建設、見事に軌道に乗せる。
独自の戦略がもたらした頂点
樟脳で成功したのち、金子は薄荷でも成功、そして明治36(1903)年、卸商のみならず製造にも進出、大里製糖所を設立する。独占的なシェアから流通に圧力をかけてきた製糖所の経営に反発して起業したのである。そして苦難の末、これも立ち上げに成功。業界の健全な再編に成功したと見るや、二百五十万円かけて建設したこの製糖所を競合相手の大日本製糖に六百五十万円で売却、巨額の差益を手にする。これがその後の鈴木商店快進撃の大きな資源となった。
大里製糖所設立以降、金子は矢継ぎ早に事業を立ち上げる。母体である鈴木商店は、第一次世界大戦における積極投機によって最盛期を迎える。
世界中の軍需品が暴騰すると読んだ金子は、「鈴木商店の大を成すはこの一挙にある。まっしぐらに前進じゃ!」と宣言する。金子がロンドン支店に送った電報は、"BUY ANY STEEL, ANY QUANTITY, AT ANY PRICE" 、ありったけの資産を担保にして、鋼鉄と名のつくものは、何でも、いくらでも、あるだけ買いまくれ、というものだった。そして船舶にも進出、船舶を発注するだけではあきたらず自ら造船所の経営に乗り出す。
鈴木が鉄を買いはじめて三カ月、鉄や船舶は高騰する。大正4、5、6(1915~17)年と雪だるま式に売上げは拡大した。その成長は投機の成功によるものだけではない。第三国間貿易という鈴木商店のお家芸ともいわれた商売戦術が功を奏していた。日本でつくったものを外国で売るという貿易だけではなく、世界の相場の動きを把握しながら、外国でつくったものを他の外国に売る。チリの硝石をロシアへ運び、ロシアで積んだウクライナ産の小麦をロンドンへ運んで売りさばくといった大掛かりな商法である。かくして、「SZK・イン・ダイヤモンド」のマークを付けた鈴木商店の船は、積荷を満載にして世界の海を航行する。これはかつて相場で大失敗した経験をふまえ、情報には金に糸目をつけず電報によって世界の情報を集めたことによる勝利だった。
五十二歳の金子が若き二十九歳のロンドン支店長の高畑誠一(のち日商岩井会長)に「天下三分の書」を送ったのは、大正6(1917)年11月のことである。
「此戦乱の変遷を利用し大儲けを為し三井三菱を圧倒する乎 然らざるも彼等と並んで天下を三分する乎 是鈴木商店全員の理想とする所也 小生共是が為め生命を五年や十年早く縮小するも更に厭ふ所にあらず」
そして妻の手ほどきでつくった俳句が
「初夢や 太閤秀吉奈翁 白鼠」
金子がいかに意気軒昂であったかがよくわかる。白鼠の俳号は、主家に忠実な番頭を意味し(広辞苑)、鳴き声が「チュウ」、すなわち「忠」に通じるからだという。
最盛期といわれる大正8~9(1919~20)年において、鈴木商店は従業員三千名、年間取引高は十六億円に及び、かつて三井物産が記録していた最高額十二億六千万円を越え、ついに日本一となる。日本はもとより、世界でも指折りの大商社となった。
なぜ常軌を逸した事業拡大をめざしたのか
鈴木商店は砂糖の専門商社から総合商社へ拡大、その余勢を駆って製鋼・造船・金属・化学・繊維・製糖・製粉・製油・製塩・麦酒・製紙といった製造業進出を重点にコンツェルン化した。そこに金子の大きな意図があったことは確かである。現在に至るまでの日本の工業立国の輝かしい軌跡をふりかえれば、「工業化のオルガナイザー」として、金子は鈴木商店を潰した汚名を補って余りある役割を果たしたといえるだろう。
しかし、なぜ金子はそうまでして事業拡大に邁進したのであろうか。ともすれば資金的なリスクにさらされる可能性が出てくるのも理解できていたはずである。
考えられる理由はいくつかある。
まず挙げられるのが、単純なトップ志向である。三井、三菱を越えて一番になるというのは、経済人としての本懐といえばそのとおりであろう。
次には、「工商立国」という金子独自の事業観である。商社としての間口を広げるだけではなく、製造業に進出することを厭わなかった。
「損しても得してもいいが、事業家は生産をしなくてはいかん」
すなわち製造業を盛んにすることは、すなわち原料を買い、製品を売ることに繋がる。つまり商社の利益のためにも製造業設立の意義があるというのだ。独学ながら博覧強記で知られた金子の頭脳は知識の上でも製造業に対する目利きに相当な自信をもたらしていたのではないだろうか。
そして、もう一つ事業拡大の大きな背景としてあったのは、現代の実業人よりも当時の実業人のほうがはるかに有していたと思われる国益志向である。「国家がやらなくてはならんことを、鈴木がやっておる」と、金子は各種工業の育成を、日本の国益と目して追求していた。
たとえば、人絹(人造絹糸)である。日本の国際的な繊維産業の地位の高さを考えれば、天然繊維を補う意味で人絹製造の意義は非常に大きい。金子の製造業へのこだわりはすべて国家への奉仕という意識が根底にあった。
一商店の番頭にすぎなかった金子はいつから、天下国家のためにのみ、事業を煙突のごとくにょきにょきと多数設立しようとしたのだろうか。考えられるのは事業成長とともに交際が広まった政治家との関係である。後藤新平をはじめ政治家との関係を深めていく中で、彼なりに実業人としての使命感が形成されたのかもしれない。
金子は自ら政治家ばりの行動を取ったことがある。第一次世界大戦中、英米は鉄輸出禁止の措置に出た。そのため連合国側であっても鉄が入らず、日本の重工業界は危機に陥った。政治家も動かない。このとき、金子は単身上京してアメリカ大使と会見、戦時により船を欲している相手を見越して、「船を売りましょう。ただし代金は鉄でいただきたい」と交渉、見事に成立させた。この行動は国難を救った美挙とされ、金子に叙勲の話が出た。が、金子はすぐに辞退したという。
こうした行動は一実業人でありながら国益を背負うといった使命感と、生来蔵していたヒロイズムが現れたものかもしれない。それと、もしかすれば、顔に似合わぬロマンチシズムといった人間性を持ち合わせていたのかもしれない。
金子と女主人ヨネとの関係は封建的といっても差し支えなかったであろう。初代岩治郎亡きあと、ワンマンといわれた金子だが、ヨネに対する誠実さは不変であった。ヨネも、終生「直吉!」と呼んでいた。ヨネの金子への信頼は絶大で、経営不振に陥って金子更迭の話が持ち上がっても耳を貸さず、鈴木商店倒産の報を聞いても顔色一つ変えなかったという。若き頃の大失敗を許してくれた女主人、その恩義に報いんとする気持ちの中に忠誠心と、わずかながらでも恋慕の情がひそんでいたとするのは筆者の思い過ごしであろうか。
企業家が持つべき使命感
大戦後の不況を受け、鈴木商店の資金繰りは次第に悪化。昭和二(一九二七)年三月二十六日、取引銀行からの貸し出し停止により万策尽きる。鈴木商店倒産は金融恐慌の引き金となり、その名は栄光よりもその挫折で歴史に名を刻んでしまった。
金子の失敗は二つあった。一つは金融の軽視である。「煙突」を建てるばかりで、回転させるための資金繰りの手立てが手薄だった。株式会社化し増資するのは遅かったし、そもそも巨大企業グループを形成しながらその傘下に銀行などの金融機関を持たなかった。金子は金利という不労所得によって社会を牛耳る金融業を批判していた。「日曜祭日は金も遊んでいる。金利を取るな」と訴え、銀行国営論まで述べていた。
もう一つの失敗は近代的な経営組織をつくることができなかったことである。優秀な人材はいたが、経営への干渉を恐れて、経理内容の開示を社内においてさえ拒み続けた。トップマネジメントとして独善的にすぎた。肥大化した組織で世代間の断絶も見受けられるようになったが、組織内を調整して解消する有効な対策も打ち出せなかった。
こと創造において抜群のセンスを発揮しながら、守成にあっては自らの古く、固陋な経営観から抜け出せず、今風にいえば、グローバル・スタンダードの近代管理経営に適応できなかったのである。
破綻後、晩年にかけて金子は黙々と債務処理に携わり、部下の再就職に手を尽くした。後年、近衛内閣の内閣参議に推されたこともあったが、「私は昭和二年のパニックを起こした元凶です」と固辞したという。
金子は、生涯を通じて私財を築く意思に乏しかった。鈴木商店が最盛期のときでさえ、生活費に窮したことがある。ところが社の自分の机の引き出しを開くと給与袋がぎゅうぎゅう詰めに詰まっていたという。晩年の住まいも、かつての部下がお金を集めて建てたものだった。
こんな逸話がある。かつての部下が訪ねていくと、「少し金が欲しい」と言う。部下が、生活費のことかと思って、ありあわせの金額を言うと、「今考えている事業のお金じゃ」と答える。思わず部下が失笑すると、「おまえは実業家になる資格がないぞ」とどなったという。金子の企業家魂はその後も不変であった。亡くなる直前まで樺太のツンドラを資源化するという途方もない事業を夢見ていた。
私財のためではなく、公益のために事業を起こす。そのためにはあらゆる可能性を追求する。それが金子の実業家としての本懐なのだった。今、経営者はいるが、金子ほどの使命感を持った人物は幾人いるだろう。金子の存在こそ企業家精神(アントレプレナーシップ)の権化として時には顧みられるべきではないだろうか。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。










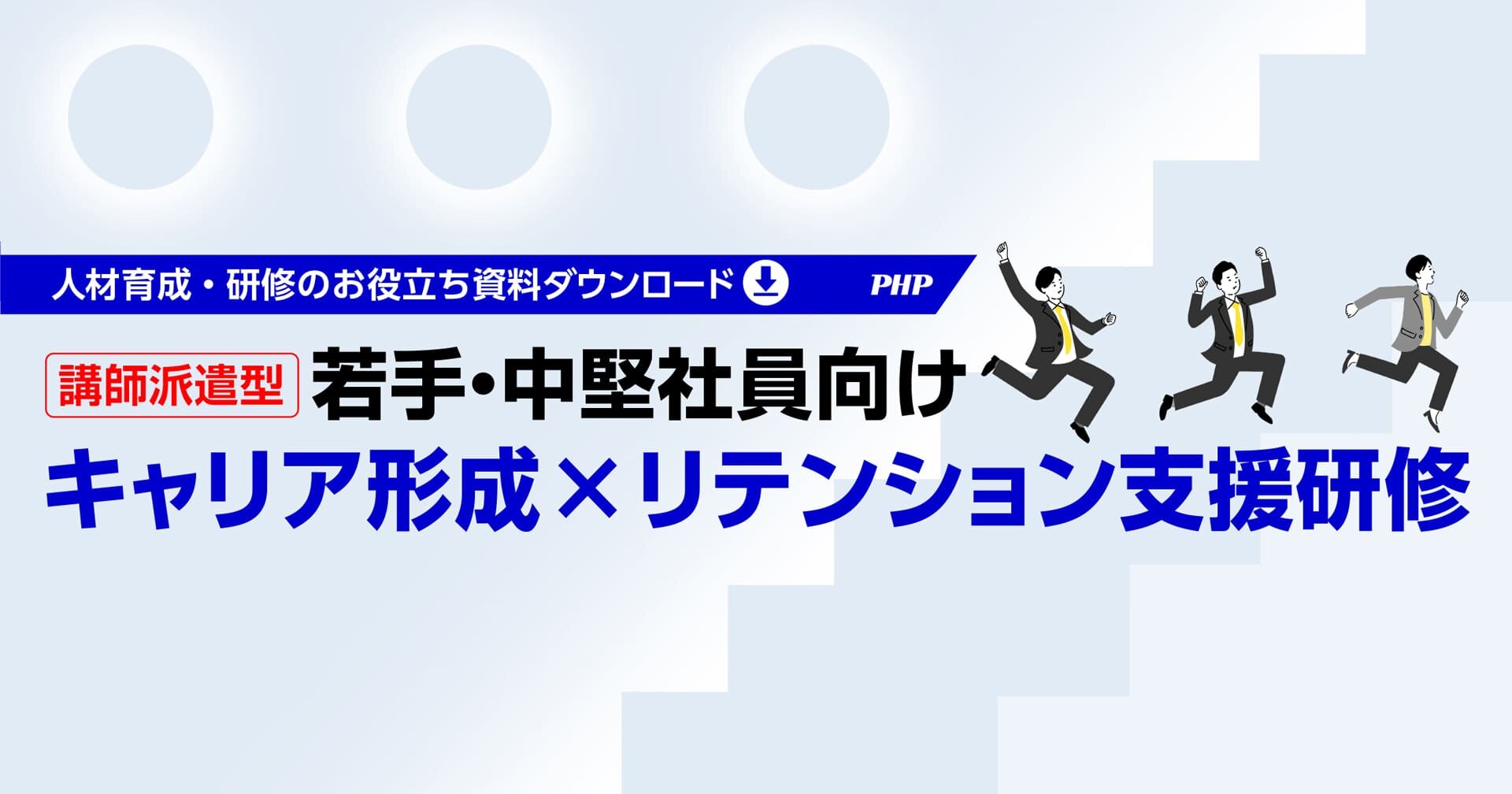















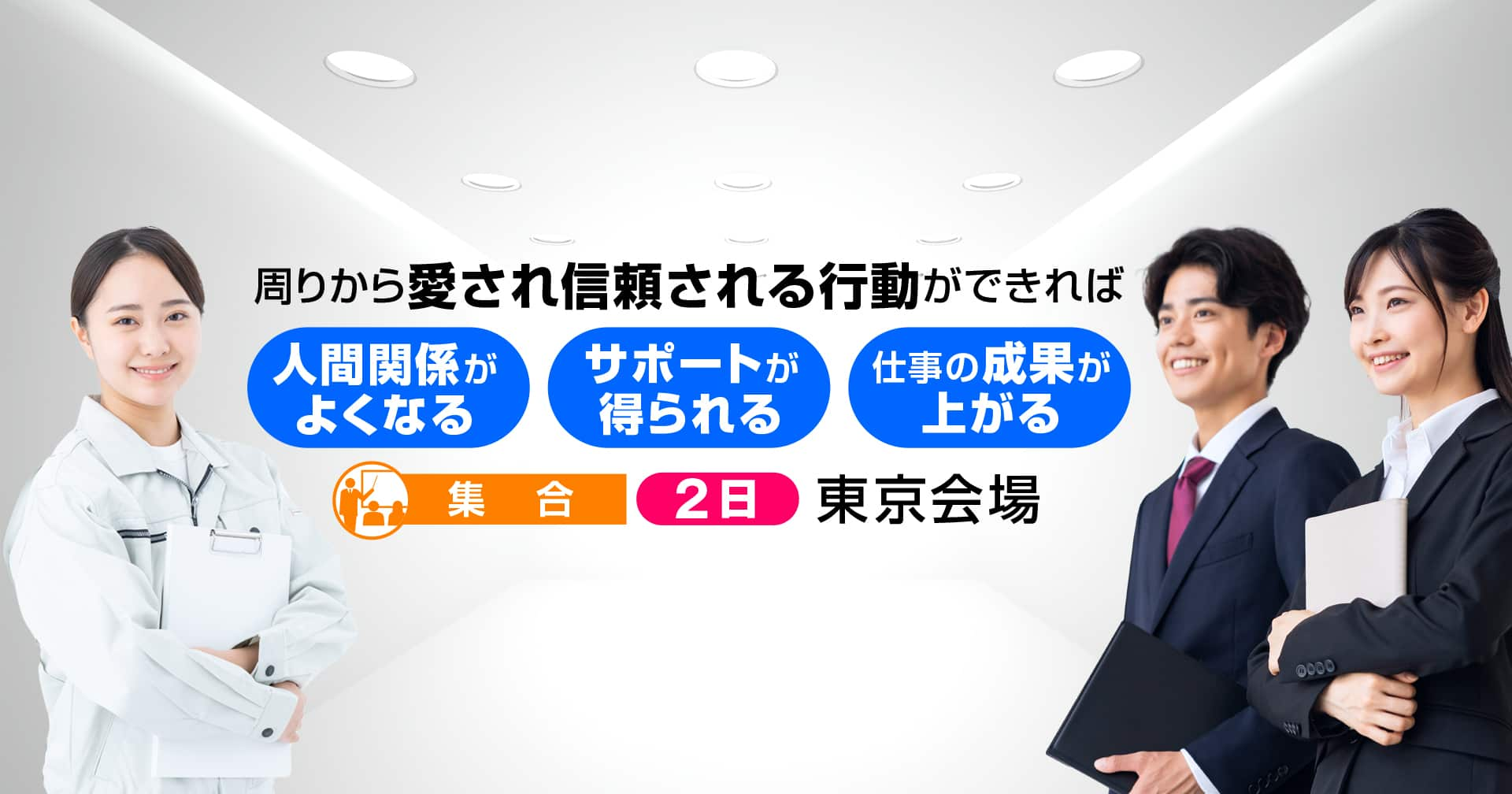










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







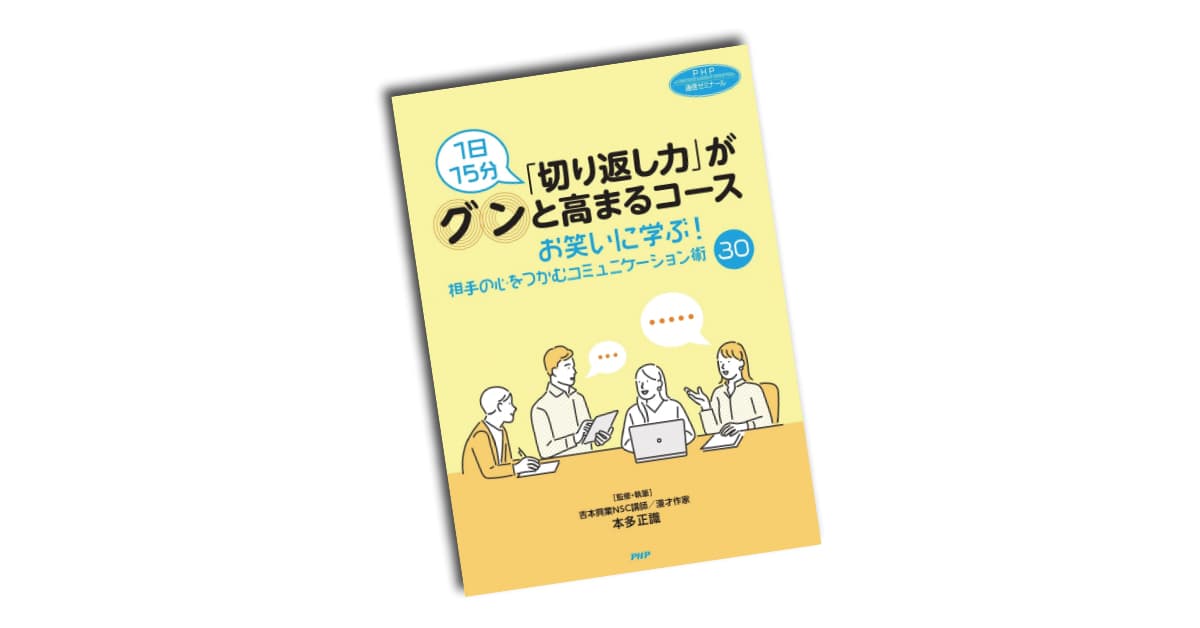






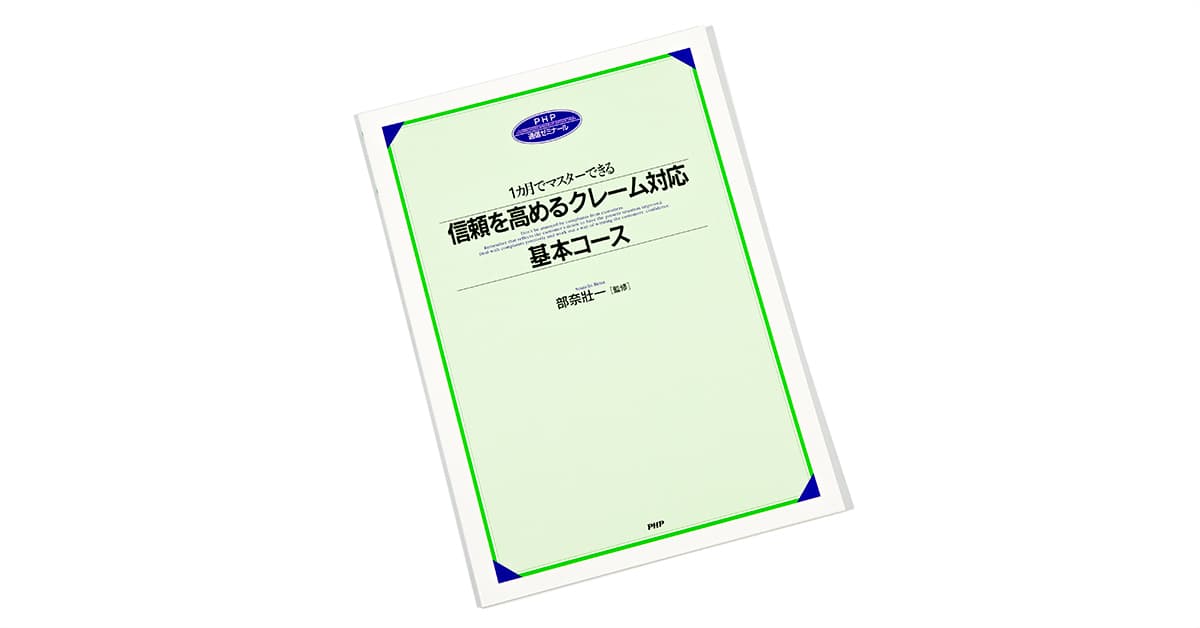





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

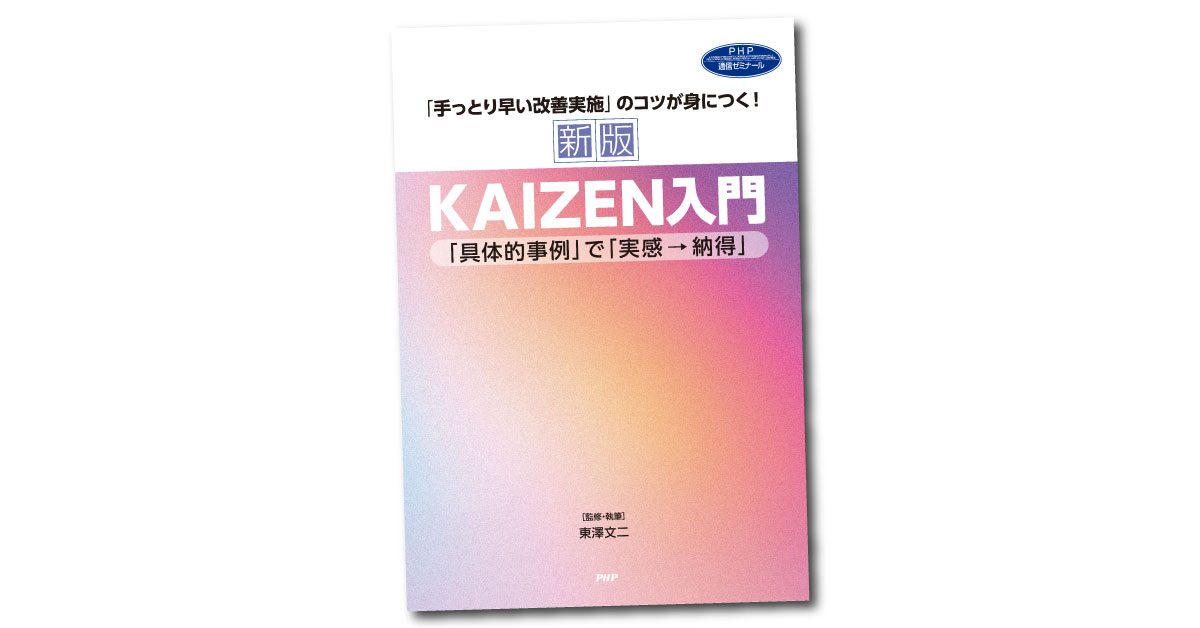










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


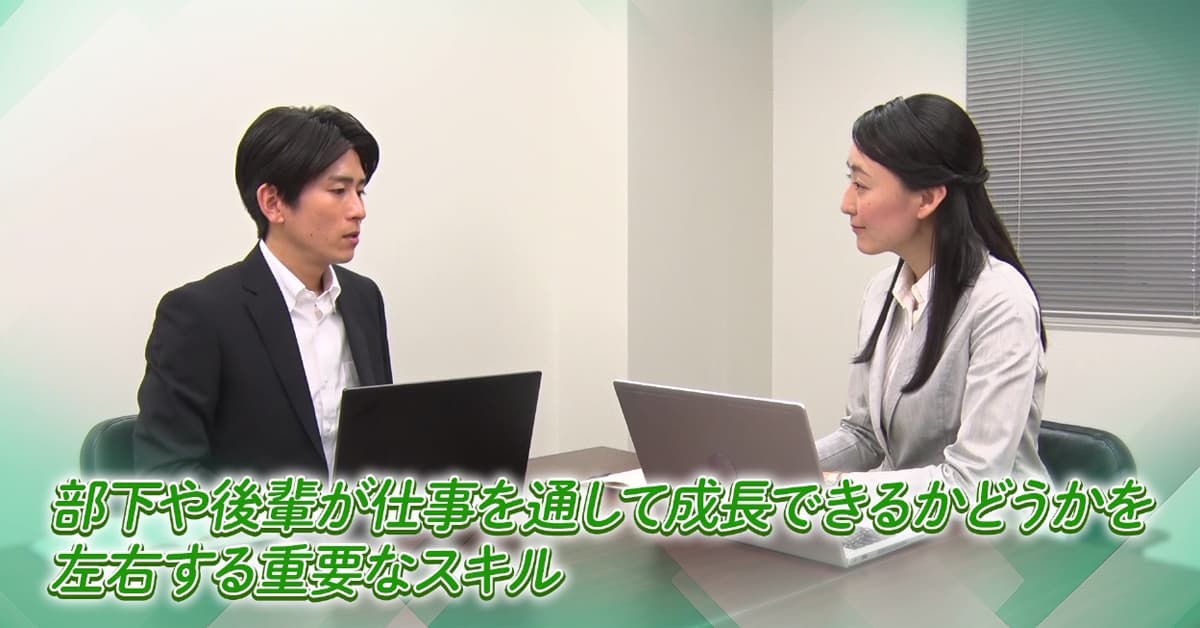
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
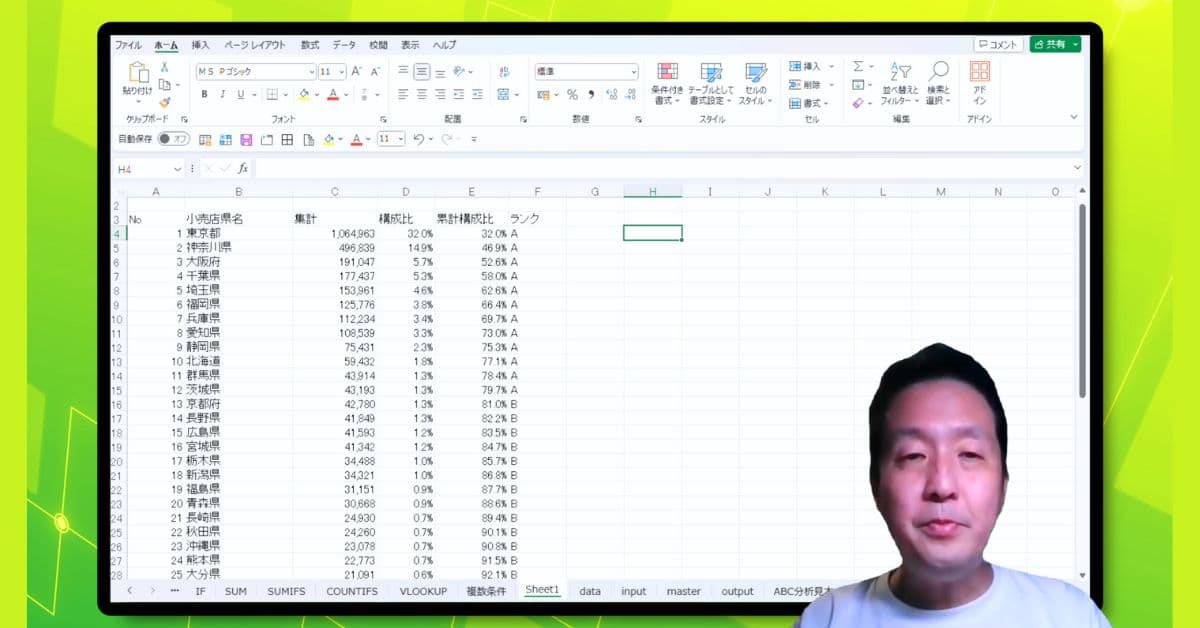
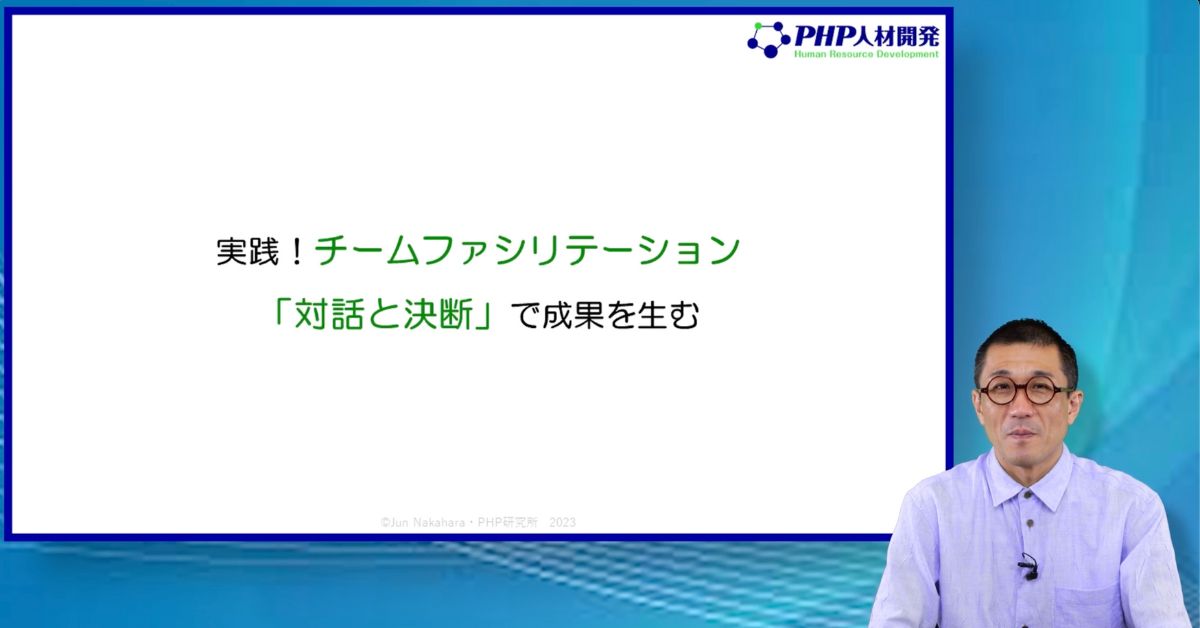
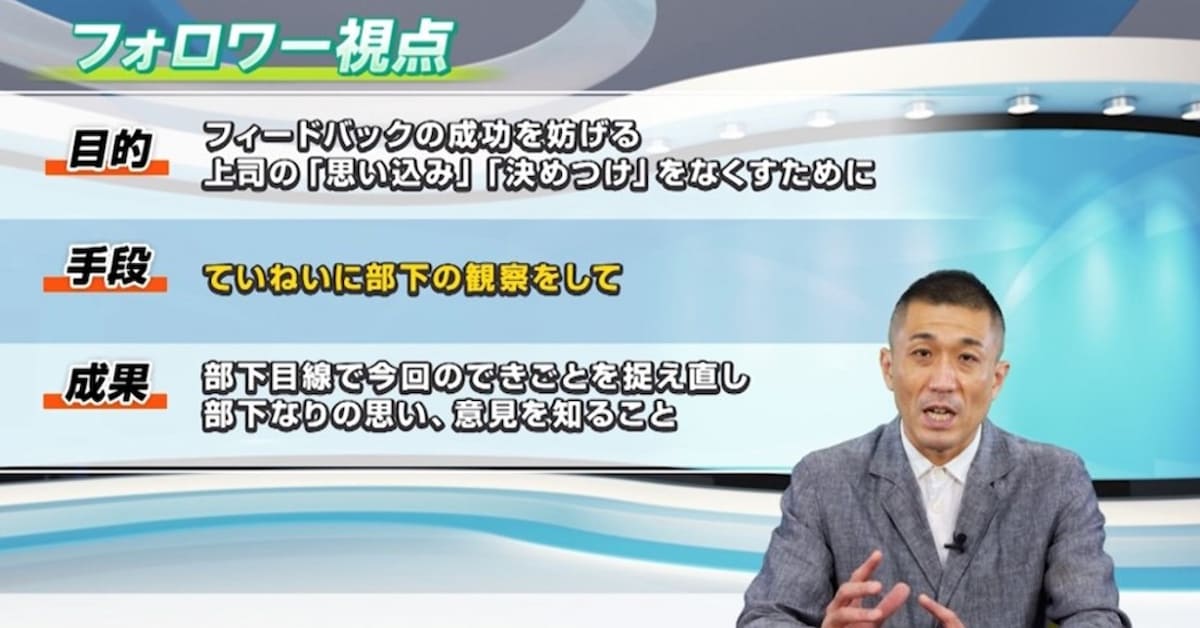

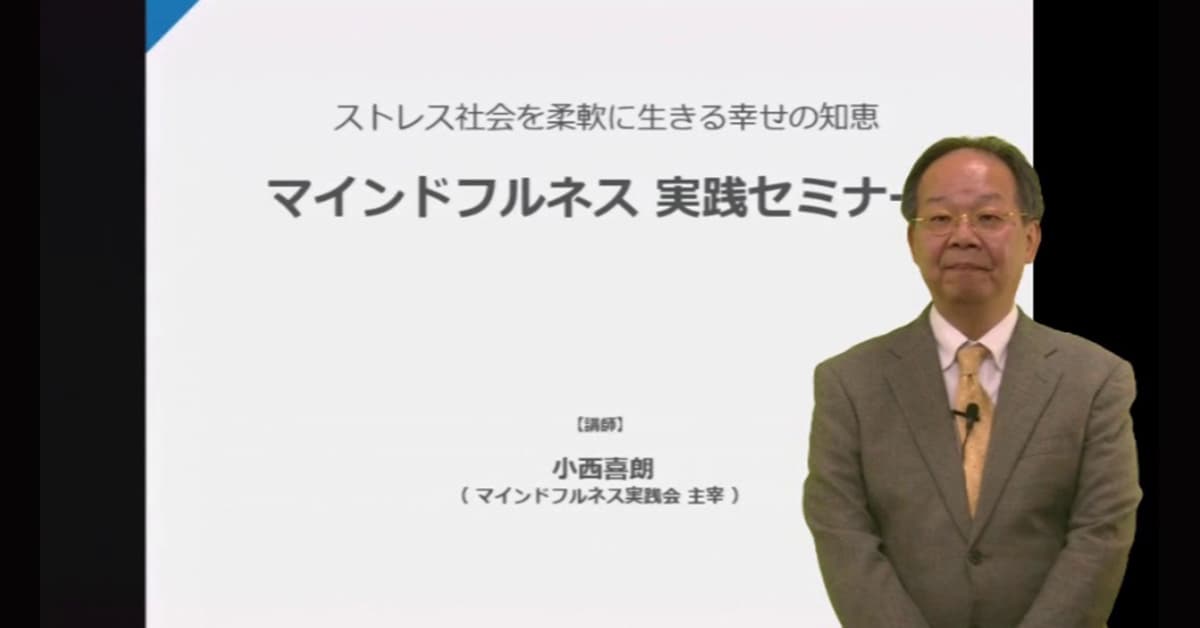

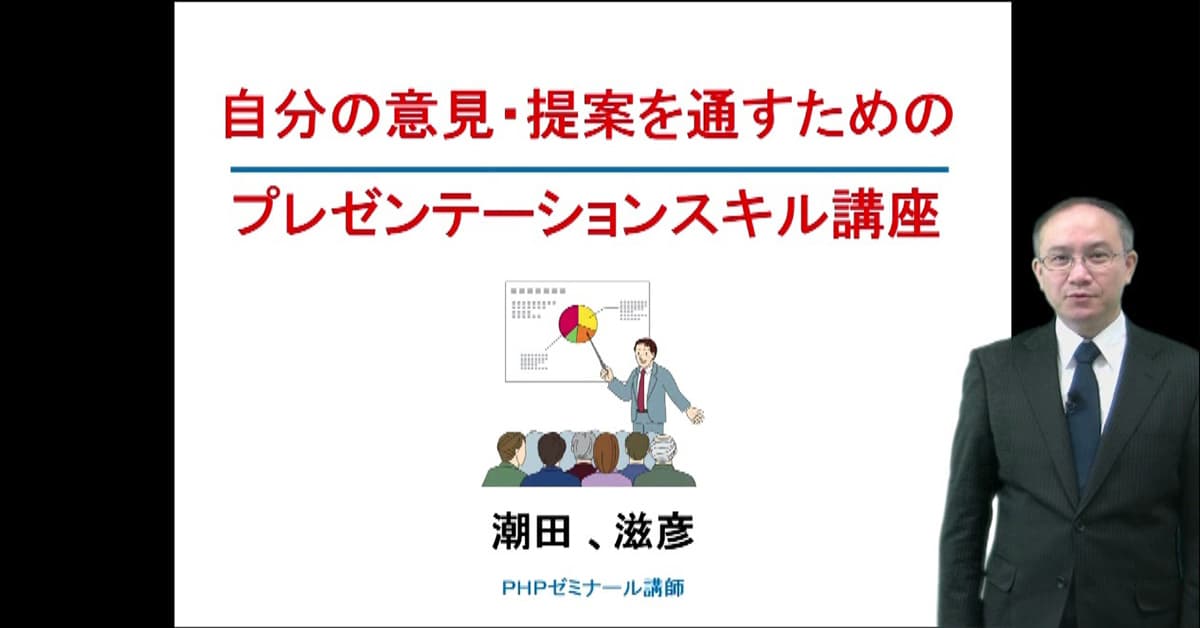
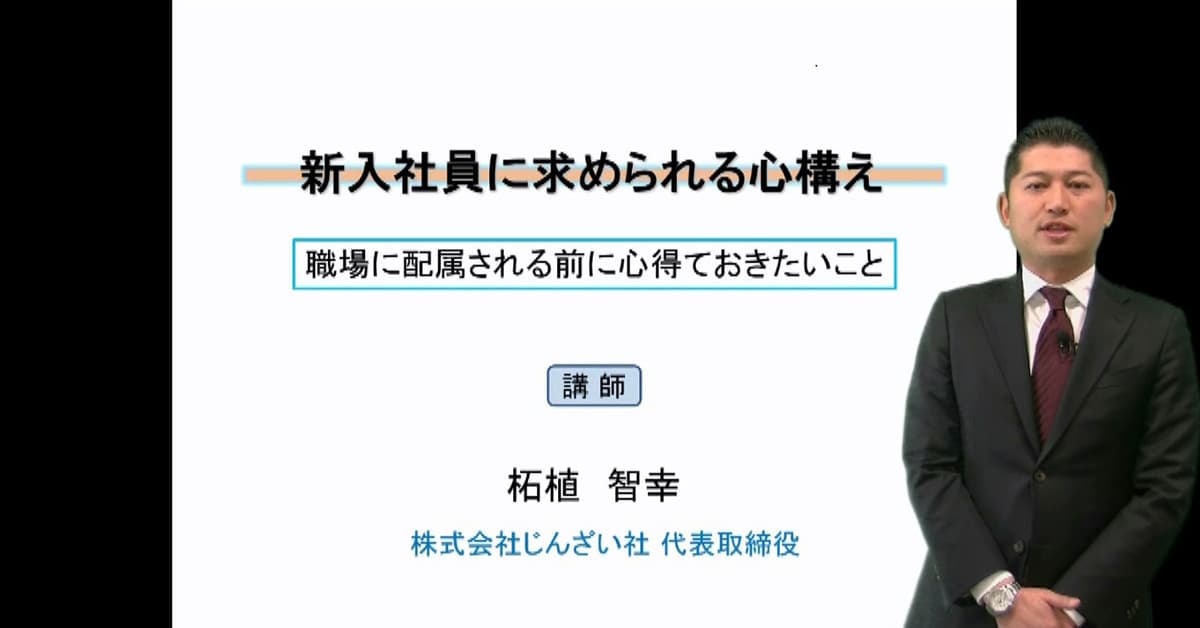
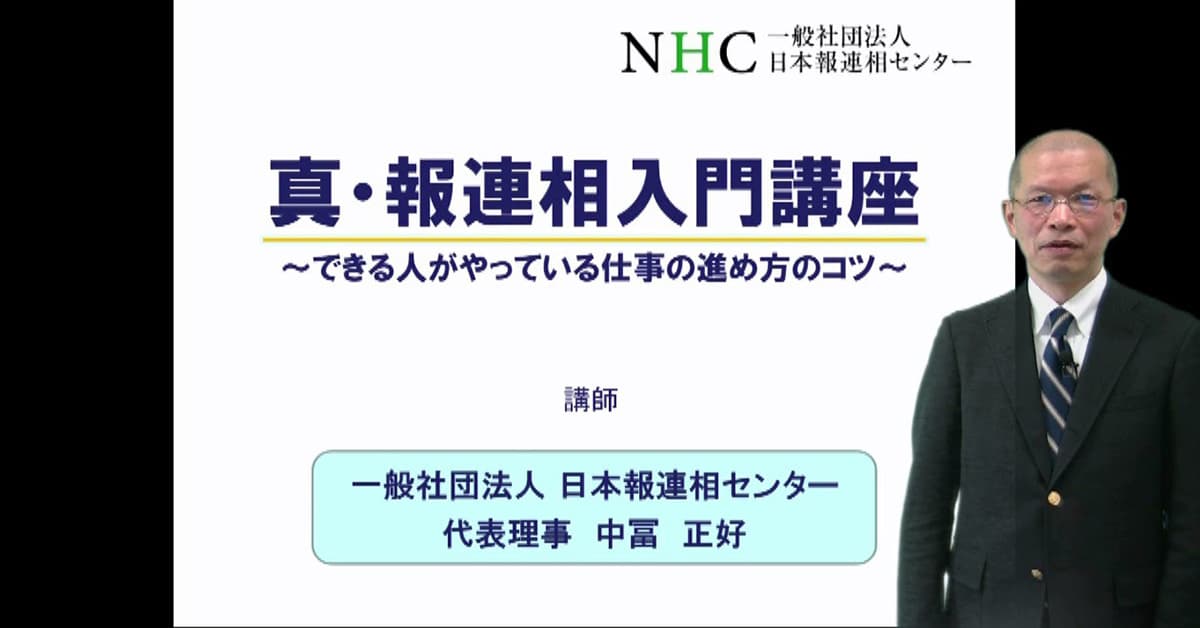
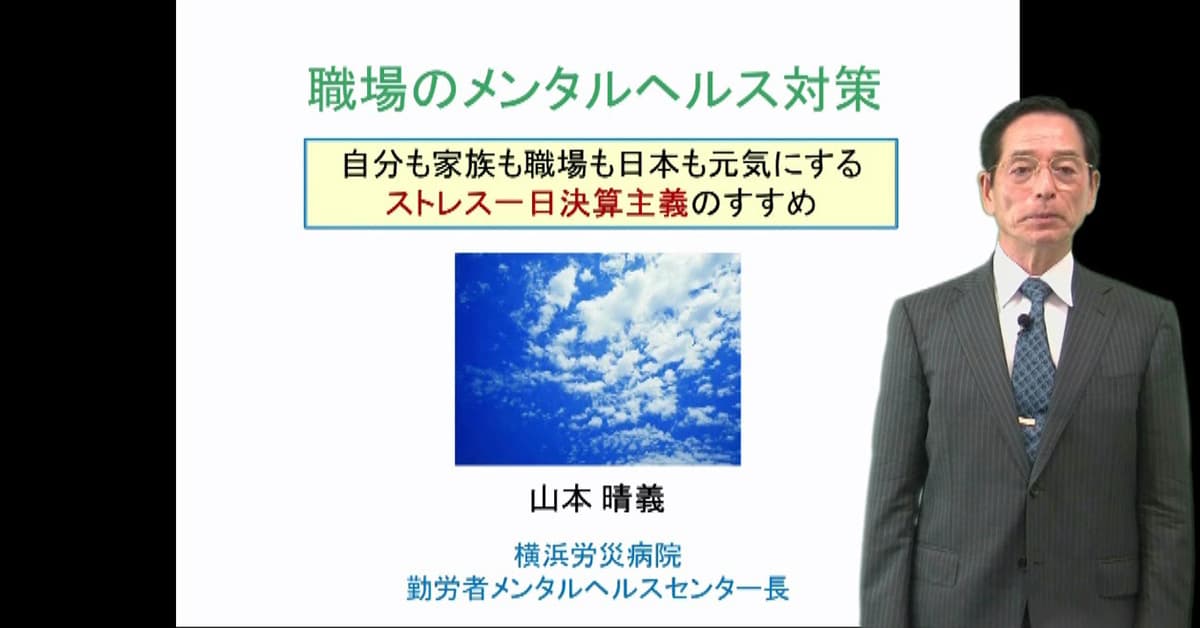
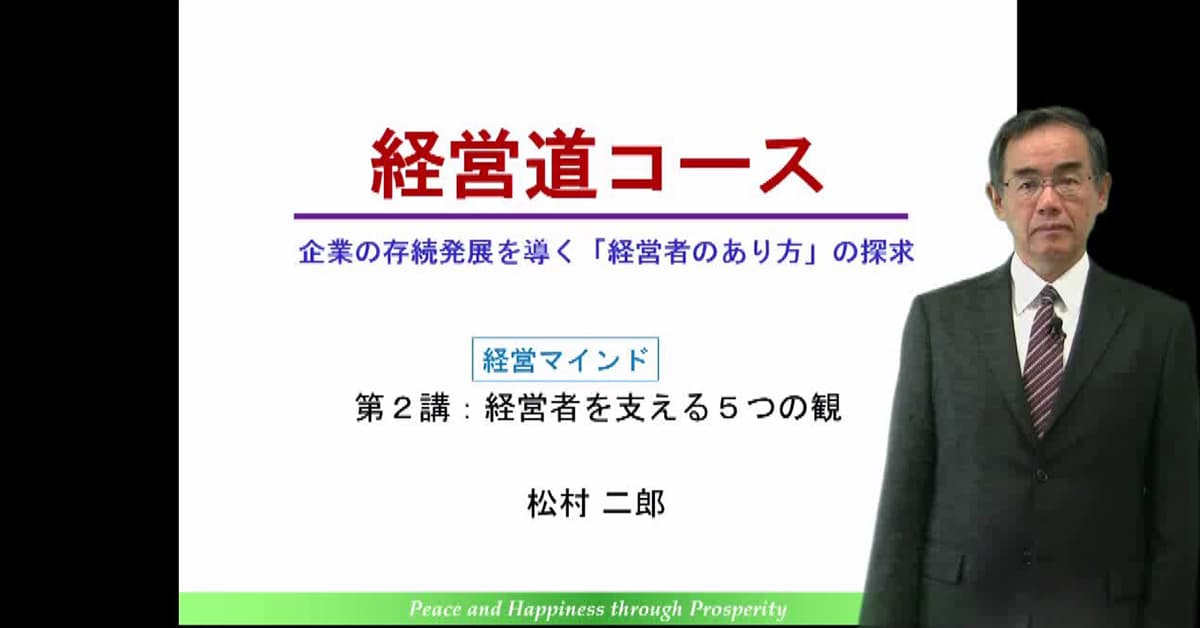
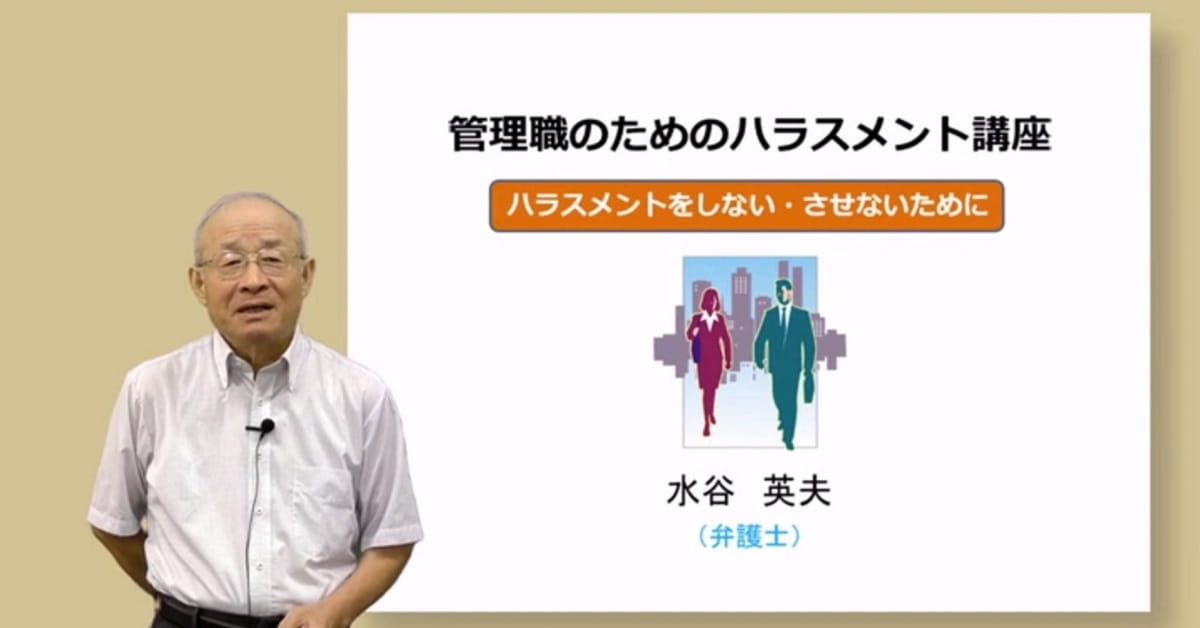

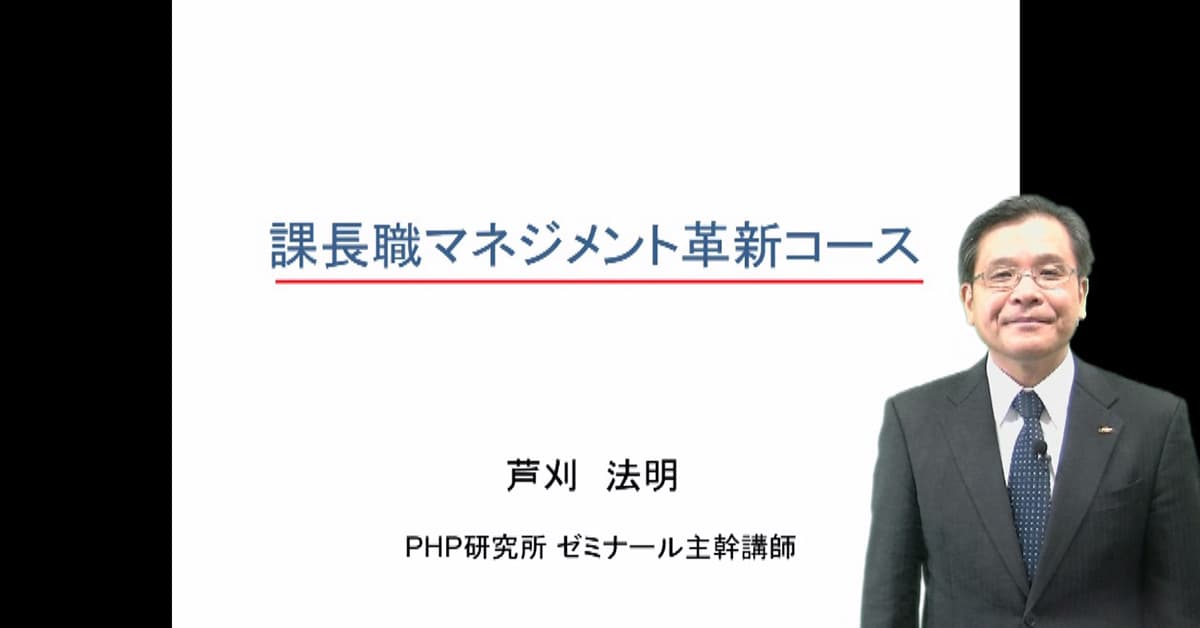



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















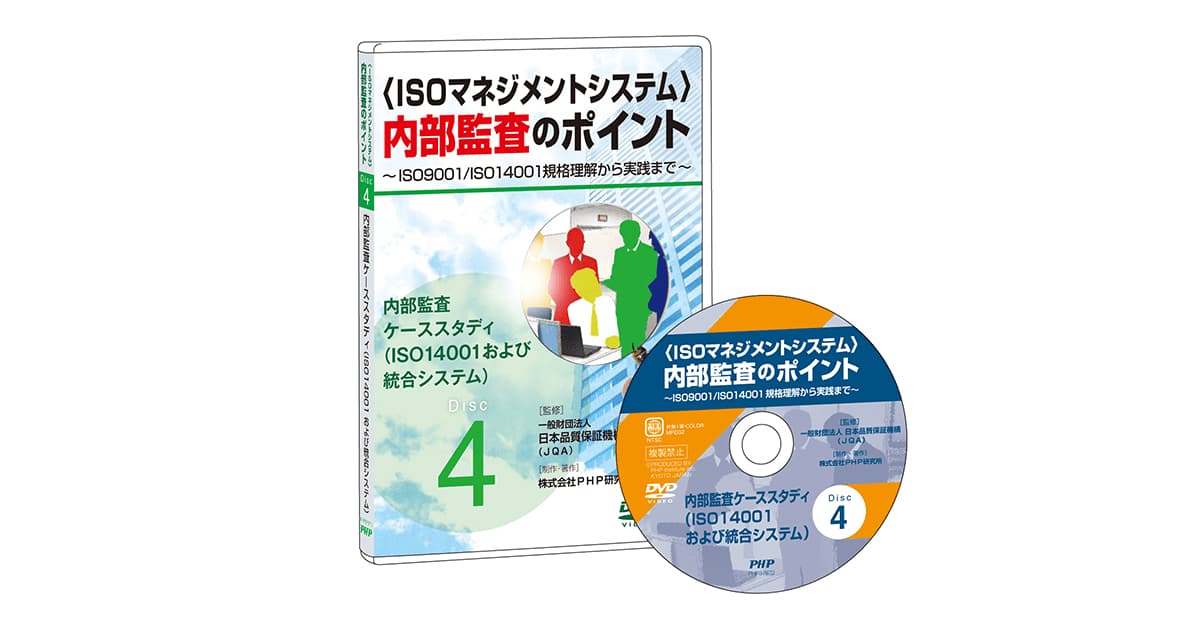





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
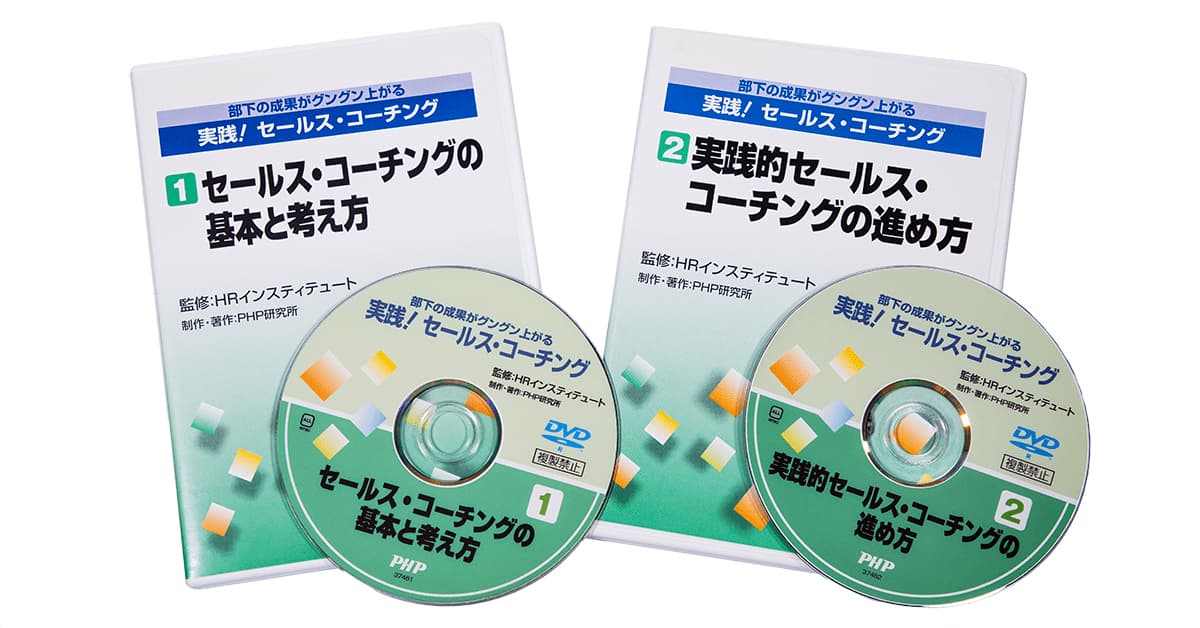




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)