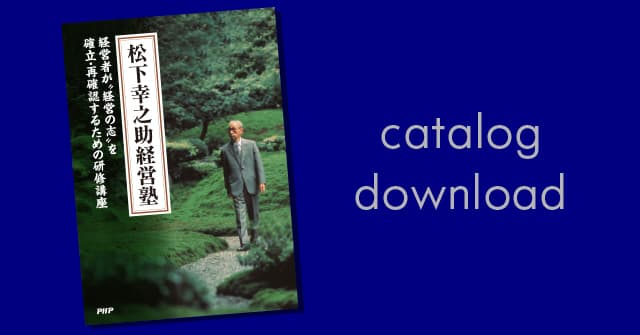中上川彦次郎の決断~大財閥再生のための近代化路線
2019年3月 9日更新

プロ経営者の元祖として繰り返した華麗な転身。大財閥再生をなしとげた中上川彦次郎の転身力・転進力がある中上川彦次郎の決断の背景に迫る。
経営者としての人生を選ぶということ、その決断の重みはどのようなものだろう。自分に組織を率いる才能はあるのか、従業員たちは協力的であろうか。さまざまな不安を抱えながらも自分なりに全うするしかない。
明治中期、日本の資本主義社会が産声を上げる頃、産業界を牽引するはずの巨大財閥でさえ、経営者の不在に苦しみ、もがいていた。そこに、福沢諭吉の甥としてその近代精神を学び、留学経験を持ち、才覚にあふれた男が人生を賭けて改革に乗り出した。三井銀行専務理事となった中上川彦次郎である。教員、官僚を経験後、新聞経営、鉄道経営とより大きな組織へと転身をくり返し、最後は一大財閥を変革した。大きな自負を持って、与えられたチャンスに身を託し、困難な経営者の道を選択した中上川の決断の背景にはどんな信念と思いがあったのだろうか。
福沢諭吉の申し子
歴史に「もしも?」は禁物だが、中上川彦次郎の人生には、もし福沢諭吉の甥に生まれなかったならば、もし井上馨と会っていなかったならば、といった「もしも?」をつい考えたくなる。運命的要素と自らの選択がせめぎ合うような、中上川の人生は四十七年と短いがたいへんドラマチックである。
三井の近代化という中上川の業績は、三井グループにおける貢献にとどまらず、日本の産業化および資本主義の発展において、欠かすことのできない役割を果たした。
中上川は安政元(一八五四)年、大分中津藩士中上川才蔵と婉夫婦の長男として生まれた。婉の四歳違いの弟が福沢諭吉である。そうした縁から、中上川は十五歳のときに上京、慶應義塾に入り、芝にあった福沢邸に身を寄せながら、語学をはじめ、西洋事情に関する知識をみっちりと仕込まれた。わずか二年で卒塾すると、中上川は故郷中津で新設された中津市学校の教員として赴任した。これは福沢の指示によるものだった。
やがて、父の死によって家督を相続した中上川はふたたび上京、慶應義塾の教師になる。ところが、半年あまりで今度は宇和島(愛媛県)の洋学校校長兼英語教師に赴任。一年でその任を終えると、また慶應で教鞭を執り、同時に福沢の求めによって翻訳等、さかんな文筆活動を行なった。福沢の肉親でもあり、かつ優秀であった中上川は、時に福沢の分身であり、片腕であり、そしてまた門下の人材の切り札として役どころが多く、多忙きわまる仕事をしていたのである。昼は教壇に立ち、夜は福沢の指示で、地図の教科書を書き、翻訳に精を出す。ただ、そうした活動に充実を感じつつも、読むことから得る知識にあきたらず、留学を志したのは自然な流れだったのかもしれない。
中上川は福沢にたびたび留学の希望を申し出たが、許可はなかなかおりなかった。福沢にとってもよほど手元に置いておきたい人物に成長したのであろう。しかし、留学をさせないのは中上川の将来を考えると得策ではないと判断したのか、福沢は留学を認め中上川のために骨を折った。
こうして中上川は、明治七(一八七四)年、二十一歳にしてイギリス留学を果たした。ロンドンでの生活は三年に及んだ。
官僚からビジネスマンへ――きらめく才覚の発揮
ロンドンでの中上川は他の留学生とは違った生活を送っていた。ロンドン大学経済学部教授レオン・レビーといった一流の学者の講義に当初は顔を出したが、「レビーの経済学もいいかげんなものだ」と人に語ったほどで、修学に励むよりはイギリス社会の実態、とくに産業について見聞を広めるのに多くの時を費やした。
中上川は日記にこう書いている。
「英人はいったいに怜悧ならず、鈍にして頑ななり。自由思想家なく古風執着し、宗教に迷信し、島人の性を具えて国の繁昌には不釣合なるがごとし」
日本では依然として西洋崇拝の風潮であった。しかし中上川は、実際の大英帝国とイギリス人を目の当たりにして、真の近代化とは何かを、自分の目で見、評価しようとしたのである。
留学も後半になると、日記にこんな気概を吐露している。
「予が今日までの思込にては、生涯政事家となる心得なりし。しかるに......政事家(政治家にあらず)の生涯ほど進退浮沈のはなはだしきものはなし。三日の天下、百日の皇帝、いわゆる水草の生涯なるものなり。臨機応変の才に富む人のほかは、決してこの不安心なる生涯を企つべからず」
中上川のいう政事とはおそらく人の上に立つ仕事をいうのではないだろうか。能力に対する自負と、強い自我が表れているのがわかる。
中上川の帰朝は、明治十(一八七七)年の暮れである。西南戦争はすでに終わり、日本はいよいよ近代化路線に専心できる時機にあった。以後、政事家たるべく中上川の働きどころはめまぐるしく変わっていく。
福沢は中上川を慶應義塾の出版局発行の新聞『民間雑誌』の仕事に据えようとしたが、折しも起こった参議大久保利通暗殺事件の報道姿勢を糾弾され、廃刊に追い込まれてしまった。身上が定まらなくなった中上川を拾ったのは工部卿井上馨であった。井上はかつて経済調査のため外遊していた時期があり、ロンドンで青年中上川と交流を持ったことがあったのである。井上は中上川の才能を非常に高く買っていたのだろう。いきなり秘書に登用する。自らが工部省から外務省に転じるとなると、中上川も同時に異動させ、そこでも当初から少書記官に、二カ月後には公信局長兼条約改正局副長に任命した。二十五歳の青年に対して破格の抜擢であることは言うまでもない。
ところが、政治の浮沈は早くも中上川の人生を変えた。明治十四(一八八一)年の政変は参議の大隈重信を失脚させた政変として知られるが、そのあおりを受けて大隈と福沢の親交から、官に在籍していた多くの福沢門下もまた追放の憂き目を見たのである。中上川もその一人として官を辞した。
官途を閉ざされた中上川だが、すぐに福沢のはじめた新聞事業『時事新報』の社長として活動をはじめた。実業人としての第一歩である。
中上川はマネジメントに何の経験も持たない。しかし、優れた手腕を発揮、『時事新報』の部数を飛躍的に伸ばした。論説主幹であった福沢は、この新聞に、当時さかんに「実業奨励論」を展開していた。そのすぐ傍らで中上川は、実業の見本を示すかのように巧みな経営をしていたのである。中上川の革新的な資質は、今では当たり前のことでも、数多く中上川の発案によるものがあることからもわかる。たとえば、当時まで内勤が一般的であった新聞記者が外で取材をして、自らの見聞のもと、記事を書くようになったのは中上川の指導による。また、読者の投書欄も中上川の企画、新聞広告も中上川が『時事新報』においてはじめたものである。
中上川は、編集を指揮し、会計を管理し、社説を書き、記者の記事を校閲、印刷業務を滞りなく進めた。プロ経営者としての能力をこの時代から充分に発揮していたのである。
山陽鉄道、そして三井入り
そんな中上川がなぜ『時事新報』を去ったのか。それはさらに大きな身の働きどころを求めたからにほかならない。中上川は貿易関係会社への就職を求めたが話がうまく進展しなかった。そんななか、慶應義塾から三菱財閥に入った荘田平五郎から新設の鉄道会社、山陽鉄道会社入りを勧められた。まったくの異分野だったが、中上川は即断した。しかし、社長就任までには紆余曲折があった。新設の公的な企業ということで別人を推す声もあったのである。中上川は自らかつての上司、外務卿の井上馨に後押しを頼んで、その職を射止めた。根回しもまた巧みであった。
山陽鉄道における中上川の業績もきわめて大きなものであった。鉄道先進国イギリスを見た経験も生きたのであろう。国家的事業の見地から、長期的視野に立って敷設を推進した。たとえば、線路は複線を重視した。資金面での問題と、軍事目的を主とすることから単線としていた計画を、大量旅客の時代の到来によって複線化がすぐに必要になるとして変更した。また、線路の勾配は「百分の一」を遵守することにこだわった。鉄道技師たちは、起伏に富む日本の地形を考えれば、「四十分の一」勾配まではやむを得ない、とかみついた。しかし、中上川は、「急勾配こそ不経済であり、開通後に本数がふえればきっと再工事を余儀なくされる」と譲らなかった。これも中上川の決断が正しかった。短期工事を優先して「四十分の一」勾配で設計した九州鉄道ではのちに再工事をしなければならなくなり、大損害を被ったのである。カーブの最大値十五度というのも、安全性の点から中上川が自ら指示した数値である。
中上川はイギリスの鉄道専門書を読破して、技師たちに勝る最新の知識を有していた。先を見越した大胆な用地取得、かつ迅速な敷設の推進。中上川は大いに敏腕を振るった。
しかし、声望が高まるにつれ、その活躍を阻害する者が現れてきた。中上川の見識は正しいものであったが、投資される金額の大きさや用地買収の意義に真っ向から反対する出資者が出はじめたのである。日本初といわれる明治二十三(一八九〇)年の恐慌も経営を圧迫し、中上川には逆風となった。
中上川の人生にふたたび大きな転換期が訪れた。そして、そのとき、中上川の人生を変えたのは、またしても井上馨だった。中上川は上京する。井上の推挙によって、三十七歳にして日本一の財閥たる三井の、さらに中心事業である三井銀行の経営責任者に就任するためである。まさに華麗なる転身であった。
維新以来、井上は三井と深い交流を持ち、その経営に顧問として参画していた。維新に際していち早く新政府側についた三井は、政府の財政資金の調達に貢献し、産業化政策に積極的に協力する一方、数々の特権を手中にして財閥の基礎を築いた。しかし、旧態依然として政商路線から抜け出る努力をしなかったために、政府要人、政治家からの不利な貸付要求を呑み続け、明治十年代後半には不良債権に苦しんでいた。三井一族は、この危急に顧問の井上に全権を委任、改革者たる人物の推挙を託していたのである。
その経緯を白柳秀湖『中上川彦次郎傳』はこう伝えている。
「井上は三井家から改革の事を委任せられて、その實際の衝に當るべき人物を、あれかこれかと物色中、或る日偶然にも汽車のなかで、山陽鐵道會社の社長中上川彦次郎と邂逅した。そのとき井上は、中上川と四方山話の話の末、談たまたま三井家の現状に及び、三井家から一切を擧げてその改革のことを委託せられて居ることを告げ、世間は廣いが、有るやうでないものは人物である。若し君ほどの人物が、二人あるならば、その一人は是非三井家に貰ひうけて、整理の衝に當ってもらひたいがと嗟歎した。(略)中上川は井上の話をきいて、それほどまでに私を知り且つ私を信じて下さるならば、山陽鐵道の方は辭退をして、何時でも貴下の御推薦で三井家の方に參りませうといふことになり、井上も意外の快諾に驚き、且つ喜び、直に中上川を三井家に推薦して、非常の大改革を斷行させることとした」
中上川にとって井上の声は天の声と聞こえたのではないだろうか。
大舞台三井での改革断行
明治二十四(一八九一)年八月、中上川が上京して、新橋の停車場に降り立ったとき、先に三井入りしていた知人が一人いただけで、三井の幹部たちの出迎えの姿はどこにもなかった。いかに井上の推挙があろうとも、また一族や社員たち自らが改革の要を感じながらも、彼らは中上川に対して決して心を開いていなかったのである。とりあえず理事として遇され、銀行業務を覚えたあと翌二十五(一八九二)年に副長に就任(のちに専務理事に職名が変更)、いきなり実質経営の権限を握る。そこからはじまった中上川の改革はだれもが驚くほど大掛かりで、妥協を排し、徹底した信念のもと、実行されていった。
中上川がめざしたのは、真の資本主義原則に基づき、ビジネスとしての合理主義を根づかせることだった。
順に述べると、まず従来の政商路線を完全にあらためた。御用金を取り扱うことで三井は信用を得て成長してきた。その陰で、政府高官との不正な癒着もまた断ち切れなかった。銀行内にはだれが名づけたのか「地獄箱」というものがあった。これは、上は大臣、知事から下は下級官僚までの借用書、領収書の類であった。職権濫用によって三井から金をせびり取った不正融資の記録、無論これらのほとんどは不良債権と化していた。そうした事態になるのは、御用金取り扱いに甘んじているからだ、と中上川は御用金取り扱いを辞退すると発表した。周囲が呆然としているなか、また三井家内部からの猛反対にも屈せず、速やかに不必要な支店を閉じ、事務を整理してしまったのである。
中上川はこう言った。「取付に對して支拂の義務を負ふ預金は、借金と何の異るところがあるか。借金を以て銀行營業の根本政策となすが如きは愚の骨頂である」(同前)。つまり、政府の御用金を預かることは、政府から借金をすることである。三井のごとき金持ちがなぜ借金をする必要があるのか。政治家の鼻息を窺ってわずかな利益を収めるやり方は、本来の三井のやり方ではないというのである。
次なる改革は不良債権の回収である。これにも中上川は容赦なく立ち向かった。なかでも、東本願寺への徹底した督促は、信徒をして仏敵といわしめた。差し押さえに対して、必死で哀訴する東本願寺側。しかし、中上川は「阿弥陀如来の差し押さえをするやも計られざれば」(砂川幸雄『中上川彦次郎の華麗な生涯』)と突っぱねる。やむなく東本願寺は、地方別に目標金額を定め、全国四百万の信徒に募金を呼びかけた。その効果は抜群だった。目標額を大幅に超え、三井銀行への返金はおろか、頓挫していた阿弥陀堂や祖師堂の改修資金さえ調達できたのである。
そのため、東本願寺の執事がわざわざ中上川に礼を述べに来たほどであった。そのとき、中上川が「仏敵中上川は地獄入りと思いたるに意外にも功徳を積みて極楽に入れますかな」と執事に問うと、彼は苦笑して、「必ずこれを請け合います」と言ったという。
さらに中上川は、財閥にとって弱いとされていた鉱工業分野への進出を志し、芝浦製作所、鐘淵紡績、王子製紙などを傘下に収めたほか、慶應義塾から藤山雷太、武藤山治、日比翁助といった有能な人材を登用して革新に富む社風を創り、三井同族を含めた組織改革にも乗り出した。しかし、改革が進むほど、三井内部からの反対の声が大きくなり、中上川は次第に苦境に立たされるようになった。
闘いの果ての死
中上川は三井入りして八年経った明治三十二(一八九九)年秋、腎臓病を発病する。以降、三井財閥のもう一つの大きな事業、三井物産を率いる実力者益田孝との軋轢、さらに自らを三井に導いた井上馨からも排斥の動きが出てきて苦慮する。あまりに中上川の改革が急進にすぎることに業を煮やし、井上は冷酷にも中上川潰しに鞍替えしたのだった。
「政事家、いわゆる水草の生涯なるものなり......」。ロンドンでの遊学時代に記したことを中上川はどう回顧したであろうか。
明治三十四(一九〇一)年十月七日、中上川は二月に亡くなった福沢のあとを追うように腎臓病悪化のため死去する。四十七歳の若さであった。
与えられた舞台に経営者人生を賭けられるかという選択に、中上川はつねに挑戦する決断をした。恵まれた教育環境とそれに応えられた才能、運命の出会い。その運命に潔く挑んだのは、男子の本懐ともいうべき健全な野心と、近代資本主義の浸透という大きな使命感が後押ししていたからではないだろうか。プロ経営者の先鞭として中上川の存在を忘れてはならないだろう。
渡邊 祐介(わたなべ・ゆうすけ)
PHP理念経営研究センター 代表
1986年、(株)PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。修士(経済学)。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学、経営理念の確立・浸透についての研究を進めている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『決断力の研究』『松下幸之助物語』(ともにPHP研究所)等がある。また企業家研究フォーラム幹事、立命館大学ビジネススクール非常勤講師を務めている。










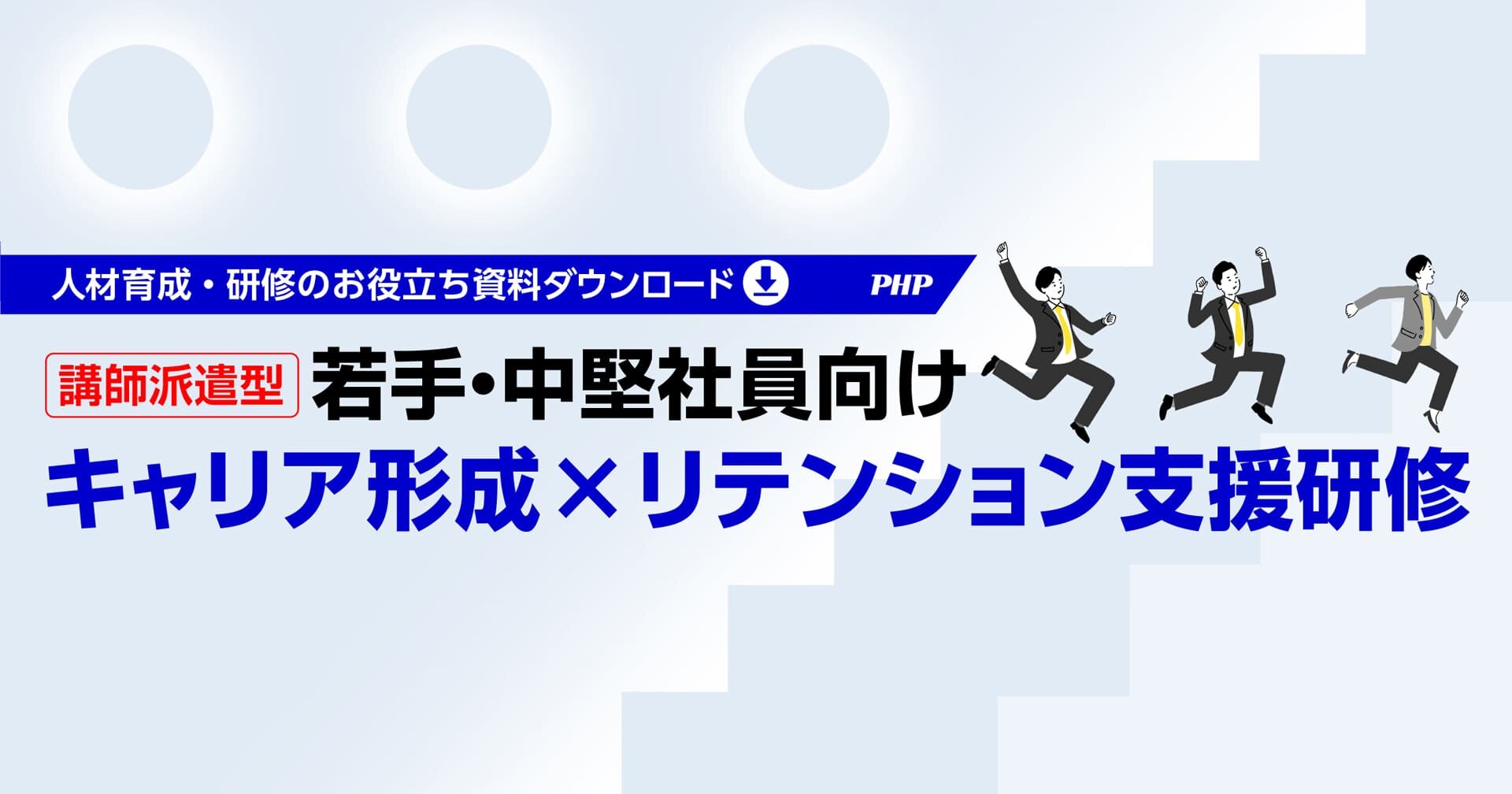















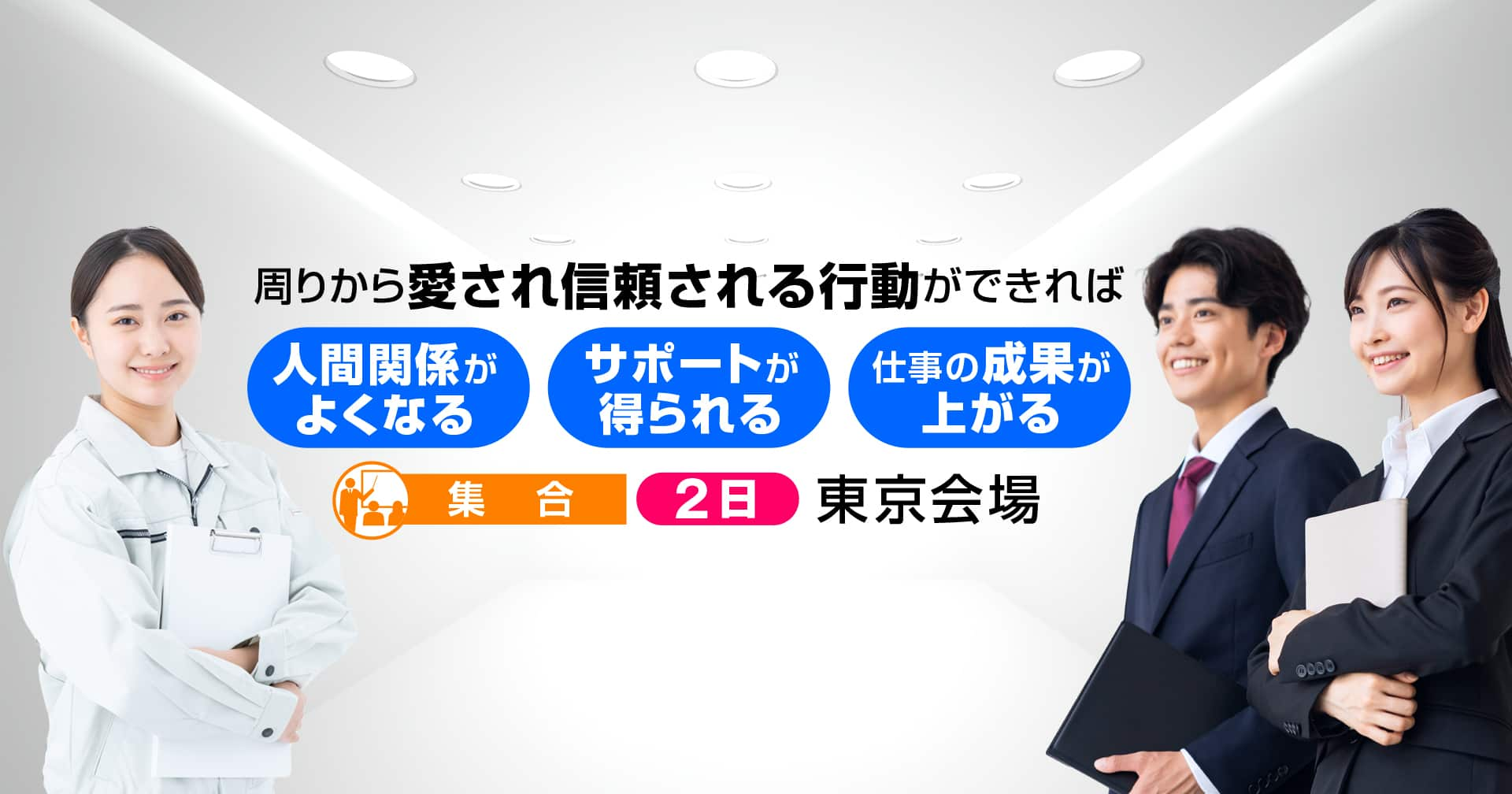










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







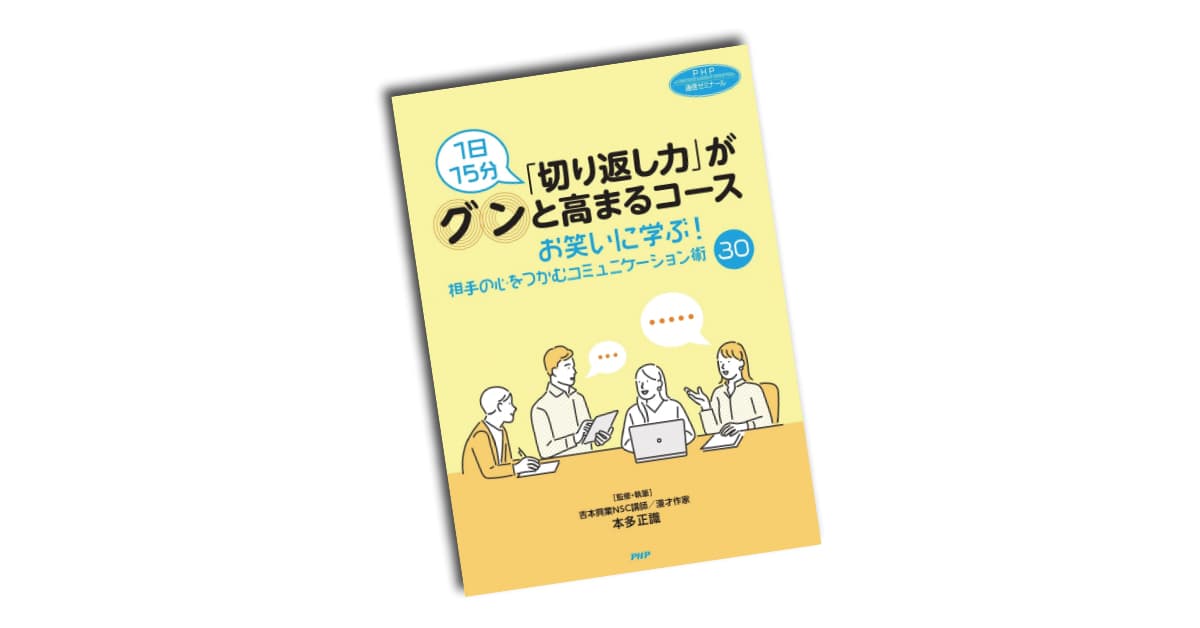






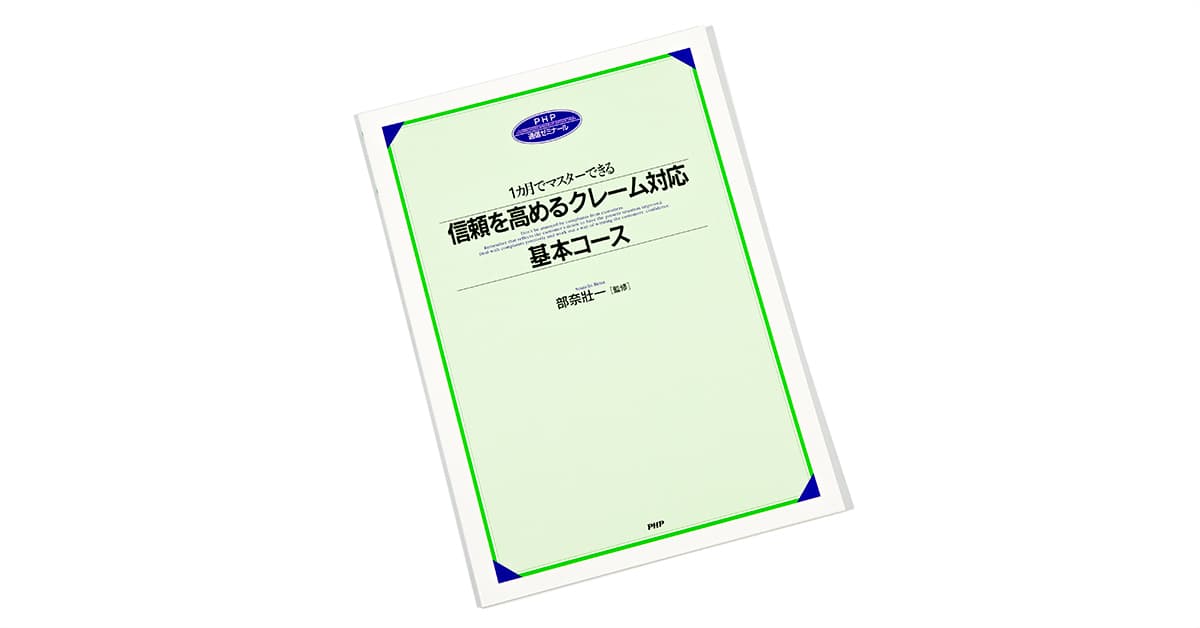





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

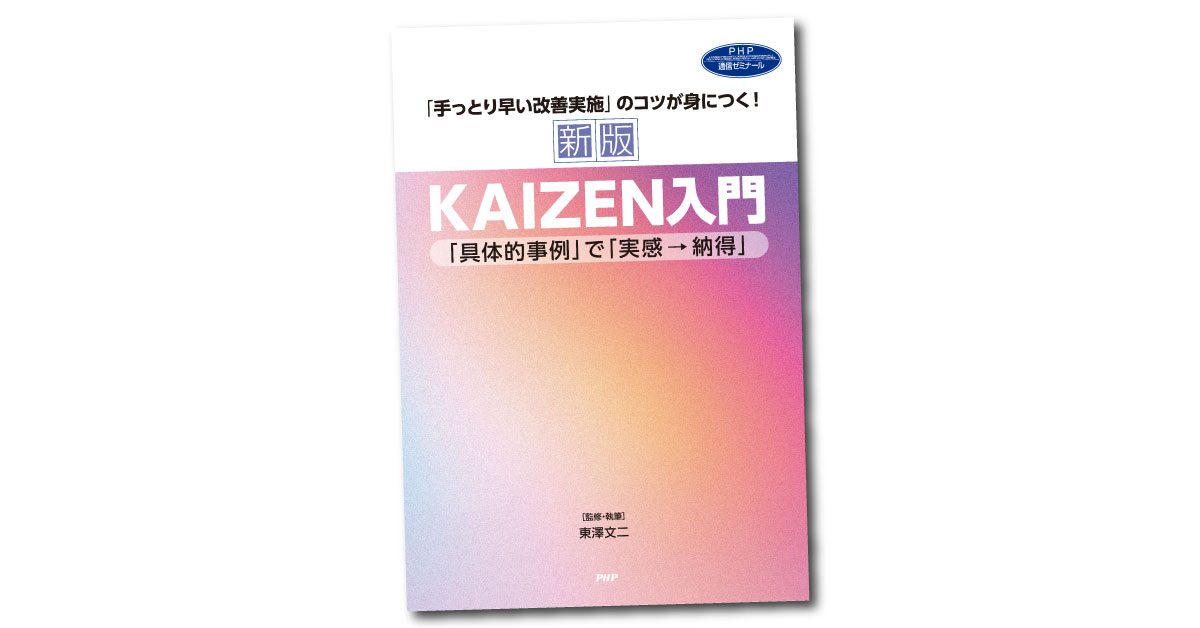










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)


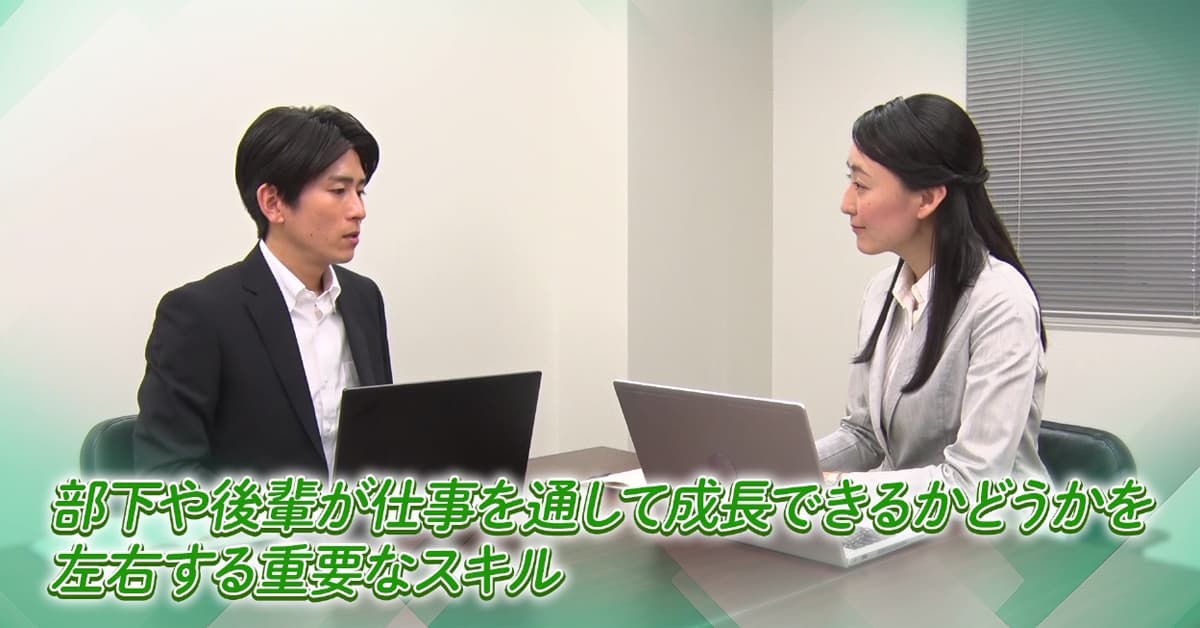
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
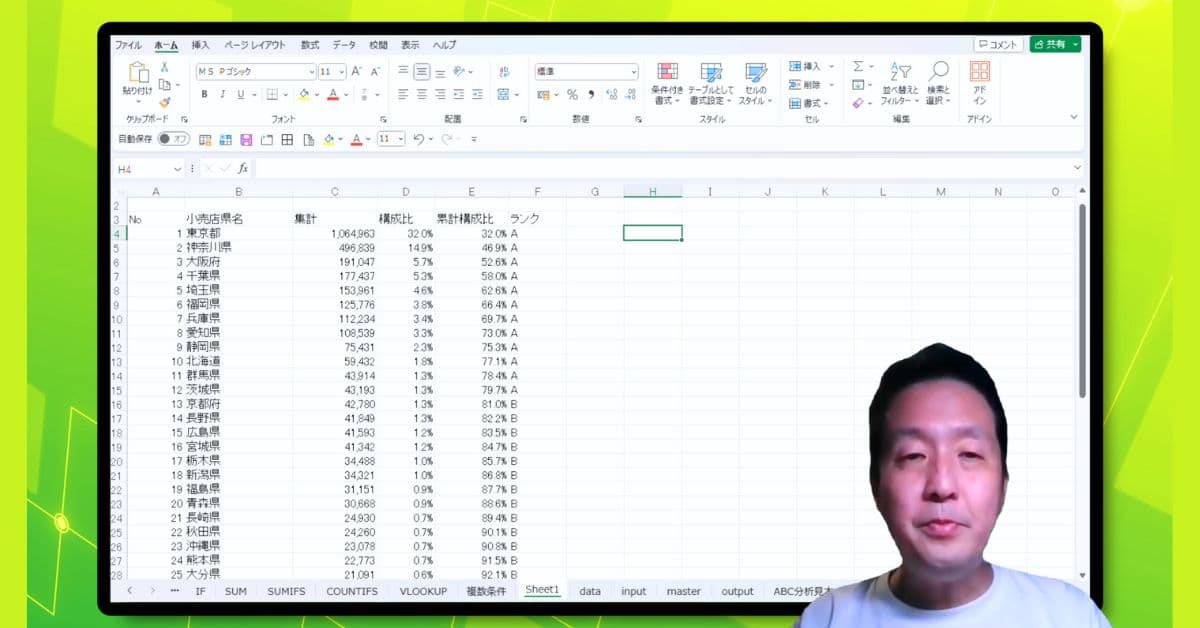
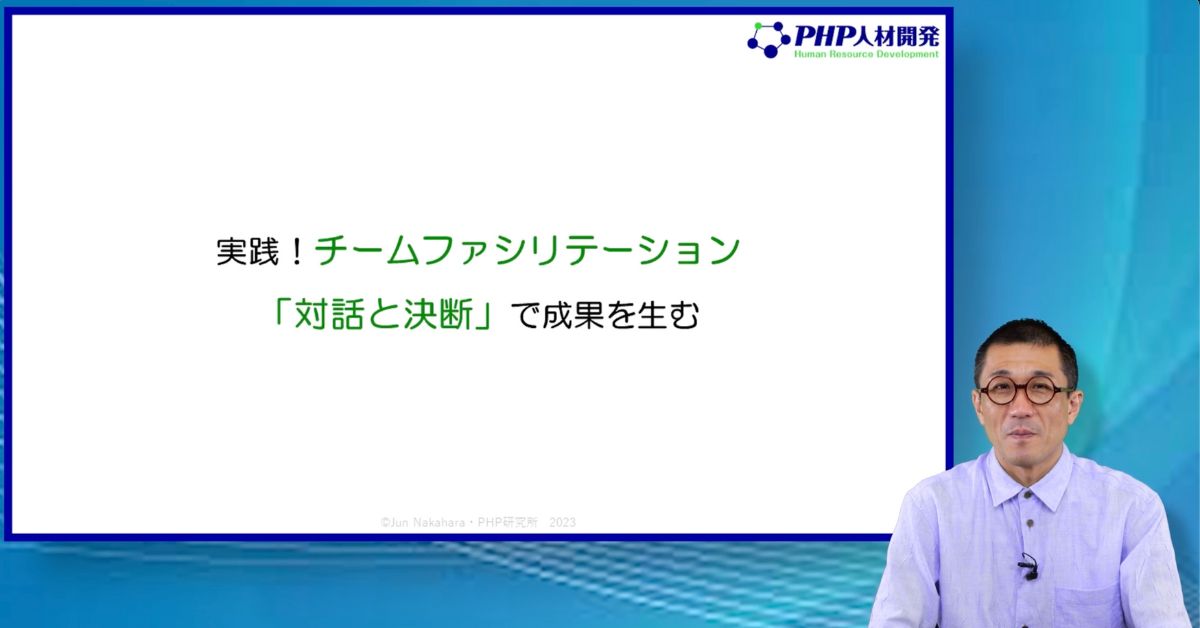
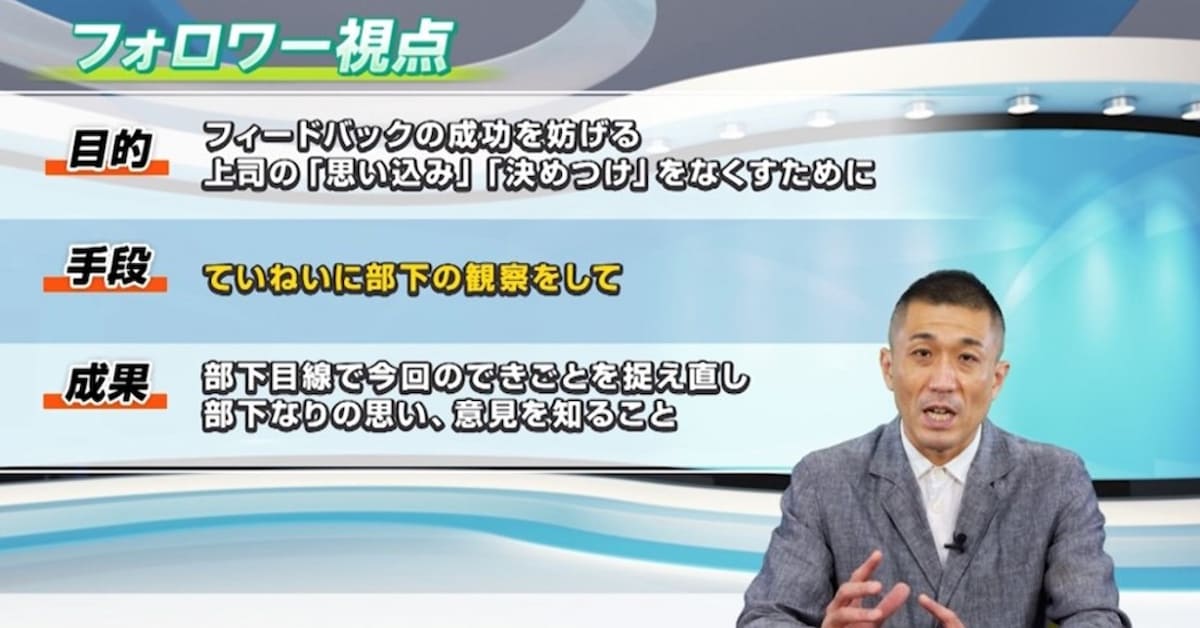

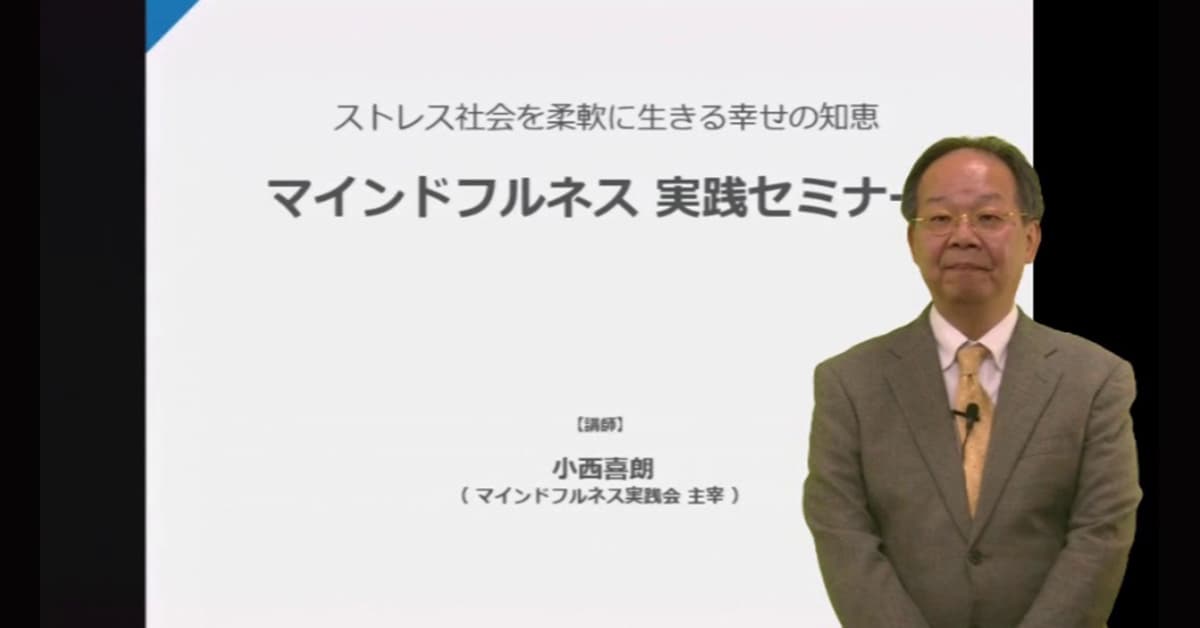

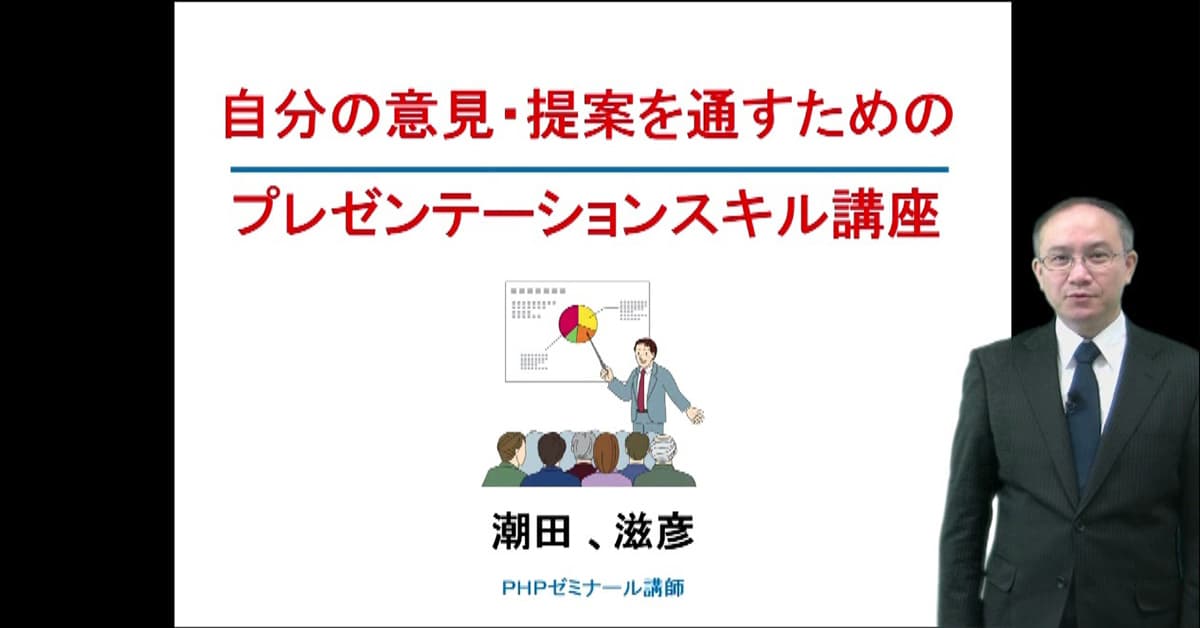
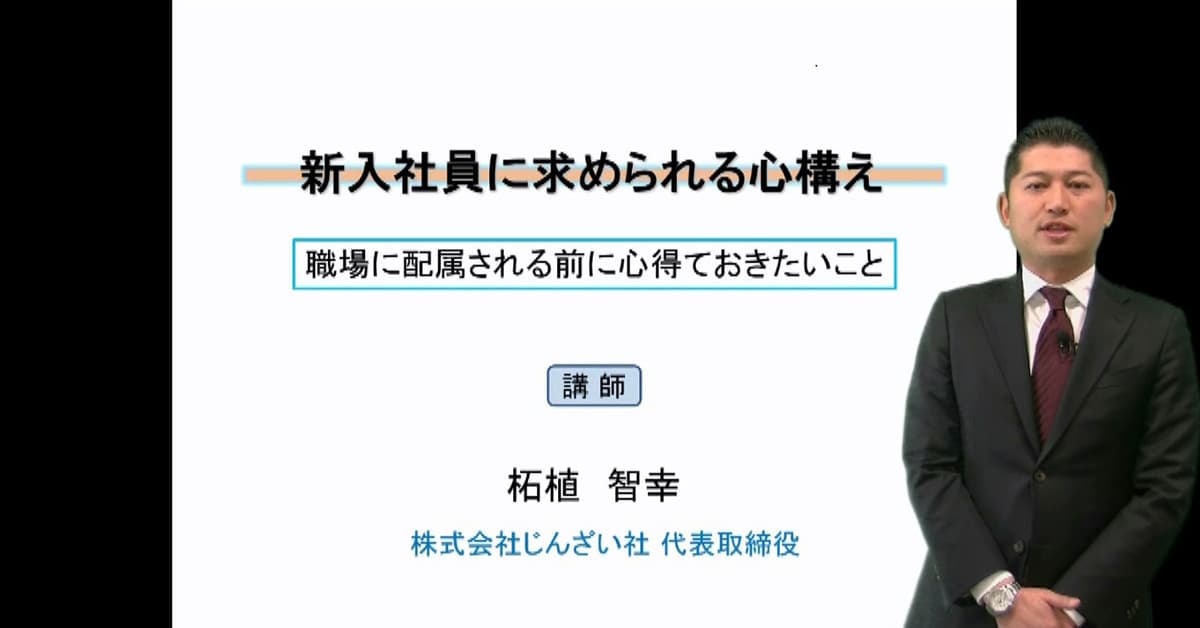
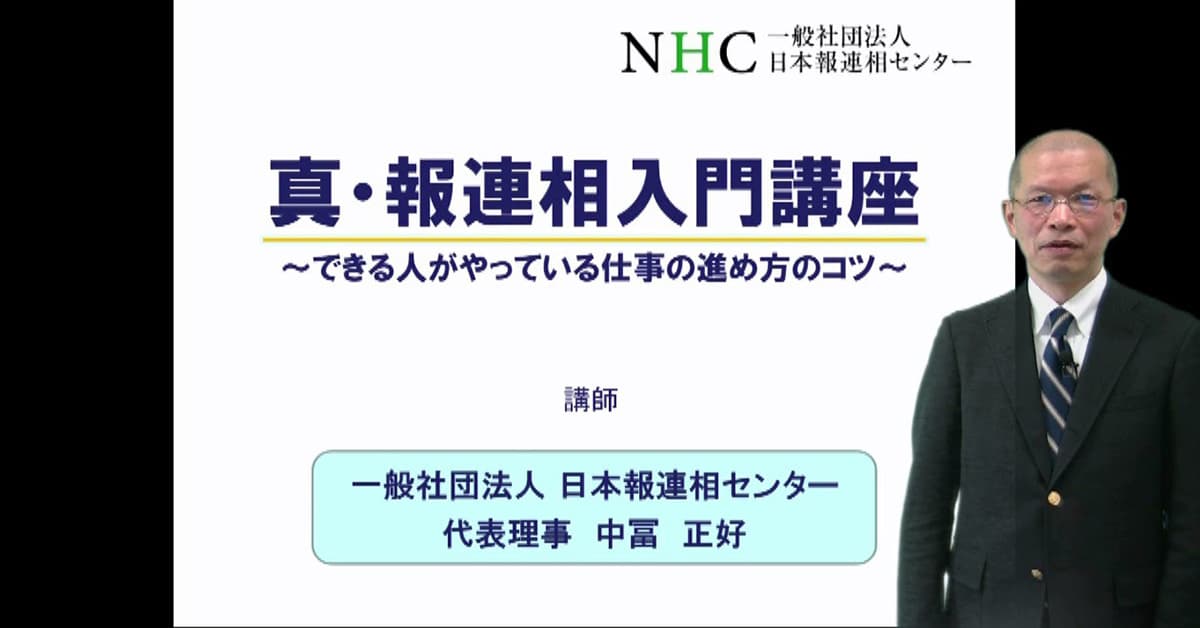
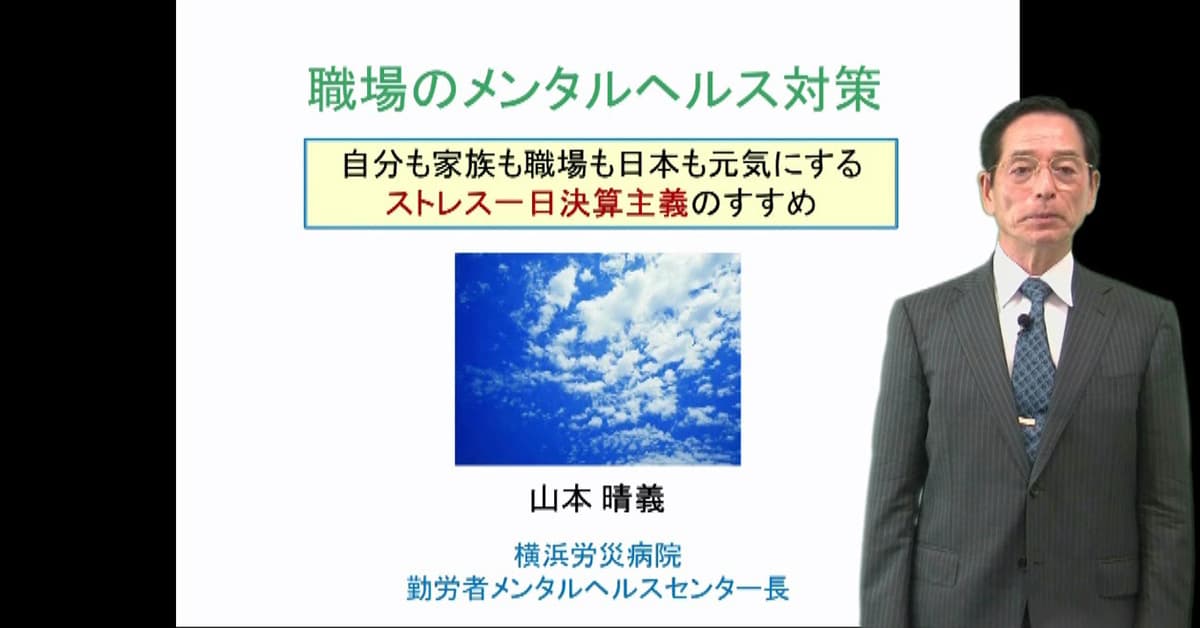
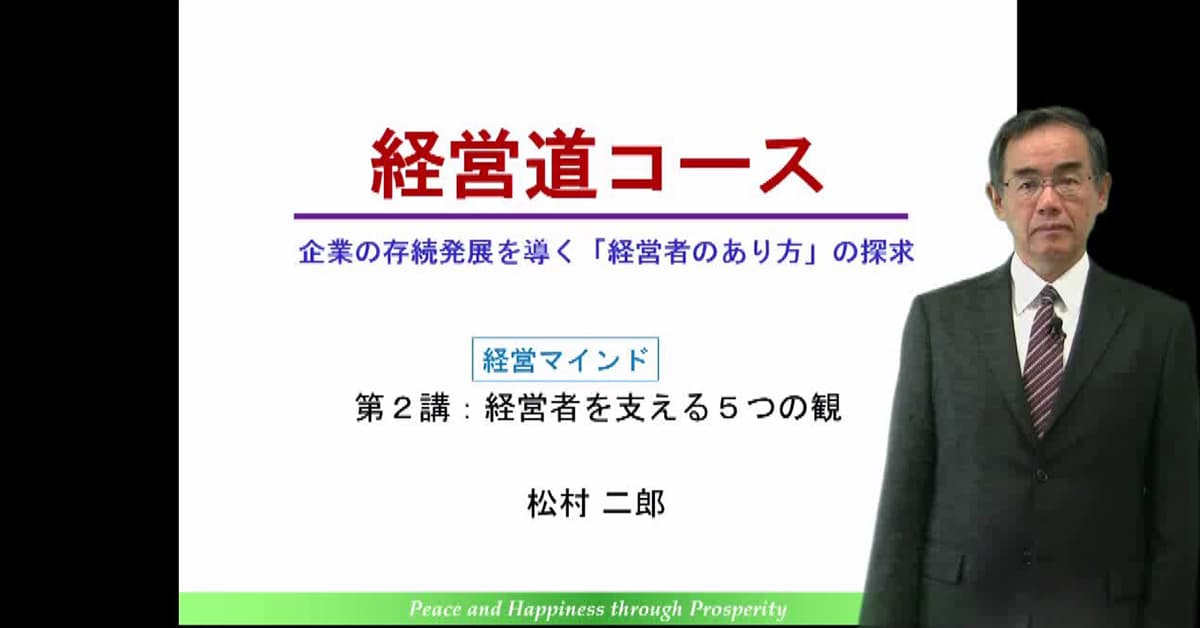
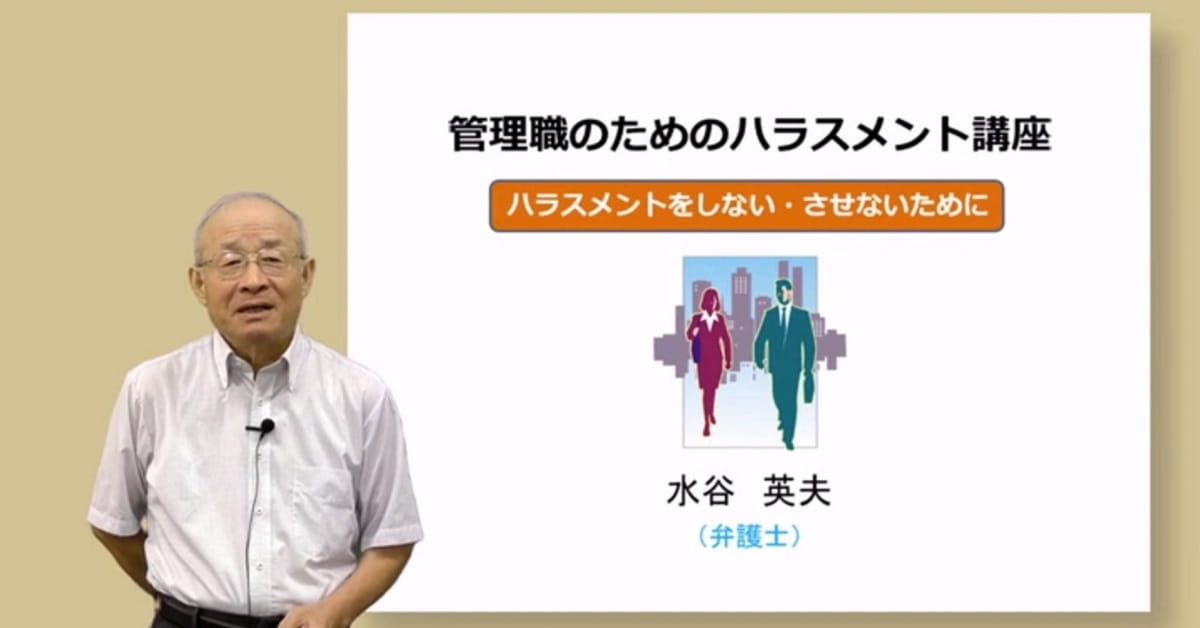

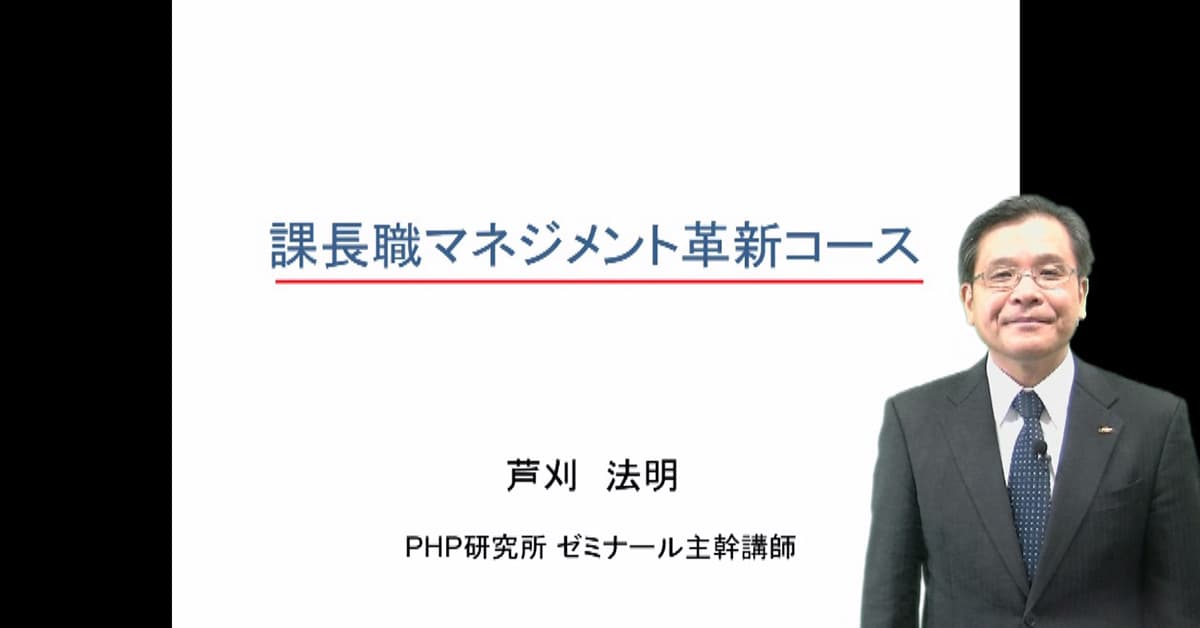



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















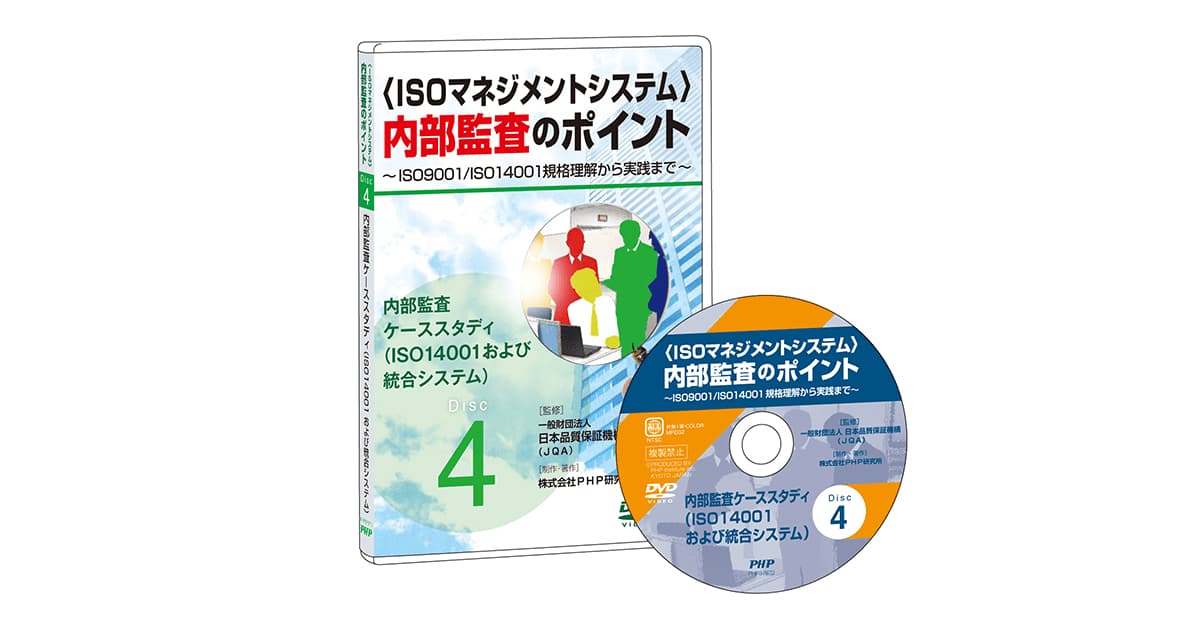





![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
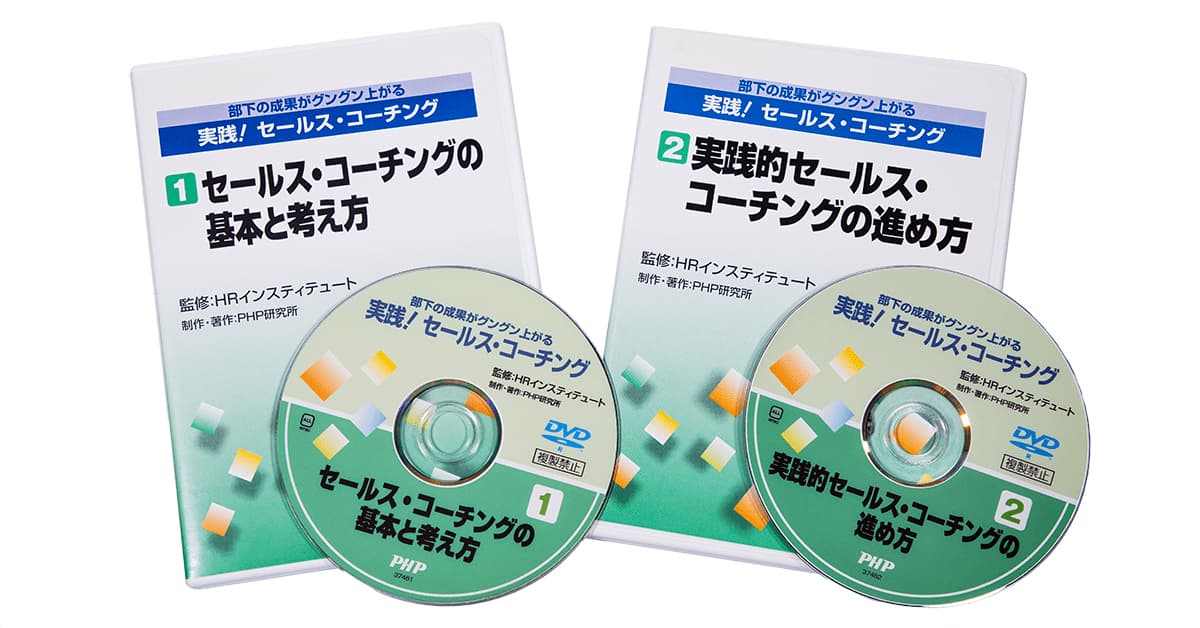




![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)