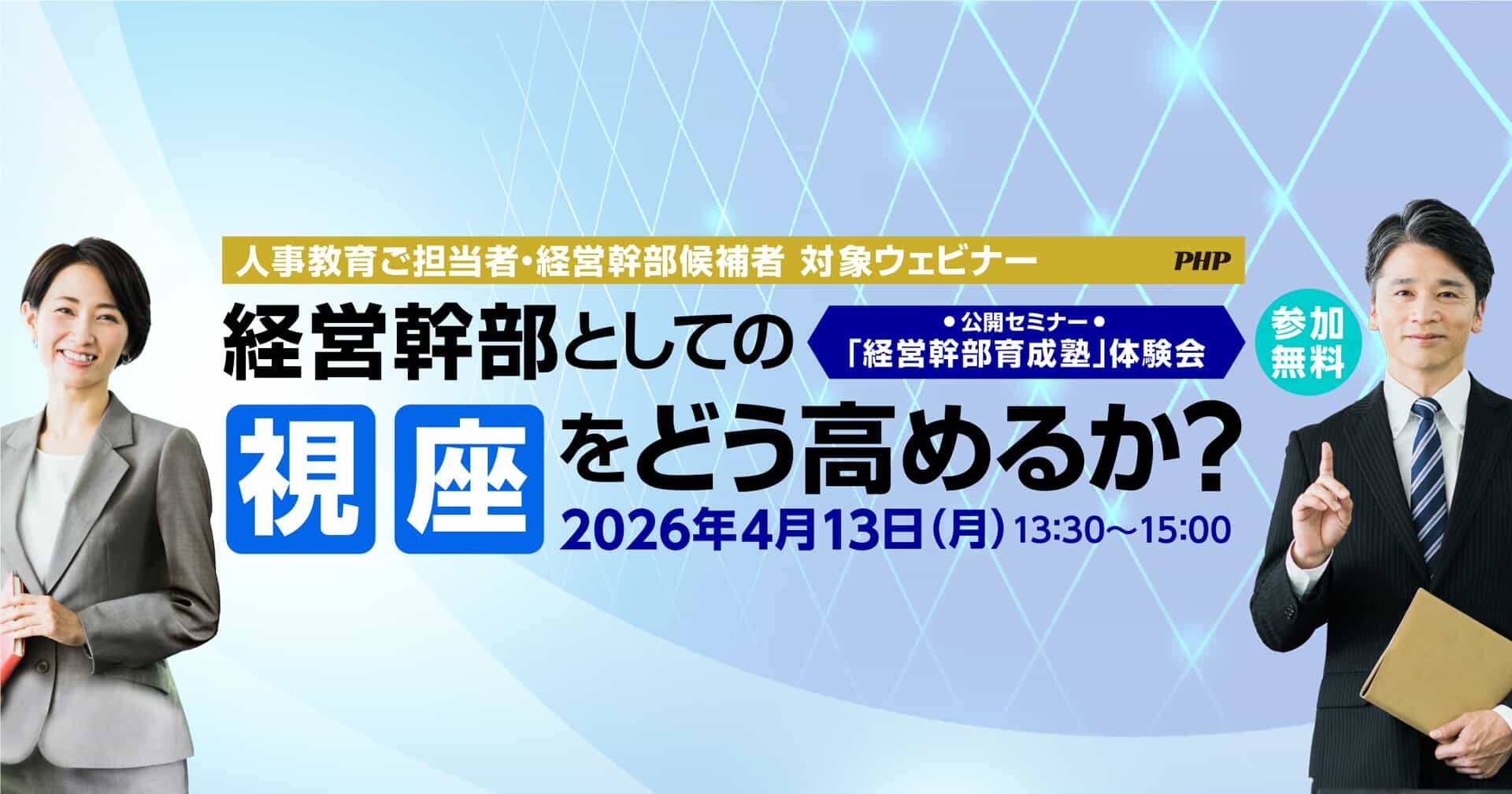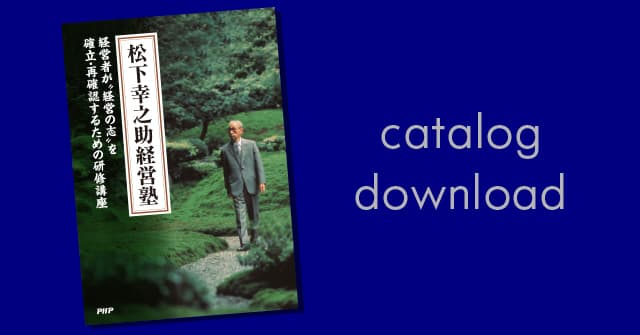「個を活かす人事」とは? 元リクルート・SPI開発者が説く心理学的経営
2019年6月21日更新

人間をあるがままにとらえる「個性化」と「活性化」のマネジメントとは? 元リクルート専務、SPI開発者の名著復刊!
26年前に刊行された人材経営論『心理学的経営』は、江副浩正氏のもと、リクルートで活躍し、主に人事測定事業と組織活性化事業を手がけた大沢武志氏(故人)の実務と研究に基づく経営論です。
大沢氏は、現在、企業の採用選考で広く利用されている適性検査「SPI」の開発をした人物としても著名です。
このたび、PHP研究所では、本書をプリントオンデマンドで復刊。あわせて電子書籍としてリリースしました。発売後、多くの経営者、人事部門の責任者からご注文が相次ぎ、大きな反響を得ています。
ここでは本書より、その一部を抜粋してご紹介します。
使用価値と存在価値
企業人としての適合性あるいは適格性をとらえようとするとき、その評価の次元を基本的には2つに集約して考えることができる。すなわち、1つが仕事に対する適性あるいは能力、すなわち課題遂行、問題解決の能力であり、もう1つが、対人的な適応能力、人間関係能力である。
つまり、仕事ができて、職場のなかで他人とうまくやっていけるという2つの能力を備えた人であれば、社員としては適格ということになる。いずれの側面が欠けても社員として十分な評価を受けられなくなる。対仕事、対人間という2つの次元は、あらゆる階層にあてはまる普遍性があり、管理職になれば、対仕事についていえば問題形成能力が求められるようになり、対人間についていえば、当然、リーダーシップが要求されるようになる。
山田雄一教授は、何ができるかという側面を「使用価値」、どういう影響力をかもし出すかという側面を「存在価値」と表現して、企業人評価の2つの次元をまとめて論じている。そして、この2つの軸を組み合わせると、いずれも評価の高いグループの人を「できる奴」、使用価値は高く、存在価値に難点のある人を「一匹狼」、存在価値は高いが使用価値が不十分な人を「いい奴」、いずれも物足りない人を「ダメな奴」という人材の四つのタイプへの分類が可能になるという。
旧来の企業経営においては、もっぱら使用価値のみが問題になり、したがって適性論も仕事に対する能力的な適性という側面からのみのアプローチが中心であった。仕事に対する能力的適性に基本的かつ広汎に関連をもつ知能を一般適性と呼んでいたことがこのあたりの事情を如実に表わしている。企業で問題となるのはあくまでも企業人としての、つまり、仕事に対する能力という観点からの評価であり、人間的な価値はまた別物という議論は、使用価値中心の時代には全くその通りと言ってよかった。
しかし、適性論としても、対人的な適応性が当然問題にされるばかりか、社員一人ひとりの個性に眼を向け、人間としてどこまで尊重できるかを経営の命題とする人材経営の時代といわれる今日にあっては、存在価値という観点からの発想が重要な意味を帯びてきたのである。
職務適応、職場適応、自己適応
筆者は、企業人適性の3側面を、職務適応、職場適応、自己適応という企業人の適応行動の3つの場面との関連においてとらえる考え方を提唱してきた。
職務適応は、仕事に対する能力によって左右される側面が大であるから、能力的適性の概念に対応する。したがって、人材の使用価値という側面につながる。
職場適応は、対人的能力、対人的適応性に関連が強いが、この適応に関連する要因は、性格特性が大きなウェイトを占める。そして職場の人間関係的風土にどんな影響をもたらすかという意味で、人材の存在価値という側面とのかかわりが強くなる。
さて、3番目の自己適応という概念が、経営的な観点から適性論に1つの転換を迫る意味合いをもっている。つまり、能力中心の適性の考え方から一歩前進して、対人的な適応の要素を取り入れ、性格的な適性が論じられるようになることで、企業人評価の2大次元、対仕事と対人間という軸が定着した。
組織の側からみれば、この2つの側面をおさえれば十分のはずであったが、個人の側に立って、果たして本人が内的な価値基準や情緒的な適応、さらには、自己本来の価値の実現という点で、どの程度満たされ、自らに適応しているか、という個人の主体的適合性の側面が、この自己適応の概念である。
職業心理学者のスーパー(D. Super)は、これを自我概念の実現と呼んで職業生活への適応の最高次に位置づけたが、いかに第三者的に恵まれている状況であっても、内的な価値の次元は、本人自信が自ら決めることである。
しかし、物質的には豊かな時代になり、個々人が自らの興味や好み、夢や希望を屈託なく主張し、多様な価値観を組織のなかに持ち込むことが許される今日、果たして、自己適応という観点からの人事がどこまで可能なのだろうか。いや、そういう個人の側からみた選択の許容範囲が大きい時代だからこそ、個人への配慮のもつ意味が大きくなっているのだろう。
企業からみれば、これは、企業目標と個人目標、そして組織文化と個人のアイデンティティ、この2つの統合への努力というテーマである。具体的には、配置や異動における自己申告制度、勤務地を選択できる制度、キャリア選択の多様な可能性を考慮した複線型の昇進人事制度などが、「自己適応」への配慮のあらわれたものとみることができる。
個と組織の融合
こうして適性論を企業人と組織との関係という観点でみてくると、社会が経済的に豊かになるにつれ、人々の組織に対する呪縛のような隷属的関係は影をひそめ、労働の質も相当に変容しつつあるように思われる。特に若い世代の間に脱組織あるいは脱管理という現象がみられるように、個人の組織からの自立という傾向が強まる一方で、逆に個人が積極的に組織にコミットし自らのアイデンティティの確立を求めるような組織と個人の関係がより緊密化するという新しい傾向を見逃すべきではないと思う。
自律化志向を強める個人を柔らかい構造に変身した組織が包み込み、統合するという新しい組織の姿は、アージリス(C. Argyris)の描いた究極の組織像に近いかもしれない。適性論も、知能や身体的機能などの人間の性能と職務要件との適合性といういわば機械論的なアプローチから抜け出し、情意的要素も視野に入れたトータルに機能する人間に迫ることが必要であろう。
企業組織に可能な限り人間的配慮を取り入れることを志向する心理学的経営の考え方からすれば、個と組織の融合というテーマは、より個人の側からの視点が優先されることになろう。それは適性に「自己適応」の観点が不可欠なものとなっていることにも表われている。
※本稿は、大沢武志著『心理学的経営~個をあるがままに生かす』より、その一部を抜粋編集したものです。
※本書はプリントオンデマンドで復刊したものです。書店では販売しておりません。
大沢武志著『心理学的経営 個をあるがままに生かす』
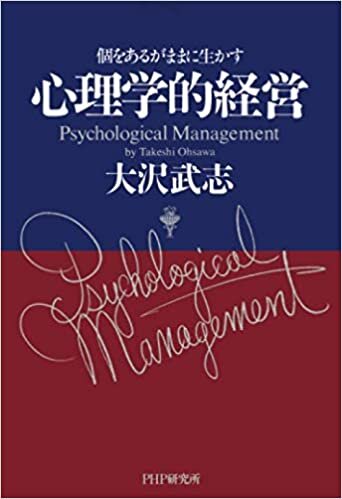
私の考える心理学的経営とは、いわば経営リアリズムであって、まず、人間を人間としてあるがままにとらえるという現実認識が出発点なのである(序章より)。人間をあるがままにとらえる「個性化」と「活性化」のマネジメントとは。 江副浩正氏のもと、リクルートで30年にわたり組織における人間の「感情」や「個性」を深く追求した著者の、実務と研究に基づく全く新しい経営論。










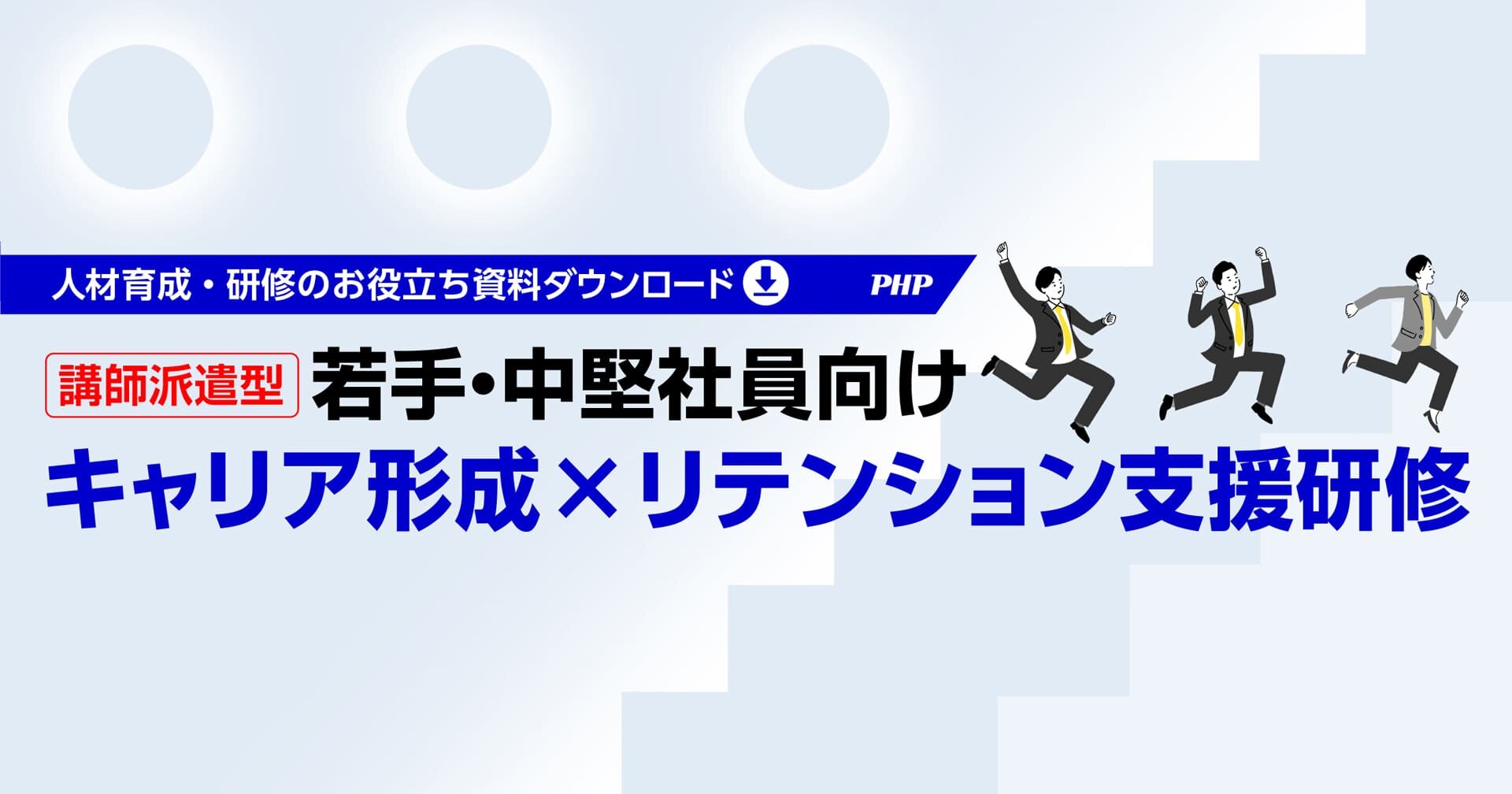





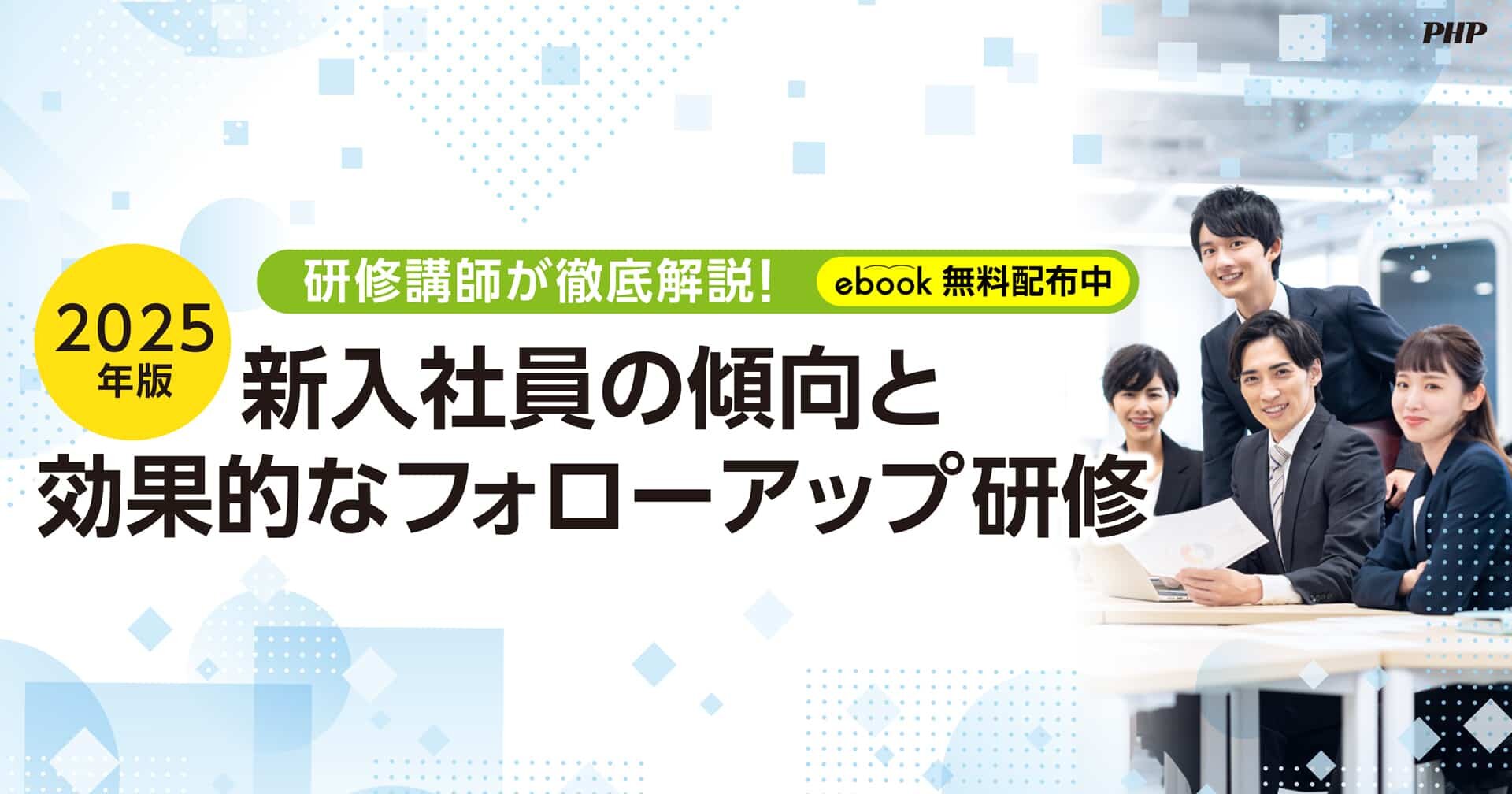









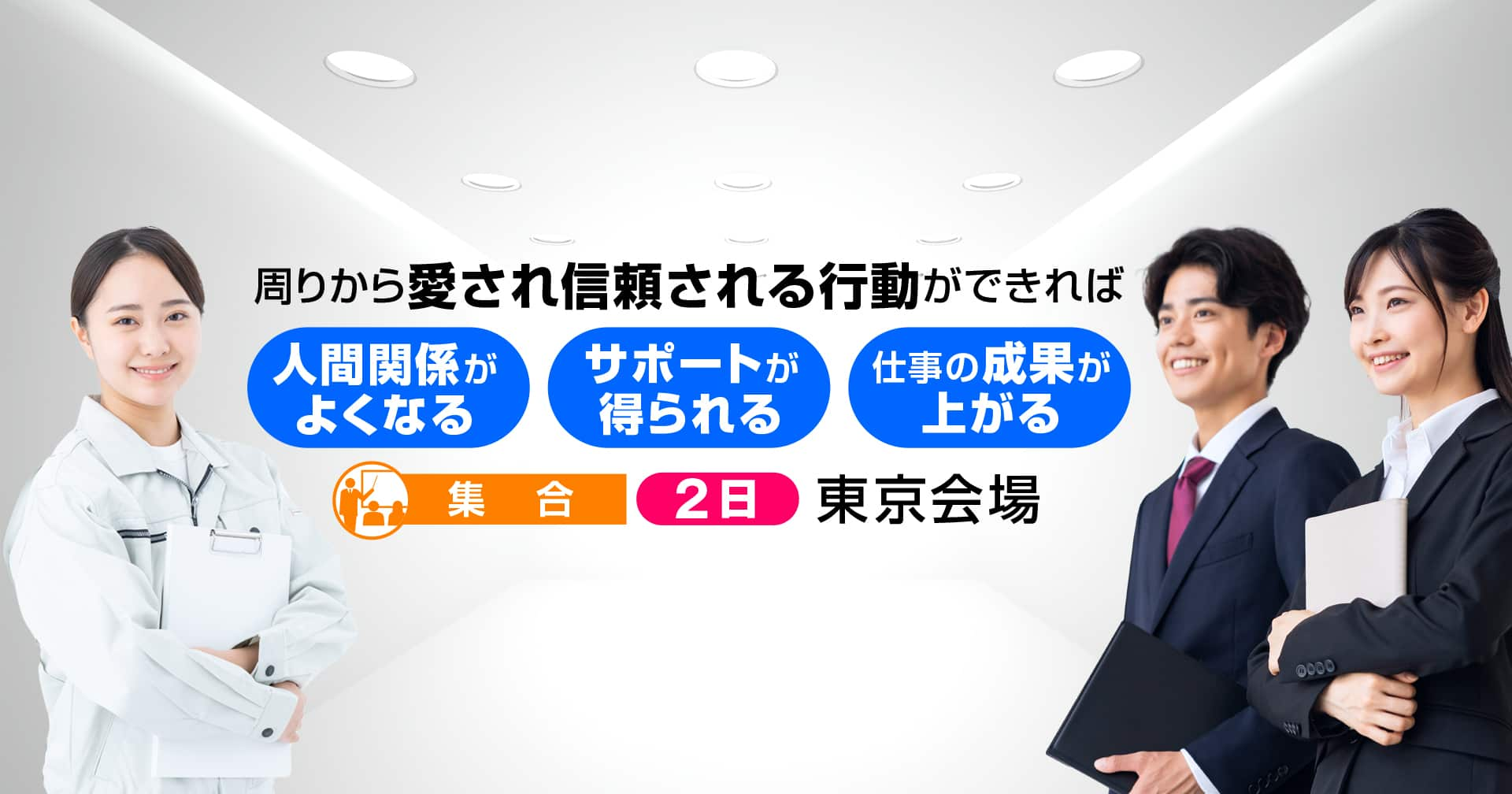










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







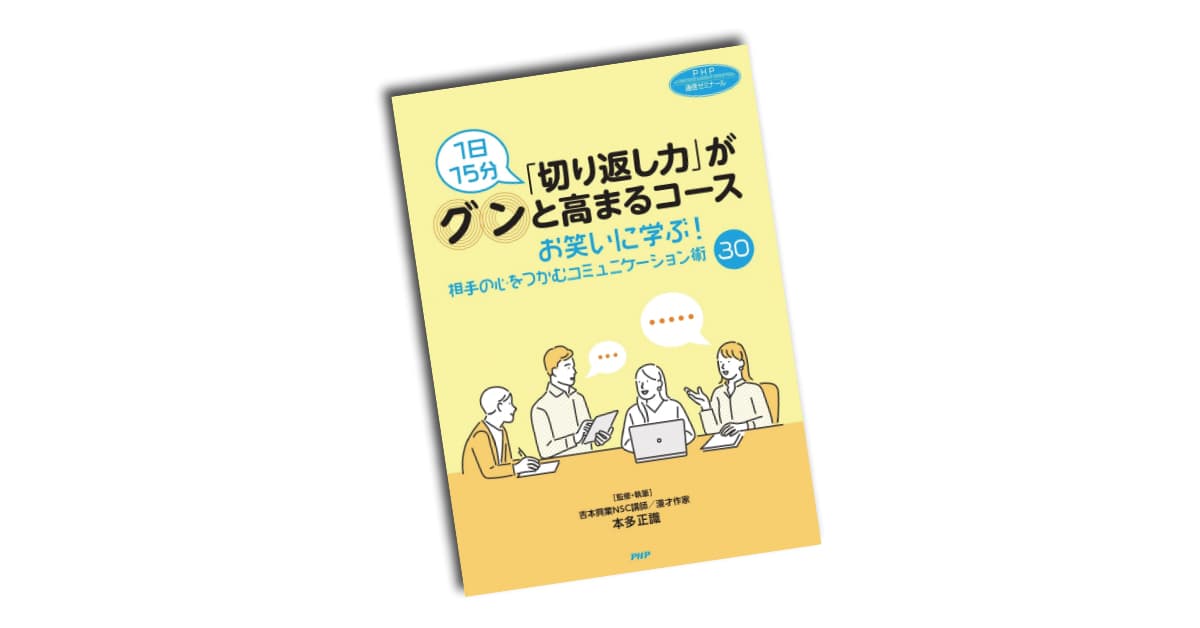






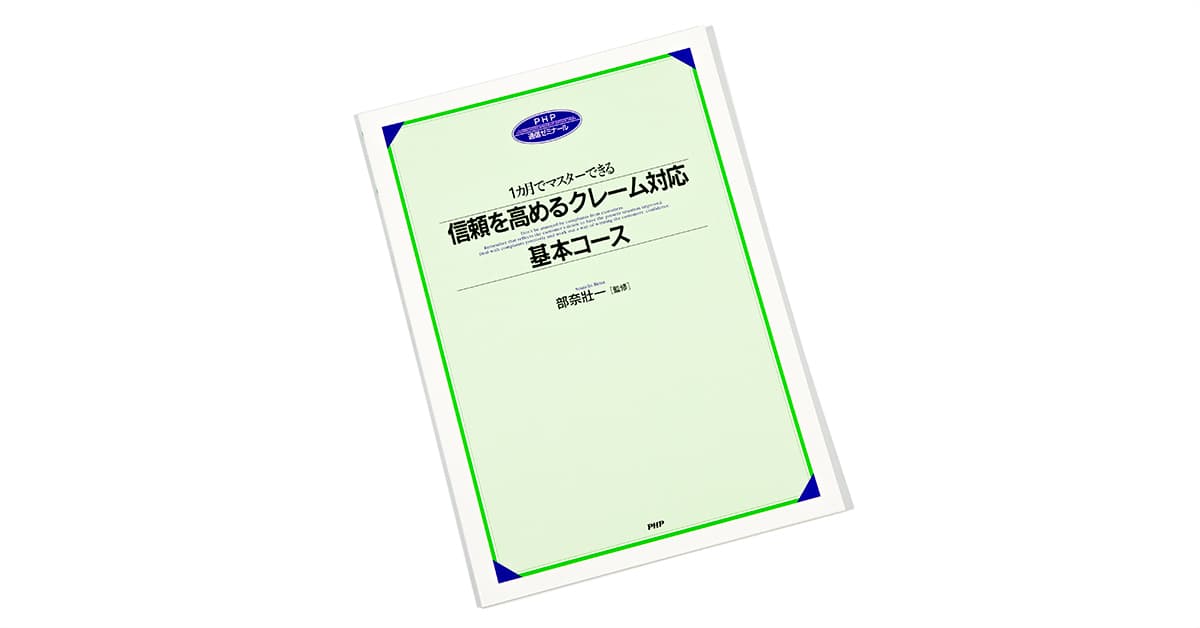





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

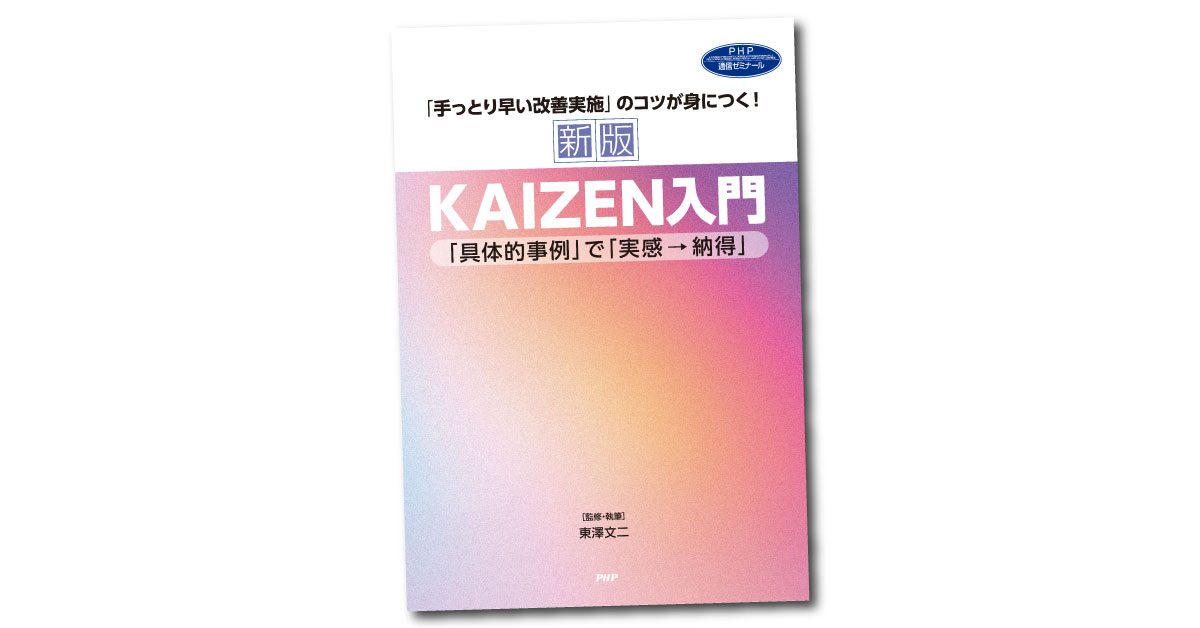










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)



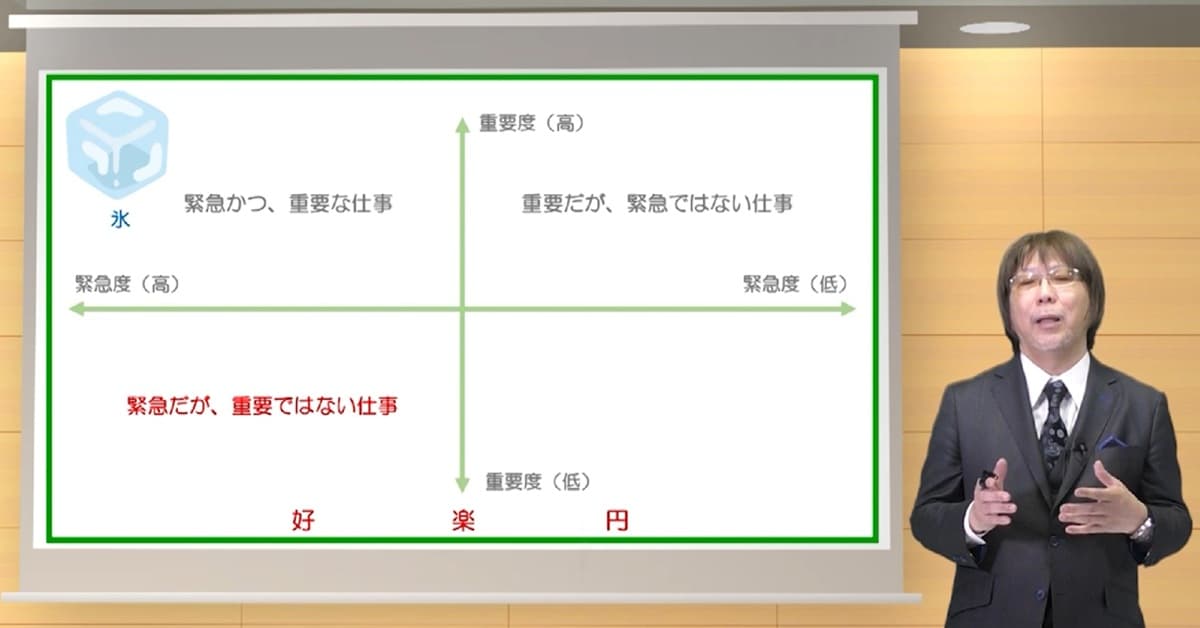
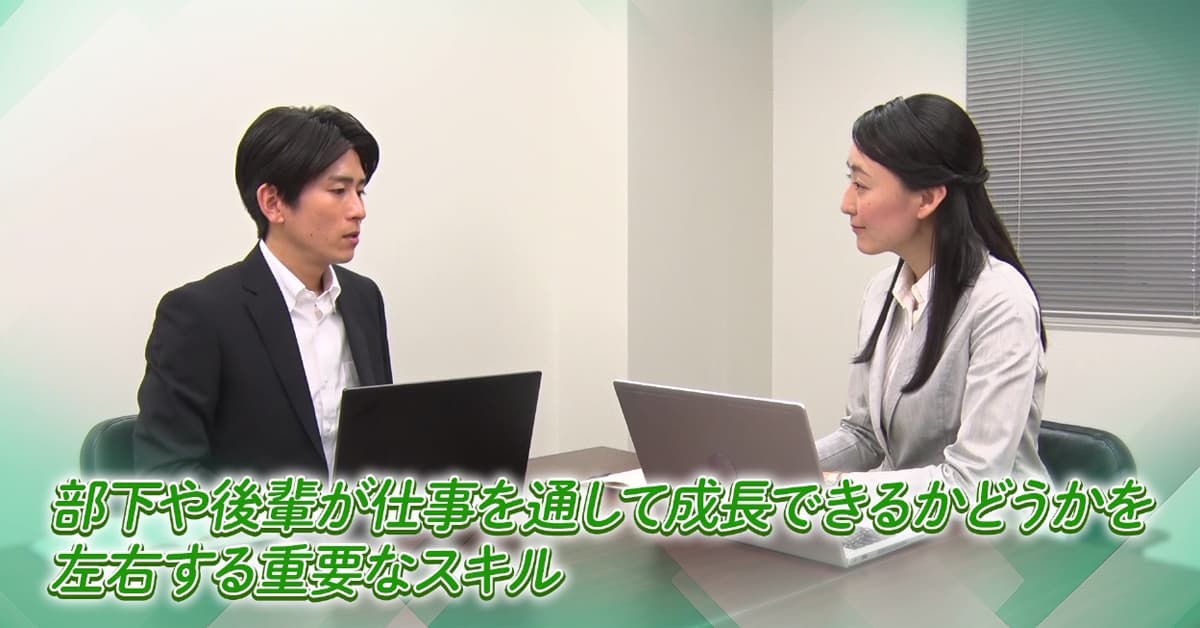
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
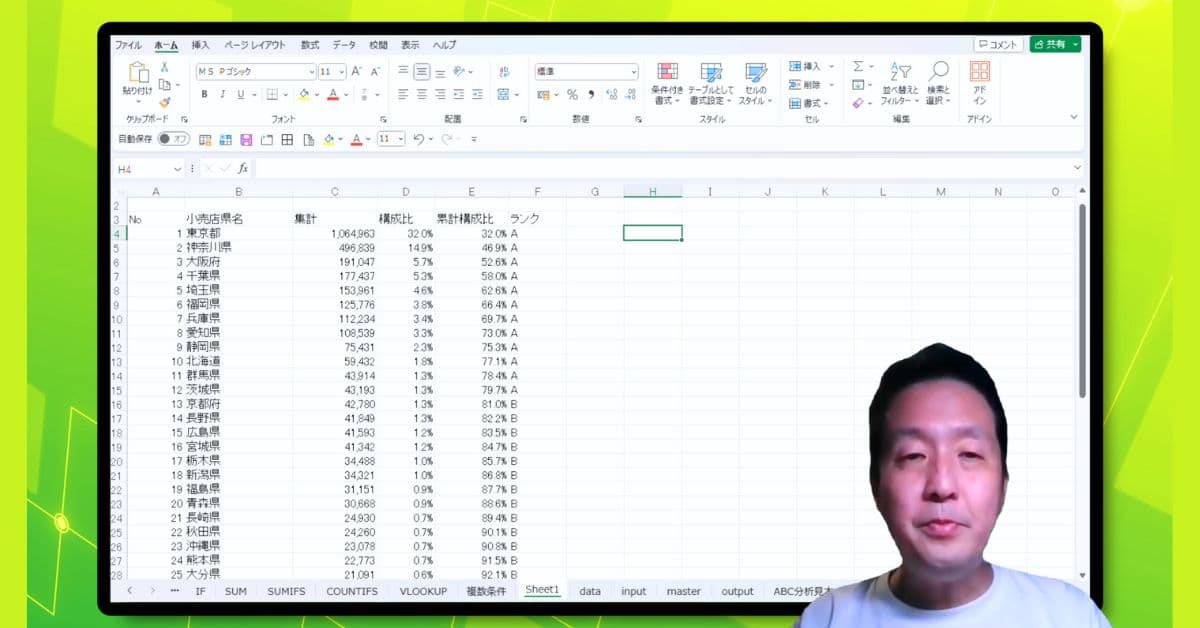

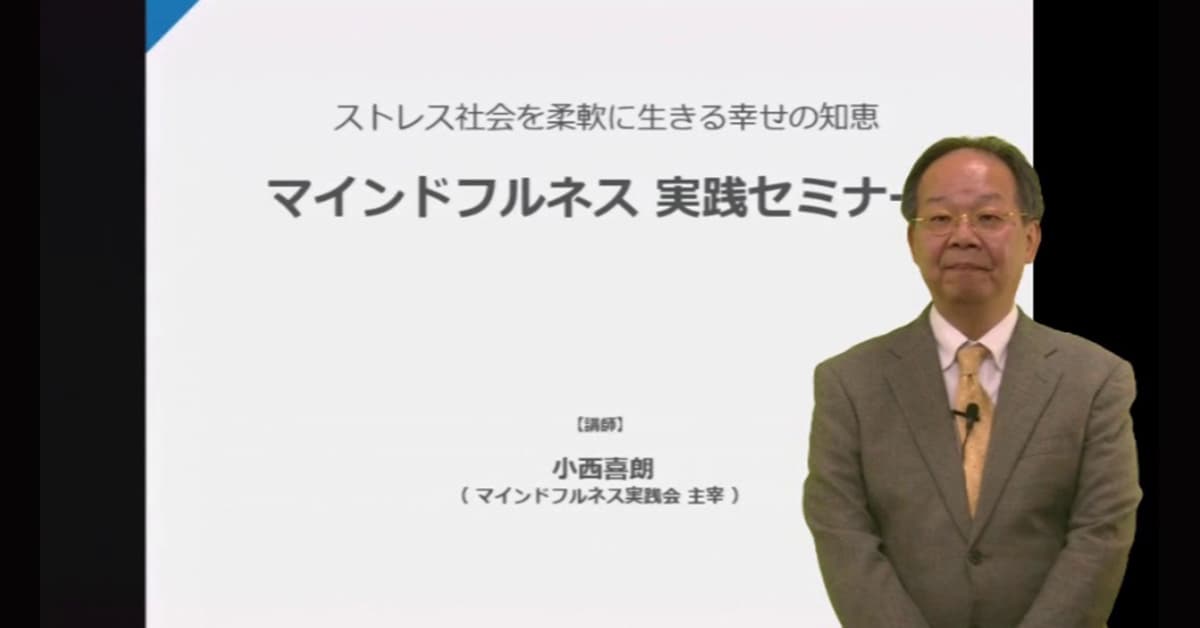

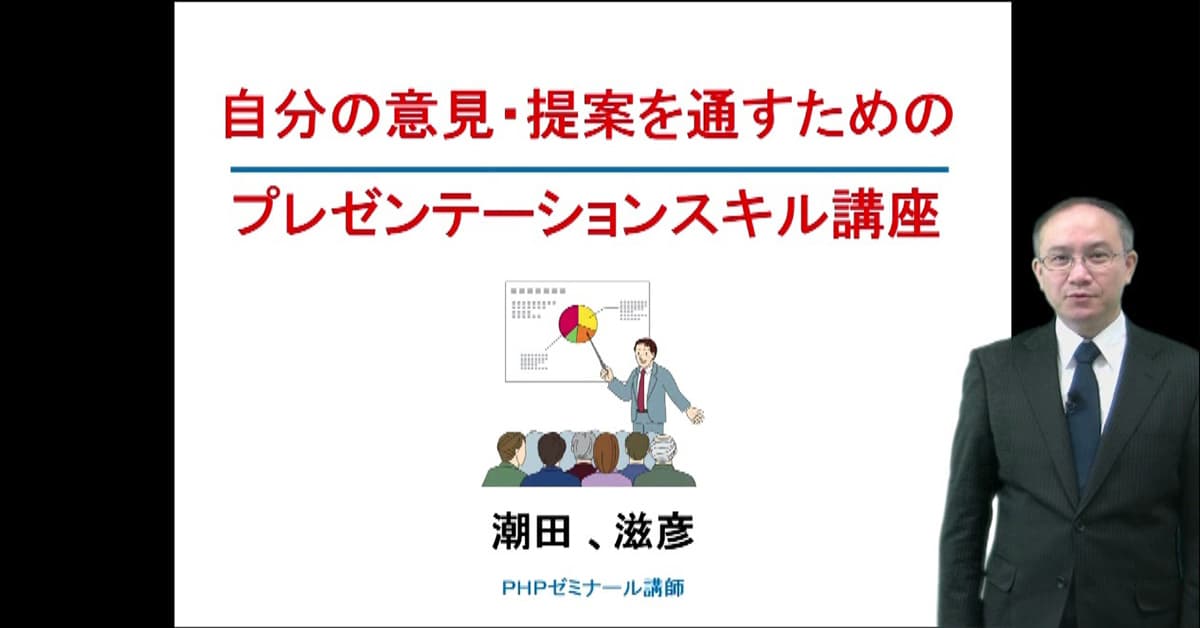
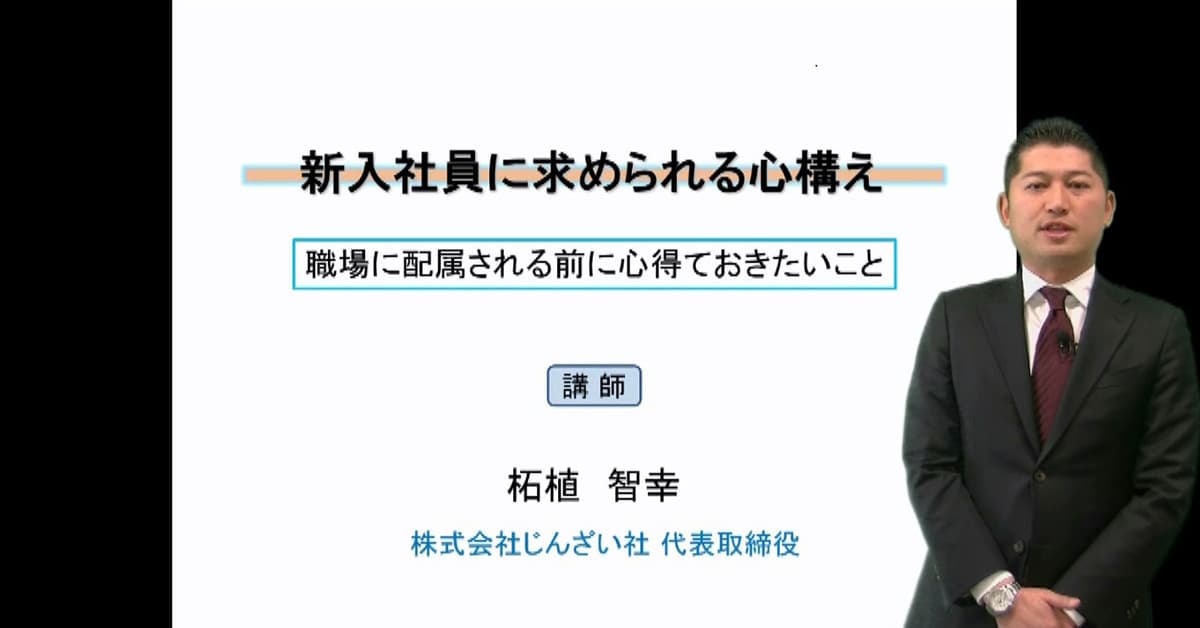
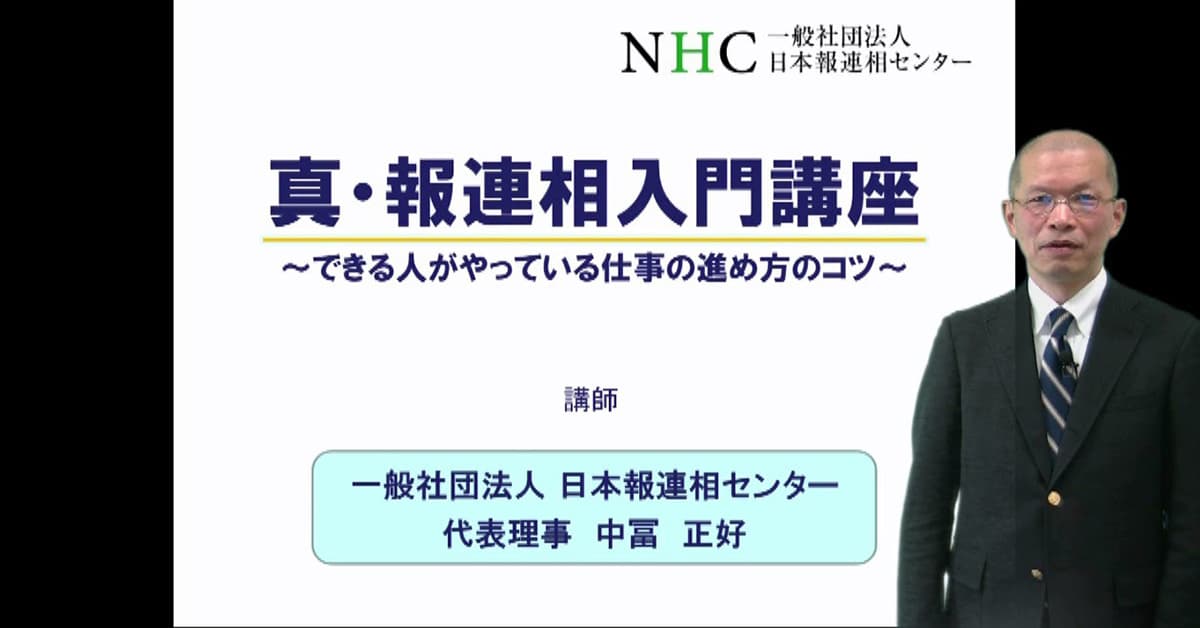
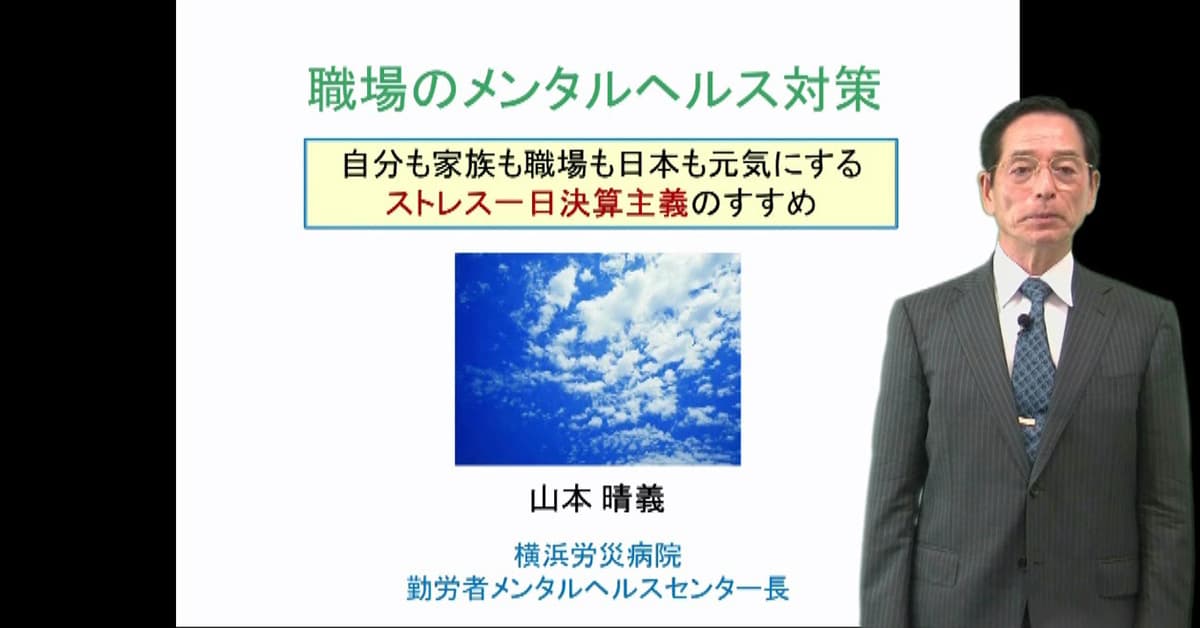
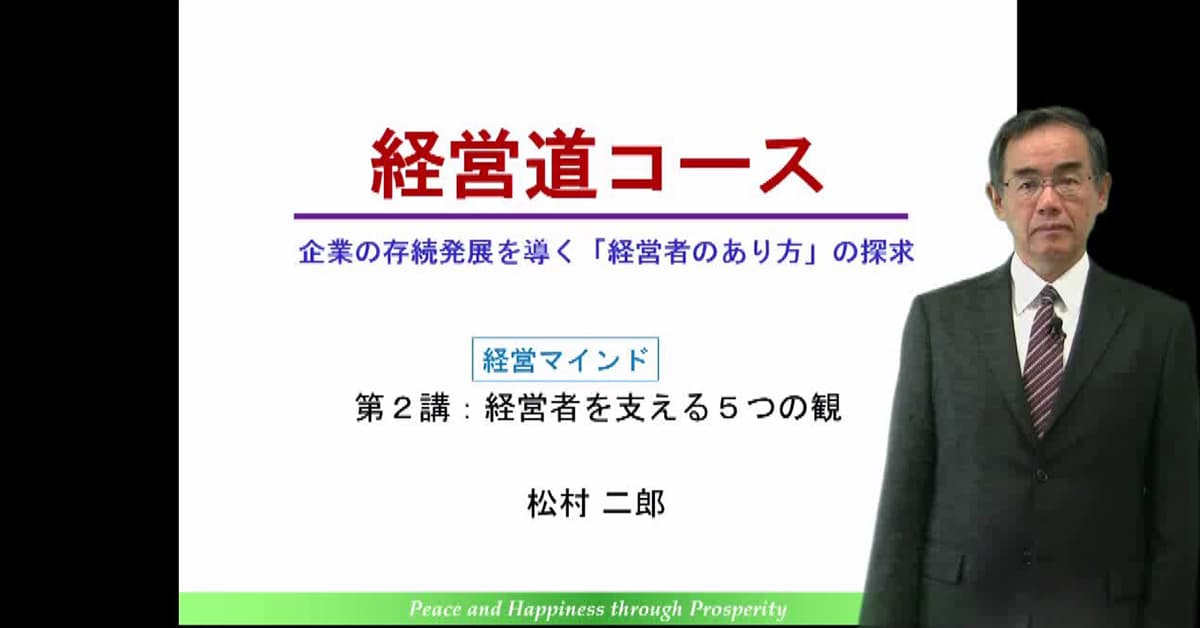
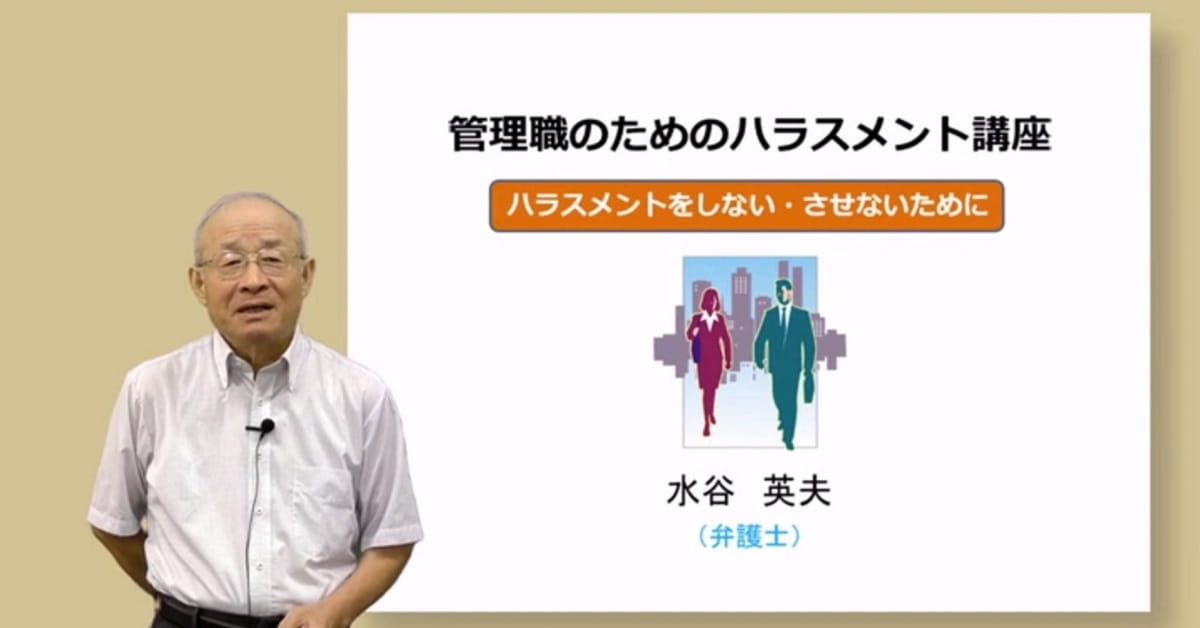

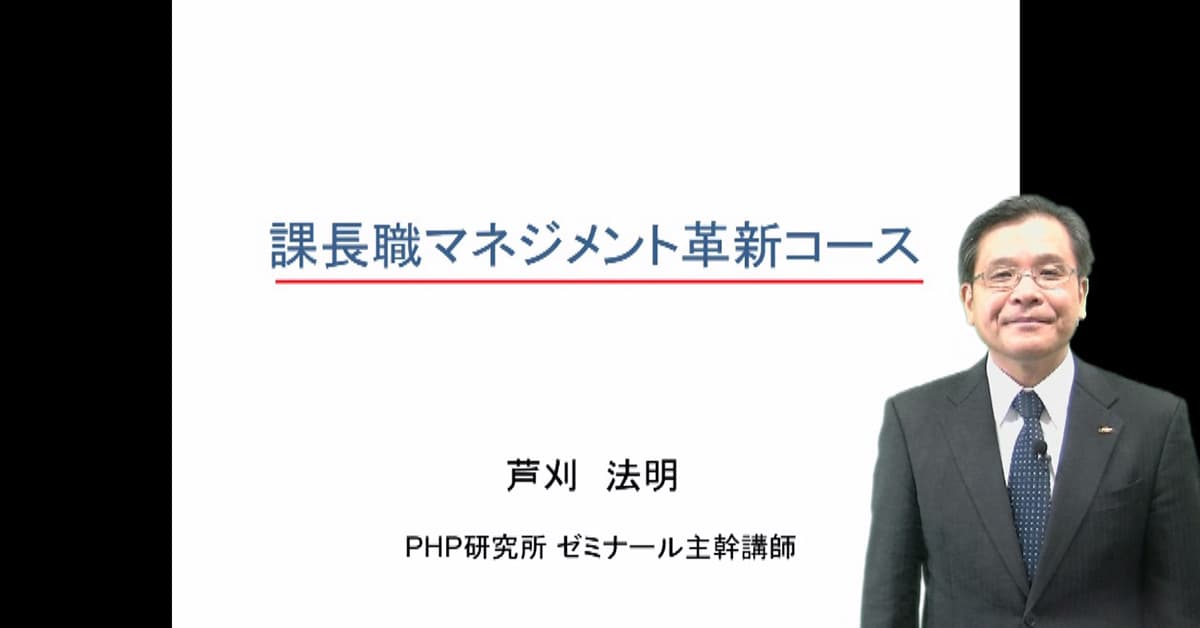



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















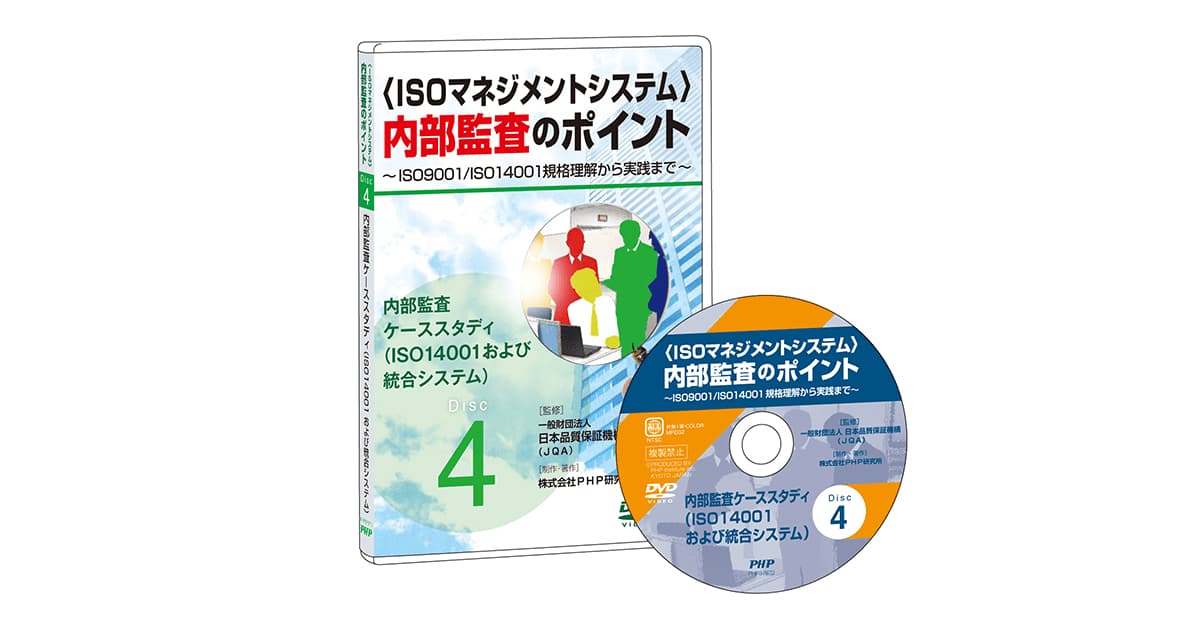




![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
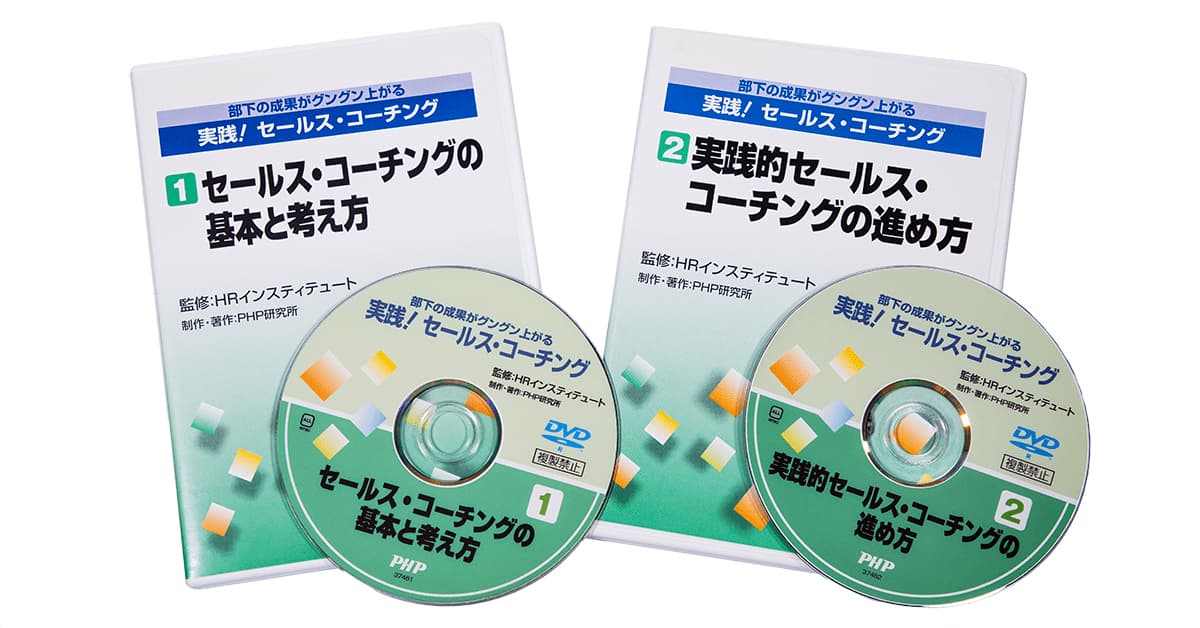





![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)