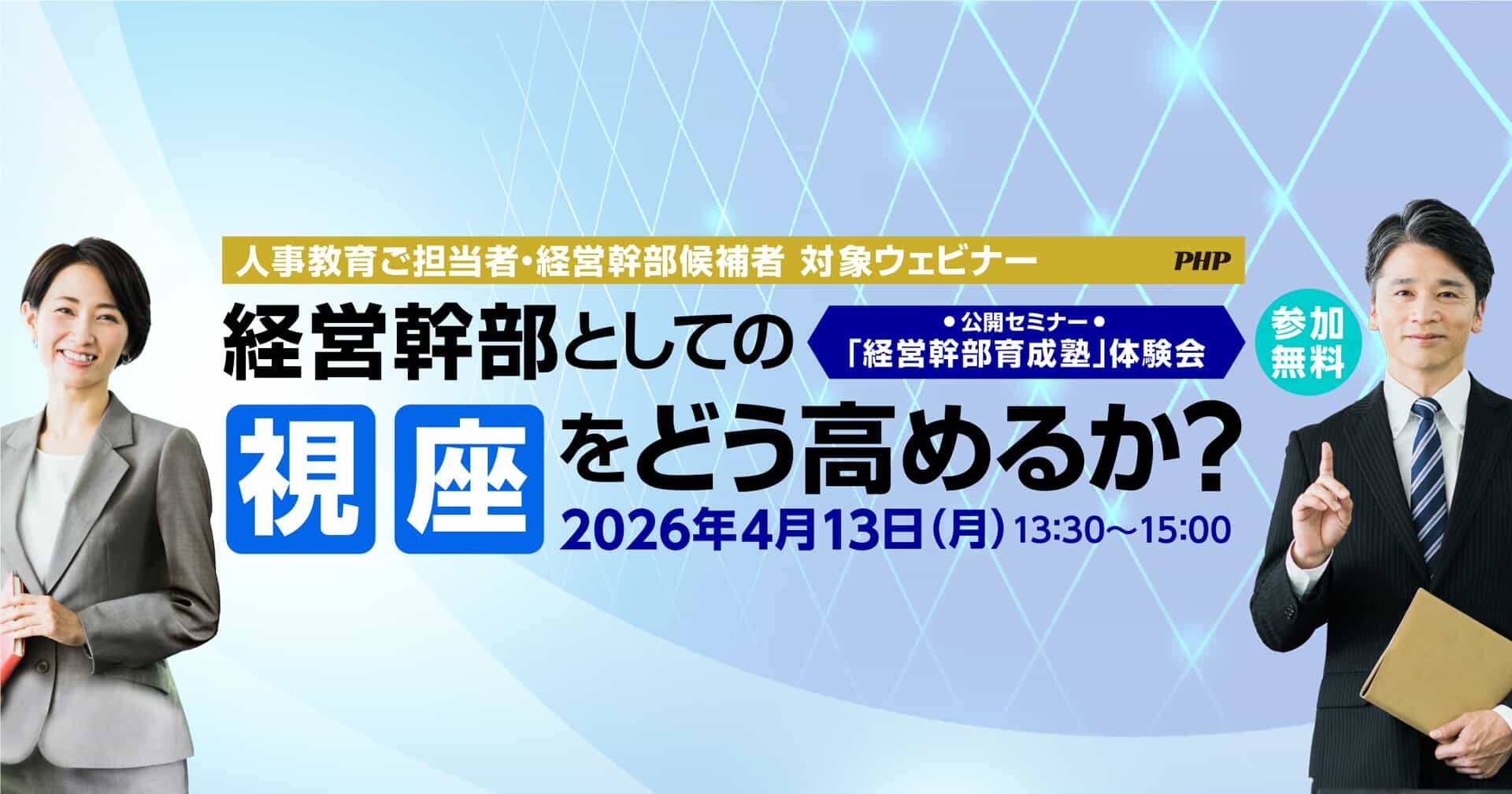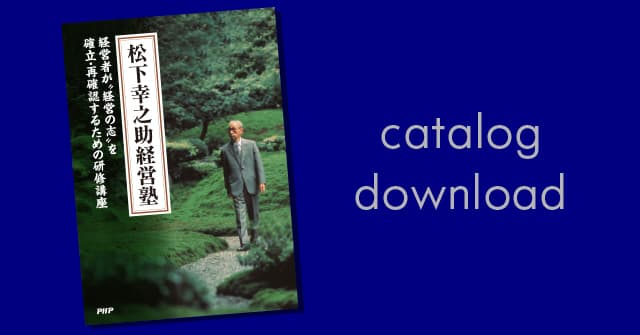個人と組織のつながりをつくるマネジメント~考え方と実践方法
2021年8月20日更新
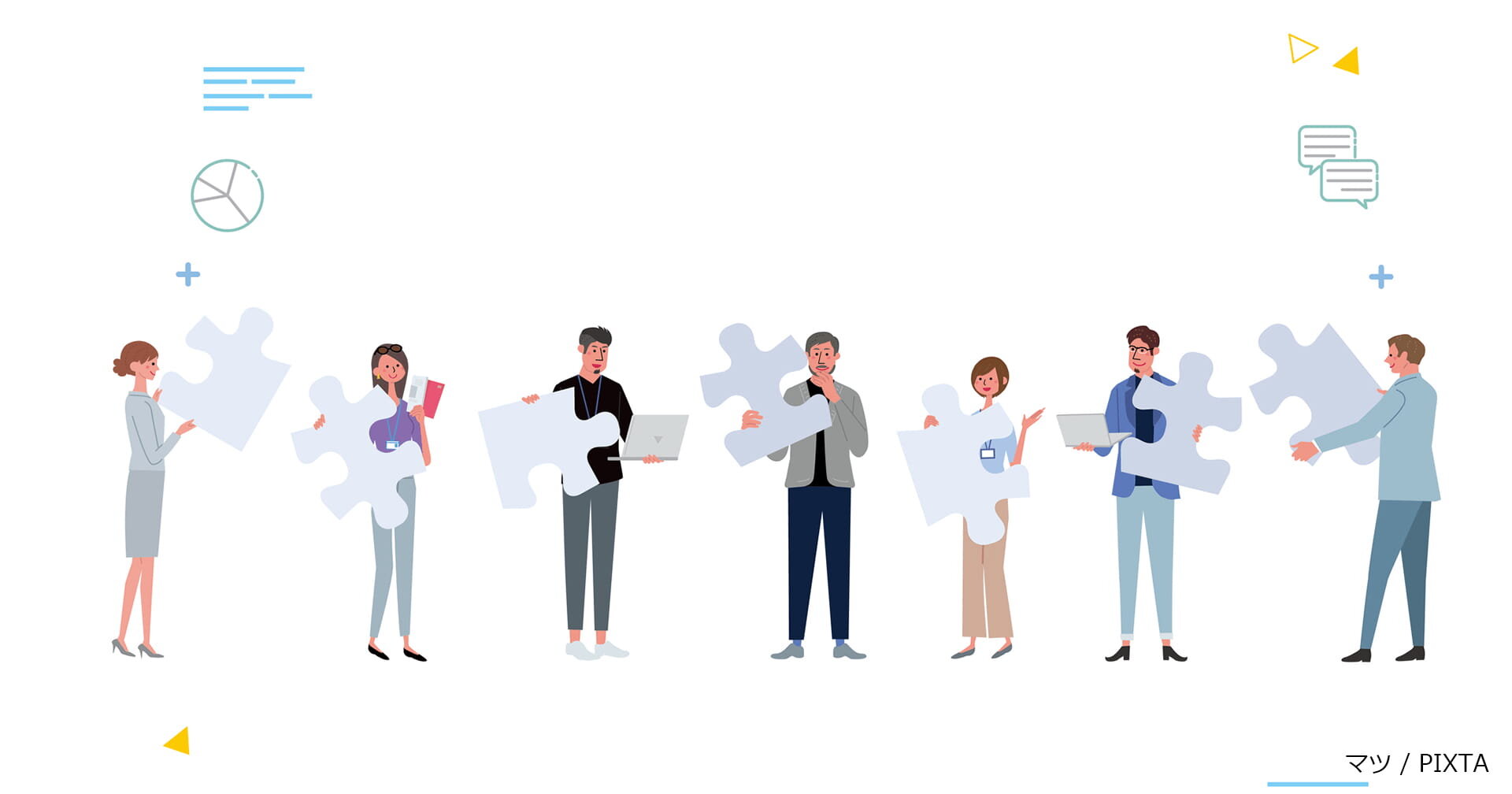
リモートワークの推進が働き方を大きく変えています。ワークライフバランスの改善、仕事の効率アップなど、数々のメリットがある反面、組織と個人とのつながりが脆弱化してしまうリスクもはらんでいます。
副業解禁の動きが加速し、業界を越えた出向・転籍が当たり前になってくると、そのつながりはさらに希薄化していく恐れがあります。
組織をマネジメントする上で強い遠心力が働いている状況下では、それ以上の求心力を生み出して個と組織をつないでおかないと、みながバラバラになりかねません。
そこで本稿では「つながりをつくるマネジメント」について、その考え方と具体的な実践方法について考察いたします。
低下するエンゲージメント
米国のギャラップ社が世界各国の企業を対象に実施した従業員のエンゲージメント(会社や仕事への愛着心、思い入れ)調査(2017年)によると、日本は「熱意あふれる社員」の割合が6%しかないという衝撃的な事実が明らかになりました。コロナ禍にゆれる現在はもっと状況が悪化しているのではないでしょうか。
かつての日本企業は「金太郎飴」と揶揄されるほど、トップの号令一下、組織全体が一つの方向を向いて仕事に取り組むのが強みでした。ところが、グローバル化、デジタル化の進展によってその強みが弱みに転じた結果、経営のかじ取りがぶれ、方針があいまいになって「わが社はどこに向かっているのか」「何のためにこの仕事をするのか」が見えにくくなってしまいました。
また、組織の大半を占めるようになった「ミレニアル世代」(1980~2000年に生まれた世代)は、旧世代と異なる価値観をもっているにも関わらず、それを理解していない管理職のもとでやる気を失っていきました。
こうした要因が複合的に絡み合って、自分の会社や担当業務に対するエンゲージメントが低下し、冷めた社員が増加していったように思われます。
トップダウン型からボトムアップ型のマネジメントへ
今後、日本企業はどうすればいいのでしょうか。
現場レベルでまずできることは、マネジメントスタイルの切り替えでしょう。つまり、指示命令で人を動かすトップダウン型のマネジメントではなく、相談調でメンバーの意見を求めるボトムアップ型のマネジメントへと意識と行動を変えることです。
トップダウン型のマネジメントからは、やらされ感が生じ、他責の姿勢、依存心、傍観者的態度につながりやすくなります。これではエンゲージメントを高めることは難しいでしょう。一方のボトムアップ型のマネジメントからは、「自分も部門経営に参画している」感覚が生み出され、主体者意識とやる気が高まって、各人のもつ情報や知恵が集まることになります。
個人と組織のつながりをつくる「平等の法則」
つながり、特に精神的なつながりとは、組織に対する帰属意識のことです。ビジネス書として異例の大ヒットを収めた『キリンビール高知支店の奇跡』(講談社α新書)の著者・田村潤氏(キリンビール・元副社長)は、経験知に基づく一つの持論をもっています。それは、帰属意識を高めるための「平等の原則」という考え方です。
社員のやる気を引き出す原動力は帰属意識だ。帰属意識を高めるためには、上司と部下がもっている情報量を同じにすることだ。意見の相違は、お互いのもっている情報量の差から生じることが多い。だから、部長や課長がもっている情報量と、末端の新入社員がもっている情報量を平等にしてあげることだ。私はこのやり方で、部下たちの帰属意識を高め、やる気を引き出してきた
PHPゼミナール「経営道コース」における講義(2017年11月)での発言
そんな田村氏のマネジメントを当時の部下たちはどのように受け止めていたのでしょうか。キリンビール高知支店で、田村氏と一緒に仕事をしていた部下の一人にIさんという女性がいます。営業事務係として入社したIさんの仕事といえば、お茶出しやコピー取りなどの補助的業務ばかりであり、本人も「自分の仕事はこの程度のものだ」と思っていました。
ところが彼女が入社2年目の時に、田村氏が支店長として高知支店に赴任してから様相が一変します。新支店長の田村氏は、全メンバーに支店の方針や課題を丁寧に説明すると同時に、一人ひとりに対する期待を伝えていきました。そこで初めてIさんは、「人として、キリンビール社員として、戦力として認められた。自分はチームの一員なんだ」と感じ、「なんとなく仕事をしていた私の仕事に対する姿勢が変わった」と述べています。
それからのIさんの変化は凄まじい。営業事務という役割にとどまらず、直接的に顧客に価値を提供するような業務や提案をどんどんしていくようになります。結婚退職後も、地元で子育て支援サークルを立ち上げるなど、キリンビール時代に学んだことをその後の人生でも活かし切っているのです。
上司と部下、双方向の報連相
部下がもっている情報を上司が求めるように、部下もまた、上司がもっている情報を知りたがっています。先日、若手社員のリーダーシップ行動を分析するため、4名の若手ビジネスパーソンに集まっていただき、インタビューをする機会がありました(※)。
あるベンチャー企業に所属する入社4年目の男性に対して「上司に何を求めるか?」と質問したところ、「上司の考えているビジョンやもっている情報をオープンにして共有してほしい。なぜならば、上司が考えていることがわかれば、部下としてどんな提案や動き方をすればいいかが見えてくるから」という意見を述べてくれました。
上司がもっている情報の中には、人事情報を含めて部下に開示できない性質のものも当然あるでしょう。しかし、それらを除外しても上司-部下間で共有しても問題がない情報は意外と多いのではないでしょうか。それらを開示することが、部下たちに「自分はこのチームの一員なんだ」という自覚をもたせたり、「上司の方針にそって、自分がやるべきことをやろう」という主体性を生み、つながりが強化されていくのです。
これまでの常識を手放し、組織における報連相を「下から上」への一方通行ではなく、「上から下」への双方向の流れも作ってみてはどうでしょうか。
※ 立教大学経営学部でBLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)の授業を受けたOB4名が、現在各企業でどんなリーダーシップを発揮しているかを調査する目的で実施した座談会形式のインタビュー(2020年12月20日、於:PHP研究所東京本部
松下幸之助「衆知を集めた全員経営」
世界的なベストセラーとなった書籍『ティール組織』(F・ラルー著・英治出版)で紹介されている企業事例を見ると、いずれの企業もボトムアップ型マネジメントを採用していることがわかります。ボトムアップ型マネジメントは最先端のマネジメント手法なのですが、実は松下幸之助が、半世紀以上前から実践していた経営の進め方と通じる部分が多いのです。
幸之助は「衆知を集めた全員経営」という表現で、自身の経営の進め方を以下のように述べています。
みんなが知恵を出し合って、いわば衆知をもって経営しなければならないということを、私はくり返し申し上げております。一つの課は必ず衆知をもって経営してもらいたい。部またしかりであります。衆知を集めるには、衆知を集められるように考えなければなりませんし、また皆が知恵を出さなければなりません。みんなが出し合うためには、気安くお互いにものを言うようにしなければなりません。上司に対しても気安くものを言う。上司もまた気安くものを言うようにする。一見、友だちのごとくやる。そして規律はピチッと守っていく。そういうようにすれば非常に愉快に仕事ができると思います
1961年12月16日
アフターコロナのマネジメント
アフターコロナの世界は、社会の仕組みや価値観が様変わりすると言われます。しかし、人間の本質というものは変わりません。すなわち、人間は「自分が必要とされている」「自分がやらなければいけない」という感覚を味わった時、喜びややりがい、責任感をもつようになる存在なのです。
リモートワークの普及が、確実に組織と個人の関係に影響を及ぼすでしょう。フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが減って、エンゲージメントがさらに低下してしまっては元も子もありません。今こそ、人間の本質に立脚したマネジメントを、デジタル技術を駆使しながら、上手に実践する時代になったのではないでしょうか。
参考記事:マネジメントとは? 5つの機能やマネジメント能力を強化する方法を解説
的場正晃(まとば・まさあき)
PHP研究所人材開発企画部部長
1990年、慶應義塾大学商学部卒業。同年PHP研究所入社、研修局に配属。以後、一貫して研修事業に携わり、普及、企画、プログラム開発、講師活動に従事。2003年神戸大学大学院経営学研究科でミッション経営の研究を行ないMBA取得。中小企業診断士。










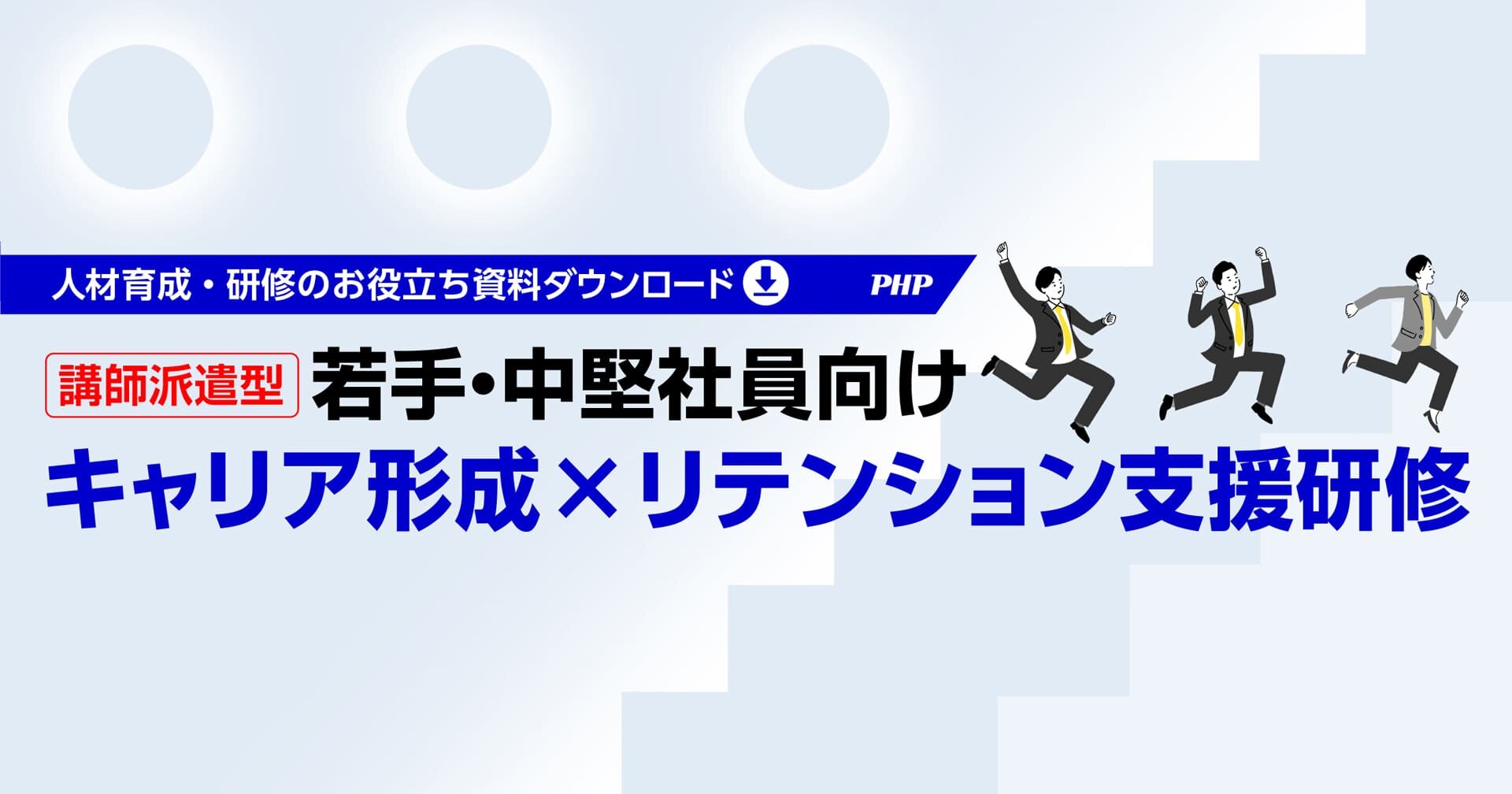





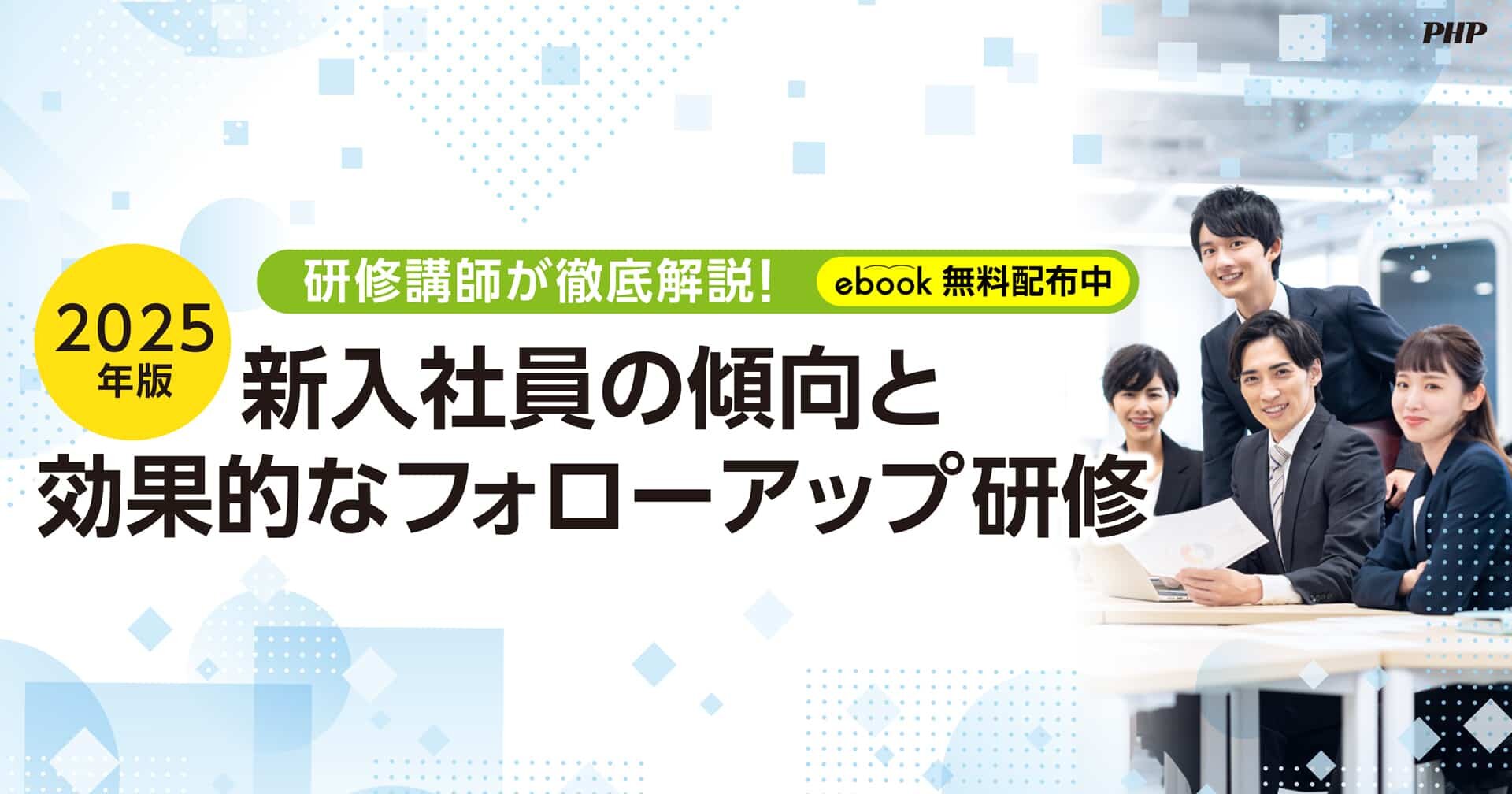









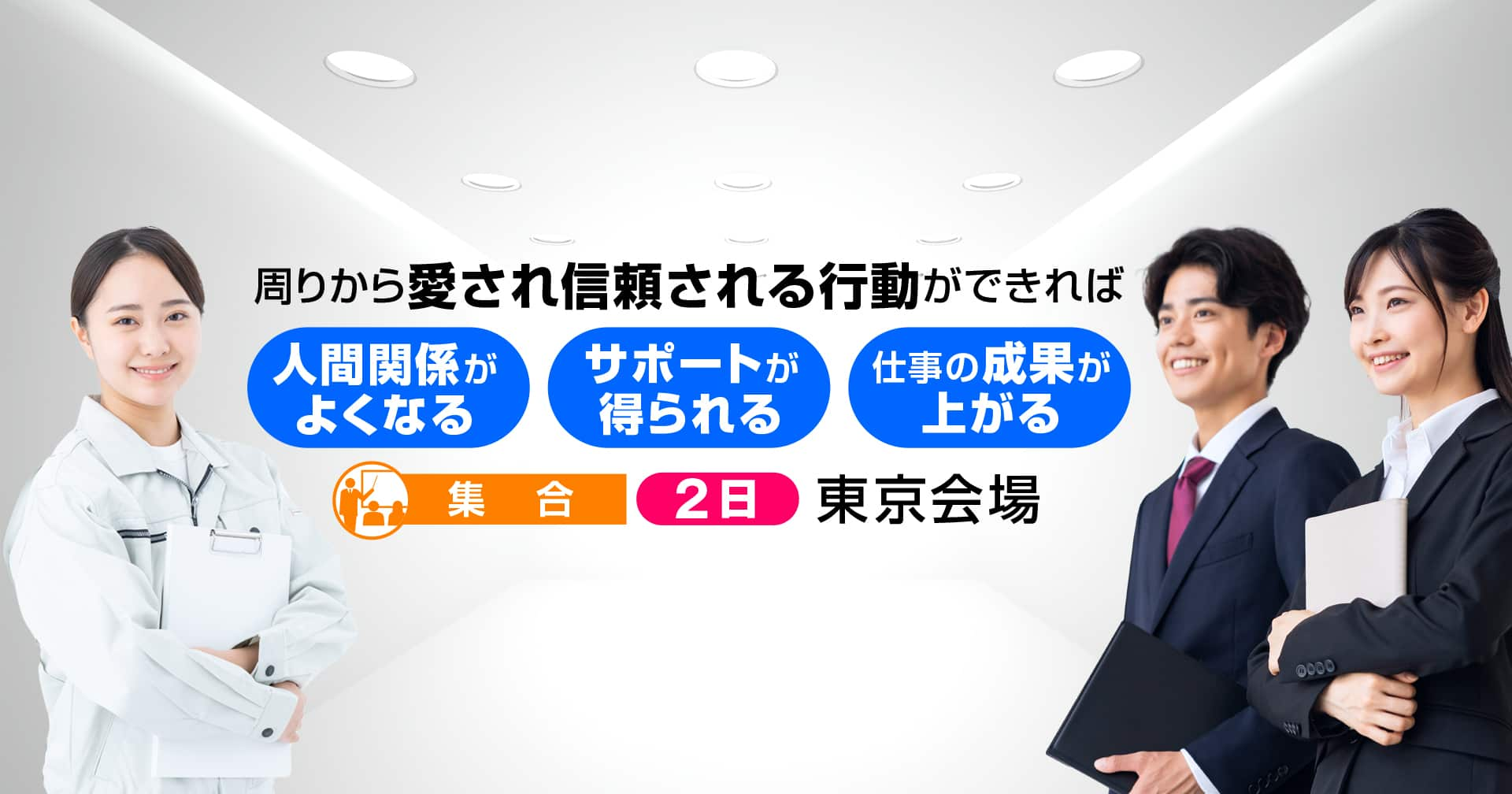










































![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)
![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)







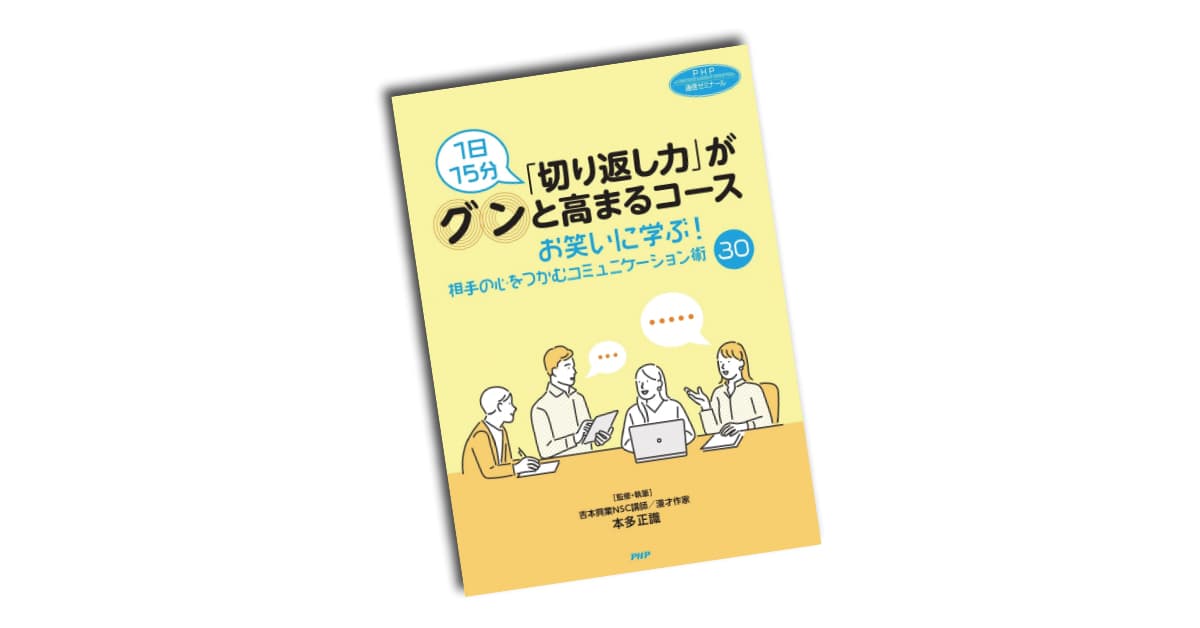






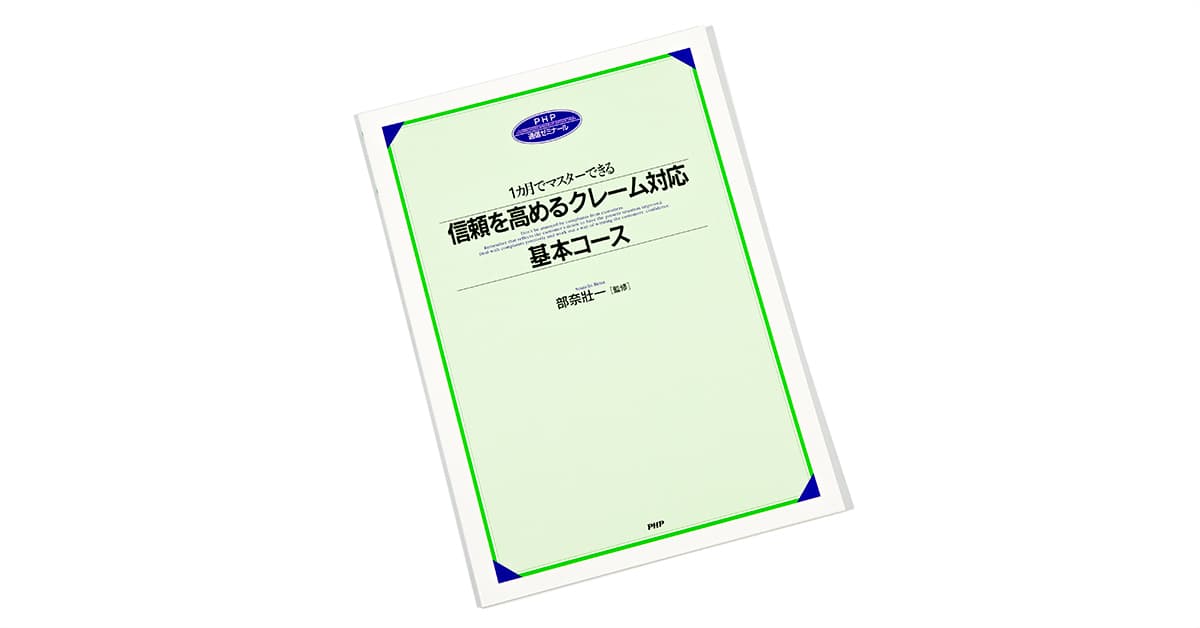





![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)
![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

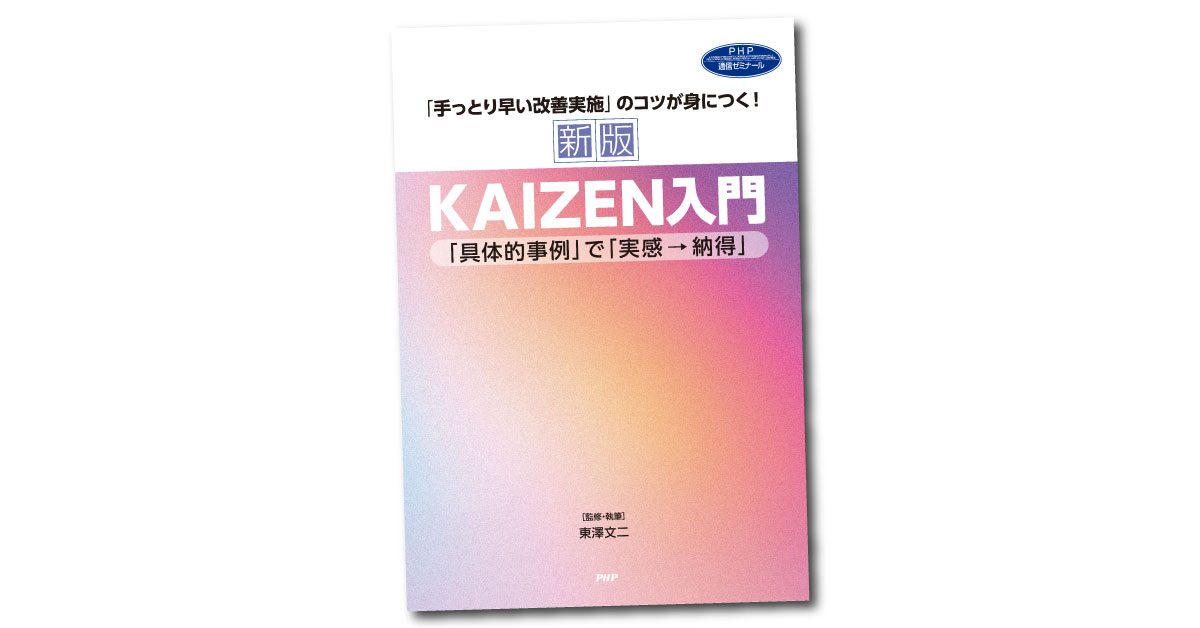










![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)



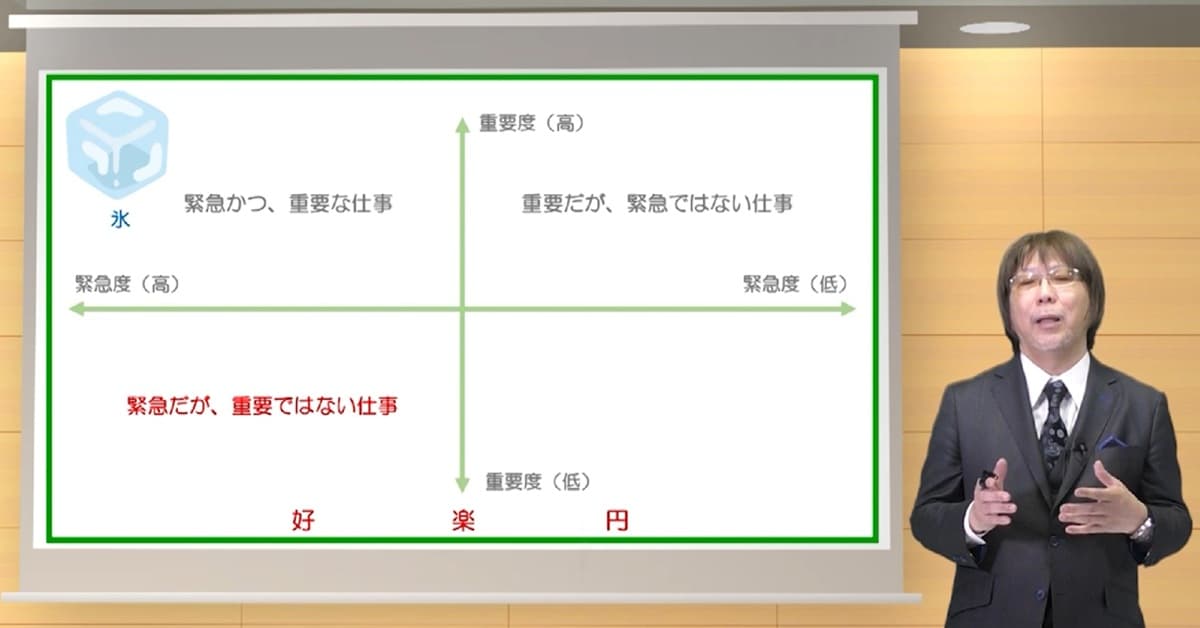
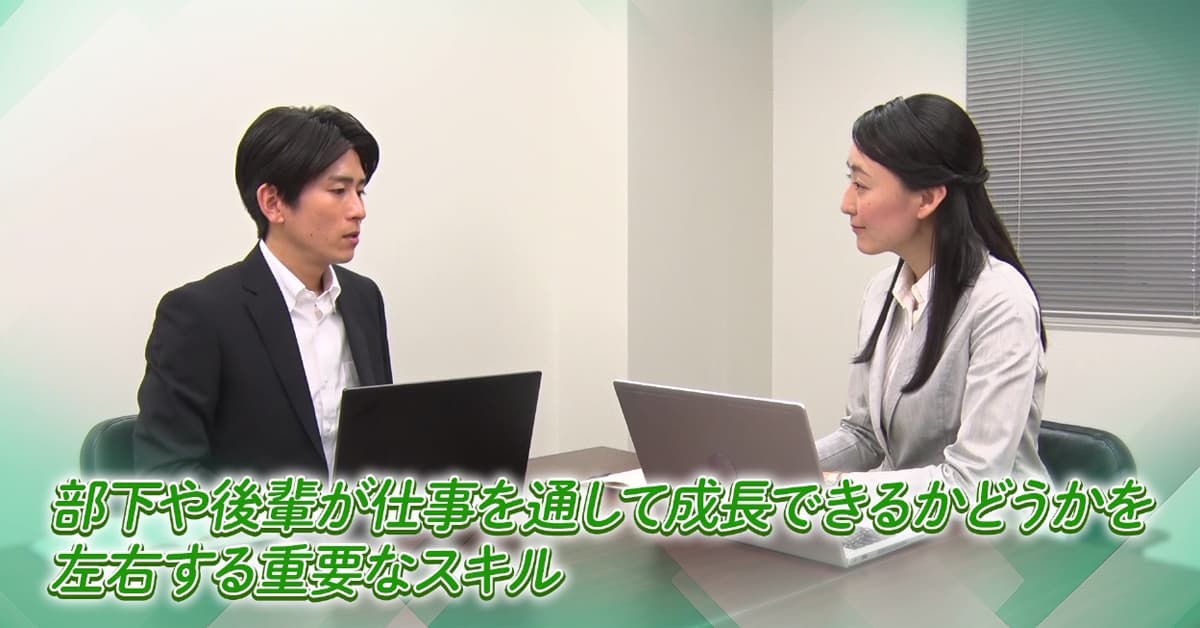
![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)
![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)
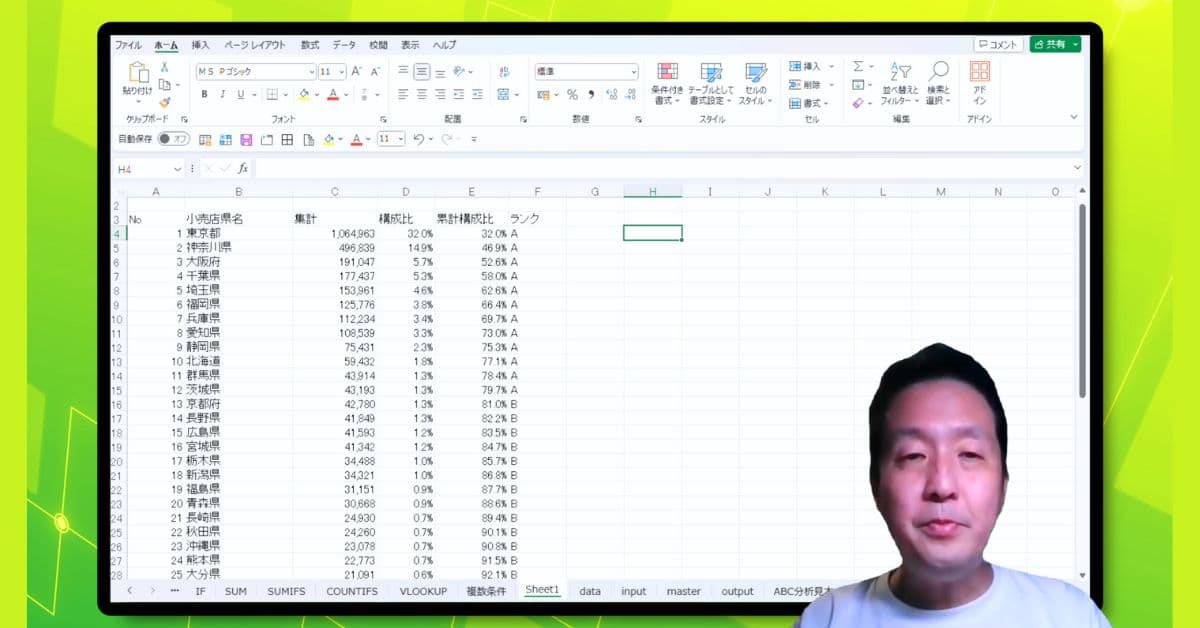

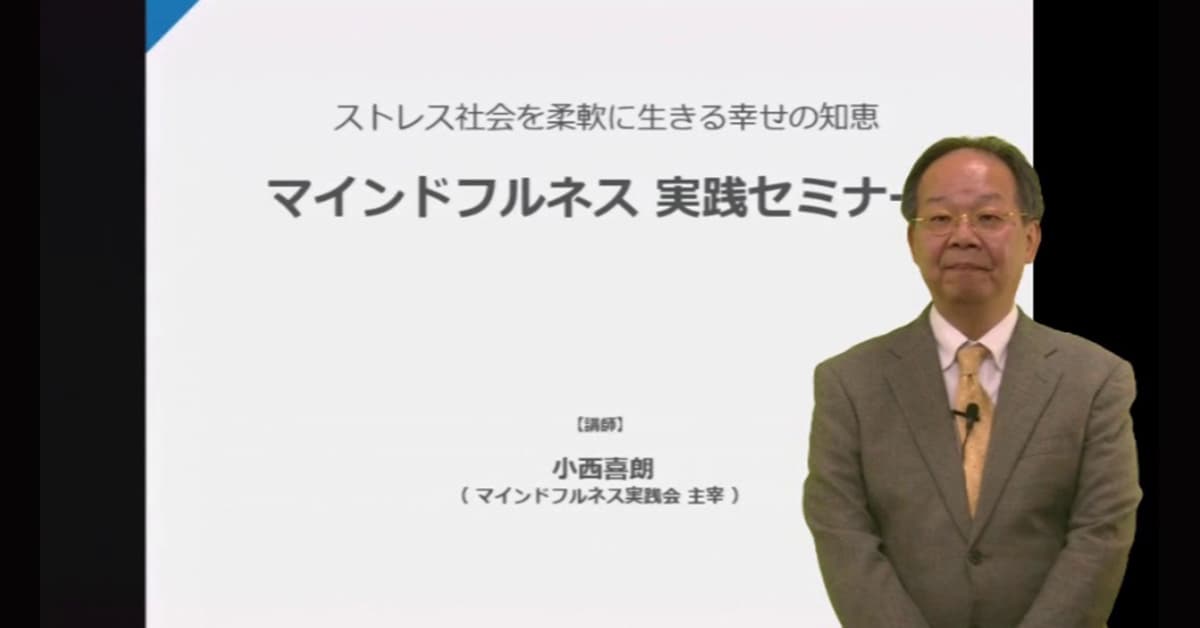

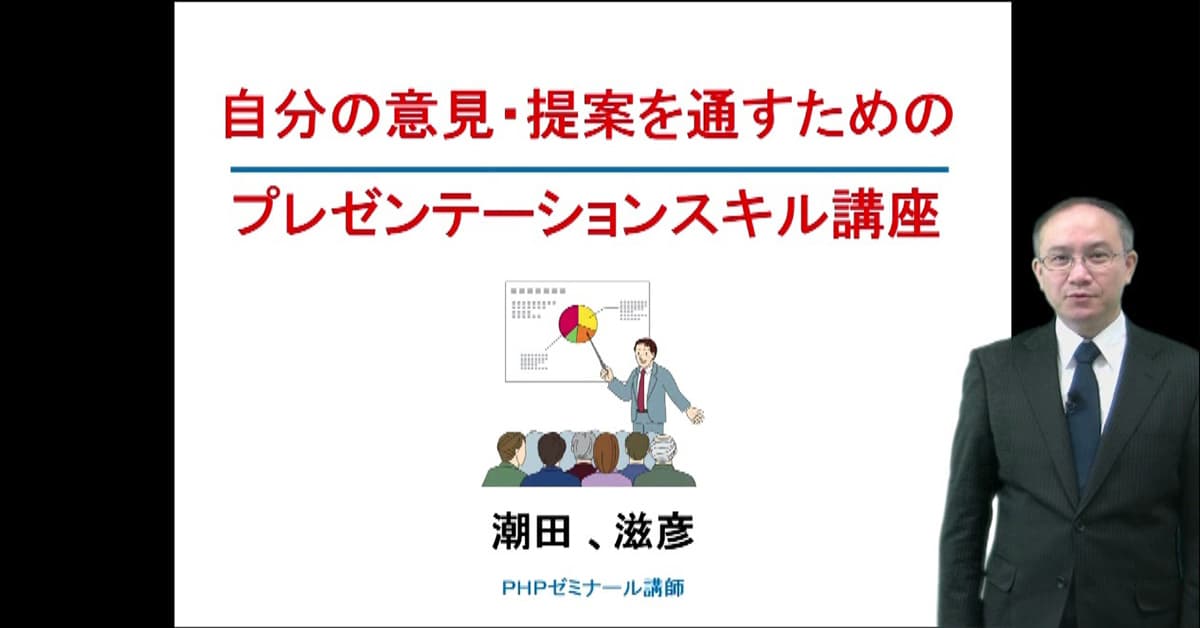
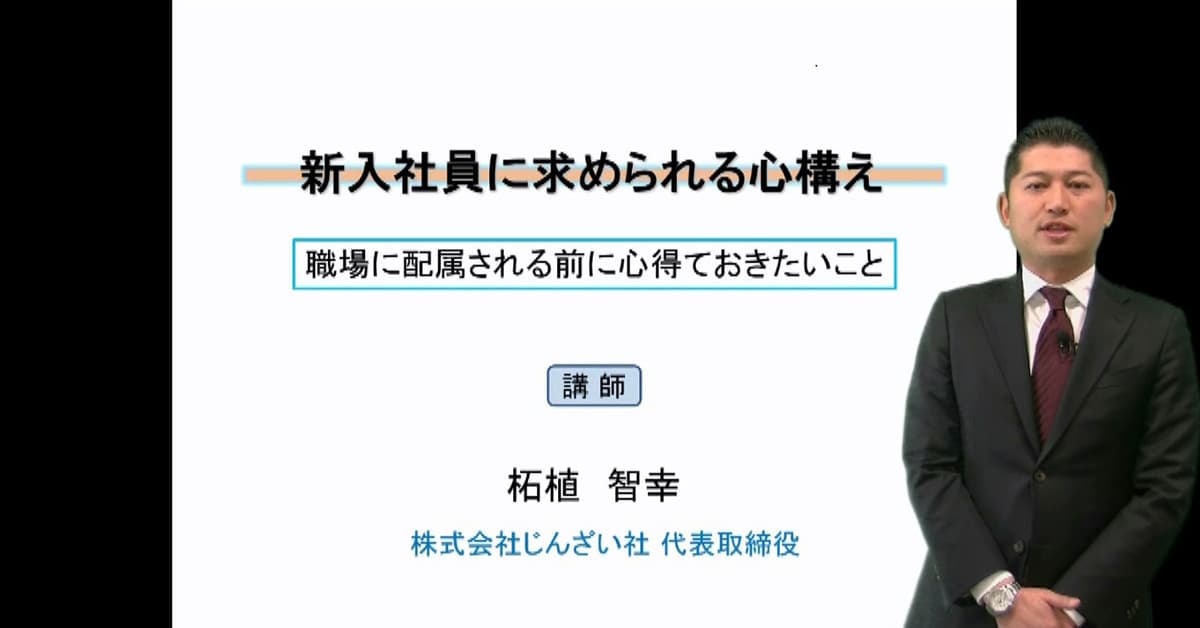
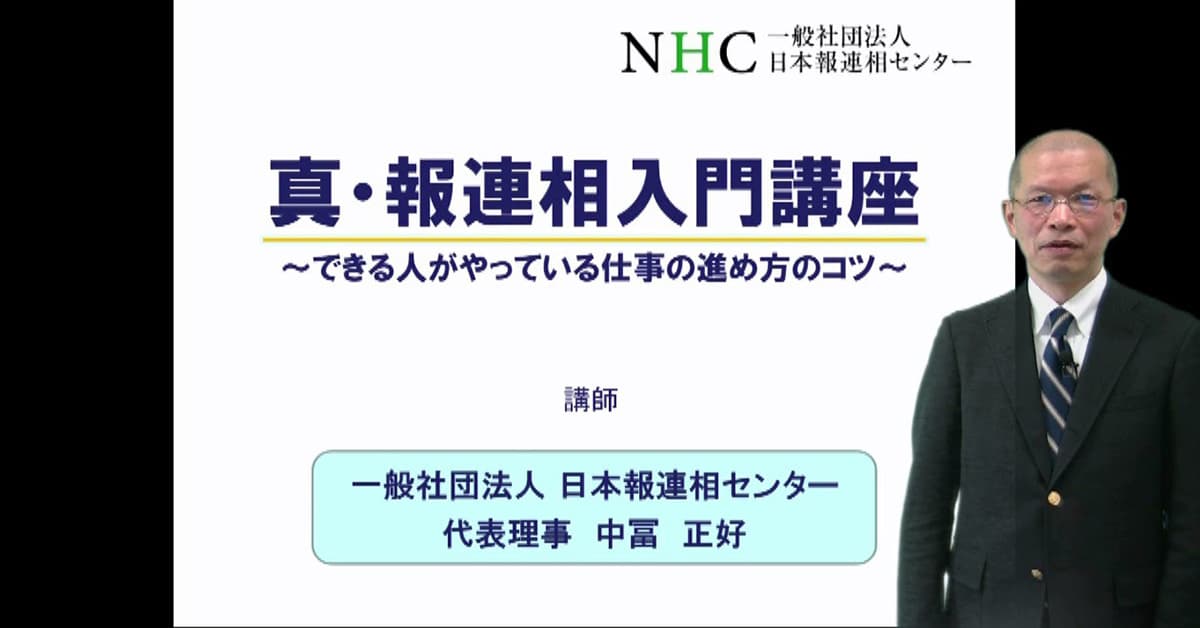
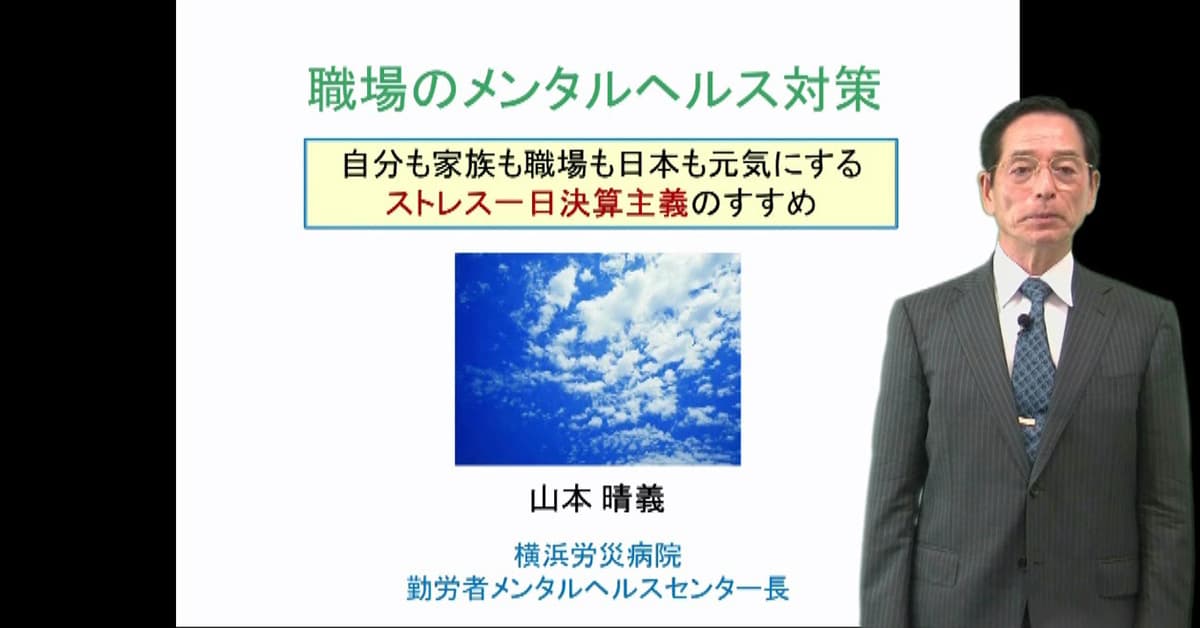
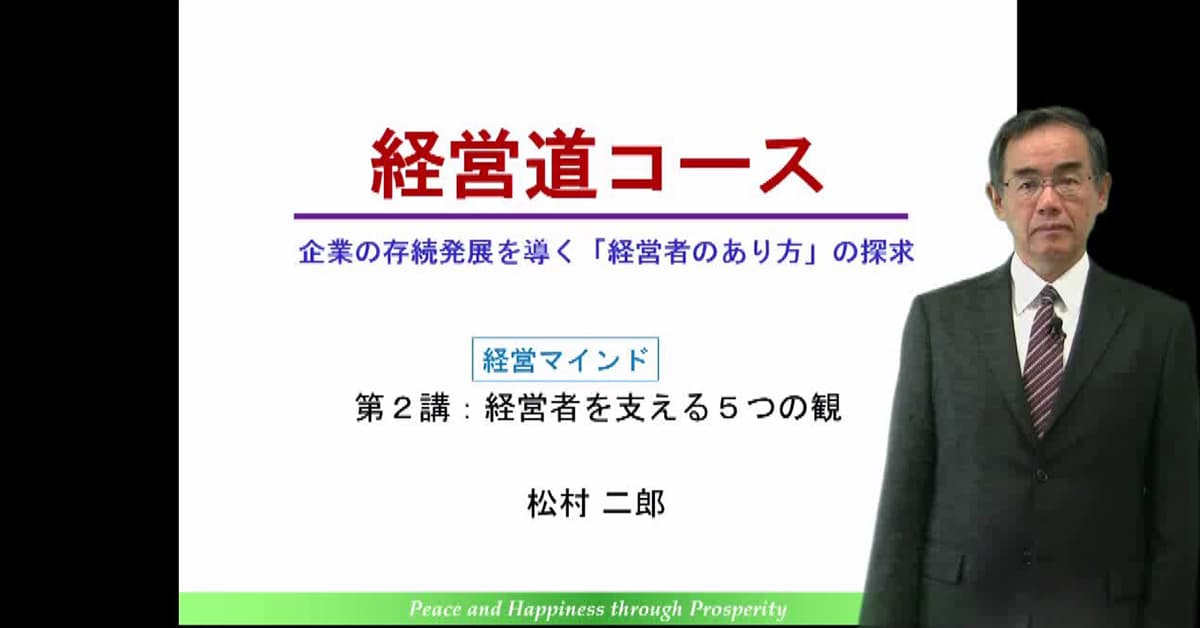
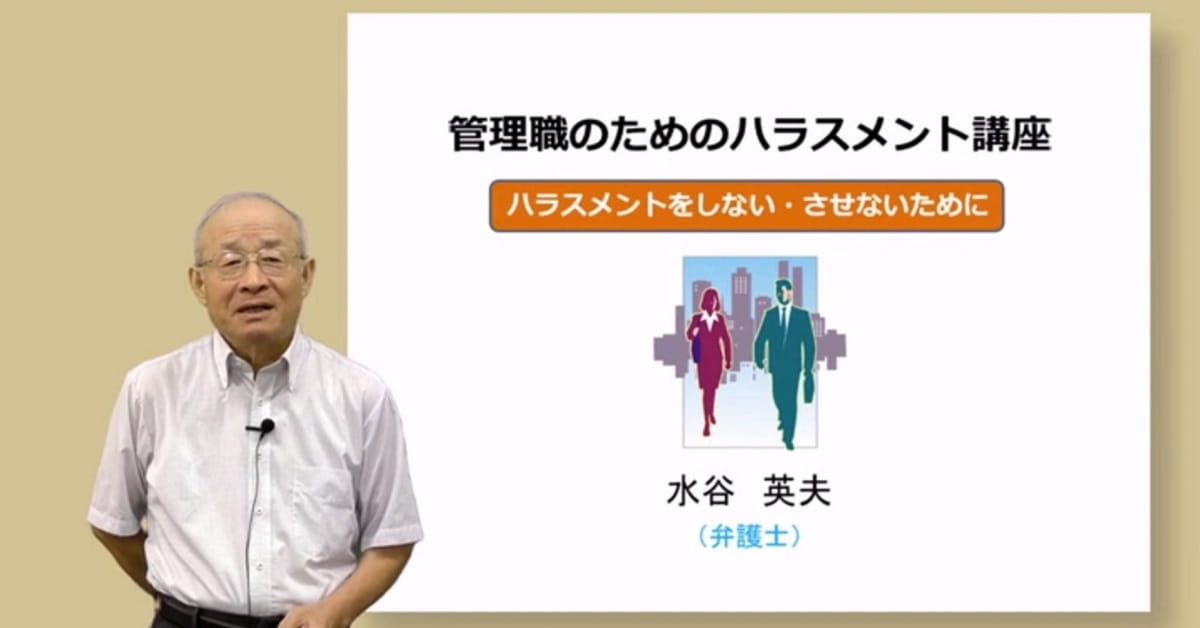

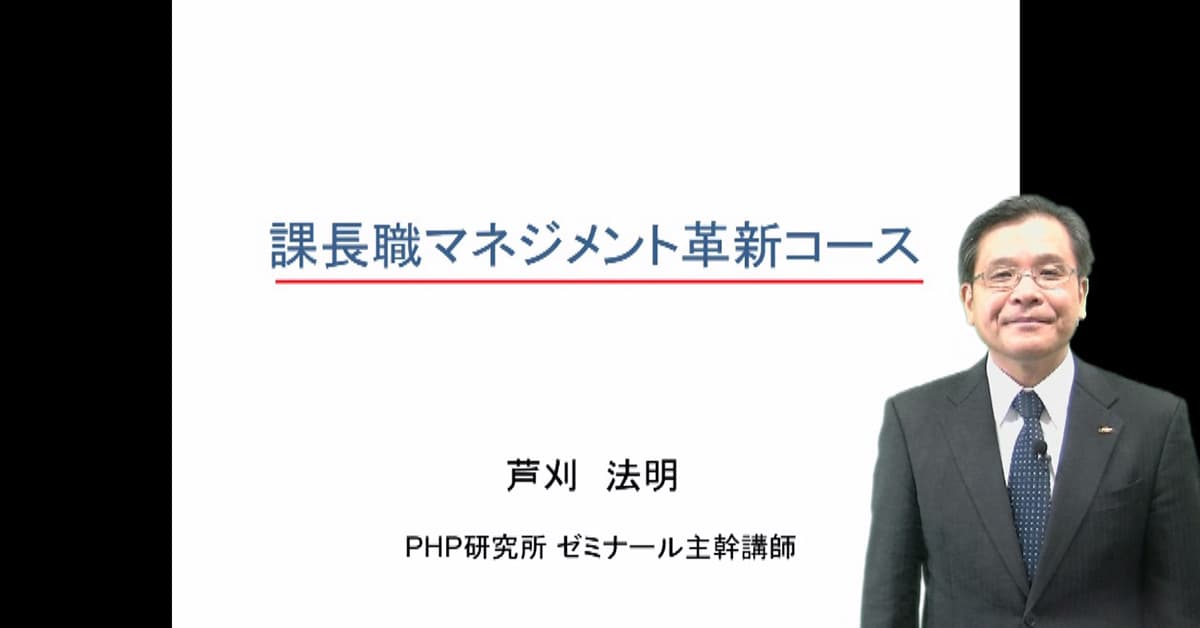



![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

















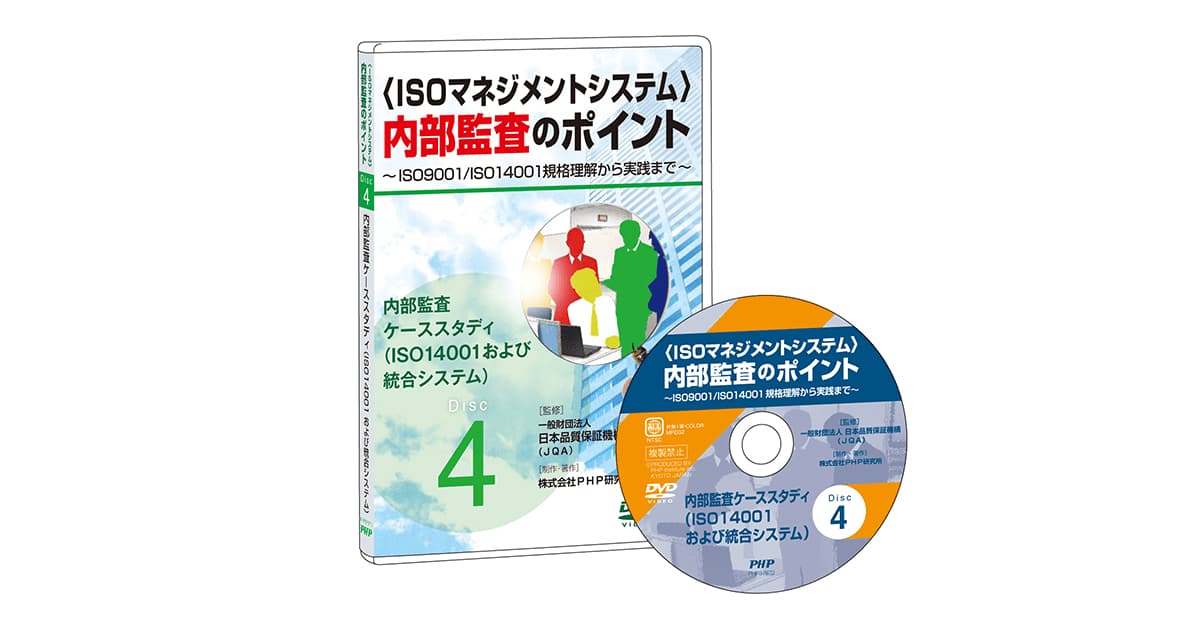




![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)
![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)
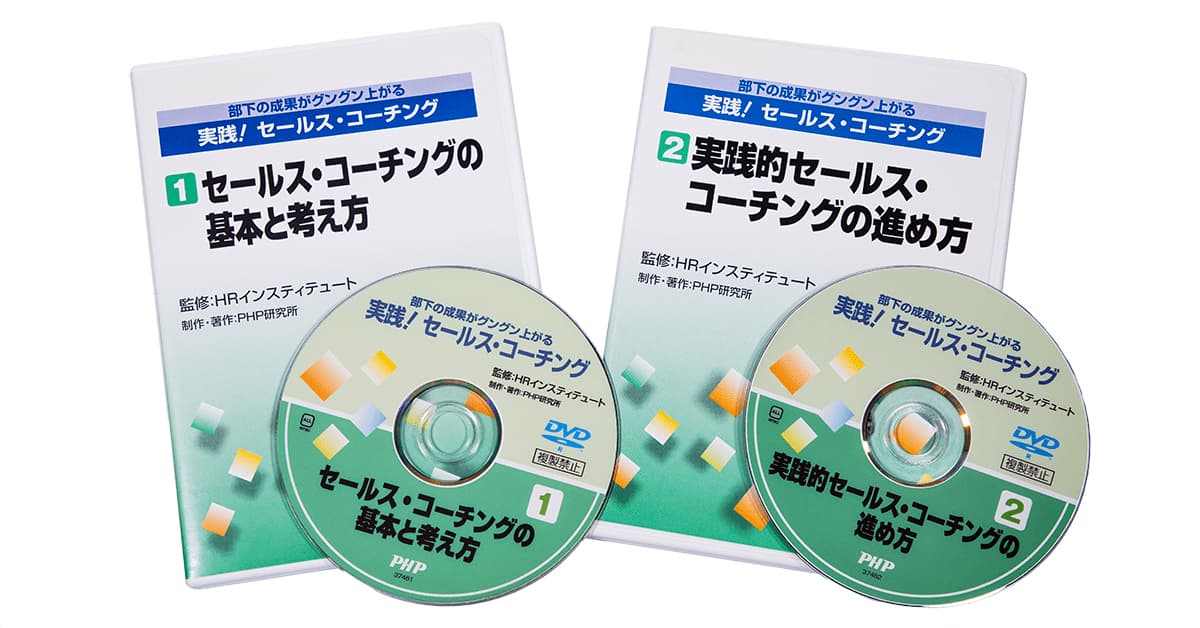





![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)







![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)





![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)
![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)